我が政治経済学部は、その淵源を、東京専門学校政治経済学科に発する。この政治経済学科は、東京専門学校を開校せしめた高邁なる時代的使命感に燃えた政治的教育的情熱そのものによって開設された。そして、それ以降、当学科は生々発展して、今日の政治経済学部に至っているのである。
「壮年政治家」小野梓(『高田早苗博士大講演集』一三二頁)を中心として、高田早苗らの「大学に於て、政治経済という様な当世必要の学問をしている」(高田早苗『半峰昔ばなし』六九頁)学生達は、鷗渡会を作った。そこにおいて彼らは新時代を迎えての近代国家形成を中心とした議論に若い情熱を燃やしていたに違いない。彼らの著作には、彼らが近代国家形成についてのヴィジョンやそれを実現するための政治・経済システムを追求していたことが明らかである。
そうしたなかで、大隈は、明治十四年十月の政変により下野した。その年の同月には、国会開設の詔書が発せられ、更に、翌十五年四月には、小野梓その他の人々は大隈を助けて立憲改進党を発足させた。
東京専門学校が開校式を挙行したのは、まさに、その年の十月二十一日のことであった。それは全く劇的というほかはない。
当時の政治情勢は騒然としていた。だからこそ、東京専門学校開校への情熱は、国家的政治的使命感に燃えて、一層激しくならざるを得なかったであろう。もし大隈が藩閥に生れ、また、政治的地位を失うことがなかったならば、「政治の躓きもなく、クーデターにあって野に下る機会もなかったろうから、早稲田大学はなかったに違いない」(本史 第一巻 一五二頁)。
明治十五年十月二十一日の開校式において、小野梓は「祝開校」と題して演説を行い、また、天野為之も、講師であるのに講師としてではなく敢えて内外政党事情社社員として、演説を行った。彼らは、その演説において、小野をして「今ヤ国家事多フシ」(『内外政党事情』明治十五年十一月一日号)と言わしめた情勢のなかで荏苒として日を空しくしていることができず、学校開校を実現させた情熱を、その言々句々に燃えたぎらせている。
更に、東京専門学校ひいては政治経済学科の特色を見るためには、学校創設に情熱を注いだ鷗渡会を中心とした人々の政治的実践との係わりを見ることが一助となるであろう。
大隈は、近代日本形成期に偉大な足跡を残した政治家であったが、他面において、ジェファソンの筆になる独立宣言により民主主義思想の洗礼を受け(本史 第一巻 一一六―一二六頁参照)、その政治を実行するためにジェファソンと同じく青年教育の重要性と必要性を識っていた偉大なる思想家であり、教育者でもあった。
この大隈を輔けた小野梓は、『救民論』(明治二年)において時代的先覚であることを示し、『国憲汎論』(明治十年、全三冊)においては当時において最も進歩的な国憲論を展開した逸材であった。彼は、実証主義的な近代政治学の日本の祖として高く評価される学究であり思想家であった(本史 第一巻 二九三頁参照)。また、他面においては、実際政治に深い関心を有し、立憲改進党結成に参画するなどの政治的実践を行った。しかし、明治十九年、三十三歳という若さで歿している。
鷗渡会のリーダーで、東京専門学校では「憲法史」「外交学」「貨幣論」「租税論」「行政法」「立憲政体論」を担当した(早稲田大学大学史編集所編『東京専門学校校則・学科配当資料』資料10、13)高田早苗は、明治二十三年、埼玉県第二区から第一回衆議院総選挙に立候補して当選し、以後六回選出されている。
「経済原論」「銀行論」「国債論」「貿易論」その他経済学関係科目を担当した(同前)天野為之は、第一回総選挙に当選したが、明治二十五年に落選し、それ以後立候補することはなかった。
「法律原論」「刑法」など法学科目担当(同前)の岡山兼吉は、第一回総選挙に静岡県第三区から当選している。
「政治原論」「政体論」「政理学」「論理学」「心理学」など担当(同前)の山田一郎は両度に亘って立候補したがともに落選し、市島謙吉は、第一回の選挙には落選したが、明治二十七年には当選している。
小野梓を慕って集まり東京専門学校開校を実現した人々、高田早苗、天野為之、岡山兼吉、山田一郎、市島謙吉らは、いずれも衆議院総選挙に立候補し、あるいは当選し、時として落選していたわけである。
彼らは、いずれも、政治学や経済学を研究し、近代国家システムの形成のみちを追求していた。しかし、新時代創造の優れた担い手である彼らは、学理的研究にだけ留まることが許されず、政治的実践にまで踏み込まざるを得なかったのであろう。後になって、学問研究の発展のために、学問的研究と政治的実践の明確な分化が必要とされるが、近代国家形成の激動期においては、時代の担い手である彼らにとっては未分化のなかで時代的使命を遂行することが求められていたのではなかろうか。それが志の高い人々の生き様であったのであろう。
更に、東京専門学校の創設は前述の如く劇的であった。そして、その学校設立への情熱は、藩閥政府に抗して近代国家システムの形成という理想に支えられて燃えていたのである。それは、私的権力欲に基づくものではなく、また、教育を生業に利用しようとするが如き低俗なものでもなかった。それなるが故に、学校設立の精神は特色を持ち、また、崇高にして高邁であり、その故にこそ、学校設立への情熱はますます激しく燃え得たのであろう。
このように、学校設立の精神が高く、また、大隈を支えて設立の中核となった人々が高い学問的見識を持つだけでなく現実的実践的気風の横溢した人材であったからこそ、東京専門学校は、時の権力者であった藩閥政府にとって脅威の的となったに違いない。従って、多く述べられている如く(本史 第一巻 三七頁、五〇四―五〇八頁参照)、政府は目に余る多くの圧力を相次いで加えてきた。
政府は、東京専門学校を大隈の政治的な私兵養成所、謀反人養成所ではないかと疑い、世間もまた大隈の政治学校であるという誤解を持っていた。
政治経済学科は、こうした風潮のなかで、東京専門学校を潰滅させようとする政府や世間からの強い圧力に抗して、敢然として政治経済学科として開設されたのであった。
その見識の高いこと、その勇気の絶大なることは、まさに、壮と言うべきである。
こうした情況のなかにおいて、敢えて、開設された政治経済学科こそ、東京専門学校の「特色を示すものとして、世間も注目し、学苑当局もひそかに誇るところがあった」(本史 第一巻 四九三頁)ものである。
この歴史的経緯のなかに、東京専門学校設立の精神的特色が語られており、政治経済学科の精神的支柱を見ることができる。
高田早苗は、大学における従来の学科構成について、その歴史や現状を十分認識していたからこそ、「(小野梓らから)専門学校に於ける学科について相談をうけたとき、主として政治学の独立を唱えた」(高田早苗「大学としての政治学経済学の過去を顧みて政治経済学部の使命に及ぶ」『早稲田政治経済学雑誌』大正十四年五月発行第一号 一一頁)のである。それは、時代や学問体系に対する高田の見識に基づくものであったろう。
そして、その主張が容れられて、「東京専門学校においては政治学を経済学とともに一つの独立せる学科として政治経済学科を置く事になった」(同前 一一―一二頁)。
政治学経済学を大学の中の科目として扱った東京帝国大学の如きもあったが、そこでも、それらは文学部の一学科に過ぎなかった。東京専門学校は、政治学、経済学を持つ一つの独立した学科として政治経済学科を置いた、我が国における最初の学校であった。高田早苗は、それを誇りをもって述べている(同前 一二頁)。
それに留まらず、「政治学は、学苑当局により、創立当初から、経済学とともに、否、経済学以上に重要視され」(本史 第一巻 四九四頁)、更に、高田は、早稲田の政治学が、帝国大学のドイツ流に対して、イギリス的学風の特色を持ち、日本における英国流政治学の中心になったことを、当然のこととして自信をもって述べている(『早稲田政治経済学雑誌』第一号 一三頁)。
政治経済学科を創案し開設させたのは、東京専門学校設立に参画した人々の、学問的見識と時代認識に強く依存するであろう。
その第一には、近代国家形成のための政治・経済システムの創建に強い意欲を持っていた彼らは、政治学、経済学の担うべき役割がきわめて重要であり、それぞれ一学科として独立せしめる必要性があると認めたことであろう。
第二に、近代国家形成への国政レベルでの実践的中心課題は政治および経済の領域にあったし、この両者には相互に関連するところが多かったことから、この独立した両者を併立させて政治経済学科にまとめたのであろう。
第三に、そうした意図を矛盾なしに実現し、却って、特色あるものにし得たのは、政治学および経済学の学問的性格によるであろう。すなわち、政治学と経済学とは、その学問的研究対象を別としている。けれども、今日的概念を以て考えるならば、両者ともに、ミクロ(微視的)・レベルではなく、マクロ(巨視的)・レベルでの思考に立つものであることにおいて共通するものを持っている。また、両者ともに、一つの学問上の研究領域として現象的技術的諸問題への接近方法の研究を深化させなければならないが、それらを包含しながらさらに深く本質的諸問題――「人間・社会・国家・世界とはなにか」など――の追求に強い関心を持たざるを得ないことを共有している。
政治学にしても経済学にしても、他の学科の中に包含されるのが一般的であったなかで、敢えて、この両者を併立して一学科を設立せしめたものは、時代的使命感と学問的造詣であった。しかも、この問題意識は、百年を経た今日においても、なおその斬新性を失っていない。
こうした経緯を顧みるとき、政治経済学科の「政治経済学」という概念は、方法論としての「政治経済学的方法」を意味してはいない。それは、政治学と経済学という隣接科学を併立的に包括して独立した一学科とし、「政治経済」学科という呼称を創案したものであろう。
現代的課題を考えてみても、「政治経済学科」設立の意義はきわめて大きいものであることがあらためて認識され、先人に敬意と感謝の意を捧げなければならない。
明治十五年十月二十一日、政治経済学科(次頁の第一図参照)は東京専門学校の開校により発足した。
この「政治経済学科」は、開設新聞広告において、「政治、経済学」を邦語講義を以て教授するとしている(『東京専門学校校則・学科配当資料』資料1――以下、資料番号を示す)。ここにいう「政治」は「政治学」を意味していることは説明を要しない。
学科の呼称は、十五―十六年度においても既に一定しておらず、開設時の入学試験案内では「政治科」(資料1)、学校規則では「政治学科」(資料3)と混用されている。また、授業内容も翌年には「政治経済学」を教授すとされ(資料5)、ここにも開設新聞広告との不統一が見られる。しかし、これは学校規則要領で政治経済学科と明示しながら、その学科課程表で政治学科として取り扱っている(資料5、7)ことから見ると、それは初期においては略式便法として用いられていたと見られる。しかし、それを当然視したのは、学科創設の理想と意義について、人々に共通するものがあったからであると考えざるを得ない。
鷗渡会員達は、大隈や小野の信頼に応えて政治学校創設の希望に燃えていたとともに、他面において、国政参加の機会を期待していた(本史 第一巻 六三四頁)が、こうした諸活動は、すべて広義に「政治」で表現できるものであったとも言えよう。
明治十八年になると、学校規則(資料12)において、「政治学科」となる。
明治十九―二十年度の学校規則(資料15)は、政治学科および経済学科を持つ「政治経済学科」を教科として、四年制の「政学部」の発足を明らかにしているが、それは、明治十九年八月の私立法律学校特別監督条規の影響を受けて、
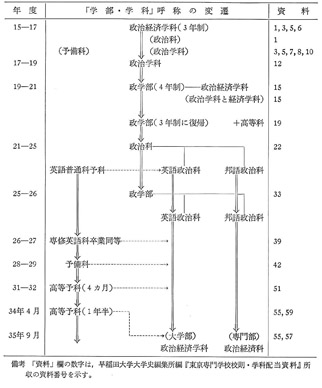
年度半ばにして三年制に逆戻りされることになった(本史 第一巻 五四三頁)。
三年制の三学科(政・法・理)制から出発した東京専門学校は、四年制の三学部制(政・法・英)を布く大改革によって一層の発展を期待したが、年度半ばにしてその志は変更を余儀なくされたのである。その代りに一年の高等科を置くことになった。
更に、明治二十一―二十二年度の新設諸科規則要領によると、学部制を見合せるとともに、法律科のほかに行政科を設置することになった。しかし、文部省の意向に従って、「法律科即ち司法科を第一法律科と称し又行政科を第二法律科と称す」(本史 第一巻 五五二頁)とする改正が行われた(資料22)。
しかも、語学力の習得の必要から、従来の「邦語による学科」のほかに、英語政治科および英語行政科を英語第一法律科とともに新設する大改正を加えた(資料22)。
そして、「この時以来、少くとも政治科に関する限りは、東京専門学校の残余の歴史すべてに亘り、邦語政治科と英語政治科の併置が定着し……そして、一は専門部に、一は大学部へと発展することになる」(本史 第一巻 五六四頁)のであった。
更に発展を期した東京専門学校は、二十五年十一月刊行の『学校改正規則および講師』(資料33)において三学部(政・法・文)制を復活し、政治学を教授する政学部を再出発させた。政学部には「政治科(邦語・英語政治科)」が設けられた。法学部には、法律科とともに、行政科(邦語・英語第二法律科)が設けられるのであった。
二十六年からは英語法律科および英語行政科が学生数僅少の故を以て廃止される一方、英語各本科に進む者のために予備授業を授ける専修英語科を設け、進学過程の充実を図って、将来の基礎を作っている。
その専修英語科は、三十一―三十二年度において、一年制の高等予科として整備された。三十三年度報告(資料55)において本校学科を大学部と専門部とに大別して新しい大学として出発することおよび高等予科を開校することが予告され、それに基づいて、大学部進学予備門としての高等予科(一年半制)が三十四年四月開校された。
そして、三十五年九月、早稲田大学が開校されたのである。
第一表に見られる如く、その教授科目は、開校以来、充実の方向を進んではきたが、それは必ずしも直線的ではなかったとみられる。それは、制度的変革を伴って行われた場合もあれば、担当者の有無などの都合による場合もあった如くである。また、同一の内容ながら科目名を変更整理したり、試行錯誤的に科目の存廃を取り扱ったと思われる場合もある。
けれども、全体的には講義科目充実の方向に向って、多くの学外者の協力を得ながら、意欲的な努力が積まれてきた足跡を見ることができる。
政治経済学科は、前述の如く、「政治、経済学」を教授する学科として設立された。しかし、各年度の『学校規則要領』を見ると、教授科目として、政治学だけを挙げ、経済学に触れていない年度もある。(二十一―二十二年度、二十二―二十三年度、二十四―二十五年度、二十五―二十六年度、二十七―二十八年度、二十八―二十九年度)。
更に、二十九―三十年度においては、政治学という表現を退けて、政学部は、国家学(帝国憲法、皇室典範、議院法、選挙法、国家原論、国法学行政法等を含む)、および、経済学、財政学、史学、国際公法等の諸科を研究させるとある(資料45)。三十―三十一年度も同様であるが、それ以後は資料に明記されるところがない。
創立期をはじめとして、以後、政治学関係科目数より経済学関係科目数が多い。それはそれぞれの科目の性格と担
第一表 政治経済学科学科目の推移(明治15-16年度―34-35年度)
当者の有無によってもたらされた結果であろう。経済学が教授科目として規則要領に記載されていない期間においても、経済学関係科目は多く、整理充実されているので、それを脱落させた理由は明確ではない。
また、政治学の代りに国家学が登場するが、二十一―二十二年度以降国家学関係科目が多く開講されてきたとは言え、それは政治学関係科目の継続や新規開講を排除してはいない。それにも拘らず、開校以来の政治学の看板が学問的性格を異にする国家学に置き換えられたことは、重要な関心を持たざるを得ないが、その理由を理解することは、筆者にはできない。
それら不明の点があるとしても、政治経済学科の科目構成の上で特色あることとして看取できることは、史学・史論(各国史・各時代史・文明史・憲法史・外交史・政治史)および哲学(特に論理学・社会学)の重視ならびに討論(国会演習)の開設であろう。ただし、経済史は、史学ではなく経済学関係科目として記載されている(資料51)。
それは、政治経済科開設期の人と精神および政治学、経済学の学問的性格によるところであろう。
政治経済学科の発展を、校則による制度的変革と学科目構成の内容的充実の視点から見ると、次の如く区分できるであろう。
第一期 創立期(十五―十六年度から十八―十九年度まで)
第二期 躍進・挫折期(十九―二十年度から二十―二十一年度まで)
十九―二十年度に三学部制を実施し、政治経済学科(または政治科、政治学科)は政学部(四年制)に発展し、政治学、経済学その他全科目の充実が急速に進められた。しかし、政府の監督条規により、その志は年度半ばにして挫折を余儀なくされ、三年制に変った。そのために、新たに高等科を設けた。
第三期 再躍進期(二十一―二十二年度から二十四―二十五年度まで)
学部制を廃止し、英語専門諸科が新設された。ここに、英語政治科と邦語政治科の誕生を迎えるとともに、カリキュラムは飛躍的な充実が図られた。それも二十五―二十六年度頃までには落着いてきた如くである。
第四期 拡張・安定期(二十五―二十六年度から二十八―二十九年度まで)
二十五―二十六年度において、再度、学部制を導入し、規模の拡張に対応した。そして、政学部が復活し、その下に邦語政治科と英語政治科が設けられることになった。ここに注目すべきことが一つ生まれた。それは、学則要領での記載順序が、従来は邦語政治科―英語政治科であったものが、二十八―二十九年度において、英語政治科―邦語政治科と逆転したことである。邦語政治科は開設以来の邦語講義の歴史の継承者として位置づけられていたが、大学開校の展望にたって、専門部になる邦語政治科は、その位置を、学部に発展する英語政治科に譲ったのである(一六頁の第一表註7参照)。
科目編成上の動きは、この間、比較的に安定している。
第五期 飛躍準備期(二十九―三十年度から三十五年九月まで)
学科目の改廃、充実の動きが二十九―三十年度から活発化してきた。また、学校全体としても制度改革が進められ、この年度に専修英語科が廃止されて英語学部(四年制)が新設され、更に、三十一―三十二年度には高等予科(四ヵ月制)が設立され、それは三十四年四月発足の高等予科(一年半制)に発展していき、三十五年開校の大学部体制への準備の過程が展開されていた。すなわち、新大学構想の実現のために、学科目の充実、制度の整理が行われていたのである。
以上の時期区分は、『東京専門学校校則・学科配当資料』(解題一四―一九頁参照)と若干異っている。それは、『資料』が学校全体から見た制度変革の推移の視点に立っているのに対し、筆者は、政治経済学科中心にみた制度変革と学科目の改廃、充実の動向を考慮したものであることに、理由があろう。しかし、その相違は、さほど大きなものではない。
我が学部が政治学科と経済学科の二学科よりなる正式の大学学部として成立したのは大正九年四月であった。正式という意味はそれより一年半前の大正七年十二月六日、官立大学と並んで私立大学の設置を認める大学令が公布され、九年四月成立の学部は同令に則って作られた学部だということである。大学令の公布を見るや学苑当局者はきわめて迅速にこれに対応し、早くも九年二月には設置認可の勅裁を得たのである。
尤も、法律上の許可が直ちに大学の実質的な発足を可能とするわけではない。実質的な発足のためには学部にふさわしい科目編成と教授陣が存在しなければならない。それは一―二ヵ月の短期間でできるものではない。また、学生の学部入学資格の問題もある。大学学部への入学資格のある学生は旧高等学校令による課程修了者である。従って、大学設置許可の二ヵ月後、すなわち大正九年四月の時点において有資格学生が存在しなかったとすれば、学部は形式的には成立しても、暫く開店休業とならねばならない。設置認可と同時に学部の実質的発足が可能であったのは、既にその前に学部にふさわしい科目編成と教授陣が整えられていたとともに、学部に入る資格を持つ学生を育てていたからである。一寸妙な表現になるが、我が学苑において大正九年四月という時点で、大学令による大学が形式的、実質的に発足し得たのは、それを遡るかなり以前に実質的な大学化がなされていたからなのである。
本史第二巻に詳述されている如く、明治三十年代早早、我が学苑は学制の根本的な充実計画の立案に着手した。計画の核心は予科↔本科制度である。この計画の上に、明治三十四年四月、修業年限一年半の高等予科を、翌三十五年九月、大学部を開設した。当時、帝国大学への入学有資格者は修業年限三ヵ年の高等学校修了者に限られていた。高等学校は大学の予科(予備門)であった。大学において高度の学術の研鑽に耐えるためには高等学校での基礎学力の修得が不可欠であるというのがこの制度の趣旨であった。我が学苑が高等予科→本科のシステムを作ったのはこの官立大学の制に倣おうとしたのであって、従って、この時点において学苑は実質的な大学化へ向って大きく踏み出したのであると言うことができる。
しかし、予科の課程が官立のそれの半分であったことは我が学苑の側の引け目であった。この引け目をなくすべく、我が学苑は大正六年四月、更に一歩を進めて高等予科の修業年限を二ヵ年とした。それに対応して、大学部のアカデミック・カレンダーを四月から翌年の三月までと改めた。大学部を九月開講のままにしておくと、高等予科修了生に半年の空白期間ができてしまうからである。
修業期間の半年延長に対応して、学科編成の整備、教授陣の充実が計られたことは言うまでもないが、この点は後出の「二 カリキュラムおよび担当者」のところで詳述されるので、ここでは触れないこととする。
ところで、大正九年四月、我が学苑は、学部の予科として高等学校と同じ三年制の高等学院を開設した。しかし、その第一回修了生が出るのは大正十二年三月である。従って、その間の三年間、学部は入学資格を持つ学生を他に求めなければならない。こうして求められたのが修業年限二ヵ年の高等予科修了生であった。ということは、文部省もまた高等予科を高等学校と同資格の学校と認めたということである。
高等予科は大正九年四月にも学生を募った。つまり、この年度、新設の高等学院と高等予科の双方がそれぞれ学生の募集を行ったわけである。高等学院は三年制であるので、前述した如く、第一回修了生が出るのは大正十二年三月である。大正八年四月、高等予科に入った学生は十年四月、学部に入る。故に、大正九年度から高等予科への入学をやめ、高等学院一本にすると、大正十一年度の学部入学者が得られなくなる。これが、大正九年、高等学院、高等予科の双方で学生を募集した理由である。
それにしても、こうした措置が可能であったのは、前段でも指摘したように文部省はじめ政府筋の高等予科に対する高い評価があったればこそである。かかる経緯を重視する筆者は大正六年の高等予科の整備・充実をもって、我が学苑における名実伴う大学の、従って政治経済学部の成立期とするのである。
(『早稲田学報』昭和2年7月発行第389号64頁)
だが、ここに一つの問題が残った。それは大正六年度に高等予科へ入学した学生諸君をどう遇するかという問題である。大正九年四月、大学令による学部が発足した時、彼らは既に旧大学部の二年生であった。資格的には、彼らもまた、学部入学の有資格者である。そこで、学苑では、そのまま旧大学部に留まり卒業するか、あるいは学部学生に身分変更するか、いずれかを学生自身の選択に委ね、身分変更を希望する学生のために別格学科編成表を用意したのである。これも詳細は後出の「二 カリキュラムおよび担当者」のところで述べられるので、要点のみを記すと、身分変更を求める旧大学部二年生は別格学科配当表によって第一学年からやり直し、大正十二年三月に正規の学生…もに学部を卒業するというものである。つまり、大正六年四月に高等予科に入学した学生は四年間で大学令による学部を卒業することができたわけである。この辺の措置も移行過程をおろそかにしない慎重、適切な配慮であった。
旧大学部時代においても、学苑は卒業生に対して学士の称号を与えていた。大学部政治経済科の卒業生には、政学士の称号が与えられた。大学令による政治経済学部発足後も暫くの間、学士号として、これを踏襲している。政治学科卒業生に政治学士、経済学科卒業生に経済学士の学位が与えられるようになるのは大正十五年からである。何故に、三年間に亘り、旧来の政学士号を続けていたのであるか、理由を明らかにすることはできない。
それでは政治経済学部の学生数はどの位であったのか。大学令による大学設置認可のための届書には各学部の在学者定数なる項目があり、政治経済学部のそれは三百二十とされている。これは一学年の学生定数であると考えられるので、三学年を通じての学生数は九百六十と定められたわけである。
『早稲田学報』第三八九号には、昭和二年三月末日調として各学部の在籍者数を掲げているが、それによると政治経済学部の学生数は第二表の如くである。
各学年とも定数を下回っている。特に第三学年の在籍者数は定数の半分に過ぎない。また、経済学科に比して政治学科の学生数が極端に少ない。第三学年の両者の比は一対十四である。更に、政治学科の学生数は学年によって著るしく異なる。こうした事実をもたらした理由についても残念ながら、説明することができない。
ここでの主題はカリキュラムの説明ということになる。しかしそれについては後段で詳述されるので、ここではごく簡単にその特徴と思われるところを述べるに止めることにする。
大正十一年度の学科編成表によると、政治学科、経済学科ともに第一学年では必修七科目、第二、第三学年では必修、選択合わせて八科目、三年間に履修すべき科目数の合計は二十三科目であった。これは他大学に比して少く、自学自修という我が学苑の基本的教育方針が此処にも現われていた。当時の常務理事・田中穂積はこれを自知自発主義と呼んで、学苑の特色ある教育方針として誇っている(『早稲田学報』第三〇〇号、大正九年二月)。
勿論、我が学苑は自学自習の名のもとに学生を放置していたわけではなく、苦しい財政事情の中、大図書館を造るなど、自学自習主義を裏づける体制を整備することに最大限、努力はしたのであって、この点は本史に詳しく述べられている。
学部の学科編成は、幾つかの科目の追加を除くと、大正九年以来、基本的には変化なしに推移したが、昭和七年に至って、大幅な変更が行われた。それは学制改革と呼んでよいものであったし、事実、そのように呼ばれた。政治経済学部長で理事であった塩沢昌貞は既に昭和五年六月の『早稲田学報』(第四二四号)に「大学教育行詰りに対する所感」と題して、改革の必要性について述べているので、改革計画はかなり以前から進められていたようである。塩沢の文章の一部を引用しておこう。
学科の整備とか案排とかについては、外面上は整っておるが、教授、指導方法に就いては実は卒直にいふと、我国の大学教育はなってゐないといはれても致し方がないのである。研究とか指導とかの方法がまだ充実して居ない。……(中略)……早稲田大学に於いては自修的研究といふことが教授上のモットーとしてあるが、此点がまだ充分に実現出来ない感がないでない……
改革の基本点を要約、列記すると、次の如くである。
(一)注入主義を避けるために、少数の基本学科目に限り精確に徹底的に学習せしめる。
(二)学部、専門部共に多数の選択科目を置く。
(三)適当な教科書及参考書を指定し、学生に予修せしめ、講義は要領を尽すだけとする。
(四)予習、討議、演習に重きを置き、教授と学生との接触を密にする。
(五)学外より専門家又は実際家を招聘し、短期講義を頻繁に行う。
(六)記憶力にのみ訴える試験制度の弊を矯め、其実力を発揮せしめる。
見られる如く、改革と言っても、それまでの基本方針、つまり学生自身による自学自習(自知自発)を再確認し、そのためによりふさわしい学科編成を行うというものであった。勿論、この改革は政治経済学部のみのものではないが、政治経済学部に即して改革の内容を具体的に示すと、こうである。
(一)これまで必修科目のみからなっていた第一学年の学科配当にも選択科目を置いた。
(二)他学部の学科目を選択の対象とした(現在の他学部聴講制度)。
(三)演習という科目を置き、これを重点科目とした。
尤も演習の置き方は政治学科と経済学科とでは異なった。すなわち、政治学科では演習として、第二学年に政治科学、一般公法、政治史を、第三学年に政治哲学、国際公法、行政法を置くという形であったが、経済学科では第三学年に経済学演習という名を掲げ、担当者として教授名を列記するという形であった。因に、この年度(昭和七年)の演習担当者は服部文四郎、林癸未夫、二木保幾、村瀬忠夫、宇都宮鼎、久保田明光、阿部賢一、塩沢昌貞、杉森孝次郎の九教授であった。
この昭和七年の学科編成方針は次第に戦時色を反映させながらも基本的には敗戦間際まで引き継がれていく。戦時色の第一は昭和八年から軍事教練が加わることである。当初、それは随意科目として置かれたが、昭和十四年度に至って必修科目となった。また、昭和十一年度から政治学科、経済学科双方の第一学年に「外国学生特殊研究」という科目が置かれた。設置の趣旨はアジア諸国、特に満州国からの留学生受入れで、日本人の学生が聴いてもよいとするものであった。これは翌十二年には第二学年に、翌々十三年には第三学年にも置かれた。
戦時色は敗戦の前年、昭和十九年十月に至って遽かにエスカレートした。同年十月十六日、学苑当局は次のような申請書を文部省に提出している。
本大学ニ於テ、戦局愈々重大ナル現段階ニ対処シ、「決戦非常措置要綱ニ基ク大学教育ニ関スル措置要綱」ニ鑑ミ、文科系学部ノ教科内容ヲ刷新シ、各学部ニ於テ多年踏襲セル科目制ヲ廃止シテ学年制ヲ実施シ、以テ学問ノ簡素化並ニ統一セル知識ノ活用ヲ図ルト共ニ教授方法ニ一段ノ工夫ヲ為シ、動員即応ノ態勢ヲ確立セントス。
尚文科系学部ノ学科課程改正ノ要旨左ノ如シ。
(一)政治経済学部
本学部ニ於テハ重点主義ニ依ル教科内容ノ簡素化ヲ図リ、科目ノ改廃ヲ行フト共ニ、特ニ大東亜戦争完遂ノ為、物心両面ニ亘リ重要ナル任務ヲ有スル政治並ニ経済研究ノ須臾モ忽セニスベカラザルニ鑑ミ「戦時政治論」、「戦時行政法」、「戦時経済論」、「戦時財政論」、「戦時配給論」、「東亜政治研究」、「東亜経済研究」他数科目ヲ配シ、尚共榮圏留学生ニ対シ「特別研究」ヲ設ケテ、皇国ニ関スル充分ナル認識ヲ得シムベキ措置ヲ講ジタリ。
昭和十九年十月および昭和二十年四月の学部学科配当予定表を見ると、第一学年には「東亜政策」(大西邦敏、杉山清)が、第二学年には「戦時政治論」(中野登美雄)、「戦時経済論」(林癸未夫、久保田明光)、「東亜史」(青柳篤恒)が、そして第三学年には「戦時財政論」(時子山常三郎)、「東亜政治研究」(大西邦敏)、「東亜経済研究」(杉山清)、「戦時行政法」(佐藤立夫)、「戦時配給論」(山川義雄)が置かれている。三学年を通して置かれた「特別研究(留日学生)」の担当者は青柳篤恒であった。
尤も、この頃、多くの学生は戦場に駆り出され、残った学生も勤労動員の工場通いで、勉強どころではなかった。右の戦時色濃厚な学科配当も殆ど有名無実であったのである。
昭和二十年の秋、敗戦の混乱にも拘らず、講義は再開されたが、学科配当のあり方には一大革命とも言うべき変化が生じている。昭和二十一年度の学科配当表を見ると、第一学年の必修科目は十科目、第二学年は必修九、選択二の計十一科目、第三学年は必修六、選択三の計九科目、三学年の合計三十科目と大幅に増加し、しかも必修科目中心主義とも言うべきものになっている。長い間の伝統であった、少ない単位数、広い選択幅という形で具体化されていた自学自習主義はここに至って否定されたかの観がある。しかし、此処では、この事実を指摘するに止める。
以上の他に、記すべきこととしては二つある。新聞学科の創設と自治行政科の設置である。しかし、これらについても後段で取扱われることになるので、此処では必要最少限に止める。
先ず、新聞学科であるが、ジャーナリズムと学苑、とりわけ政治経済学部との縁は深い。学部では既に昭和二年度から随意科目として「新聞研究」(喜多壮一郎担当)を置いていた。戦後早早これを一学科にまで高めることが必要と判断され、昭和二十一年八月二十二日付で新聞学科設置認可申請書を文部省に提出した。申請は九月十六日、文部大臣田中耕太郎の名を以て認可された。学生数は五十名、採用方法は一般公募ではなく、学院からの進学者と在学生中転科を望む者を以て満たすことに決められた。
その学科編成は政治学科、経済学科と比べると著しく異なっている。前述した如く、両学科とも自知自発主義で、戦後必修科目が大幅に増えたとはいえ、科目の殆どが原理的、一般的なものであったが、新聞学科には写真研究、速記術、タイプライティングといった如き具体的、技術的な科目が多かった。卒業後すぐにジャーナリストとして活躍できる技術を身につけさせることが、その狙いであったことは言うまでもないが、後に、これが同学科の弱点として問題になっていったのは皮肉である。
次に自治行政科であるが、これは初め学部にではなく、専門部政治経済科の一部門として設置された。そこで、前提として専門部政治経済科、関連して専門学校政治経済科について一言しておく。
専門部の実質的な出発は明治三十五年九月であった。その年は前述したように高等予科→大学部という体系が成立した年である。その年、中学校から直接に入学できる専門学校が設置された。それが専門部である。大正九年四月、大学部は名実と伴う大学学部に昇格したが、専門学校令には変化がなかったから、専門部は従来通り続けていけばよかった。しかし、手直しが全く不必要であったわけではなかった。手直しが必要とされたのは学苑内の位置づけについてであった。それまで、専門部と大学部とは法律上は同格の専門学校で、いわば併列的位置にあったのであるが、今や大学部は大学令による大学となり、学苑はそれら学部の集合体としてのユニバーシティとなったので、専門部はこのユニバーシティの附属学校へと位置を変えることになり、ために学則変更が必要となったわけである。新しい専門部学則は大正九年七月二十九日に認可された。
それまで、専門部各科の科長は大学部各科長の兼任であったが、学則変更によって、専門部部長のもと、各科には学部から出た教務主任が配されるという形を採った。しかし、昭和二年からは、各科ごとに対応学部から学科長、教務主任が選任されるというように変更された。とはいえ、教員組織は学部とほぼ共通で、学科編成も一学年に国語、地理学等の教養的な学科が配されたことを除けば、学部と殆ど同じであった。
次に専門学校であるが、これは関東大震災の翌年、大正十三年四月に開設された夜間学校である。学苑にはもともと専門部に見合う夜間の学校を造ろうとの気運があったのであるが、大震災によって神田の諸学校が罹災し、勤労学生の勉学に多大の支障を来したので、急速に実現に向って動くことになった。
「早稲田専門学校学則」によると、政治経済科、法律科、商科の三学科があり、学生には第一種学生と第二種学生とがあった。第一種本科生は中学校卒業生または文部省検定合格者であり、第二種別科生は学苑が行う試験に合格した者である。第二種の学生はさまざまな人生経歴を持つ者達であった。彼らはこの窓口があったことにより学苑の人となり得たことを喜んだが、学苑もこれによって、この裾野を広く社会に広げる機会を持ち得たのであった。専門学校の学科編成、担当者も、専門部の場合と同様、学部のそれと殆ど同じであった。
ここで、専門部に自治行政科が設置されるに至った事情を記す順序となった。同科(正確には自治行政専攻)の認可申請がなされたのは昭和二十二年十二月二十四日で、開設は翌二十三年四月である。「設立理由書」によると、その目的は地方自治体の指導者の養成である。そして、その根底には、「民主主義は人民自治を理想とし、人民自治は地方自治体の健全なる発達を基盤とする」との認識があった。学科編成は政治経済科のそれとは非常に異なり、必修科目を主として履習科目数が非常に多く、しかも政治、経済、法律の諸学科から農地制度論、協同組合論、社会教育論、都市および農村計画論にまで及び、ヴァラエティに富んでいた。良く言えば多彩、悪く言えば総花的であった。地方自治体ですぐに役立つ人材の養成という意欲が、このような学科目編成を採らせたのであろう。
ところで、自治行政科(専攻)設置計画も昭和二十二年という時点で突然に出てきたわけではない。農村の次代を担う人材を養成することの必要性の認識はかなり以前から学苑にはあった。その一つの現われを、我々は農学部創設計画のうちに見る。昭和十八年六月十四日の理事会は翌年四月を目指して、農学部を開設することを決定した。理由の一つは農村の次代のリーダー達を学苑に吸収しようとすることであった。
しかし、この決定は実現には至らなかった。十二月二十二日の理事会はこの決定を白紙に戻して、新たに専門部の一科として農学部を設けることを決めた。しかし、これもまた実現の運びには至らなかった。敗色が日本を覆い、食料を含めてあらゆる物資が不足し、学生、生徒の大半が戦場に、工場、農村に駆り出されていた当時の事情を思えば、学部、学科の新設は、客観的には全く不可能であった。
しかし、農村の次代を担うリーダー達を学苑に吸収し、訓練したい、それが必要であるとの認識は抱かれ続けたわけで、これが昭和二十三年四月の専門部政治経済科自治行政専攻誕生の母胎であったと筆者は推測するのである。
大正九年、大学令による政治経済学部が発足した時の専任教授は
の僅か八名であった。同年秋(十月)には大山郁夫が教授として復帰する。
大正十一年の『早稲田の今昔』には教員一覧が載せられてあるが、教授、講師を混じてイロハ順に掲げているので、誰が教授であり、誰が講師かは判然としない。こういう限界はあるが、政治経済学部関係教員を示すと、左の五十五名である。
猪俣津南雄、出井盛之、馬場哲哉、服部文四郎、原久一郎、(農博)橋本伝左右衛門、二階堂保則、新田孫三郎、本多浅治郎、太田正孝、大槻信次、大久保常正、大山郁夫、(法博)岡田朝太郎、渡俊治、(法博)河津暹、神尾錠吉、(法博)横田秀雄、横山有策、高橋清吾、立川長宏、(法博)田中穂積、伊達保美、(法博)副島義一、(法博)中村進午、中村萬吉、内ヶ崎作三郎、宇都宮鼎、(法博)浮田和民、梅若誠太郎、久松廉告、草野豹一郎、山崎貞、山本勇造、(文博)山岸光宣、松井等、(法博)牧野菊太郎、煙山専太郎、五来欣造、江間道助、(文博)遠藤隆吉、安部磯雄、青柳篤恒、(法博)栗津清亮、西条八十、菊池三九郎、遊佐慶夫、(法博)塩沢昌貞、志賀重昂、信夫淳平、島村民蔵、島村他三郎、清水行恕、(法博)平沼淑郎、鈴木貫一郎
それから三年後の政治経済学部教授は二十二名で、その氏名は次の如くである。(大正十四年四月一日刊『早稲田学園』による)
服部文四郎、林癸未夫、二木保幾、本多浅治郎、大山郁夫、高橋清吾、(法博)副島義一、(法博)中村進午、中野登美雄、内ヶ崎作三郎、(法博)浮田和民、梅若誠三郎、(法博)牧野菊之助、煙山専太郎、五来欣造、(文博)遠藤隆吉、安部磯雄、阿部賢一、青柳篤恒、(法博)塩沢昌貞、志賀重昂、(法博)平沼淑郎
林癸未夫、二木保幾、中野登美雄、阿部賢一の四氏を除いて、他の十八氏はすべて大正十一年の一覧にある。この十八氏は大正十一年度、教授であった人々としてよいのではなかろうか。大正十一年度一覧にあって大正十四年度にない人々で主な方は猪俣津南雄、出井盛之の二氏である。猪俣は共産党シンパと目され、大正十二年のいわゆる研究室蹂躙事件を機として、学部を去ったのである。
大正十四年度、新たに加わった四氏のうちの一人中野登美雄は前年の大正十三年一月、学苑が設けた助教授第一号として就任、一年で教授に昇進したのである。
学部発足時の教員組織は明治四十年以来の教授、講師の二本立てであった。助教授、専任講師、助手の制度はなく、教授でない者はすべて講師であった。講師の中には将来、教授となることを約束された人、すなわち戦後の組織中の専任講師に当る人々もいた。例えば、大正十四年度、講師の一人であった久保田明光がそれである。しかし、給与を含めて待遇としては学外から来る講師と同一に扱われた。こうしたあり方は敗戦に至るまで続いたらしい。助教授の名称は理工学部にのみ早くからあったが、実態は教務補助であった。故に、教員一覧表などに載る際には、講師のあと、つまり最後尾に記された。名のみで、地位は補助者に過ぎないのが理工学部助教授であった。
本格的な制度としての助教授制度ができたのは大正十三年一月であった。この時、政治経済学部助教授となったのが後の総長中野登美雄であった。『早稲田学報』(第三四七号、大正十三年一月十日刊)には次のような記事が載っている。
新助教授嘱任
旧来本大学の助教授制度は主として理工学部にのみ限られて居りしが、今日之れを各部科に拡張し適用することとなり、以て左の如く専属助教授の新任を見たり。
政治学部 中野登美雄氏
法学部 中村宗雄氏
右同 高井忠夫氏
商学部 末高信氏
右同 長谷川安兵衛氏
因に前記五氏は何れも本大学出身にして、且つ留学生として欧米に学び、昨年来順次に帰朝し、その生新の研究を提げて教壇に臨まれるを以て、本大学の内容に一段の精彩を添へたり
学苑の、そして政治経済学部の教授陣が急速に充実されていったあとを偲ぶことができるであろう。しかし、教授二十二名という数は戦前、これが最大で、以後、教授数で見る限り、減退する。昭和六年度の学部教授数は十七名である(昭和六年四月二十日刊『早稲田学園』による)。
大正十四年から、六年間に大山郁夫、副島義一、内ケ崎作三郎、梅若誠太郎、牧野菊之助、遠藤隆吉、安部磯雄、志賀重昂の八氏が退き、代りに大正四年度講師の列にあった宇都宮鼎、杉森孝次郎の二氏、および浅見登郎が新たに教授に加わった。大山郁夫、安部磯雄の二氏退任の理由は昭和二年、それぞれ労農党、社会大衆党の党首に就任されたことである。大山の辞任に当っては、いわゆる大山事件がおきている(これについては本史第三巻に詳述されている)。
昭和六年度、学部助教授として、内田繁隆、久保田明光、天川信雄の三氏の名が掲げられている。この年度の講師は左記の二十二名である。
磯谷孝次郎、H・B・ベニンホフ、時子山常三郎、大西邦敏、大森洪太、(経博)太田正孝、渡俊治、立花嘉美、高井忠夫、中村佐一、村瀬忠夫、内ヶ崎作三郎、(法博)野村淳治、柳川勝二、小林新、酒枝義旗、喜多壮一郎、(法博)信夫淳平、清水孝蔵、島田孝一、島村他三郎、末高信
講師の中村佐一、時子山常三郎、大西邦敏、酒枝義旗の四氏は後に教授となった方々で、大正十四年度において久保田明光氏がそうであったように専任講師的立場の人々であった。なお、大正十五年七月には助手規則ができている。助手と言っても無給で、ただ大学院の学費を給付(免除)されるだけの身分であったが、この制度によって最初の助手となったのは政治経済学部関係では内田繁隆と中村佐一の二氏であった。昭和六年、その内田は助教授で、中村は(専任)講師であったわけである。
昭和十八年年度の教授も昭和六年度と同じく十七名。天川信雄、大西邦敏、川原篤、久保田明光、小松芳喬、酒枝義旗、時子山常三郎、中村佐一、吉村正の九氏が新たに教授となり、二木保幾、本多浅治郎、高橋清吾、中村進午、宇都宮鼎、浮田和民、阿部賢一、浅見登郎、塩沢昌貞の九氏が退任、あるいは逝去されたのである。
助教授は杉山清、平田冨太郎の二氏。また原田鋼が専任講師的な地位の講師であった。
翌十九年度になると、佐藤立夫、山川義雄の二氏が同じような意味での講師に就任する。以降、旧制学部(大正九年の大学令による学部)終了までの専任教員人事を見ると、敗戦の昭和二十年十月に蠟山政道、昭和二十二年度に増田冨寿、翌二十三年度に保田順三郎、安藤彦太郎、市村今朝蔵、出井盛之の諸氏が加わる。うち、佐藤、山川、増田、保田、安藤、市村の諸氏は新制学部に切替った後も教員として引続き、それぞれ教授に就任されている。
なお、専門部、専門学校の政治経済学科には学部と別個の教員組織はなかった。
大学令による学部が発足した時、大学部政治経済学科長の安部磯雄がそのまま初代学部長となった。
学部長が安部から塩沢昌貞へと代ったのは大正十二年十二月二十四日という異例な時期であるが、何故こういう時期に異動が行われたのかは分らない。大正十三年二月には教務主任制度ができた。政治経済学部では政治学科教務主任、経済学科教務主任が置かれ、前者には高橋清吾、後者には二木保幾が就いた。
塩沢学部長時代は長く昭和十七年九月まで続いた。その間教務主任は何度か交替している。昭和二年二月には大山事件に係わって政治学科教務主任の高橋がやめ、中野登美雄が就任した。中野、二木両教務主任時代は昭和九年九月まで続き、その十月四日、経済学科教務主任が二木から久保田明光に代った。昭和十六年七月には、政治学科教務主任が中野から内田繁隆に代った。
昭和十七年十月四日、長い塩沢学部長のあとを受けて、中野登美雄が学部長に就任し、教務主任には政治学科川原篤、経済学科小松芳喬といわゆる若手教授が就いた。中野は昭和十九年九月総長となったので、林癸未夫が学部長となり、政治学科教務主任には吉村正が就く。小松は留任。林の学部長時代は一年余で終り、敗戦後の昭和二十年十月には久保田明光が学部長となる。この時から、教務主任は一人制となり、杉山清が就任した。二十三年五月、杉山のあとを中村佐一が襲う。
昭和二十四年四月、大正九年以来の学部は終り、新制学部が発足する。第一政治経済学部、第二政治経済学部の発足である。第二政治経済学部は夜間大学であるが、専門学校の後身というわけではない。第一、第二という二つの新学部が各旧学部のあとにつくられた事情については、本史で詳述されている。
こうして成立した第一政治経済学部長には引続き久保田が就き、第二政治経済学部長には時子山常三郎が就いた。旧学部、専門部は学生がいなくなるまで残ったので、久保田は旧制政治経済学部長、専門部政治経済科長を兼任することとなった。この久保田の地位は同年七月五日、中村佐一によって引き継がれた。
次に、専門部政治経済科の役職者について見よう。前段で述べた如く、専門部の新発足当時は、その各科長は対応する学部の学部長の兼任するところで、各科には教務主任だけが置かれた。初代の政治経済科教務主任は五来欣造であった。しかし、昭和二年十月から、各科長が選任されるように改まり、最初の政治経済科長には服部文四郎が就任した。服部の科長時代は昭和二十一年三月まで、実に十八年間に亘って引続いたのである。代るのは教務主任だけであった。五来は昭和六年三月まで教務主任を続け、天川信雄にバトンタッチした。昭和十四年五月から、学部にならって二人制となったので、天川と並んで時子山常三郎が教務主任となった。昭和十六年七月から十七年十月四日までの間の教務主任は川原篤と時子山常三郎、十七年十月から二十一年三月までの間は大西邦敏、時子山常三郎であった。
昭和二十一年四月一日、服部文四郎が科長の地位を退いて、政治経済科長には中村佐一が就くが、同年の十月一日には早くも時子山と代った。昭和二十四年四月には、前述した如く、久保田明光が科長を兼任することになった。
教授個人の研究活動およびその成果は後出の「三 人と学説」のところで一人一人について紹介されているので、ここでは学部としての研究活動に限って述べる。学部としての研究活動とは早稲田大学政治経済学会の活動である。
早稲田大学政治経済学会の創設の議は学部発足後間もなく起ったらしい。名実伴う大学学部となったことから来る教員の自負心と、そうなった以上官立大学に負けないだけの研究を行い、且つそれを客観化しなければならないとの責任感が学会創設計画の根本的動機であった。計画が熟して、いよいよ創設となったのは大正十三年であるが、月日まで特定することはできない。此処では会長、幹事、編集委員が教授会で決った十一月五日を以て創設の日としておく。会長は塩沢昌貞、幹事は高橋清吾、編集委員は五来欣造、高橋清吾、二木保幾、大山郁夫、阿部賢一、林癸未夫の六氏で、五来が編集長となった。
学会の最大の事業は機関誌『早稲田政治経済学雑誌』の発行であった。それを実現させるためには少からざる資金がいる。資金源は学生の納付金に求められた。すなわち、学部、専門部政治経済科および専門学校政治経済科の学生を会員とし、授業料とともに学会費を納入させたのである。こうした『早稲田政治経済学雑誌』の第一号は翌大正十四年五月に発行された。第二号の発行は同年十月である。大正十五年には第三号、第四号、第五号と三冊の発行を見、昭和三年からクオーターリィに、昭和九年からはバイ・マンスリへと発展していったのである。
次に、第一号と第二号の目次を掲げておこう。
第一号
巻頭の辞 教授 浮田和民
大学としての政治学経済学の過去を顧みて政治経済学部の使命に及ぶ 総長 高田早苗
論説
支那革命の当時統治権が清帝国から中華民国へ移転せる法理の考察 教授 青柳篤恒
為替相場の理論と実際及之が金融政策 教授 服部文四郎
我が予算の編製を論ず 講師 宇都宮鼎
エーゲ海の側岸に於ける刻下の民族大移動 教授 煙山専太郎
修正派としてのサンヂカリズム 教授 五来欣造
政治科学及び政治の概念について 教授 高橋清吾
福祉経済学者の租税論 教授 阿部賢一
社会政策概念の史的発展 教授 林癸未夫
経済学方法論概説 教授 二木保幾
欧米人の日本植民政策批判に就て 助教授 浅見登郎
人口理論の社会的背景 講師 久保田明光
雑録
佐藤信淵の政治学説 大学院在学 内田繁隆
第二号
欧洲の社会思想概観 教授 塩沢昌貞
無産階級倫理の基調 教授 大山郁夫
多数者政治に於ける形式と実質 教授 高橋清吾
収益分配の制度的一考察 教授 阿部賢一
資本主義の概念、本質及成立 教授 林癸未夫
価値論に於ける肯定の否定 教授 二木保幾
現象学的純正法学の梗概と其批判的研究 教授 中野登美雄
日米露三ヶ国とカムチャッカ 助教授 浅見登郎
新陳五百年 教授 平沼淑郎
浮田の巻頭の辞は「……政治も経済も社会的現象の一要素且つ世界的組織の単位として研究されなければならぬ。研究の順序としては一応古代のプラトンやアリストテレスに立戻らなければならぬけれども我々は彼等に超越して勇往邁進しなければならぬ」と言う言葉で終る気宇壮大な学問論であって、当時の学部教員の意気軒昂たる心理状態を彷彿とさせる。高田の文章は「……日本の大学に於いて政治学経済学を初めて大学の中の科目として取扱ったのは当時の東京大学であるが、之を一つの独立の学科と見做し、他の法律学其他と対立せしめたのは我東京専門学校即ち今の早稲田大学が最初であると申して宜しいのである」と、政治経済学部の地位を鮮明にしたうえで、そのあるべき政治学、経済学を次のように述べている。それは勿論、高田の考えであり、希望であるが、筆者は此処に引用しておく必要を感じる。
我日本に於ける政治経済学科の変遷、沿革の概要は右に述べた通りであるが、尚一言付け加へて置きたいのは政治学経済学、中にも早稲田に於ける政治学が帝国大学の独乙流なるに対して英吉利的学風を以て特色となした一事である。元来故大隈侯爵其人が英国に於ける立憲政治の謳歌者であつたのは勿論、之を補けた小野梓先生の如きは弱冠にして英国に留学し、英国憲法の運用を研究されたのみならずベンタム、ミル等の功利説を深く学んで帰られたのである。而して最初から政治学、憲法等の講座を担当した余の如きも東京大学に於て英国風の教育を受け、加ふるに英国の歴史、其憲法史等を好んで学修し、更には英文学に心酔して居たと云ふ様な訳で其教ふる所総て英吉利流であつた事は自然の勢である。夫や是やが原因をなして早稲田が我日本に於ける英国流の政治学の中心と成つたのは毫も怪しむに足らぬ事と云はねばならぬ。
思ふに今日、政治学を研究する上に於て徒に独乙風を吹かせ英吉利流を主張するが如き時代でない事は勿論であらうし、英吉利と云はず仏蘭西と云はず将又独乙と云はず世界各国の長所を採つて以て一団となし、結局日本的の政治学を組織せねばならぬであらうが、夫と同時に今後は政治学なるものを或は文学科の一部として取扱ひ、或は法律科の食客として之を遇するが如きは政治学の性質上頗る不合理なると同時に時代の進歩に伴はざる処置と云はねばならぬ。
余をして言はしむれば彼の儒教が重きを治国平天下におき政治と云ふ事を其教義の中心と為して居るが如く、政治学なる者を極めて広義に解釈し、財政学、経済学、史学、哲学、社会学の如きも要するに政治学の要素と見做すと云ふ事が最も適当の如く思はれる。国法学の如きも政治学の一部分たるには相違なきも其総てでない事は論を俟たない。而して一面法律的に政治学を研究する事は元より必要な事であらうが、哲学史学を基礎とした政治学が更に一層我日本の社会に勢力を占むるに至らん事を深く希望する次第である。
戦後、我が国は一連の教育制度の改革を実施したが、そのなかで新制大学の発足はいかなる意義を持つものであったか、またこれに対して早稲田大学はいかなる構想をもって対応したか、そして具体的にいかなる移行措置を講じたか、更にその後、現在に至るまでいかなる変容が見られたかについて見てゆくことにしたい。
戦後、文化国家の建設を目指して、「真に自由な新しい日本人が創造され、教育されることが希求された。昭和二十三年三月、島田孝一総長は、「新制大学発足にあたって」(『早稲田学報』昭和二十四年四月発行第五八九号 一頁)と題して所信を表明したが、そのなかでもこの点に言及している。すなわち、教育の本来の目的は、「我が国のあらゆる領域において新しい秩序を積極的に建設して行くとともに、人類の生活に対して何ものか新しい価値をプラスして行く創造的な国民を育成して行く」ところにあると言うのである。もしそうだとすれば、大学はいかなる具体的な方法を採用してその職能を果すべきかを熟考しなければならない。
現行憲法のもとに、昭和二十二年三月に学校教育法が制定されたが、そのなかで「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的および応用的能力を展開させることを目的とする」(五二条)旨がうたわれている。大学において人文と自然とに関する「真理の探究」がその職能のなかで重要な地位を占めていることは言うまでもない。もとより大学の目的、本質をかく解するからと言って、大学の職能のなかで「人間の育成」を第二義的なものとしていささかでも軽視することは許されない。将来、我が国の政治、経済、文化等を中心とする新しい環境に単に適応して、ひたすら自分自身の利益の追及のみに専念するのではなくて、いずれの領域においても指導的な役割を果しうる「人間の育成」こそ、今日、大学に課せられた重要な責務であるからである。昭和二十一年の初頭に来日したアメリカ教育使節団の提出した報告書でも、大学の職能として、「真理の探究」が第一に挙げられたが、同時に「社会人の育成」と「職業人の訓練」が重視されたことは意義深いものがある。総長が大学の責務として「人間の育成」を強調したことが新制大学発足に際して一つの指針になったであろうことは想像に難くない。このような視点にたって旧来の大学制度に対する根本的な検討が行われた。こうした情勢のもとで、我が早稲田大学は、新たに発足する新制大学について、特にあるべき学部体制についていかなる構想を持って対応したであろうか。
早稲田大学における新制大学の構想は、教育制度改革委員会における具体的な検討のあと、昭和二十三年二月五日に成案を得て、同委員会の大浜信泉委員長より島田孝一総長に答申された報告書において、その輪郭が明らかにされた。その後、新制大学設置に関して、設置委員長会、同委員会、教養科目委員会、体育科目委員会、教員選考委員会等が設けられ、早稲田大学における新制大学の具体案が練られ、その結果得られた案が、同年七月三十日に文部省に申請される運びとなった。このとき学部には昼間と夜間とが設けられ、昼間は第一学部、夜間は第二学部と呼称されることとなった。我が政治経済学部においては、第一学部の設置委員長は久保田明光、委員は中村佐一、吉村正、大西邦敏、小松芳喬、平田冨太郎が選任された。そして第二学部の設置委員長は時子山常三郎、委員は中村佐一、平田冨太郎、酒枝義旗、吉村正、大西邦敏が選任された。大学教務部より文部省への申請において、第一学部には、既存の政治学科、経済学科、新聞学科のほかに、自治行政学科が新設されることになった。他方、第二学部には、政治学科と経済学科が設けられることになり、いずれの学部卒業者にも学士号が付与されることになった。従来、旧制度の大学令に拠る学部の存在は少くとも夜間授業という形においては存在しなかったが、第二学部の設置によって、昼間授業に応じることのできなかった若き人々の前に門戸が開かれることになった意義は大きい。
また新制大学発足にむけて、従来の大学における学科課程への反省が見られたことも見逃すことができない。すなわち、これまでいずれかと言えば、一般教養に関する課程が少く、専門科目に関する課程が早期から広く行われる傾向があまりにも強く見られたことに対して、これを是正する方向が打ち出されたことは注目されてよい。島田総長も、この点が改められない限りは、大学の責務である「人間の育成」と言う目的を達成することは容易でない、とし、「この弊を改めたところに新制大学の出発の画期的な意義は発見される」と評価した。そして「従来はややともすれば、一般教育と専門教育との関連、あるいは一般教育と職業教育との交渉の如きを軽視して十分に顧みることをしなかった」という反省に立って、新制度では、「自由な思考に対する多くの背景と、職業的訓練の基礎とを提供するために、人文、社会、自然の三原則に属する相当潤沢な学科課程が配当されることになった」と述べている。我が政治経済学部に関して言うならば、総長の所信において表明されたいわゆる「職業教育」ないし「職業的訓練」に直接結びつく専門科目が、他学部に比較して少ないことは学部設置の趣旨よりやむを得ないところであろう。いな、寧ろそこに本学部の特色があると言ってよい。
それはともかくとして、専門科目のほかに一般教養科目が大幅に取り入れられることになった所以は、新制大学を卒えた者が「新しい日本の社会、すなわち近代的自由社会に処して自分の職業とする専門の知識を働かせると同時に、民主社会の一員としての役目を果すに適する」と考えられたからである。また新制大学では専門知識が旧来の大学より低下するのではないかという批判に対しては、「より高度な専門学科を履修したい者は当然大学院まで進むべきで」「専門知識は大学院まで延長するのが新しい制度の建前である」(伊地知純正「新制大学の教養科目について」『早稲田学報』昭和二十四年四月発行第五八九号 三頁)と考えられた。
因に、学生の四年間に履修する単位は、第一政治経済学部に例をとると、その後変遷は見られるが、一般教養科目四四単位、専門科目八四単位、体育四単位、計一三二単位とされた(詳しくは、後出「二 カリキュラムおよび担当者」参照)。
早稲田大学は、既に触れた準備段階を経て、昭和二十四年四月の新学年を期して、新学制に一斉に切り換えられた。旧制政治経済学部(学部長久保田明光)に代わって、既定の方針通り、第一政治経済学部(昼間)および第二政治経済学部(夜間)が設けられた。第一政治経済学部(学部長久保田明光)は、旧制度のもとに設置されていた政治学科と経済学科、更に戦後設置された新聞学科(昭和二十一年八月二十二日申請、昭和二十一年九月十六日認可)に加えて自治行政学科(旧制専門部に自治行政専攻が設けられていた――昭和二十二年十二月二十四日申請、昭和二十三年二月十二日認可)の四学科が設置されることになった(設置に至る背景については、新聞学科および自治行政学科の項を参照)。他方、主として勤労学徒のために設けられた第二政治経済学部(学部長時子山常三郎)には、政治学科と経済学科の二学科が設けられた。この第二学部の発足に伴って、これまで昼間授業に応じることのできなかった多数の若き勤労学徒に文字どおり門戸が開かれた。少くとも、発足の当初、相当数の学生が昼間仕事を持つ者であったことから、その設置の趣旨は十分に生かされたと言ってよい。後述のように、第二政治経済学部は、十数年を経て廃止されることになるが、その出身者の中には、第一政治経済学部出身者に劣らず、各方面において早稲田OBとして活躍しているものが少くないからである。
ところで新制大学発足に際して、我々の学部では具体的にいかなる移行措置が講ぜられたであろうか。
先ず、この旧制度から新制度への切り換えに伴って、第一政治経済学部自治行政学科二、三年を除いて、一斉に第三学年まで開設し、昭和二十六年で一応完成するものとされた。そして従来の高等学院、専門部政経科および専門学校政経科学生は左の基準によって新制の第一政治経済学部および第二政治経済学部へ移行し、更に学外から入学編入試験で若干公募した。
一年修了者 新制学部一年へ
二年修了者 同二年へ
三年同(卒業者) 同三年へ
(一)旧制高等学院学生は全員その系統の新制学部へ移行し、廃止する。
(二)専門部、専門学校学生は、一年修了者は全員、二年以上は希望者のみ、それぞれの系統の新制学部へ移行し、希望しないものは旧制のまま卒業せしめて本年(昭和二十四年)限り廃止する。
(三)旧制学部は本年(昭和二十四年)四月入学の分から新規募集を中止し、現在在学生は旧制のまま順次卒業せしめて昭和二十五年度を以て自然廃止となる。
このような措置を講ずることによって、旧制政治経済学部は装いも新たに第一政治経済学部および第二政治経済学部として発足することになった。教授陣も、その多くは両学部を兼担したが、専門科目担当の教授(助教授、講師を含む)のほか、一般教育科目担当の教授を迎え、その数も増えたことは言うまでもない。これに伴って研究室も増設され、学生のために大学図書館のほか学部図書室が新設された。
なお新制大学の発足に伴って、同一学部に専門科目と一般教育科目とが併置され、いわゆるタテワリ方式が採られたところに大きな特色が見られる。
新制大学発足に伴って、第一政治経済学部では、古き伝統のある政治学科、経済学科に加えて、第二次大戦後、昭和二十一年十月に発足した新聞学科、更に新たに自治行政学科が設置されたが、発足後十余年を経て、そのあり方が問われることになった。他方、主として勤労学生のために設置された筈の第二政治経済学部も、時代の進展に伴って著しく変化を見せたため、その存立の意義が問われ、慎重な検討の結果、遂に第一政治経済学部における新聞学科および自治行政学科の廃止とともに、昭和四十一年度における社会科学部(夜間)の新設に伴って第二政治経済学部の廃止の方針が打ち出された。そしてこれらの措置は昭和四十年秋に講ぜられたが、我が政治経済学部はここに大きな転換期を迎えたと言えよう。以下、これらが廃止されるまでの経緯について述べることにする。
新制大学発足とともに、両学科は大きな抱負・期待をもって発足したが、十六年を経て廃止の措置を講ぜざるを得ないことになった。ここでは所期の目的を十分に達成し得なかった事由を明らかにし、廃止に至る経緯について述べることにしたい。
既に触れたように、新聞学科は、戦後、間もなく昭和二十一年十月に発足したが、その理由書に述べられているように、「社会文化の向上、世論の健全妥当な発達は、正に民主国家の必須条件である」との認識に基づき、そのための優秀な新聞人を養成することこそ国の要請に沿うものであるとして新聞学科を創設したのであった。
また新制大学発足とともに設けられた自治行政学科は、政治、経済、社会の各般に亘って地方民主化の実現が企図されている状況を踏まえ、地方自治の健全な発達のために指導者を養成して国の要請に資せんとするものであった。
以上において明らかなように、両学科はそれぞれ時代の要請に応じて発足したものであるが、発足後、十余年を経過しても、後述のように、専任教員数の絶対的不足等のため、独立の学科として存続せしめることが妥当であるかどうかが問われた。かくて昭和三十八年二月には、先ず、新聞学科学科目検討委員会が設置され、次いで翌三十九年二月には学部組織検討委員会が設けられた。そして当該委員会ならびに教授会において、数次に亘る検討が重ねられた。翌四十年七月十四日には、第一政治経済学部(学部長小松芳喬)教授会は、その検討の結果を次のように表明した。
(一)新聞学科、自治行政学科の専任教員数は現在著しく不足しているが、これらの分野の研究者の絶対数は現在我が国で僅少であるため、その早急な補充はきわめて困難である。
(二)現在自治行政学科に配当されている学科目は、政治学科に配当されている学科目と共通するところが多く、また自治行政学科独自の学科目はこれを政治学科に配当しても支障がない。教育的にはむしろ自治行政学科を政治学科に統合することが望ましい。
(三)新聞学科については、過去数次にわたる検討に際しても、常に強調されたことであるが、政治学科及び経済学科に配当されている基礎的な専門教育科目を、学生に従来以上に履修せしむるべきであるという見解が強い。
しかし、これ以上政治学および経済学関係の学科目を新聞学科の学生に課するとすれば、新聞学科創立以来の職業教育の伝統を維持することは困難であり、学科として独立の意義は失われる。
(四)しかも、マスコミ界に進出する学生が、政治学科および経済学科に多数存在する現状にかんがみ、新聞学科の主要専門教育科目については、政治学科および経済学科の学生にも履修しうる途を開くことが必要と考えられる。そのためにも、従来のように新聞学科を封鎖的な独立学科として存続することに対しては再考を要する。
(五)なお、マス・コミュニケーションに関する研究については、大学院に当該コースを設置するよう他学部と協力して努力し、大学院のレベルで独創的研究の推進を図るとともに、その専門研究者の養成の途を講ずることが望ましい。
以上のような諸点を挙げ、教授会は次のような決定を行った。
(一)昭和四十一年度以降新聞学科および自治行政学科の学生募集を停止する。
(二)新聞学科および自治行政学科に配当されている主要な専門教育科目は、検討の上、これを政治学科または経済学科、もしくは両学科に配当し、両学科の学生が履修できるようにする。
(三)他学部と協力して、大学院にマス・コミュニケーション研究に関するコースを設置するよう努力する。
以上のような教授会の決定に対して、学内外よりさまざまの批判がなされたことは否定すべくもない。そこで教授会は、更に学部組織について検討を重ねたが、その結果、同年十月十九日、新聞学科および自治行政学科は、学部教育の段階においては、独立の学科として編成するよりは寧ろより広い基盤に立たしめることが適切であるという結論に達した。この結論に基づいて、昭和四十一年以降両学科の学生募集を停止することが再び決定された。この点について、教授会は次のように表明した。
新聞学科は、その名称に「新聞」の表現を用いてはいるが、それは単にマス・メディアの一つとしての新聞のみを対象とする趣旨ではなく、ラジオ、テレビ、映画、定期刊行物などを含めたいわゆるマス・メディアおよびマス・コミュニケーション現象一般を対象とするものと解しなければならない。しかし、このように広義に理解したとしても、学部教育における学科としては、政治学科または経済学科と対比した場合あまりに専門的に偏するうらみがある。
自治行政学科についても、ほぼ同様のことが言える。民主政治において地方自治が重要であることは言うまでもなく、また、自治行政が学問研究の対象として一分野を構成することは疑いないが、これを直ちに学部教育の次元における学科の基盤とすることには難点がある。
ここで教授会が示した理由は、先の七月十四日のそれより詳しい。ひとたび両学科の学生募集停止を決定すれば、それに伴って昭和四十一年度以降採るべき措置が明らかにされなければならない。この点については、次のような決定が行われた。
(一)学生募集停止後も、現在両学科に在籍する学生が卒業するまでは両学科を存置し、勉学の初志を尊重して、できる限り改善を図る。
(二)両学科の学生で希望するものがある時は、新聞学科の場合は、既に履習した科目により政治学科または経済学科に、自治行政学科の場合は政治学科に、それぞれ転科することを認める。
なおこの決定に伴って、教授会は、新聞学科、自治行政学科に配当されている主要専門科目については、新学部組織のもとにおいても、最も適切な形式と内容において、政治学科または経済学科もしくは両学科にこれを存置し、昭和四十一年度以降入学する学生が選択履修できるよう、またマス・メディアおよびマス・コミュニケーション現象の研究については、大学院または他の研究機関を全学的規模により設置するよう努力することを申し合わせた。実際には大学院政治学研究科に講座「マス・コミュニケーション理論」が設けられ、研究者の養成が行われている。
新制大学発足に伴って、昼間通学を困難とする勤労学生のために第二政治経済学部が設けられたことは、既に述べた通りであるが、その抱負は発足当初には強く貫かれたものの、その後入学する学生に著しい変化が見られた。昭和四十年十二月七日に開催された第二政治経済学部教授会(学部長佐藤立夫)は、この事実を卒直に認めた。特に近年「勤労学生の数は激変し、昼間の通学に差支えない学生が多数を占めるようになり、第一学部への転部を熱望する学生諸君の数がきわめて多い」という状況を認めた。そしてこの認識の上に、昼間通学が可能な学生に対して、大学が第一学部の学生定員を増加することによって、門を更に開く方針を立てた事由を明らかにした。そしてこれまで「第二政治経済学部にあって勉学することを希望したような諸君に対して、昭和四十一年度発足を予定されている社会科学部が現在我が学部に設けられている主要科目の大要を網羅しているので、その要望に応え得るはずである」として、これを機会に、昭和四十一年度より新入生募集を停止することに決定した。
この決定に伴い第二政治経済学部の名称は、当時在学中の学生が卒業する最終の時期を以て第一政治経済学部の名称とともに廃止され、新しく「早稲田大学政治経済学部」と呼ばれることになった。
以上において明らかなように、昭和四十年に我が政治経済学部において採られた一連の措置は、戦後の学部の歴史において一大転換期を意味するものであった。その後、早稲田大学は、授業料値上げ問題とも絡んで、学生の熾烈な反対運動の渦中にさらされることになったが、この時に政治経済学部が採った措置そのものについては、特にこれを変革しようとする動きも見られず、今日に至っている。
なお廃止の措置が採られた新聞学科および自治行政学科ならびに第二政治経済学部の出身者のなかには、既に国会議員として、あるいは大学教授として政界、学界において頭角を表わしている者、更にジャーナーリズムおよび財界等において早稲田OBとして縦横に活躍している者も少くない。それだけにこれらOBのなかには、その廃止を惜しむ声も聞かれる。
新制大学発足以来、政治経済学部の専任教員の陣容について、これを増強すべきだとする意見が存した。特に助手採用に関して、旧制では大学院において、新制では大学院博士課程において一定の研究成果を挙げた、指導教授の推薦する者に研究報告をさせ、その審査に基づいて教授会が採否を決定する方法が採られていた。その後、学部教授会は、昭和三十七年十二月に助手採用方針に関する委員会を発足させることを決定した。当該委員会は昭和三十八年一月に開催され、教員陣容増強の方法、増強を必要とする専攻分野(学科目)の問題、養成方法の問題等が審議され、採用方針が示された。すなわち大学院政治学研究科および経済学研究科において博士課程を修了し、博士候補者検定試験(現在、この試験は廃止されている)に合格した者のうち、一定の資格を有する者について、指導教授が所属研究科委員会に推薦し、更に当該委員会がその推薦に基づき選考のうえ学部に推薦する者について採用試験を行うことになった。
次いで、昭和四十年四月、教授会は専門科目助手採用方法内規を決定した。この内規によって専門科目担当の教授および助教授の中から、学部長が教授会の議を経て委嘱した委員によって組織される助手選考委員会が組織された。その後、翌昭和四十一年十二月には専任教員の新規嘱任および昇格の推薦方法が議せられ、教授会は、あらかじめその該当者を披露し、これに対する意見を徴した後、次回の教授会において協議決定する方法を採ることになった。
その後、助手の採用状況は、学部の要請に必ずしも十分に応えるほどには至らなかった。このため専門科目担当専任教員の増強を図る方策として、学科目配当表上、緊急度の高い学科目を担当する専任教員については、学外から採用すべきだとして、そのための方途が講ぜられた。昭和四十九年に、助手選考委員会運営のための覚書として専門科目担当教員拡充要綱として示されたものがそれである。同要綱によれば、学外から専任教員を採用する場合、その資格(教授、助教授、講師)は、業績、研究教育歴、年齢等を考慮の上、決定されることになった。
現在、学部には、助手の採用のために次に挙げるような試験が行われている。
(一)第四年度生(もしくは当年度卒業予定者)で専門演習履修者に対して行われる大学院大隈奨学金受給予約者採用試験
(二)本大学ならびに助手選考委員会が指定した他大学前期課程第二年度以上の在籍者で修士の学位未取得の者に対して行われる予備語学試験
(三)本大学院政治学研究科もしくは経済学研究科後期課程第二年度以上に在籍する者に対して行われる特別語学試験
以上に述べたような試験を行うことによって学部の専任教員の強化拡充に努めているが、受験者の資格など具体的な細目については若干の改変が見られる。
我々は、専門科目担当教員の強化拡充のために幾つかの方策を考え、これを実施してきたが、当初の意図に拘らず、必ずしも所期の目的を達したものとは言い難い。これまで専門科目助手採用方法内規に基づいて、既に助手に採用され、その後、専任講師、助教授を経て教授として活躍している者も少なくないが、その数は未だ十分とは言えない状況にあるからである。また専門科目担当専任教員の増強のために、学科目配当表上、緊急度の高い学科目を担当する専任教員として学外から若干名を採用しているが、その数は少ない。これは専任科目担当専任教員の増強を図ることが実際にはきわめて困難であることを如実に物語っている。制度的にはかなりよく考えられたものであっても、実際にこれを運用する際には、なお克服しなければならない障壁にぶつかる。これまでの経験に徴し、改めるべきものは改め、教授陣の更に一層の強化充実を図ることこそ我々の責務であると考える。
政治経済学科が創設された明治十五年の学科目配当に関しては、三つの資料がある。「学校開設新聞広告」「私塾設置願」「学校規則」である。いずれも『東京専門学校校則・学科配当資料』に資料1、2、3として収められている(同『資料』は資料60まで収載)。このうち前二者(資料1、2)と後者(資料3)との間には、政治学関係の主要専門科目をめぐってかなり重要な違いが発見される。その決定的な部分は、資料3には「政治学」の見出しの下に(以下、課程表上、この見出しの下に包含された科目を「政治学」科目と称する)「政治原論」と「政体総論」ならびに「立憲政体論」の三科目が配当されているのに、資料1と資料2とにはそれが全くない点である。「万国公法」と「憲法史」(「史学」の分類)についても同様である。どの資料にも共通して挙げられているものをその記載順に列挙すると、「憲法」(総論または要論)、「行政法」(大意・詳論)、「外交学」(大意)、「政理学」(大意)である。ただ「行政法」は資料3では「行政学」となっている。
初期の科目配当に関する資料上の違いをどう解読すべきかは、本史第一巻に譲る(四九二頁)として、その後、明治三十五年における早稲田大学改組等、幾多の星霜と曲折とを経ながら大正九年に大学令の適用を受けるに至るまでの間における、政治学科の主要専門科目とその担当者の変遷を、明らかにすることが本節の目的である。
この時期全体における科目配当の歴史を通覧して、明治二十一年度を境に顕著な変化が生じていることを指摘できる。第一に、課程表の立て方が、史学科目(以下、課程表上「史学」の見出しの下に包含された科目をいう)に始まって、法学科目(以下、課程表上「法学」の見出しの下に包含された科目をいう)を通り「政理学」に終る、創設期のややアトランダムとも見える方式から、改めて、政治学科目を筆頭に据え、史学科目、法学科目と並べる方式へと、並べ方の理念の変化が窺える。第二に、そしてこれが最も重要な変化と考えられるが、政治学科目の内容が大幅に変り、その他の関係科目の種類も著しく増強された。明治の末期から大正の初めにかけて、究極的には、次のような四系列の科目配当から成る学科目編成の骨格パターンが形成されるようになった。これが、その後の政治学科における科目編成の原型を成していると言ってもよかろう。
第一の系列は政治学科目群である。ここで、この時期に現れた重要な変化は、「政治原理」の消滅とそれに代わる国家学の台頭である。尤も、明治三十年代の後半から四十年代の初めにかけて、一時、両者が並列する時期もあったが、国家学中心の排列は基本的に変っていないように思える。次いで、「国法学」や「日本憲法」の如き憲法関連系の科目と「行政法」など、これまで法学科目とされてきたもの、それと「政治学史」「政治哲学」「自治行政(自治政策)」などの諸科目が、漸次、政治学科目に編入されている。
こうして、政治学科目の範疇は次第に充実してきた反面、政治学の独立――国法学や国家学からの――という政治学科創設以来の理念は、少くとも学科目編成の表面上では、初期のそれと比べてやや個性の薄れたものとなった印象を免れない。しかしこの印象を事実とするには内容的検討を伴う必要があろう。その点については後に多少触れたいと思う。
第二の系列は、史学科目の「憲法史」「政治史」「外交史」、法学科目の「国際公法」など、その他の主要な関係専門科目である。これらの二系列科目群に、第三の系列として「名著研究」「原書研究」など今日の「外国書研究」の類いの科目が、更に第四の系列として「国会演習」「国法行政法」ならびに「国際法」の実習、そして最終的にはセミナリーに連続する、今日の演習相当科目が連なる。
ただし、右の第二系列に属する科目のうち、本節が主として政治学科目ならびにその他の主要な政治学関係専門科目に重点を置く建前から、論理学、社会学、心理学系統の科目は一切、また史学関係や法学関係の科目でも採り上げられなかったものがある。ことに法学関係科目中、「法学通論」「法理学」「国際私法」「民法」「刑法」「商法」などの科目が省かれていることを明らかにしておく。ただ明治十五―二十八年度頃までは「法学通論」「法理学」が、それから四十年度頃までは「法学通論」と民・刑・商の各法律科目、明治四十―大正七年度までは民・刑・商の各法律科目が、そして「国際私法」は明治三十―大正七年度まで、それぞれ、概ね継続的に課程表上に設置されていた。そのことだけは付け加えておく。
また担当者の面では、明治のかなり後の時期まで、一人が幾つもの重要科目を継続的に受け持つという例が見られた。「政治学」「国家学」「政体論」等の政治学系の科目、「憲法論」「各国憲法」「憲法史」等の憲法関連科目をはじめ、外交学等に亘る広い分野を担当した高田早苗、「国法学」をはじめ「国家論」「外交史」「西洋政治史」等を担当した有賀長雄はその最たるものであろう。そうしたあり方自体については、今日の時点から見てとかくの論評はあり得るにしても、そのことから、寧ろ当時における官憲の圧迫や財政的基盤の弱さなどに堪えて、この学苑の基礎を担った先人たちの苦節の一端を窺いみる思いを禁じ得ないのは、筆者一人に止まらないであろう。学苑出身者が課程表上に担当者として名を連ねるに至るのは明治四十年に入ってからのことであるが、政治学系の重要科目を担当するに至ったのは、大正のことに属する。
前記資料3に依拠すれば、「政治原論」は明治十五年度に設置されていたことになる。担当者は山田一郎。近代日本において政治学を国法学や国家学から分離し、一個の独立科学として理論的構築に成功した最初の学者であったとされる(早稲田大学七十五周年記念出版・社会科学部門編纂委員会編『近代日本の社会科学と早稲田大学』――以下、『社会科学と早稲田』と略称す――一〇頁)。外国の説を受け売りする人の多かった創立当時の学苑講師陣の中で、独り山田の政治学講義のみ全く独創のものであったと評したのは、山田が、明治十八年、移転問題で学苑を去った親友岡山兼吉と行を共にした後を襲って、一年間だけ「政治原論」を講じた市島謙吉の述懐である(『社会科学と早稲田』一四頁)。
あたかも、山田が学苑を去ったことを区切りとするかの如く、「政治原論」は、この年度で途切れる。そして三年後の明治二十一年度以降、大正八年度までは、引き続き「国家学(論)」(明治三十二年度まで。ただし明治二十一年度は英語政治科のみに)または「国家学原理」(明治三十三―大正八年度)が、「政治学」科目の首座を占めるようになる。この間同科目は、第一年配当科目として置かれていた(明治三十五―四十二年度は、資料の課程表が学年配当の記述を欠くため厳密に言えば不明だが、その前後の配当状況から類推してほぼ間違いあるまい)ため、前年度の高等予科における年限延長の影響で、同学年を欠く大正七年度はこの科目は大学部の課程表上に現れない。担当者は、高田早苗(明治二十二、二十三、二十五、二十九、三十一―三十八の各年度)、織田一(明治二十四―二十五年度)、有賀長雄(明治二十一、三十八の各年度)、井上密(明治二十七年度)、浮田和民(明治三十二、四十―大正二、七―八の各年度)、大山郁夫(大正三―六年度)。明治二十六、二十八、三十の三年度は不詳。ただ明治三十三年度(資料58によると三十四年度も)を除き、三十一―四十二年度に限って、「政治学(論)」は再び課程表上に復活している。従って、この時期は「国家学原理」と「政治学」とが並列したことになる。ただし、そのうち三十一―三十四年度は英語政治科、三十五―三十六年度は専門部のみである。担当者は一貫して高田。ただし三十四年度については、高田の名の横に中括弧を附して梅若誠太郎の名がある。代講の意か……。
明治二十一年度以降、「国家学」が「政治学」科目の首座を占めるようになったのは何故か。また「政治学」の復活が三十一―四十二年度に限られ、しかもその大半が正則・邦語政治科に無関連であったことの理由などについては、この科目の重要性から言って関心が持たれるが詳らかにし得ない。ただ、課目表上の表面的な変化から政治学科独立当初の理念が後退したと見るのはいささか速断にすぎよう。何故なら、高田の「国家学」にしても、その実は「実相的国家論」であり、ラスキーやマッキーバーの多元的国家論の流れを汲むものであって、ドイツ流の国家学や国法学から全く区別されるべきものであったし(『社会科学と早稲田』四六頁、五〇頁)、また高田以外の担当者による「国家学」にしても、社会学を方法的基礎としたと言う点で同然であったと見られるからである(『社会科学と早稲田』七六頁、ならびに七一頁以下)。恐らくこの間の事情には、初代の「政治原論」担当者であった山田を学苑から失った後の後継者の問題があったのではあるまいか。そのことは、三十一―四十二年度の間における「政治学」の復活そのものにしても、その担当者が、二十一年度以降ほぼ一貫して「国家学」の担当者であった高田その人にまたなければならなかった事実が雄弁に語っていると思われるがいかがであろうか。
それとの関連でも注目されるのは、「政理学」と「政治哲学」とである。「政理学」は、明治十五―二十一年度の七年間だけ設置されている。明治十五年度の課程表では、単独の科目として記載されていたが、十六年度からは、課程表が類別を明確にするものである限り、常に「政治学」科目として扱われている。担当者は、十七年度が山田であること以外は明らかとならない。
「政治哲学」は、明治三十七年度に初めて課程表に現れる。担当者は上野貞正である。そもそも「政理学」というのは、明治の初めの頃、「ポリテイカル・フィロソフィ」の訳であった(『社会科学と早稲田』二一頁)ということであるから、「政治哲学」の出現は、前者の消滅十六年後における復活と言えないでもない。それ以上に、この科目との関わりで興味がひかれるのは、実は、担当者の一人であった浮田が、校務に忙殺される高田の後を継いで「政治原論」を担当したとされている事実についてである(『社会科学と早稲田』一一、五四頁)。課程表で見る限り、そのことは裏づけられない。「政治学」は、大正八年度までの間、明治四十二年度の高田で終っている。浮田はこの時期、高田と重なりながら、「国家学原理」(明治四十―大正二年度)と「政治哲学」を担当していた。高田の「政治学」が、今日でいうガバメントの研究に近く、実証的・目的的な内容のものであった(『社会科学と早稲田』一〇頁)ということから、浮田の「哲学」が、この科目の性格上、名目はともあれ「原論」的地位において受け止められていたと言うことであろうか。
設置後の継続は断層があり、明治三十六年度を除いて、四十―四十三年度と続き(担当・浮田)、その後五年間中断の後、大正五―八年度とまた復活している(担当・大山)。一貫して大学部に設置され、大正五―八年度の間は、明らかに「政治学」科目に包含されている。その余の設置年度は資料上不明であるが、同様と考えて差支えあるまい。なお、明治十九年度の出題資料中に、「政治哲学」という科目の記録がある。担当者は天野為之であった。
「政体総論」または「政体論」は、明治十五年度に始まり、二十五年度までで消滅している。十七年度は、山田の担当が明らかとなっている。山田の後は二十一年度まで高田が担当した。資料上不明の十五、十六の各年度も、山田が担当したと考えることを不都合とする、積極的な根拠はないように思える。
「立憲政体論」「立憲機関論」は、明治十五年度から三十四年度まで続いている。ただし、二十―二十二、三十二、三十三の各年度を欠く。三十四年度も、置かれていない(資料59「学校規則一覧」)。二十一年度以降は、「代議政体論」として、専ら英語政治科に置かれている。担当は、十八―十九、二十九、三十四の各年度が高田(ただし三十四年度は梅若の代講か)、三十一年度が浮田、資料上不明の年度については、少くとも三十年度までの間は、当時の状況から推して、高田と考えても誤りではあるまい。
「憲法要(総)論」も、明治十五年度の課程表では、単独科目として設置されていた。しかし、それ以後、十九年度までは「英国憲法」「米国憲法」、またはその双方に変っている。英国の立憲思想を我が国憲政の理想として標榜し、帝国大学のドイツ風に対するにイギリス的学風に政治学科の学問的基盤を立てようとした、小野梓、高田らの理念がここに端的に息づいているようにも思われる。憲法系の科目が法学として区分されていた時期に当たる。
明治二十年以降、大正八年まで、憲法系の科目は一貫して継続するが、科目の配当様式に基本的な変化が現れる。第一に、二十一年度以降、憲法系の科目は政治学科目に位置づけられている。ただ、三十二、三十五―四十三の各年度は資料上不明である。しかし、明治四十四―大正八年度も、引き続き政治学科目の扱いであることから推して、この期間を否定的に解する積極的理由はないと思われる。第二に、科目配当は、基本的に四つのパターンによっている。第一のパターンは、「憲法論」「憲法原論」「日本憲法」「憲法及議院法」「帝国憲法」「憲法論」などと科目名は変ったが、概ね、これらのどれかと、外国憲法の科目(「英国憲法」「米国憲法」または「各国憲法」)とを組み合わせ、これを二学年に亘って配当するもの。大体、三十四年度頃までがこれに属する。ただし、その時期の大部分は、邦語政治科・英語政治科両立時代と重なっており、この配当方式が両政治科に完全に一貫していたわけではない。どちらかと言えば、より前者に当てはまる。第二のパターンは、三十五年以降のことで、大学部と専門部との二元制の時期に当たる。大学部では、「憲法論」と、「日本憲法」または「帝国憲法」との、専門部では、「日本憲法」と、「各国憲法」との組み合わせ方式が採られている。前者は四十二年度まで、後者は三十七年度まで続いた。
第三のパターンは、第二パターンの専門部の場合に近い。「帝国憲法」と「比較憲法」とを組み合わせて二学年に配当するもので、大正四―五年度がこれに当たる(大学部、専門部共)。この型は、一時、明治二十八年度の英語政治科で採られた場合もある。第四のパターンは、憲法系の科目が「帝国憲法」に一本化された時期のものであり、明治四十三年度から大正四―五年度を除き、八年度まで続く。
資料上明らかにし得る担当者は、「憲法原論」または「憲法論」が高田(明治二十、二十五、三十六―三十八、四十―四十二の各年度)、「憲法及議院法」が高田(明治二十五、二十七、二十八の各年度)、「日本憲法」または「帝国憲法」が、高田(明治二十二、二十九の各年度)、織田(明治二十三年度)、本野一郎(明治二十四年度)、副島義一(明治三十一―三十六、四十―大正八の各年度)、竹井耕一郎(明治三十五年度)、美濃部達吉(明治三十七年度)、清水澄(明治三十八年度)の各講師、「英国憲法」が磯部醇(明治十七年度)、片山清太郎(明治十九―二十年度)、高田(明治二十一―二十三、二十七の各年度)、石塚英蔵(明治二十三年度)の各講師、「米国憲法」が高田(明治十八―二十年度)、「各国憲法」が高田(明治三十一、三十二、三十五―三十七の各年度)、「比較憲法」が美濃部(大正四―五年度)である。
「国法学」または「国法論」も、明治二十一年度に設置され(この年度は英語政治科のみに)、大正五年度に消滅するまで一貫して課程表上に地位を占め、政治学科目として類別された重要科目の一つと言える。尤も、明治三十二、三十五―四十三の各年度は、資料上その類別が明らかではない。しかし、この場合も、前記憲法系の科目と同様の理由によって、そのように見て差支えあるまい。明治二十九、三十、三十三の各年度には、この科目が、「国法原理」と「比較憲法」とを内容とするものであることが課程表に明示されている。この科目が消滅した時点で、「比較憲法」が新設されたのは、後者の独立を意味するものであろう。なお、三十七年度の大学部に限って、「公法」が置かれたことがある(担当・杉山直次郎)。
明治二十二、三十一―四十四、大正二、三の各年度は、専ら有賀によって担当されているが、明治四十五、大正元年度のみ副島に代っている。資料上明らかとならない明治二十一、二十三―三十年度も、有賀によったものと見て差支えあるまい。
創設期における科目検証の困難を感じさせるものに「行政学」と「行政法」がある。明治十五年度の前掲資料1には、「行政法」が独立科目として、「大意」(第二年配当)と「詳論」とに分けられて開設されている。ところが、本節の冒頭でも触れたように、資料3では、これは「行政学」となっている。しかし、同資料所掲の参考書から推すと、その内容は、どう見ても「行政法」と言わざるを得ない。十六年度になると、混迷は一層深まる。そこでは、これは法学科目の部に「行政法」として収まっている(資料6)かと思えば、他の二資料(資料5と資料7)では「行政学」として、しかも、共に「法学」または「法律学」の見出しの下に掲載されている。その上、十八年度には、課程表上には「行政法」(二学年に配当)が(資料12、13)、学年試験の出題では課程表にない「行政学」(出題者・天野為之)が出ている(資料14)といった具合である。初期の「行政学」と「行政法」とに関しては、一概にこれと定めがたい印象を受ける。見様によっては、本邦初の政治(経済)学科として、独立した当時の学科目編成に見られた試行錯誤の跡かもしれない。
当初、そのような経過を経て、「行政学」は、明治十九年度に政治学科目として扱われ、二十八年度まで続いている。ただし、最後の年度は、英語政治科のみの設置であった。担当は、十九年度が高田、二十一―二十三年度が有賀、二十四年度は織田となっている。その他の年度は明らかでない。
これに対して、「行政法」の軌跡はもっと多様に見える。前記した明治十五、十六、十八年度を別として、十七年度には「英国行政法」が、二十一年度には「日本行政法」が英語政治科に二学年に亘って配当された。更に二十二年度に至っては政治学科目に編入され、邦語政治科に設けられている。その後数年間は、設置されたり(二十五、二十七の各年度は、課程表にはないが出題資料に出ている)、されなかったり(二十三、二十四、二十六の各年度)を繰り返す。二十八年度以降は科目としても定着し(ただし二十八年度は邦語政治科のみに置かれる)、ほぼ四十三年度頃までには汎論、各論に分けられた上で(そのこと自体は、二十八、三十二、三十四―三十七の各年度も)配当も二学年に亘るというパターンが定型化し、大正八年度まで続く。担当者は、高田(明治十七年度「英国行政法」)、宇川盛三郎(明治二十一―二十二年度)、織田(明治二十五、二十七―三十一の各年度、三十二年度各論)、美濃部(明治三十一年度、三十六年度汎論、三十七―三十八年度)、竹井耕一郎(明治三十二、三十四各年度汎論、三十五年度各論)、一木喜徳郎(明治三十三、三十四の各年度)、副島(明治三十四年度「各論」、三十五、三十六、三十八、四十―四十二、四十三年度「汎論」「各論」四十四―大正八年度「汎論)、島田俊雄(明治三十五年度「各論」)、清水(明治三十六年度「各論」、大正二年度)、梅若(明治三十六年度「比較行政法」)、牧野英一(明治三十八年度「仏書」)、島村他三郎(大正三―八年度「各論」)。
明治十九年度に、「地方政治論」が政治学科目として設けられている。憲法制定や国会開設に先立つこと二年、早くも地方政治に関する科目が置かれたことは注目に価する。しかし、その内容も、担当者も、現在の資料によっては知るよしもない。明治十七年に加波山事件や秩父事件などが相次いだ背景を想起すれば、あるいは地方政治の実情をとも思わないでもない。しかし、政治(経済)学科創設初期の理念から推せば、英国の地方自治に関するものかとも思われる。(それかあらぬか、二十一年度の英語政治科には、「英国地方政治論」が「英国中央政府論」と並んで設けられている。共に担当者は不明。)そうとすればなおさらのこと、担当者は、恐らく高田であったであろう。ただ、この科目は一年限りで消滅している。
明治四十年度には、「自治行政及法制」が設けられた。系譜的には前記科目を継ぐものと考えられる。担当は井上友一である。この科目は、四十三年度の課程表では選択科目として扱われているから、資料上不明の前三年も、恐らく同様であったであろう。ところが、四十四年度には、一転して政治学科目に包摂されている。大正二年度以降は、八年度まで、科目名も「自治政策」と変ったが、随意科目とされた大正六年度を除き、八年度までずっと政治学科目として扱われている。担当は通して井上。
今日では政治学科における重要科目の一つに数えられる「政治学史」が初めて課程表上に現れたのは明治三十六年度。それ以降、大正七年度まで、一貫して継続している。八年度を欠くのは、この年度が、配当学年であった第二年を欠くためである。明治四十四年度以降、政治学科目として扱われるようになった。担当者は、浮田(明治三十六―三十八年度)、副島(明治四十―大正二年度)、大山(大正三―六年度)、高橋清吾(大正七年度)の各講師。
このほか、明治三十一年度には、英語政治科における政治学科目として、「英国膨脹論」(担当者不明)が、また邦語政治科の政治学科目として、「国会法」が二十一年度に(担当・高田)、「選挙法」(担当者不明)が二十四年度に、それぞれ設けられたほか、二十六年度には、「議院法」が邦・英両政治科に置かれている。「議院法」に関しては、これが政治学科目かどうか、担当者は誰かなど、いずれも資料上不明である。しかし、その前後の年度に置かれている「憲法及議院法」が、政治学科目であったことから推して、肯定的に考えてよいのではないか。担当者も同様高田であろう。
なお、明治二十一年度英語政治科に、「国会史」が政治学科目として置かれたことがある。担当者は不明であるが、当時の状況から推して高田か?
史学は、政治(経済)学科開設の当初から、一貫して課程表上に位置してきた科目の一つである。しかし、この部門で、政治学関連科目として早い時期から課程表に現れるのは、「憲法史」、なかでも「英国憲法史」である。これまた、政治学科創設の当初に、深くイギリスの立憲思想に学ぼうとした精神の現われであろうか。明治十六―三十四年度の間連続している。配当が二学年に亘る年度もあった。担当者は、明治十七―二十一、二十五、二十七、二十九の各年度が高田、二十二年度が坪内雄蔵、二十三年度が下山憲一郎、三十一―三十四年度が松平康国である。
史学の部で、課程表上、「近代史」または「近世史」が、十八、九世紀の「政治史」であることを明記したのは、二十五年度以降のことである。明治三十一年度から大正八年までは、科目名こそ「最近政治史」「最近時政治史」「近代政治史」「政治史」と変ることはあれ、一貫して続いている(ただしそのうち明治三十五―三十七年度は専門部のみ)。資料上不明の明治三十五―四十二年度を除き、四十三年度以降は、配当も複合的で、三学年または二学年に亘る場合もあった。課程表上、ほぼ一貫して史学科目として分類され、政治学科目として位置づけられたのは、僅かに四十四年度一ヵ年のみ。また、この時期の「政治史」は、明らかに今日の「西洋政治史」であって、「日本政治史」はまだ現れていない。担当者は、浮田(明治三十、四十―大正六年度)、有賀(明治三十一―三十八、四十一―四十四、大正二の各年度)、本多浅治郎(明治四十一年度)、煙山専太郎(明治四十三、大正三―八の各年度)の各講師。
明治十五年度に「外交学」が設けられていたのは、ひとつの注目に価する。恐らく、今日における国際政治学の先駆を成すものであろう。その意味では、創設時における政治学科指導陣の先見の明を垣間見る感がある。十八年度までこの形で続き、十九―二十年度には、「外交政略」と変っている。十七年度から二十年度にかけて、担当は高田であることが知られている。ところが、この科目は、二十一年度に「外交史」に変る。邦語政治科に設けられ、担当は同じく高田である。その後、六年間中断の後、二十八年度に、英語政治科に、二十九年度には、邦・英両政治科に、「近世外交史」として復活する。それから大正八年まで、一貫して続いた。尤も、その間、科目名は、「近世外交史」、「外交史」、「近時外交史」と変っている。その上、この科目が、英語政治科のみに設けられた年度(明治三十五―三十六年度)、二講座設定された年度(明治三十八年度)、そしてその一講座が「東洋外交史」(明治四十―四十二年度)、または「東洋近時外交史」(明治四十三年度)であった年度がある。なお、随意科目として、大正五年度に「近代外交論」(担当・島谷)、大正七年度に「最近支那対外関係」(担当・青柳篤恒)が設けられている。これらの科目が設けられた明治二十年代から大正にかけては、我が国が先進諸列強を相手に近代国家としての地歩を固めようと凌ぎを削っていた時代である。恐らく国民的人材の養成を意図する政治学科としても実践性の高い科目の一つだったに違いない。課程表上は、終始、独立科目としてであって、政治学科目として扱われたことはない。担当者は、「外交学」が高田(明治十七―十九年度)、「外交政略」が高田(明治二十年度)、「外交史」が有賀(明治三十一、三十二、三十五年度、英語政治科は三十六、三十七年度、専門部は三十八、四十―四十二の各年度)、「東洋外交史」が巽来次郎(明治四十―四十三年度)、「近時外交史」が有賀(明治四十四―大正三年度)、煙山専太郎(大正四―七)、信夫淳平(大正八年度)の各講師。
法学科目の中で、「万国公法」も、明治十五年度から大正八年まで一貫して続いた科目の一つである。その間、科目名は、「列国交渉法」「国際公法」と変ったし、明治三十五、三十六の両年度は、専門部のみの設置であった、明治二十八―三十年度は戦時、平時の別が明示されている。担当者は、山田喜之助(明治十七年度)、三宅恒徳(明治十八―二十年度)、三崎亀之助(明治二十一年度)、鳩山和夫(明治二十二―二十三年度)、秋山雅之介(二十四年度)、中村進午(明治二十七、二十八、三十三―大正八の各年度)、有賀(明治二十一、三十二年度)の各講師。
「原書研究」が継続的に設けられるようになったのは、四十一年度を出発点としている。その後、資料上不明な大正二年度を除けば、四十三年度から大正八年度まで、大学部で三学年を通して配当されている。これに対して、専門部には「英語」が置かれていて、「原書研究」はない。しかし、その内容は、「原書研究」と同様の「ポリチカル・クラシックス」を含んでいたり、担当者も同一人であったりすることが多い。違いは名目的であったのかもしれない。配当は、不明の大正二年度を境に、前が大学部と同パターンで、後が二学年となっている。
「原書研究」の設置は、実は、ある意味で、政治(経済)学科創設以来宿年の課題に対する一つの解決であったとも見れる。というのは、学苑が創設された時の一大主張は、「泰西専門の学」を邦語を以て教授することにあった。それが外国語を以てされることを通常とする当時にあっては、このことは、今日から計り知れない変革事であったと思われる。他方、「泰西専門の学」の蘊奥を探らしむるために必須の語学力殊に英語力をいかに養成するかは、小野、高田をはじめとする当時の政治学科首脳陣の頭を離れなかった一大課題であった(本史 第一巻 四六四、五六三頁)。創立の当初から、英語を以て専門の学を講ずる英学科(独立の学科ではない。後、英学兼修科、更に兼修英語科と改まる)を、正則・政治(経済)学科に附置してこれを有志学生に開放したのも、また、明治二十一年度に至って、独立の英語政治科を新設したのも、すべては、その永年に亘る解答の努力であったと思われる。明治三十五年、学苑が大学部・専門部制を採るに至った時点で、英語政治科の理念は大学部に引き継がれた。「原書研究」が課程表に登場したのは、その一つの結論と言えよう。
「原書研究」の担当者は、吉田巳之助(明治四十一―四十五、大正三の各年度)、梅若(明治四十一―四十五、大正四―六の各年度)、永井柳太郎(明治四十五、大正三―五の各年度)、浮田(明治四十五・大正元、三―七の各年度)、大山(大正六年度)、高橋(大正七―八年度)。
なお、「原書研究」の開設に先立ち、明治三十七―四十年度に亘って、「名著研究」が置かれている。その内容は詳らかにし得ないが、恐らく、「原書研究」の先駆的科目ではなかったかと推察される。担当は浮田である。
明治二十一年度に、高田の「国会法」と並んで「国会法演習」が設けられた。国会開設に先立つこと二年であった。高田の強い主張によったものらしい(本史 第一巻 七七〇頁)。最初の二年は、課程表上、「討論」の見出しの下で、「討論」「国会法演習」として、共に邦語政治科のみに設けられたものである。尤も、十九年度にも、「会議討論」という科目が同科に置かれたことがある。しかし、その内容は明らかではない。二十四年度以降は、「国会演習」に一本化され、二学年に配当されるようになった。二十八年度から、英語政治科にも置かれ、そのままの形で大学部・専門部制に移行する直前(明治三十四年度)まで続いている。ただ、これがいつ消滅したかはあまりはっきりしない。本史第一巻によると、三十五年度に専門部、四十年度に大学部と、それぞれ置かれていたことになっている(三九二頁)。これをとれば、四十年代まで続いたということになる。
「演習」といっても、この科目は、今日のそれではなく、実は「擬国会」であった。本史第一巻によれば(七七六頁以下)、第一回目を実施した後、二十二―二十三年度は、実際には行われず、二十四年度から本格化したようである。議長、副議長、政府委員等の役職には、高田をはじめ学苑政治学科のそうそうたる諸教授が、議員には、第二、三年の学生が中心となったが、時には、かつての政府閣僚経験者や、現職の衆議院議員らも参会することがあるという盛大さであった。討論の議題も、「貨幣問題」「民法修正問題」、軍縮などの「対外関係問題」「選挙法改正問題」など、当時の重要な政治課題や政策問題が取り上げられている。来聴者は、学生に止まらず、時の国会議員や市民などで大講堂が溢れたと言う。まさに、政治学科の特色を遺憾なく発揮し、学苑の存在を世上に轟かした、「早稲田名物」の異色科目であった。
今日の演習の先駆は、明治三十七年度の「国際法実習」(担当・中村)に始まる。翌三十八年度には、これに「国法行政実習」(担当・美濃部)が加わった。いずれも大学部のみに設置され、大正四年度まで続いた後に、セミナリーに引き継がれてゆくことになる(「国法行政法演習」は五年度まで随意科目として残る)。ただし、三十九年度は、資料を欠き不明なのと、「国法行政実習」は、四十年度以降、「国法行政法実習」と科目名が変っている。
大正五年から、大学部において、セミナリーが発足する。五、六年度と「政治学研究」が大山、また「国際法研究」が中村、七年度には「国法行政法研究」が副島、「国際法研究」が中村、更に八年度には「政治学、国法及国際法研究」が高橋、副島、中村、浮田らの諸講師によって担当されている。なお、明治二十四―二十六年度に、英語政治科に、「研究会」という科目が設けられた。これを、今日のゼミナールの先駆と推定する説もある(本史 第一巻 六九六頁)が、内容については詳らかにし得ない。
創設当時、学生達を大いに感動させた小野の「国憲汎論」に関する名講義は、実は、科外講義の形で提供された。それが設定されたことを明らかにする最初の記録は、明治二十五年度における「各学部委員および講師会決定」であったと言われている(本史 第一巻 六八五頁)。しかし、資料的にはそれより早く、十七年度の「講師受持課目新聞記事」にそのことを示す記載がある(資料10)。それには、各学科の科目と担当講師名とを列記した後、「右の外…小野梓…も…日本財政論等を臨時科外に講演せられ且毎月一回諸名士を聘して学術上の講義を開かるると云ふ」と書かれている。ここには直接「国憲汎論」を示す語はない。しかし、「日本財政論等」に含まれていることは推察に難くない。科外講義については、その点を明らかにするに止める。
また、きわめて特異な科目例として明治四十二年度から二ヵ年間、随意科目として、陸・海両軍の「軍政学」が設けられたことがある。政治経済の学問をする者は一般の人以上に軍政のことを心得る必要がある、というのが設置の趣旨であった(当時の学長高田の弁。本史 第二巻 四二二頁)。講師として、陸軍中佐田辺元治郎と海軍少将成田勝郎が委嘱された。この異例な科目の設置をどう評価するかは一つの問題であろう。しかし、「骨の髄からのリベラリスト」高田(小松芳喬「政治科今昔」、新庄編『回想・早稲田大学一〇〇年』一一〇頁)の意図が、軍に対するシビリアン・コントロールの国民的見識を養成することにあったと見るのは筆者の主観にすぎるであろうか。
付 記
資料は、文中に挙げたもののほか、主として『政治経済学部教員学課担任名簿――自明治三十五年至昭和十七年』(早稲田大学大学史編集所)に拠った。
なお、学年暦の呼称は、当時、一年度が九月に始まり翌年八月までで、正規には、例えば明治二十―二十一年度と呼ぶのが通例であったが、本稿では、便宜上、これを二十年度というふうに省略し、すべてその例によった。
大正九年、「新大学令」が施行されて、それまでの大学部政治経済学科は政治経済学部になった。と同時に、政治学科と経済学科との区別が明らかにされた。しかしカリキュラムについて、両学科に共通の必修科目が、七科目にも及んでいた。それぞれの学科の必修科目は三年間に十八だったので、半数に近い。そして、共通の必修科目のうちの六つまでが、第一学年に配当されていた。この六科目は、「政治学」「憲法」「経済学原理」「政治史」「民法」「刑法」である。残る共通の必修科目は「財政学」で、第二学年に配当されていた。第三学年には、そうした共通の必修科目は、配当されていない。
政治学科も経済学科も、政治経済学部を形作る二つの学科であることを前提に、だから同じ学部に属するという共通の基盤作りを先ず……というのが、このようなカリキュラム編成を考えさせたのだろう。こうした共通の基盤の上に、政治学科、経済学科のそれぞれの専門の勉強が期待されたに違いない。政治経済学部という特徴的なあり方が、そのようにして表わされた。
このようなカリキュラム編成の基調は、そのまま昭和二十四年に新制大学が発足するまで続いた。ほぼ三十年である。この間、大正デモクラシー、経済不況、戦争、敗戦、占領という激動に大学も揉まれ、それの影響がカリキュラム編成にも影を落とした。それでも、政治経済学部の伝統はカリキュラム編成から消えなかった。政治学科に焦点を合わせて概観してみよう。
政治学科の必修科目は、第一学年については両学科に共通の必修科目のほか、「政治学」という科目の「英語原書講読」があるだけだった。このような「原書講読」は、第二学年、第三学年にもあって、しかしこちらの方は「特殊研究」という科目名になっている。この違いの理由は何であったのか、よく分らない。同じように「原書講読」であっても、一年の場合と上級学年の場合とでは教え方が違っていた、ということなのだろうか。だがどう見ても不自然である。そのためもあったのだろうか、五年後の大正十四年に、第一学年のこの科目も「特殊研究」と名称変更されて統一された。特殊研究の担当者も、年輩の教授だけでなく、若手の専任教員も当たるようになった。
必修科目は、第二学年には前記の財政学と特殊研究のほか、四科目が配当されていた。すなわち、「国法学」「行政法総論」「政治学史」「最近政治史」、の四科目である。昭和二年、「国際政治論」の科目が新設されて、これらに加えられた。また、きわめて稀に、「政治学研究」という科目が置かれたことがあった。大正十三年と十四年の二年間と、昭和三年から五年の三年間、それから戦後の昭和二十三年との三度である。因に、大正の時と戦後の時の担当者は大山郁夫で、昭和初期の時の担当者は杉森孝次郎だった。
第三学年の必修科目は、前記の「特殊研究」のほか、「政治哲学」「自治政策」「近時外交史」「国際公法」の四科目であった。
政治学科のこのような必修科目も、両学科に共通の必修科目の場合と同じように、大体そのまま戦後に及んだ。ただし、科目の名称がずっと初めのままというのは少なかった。この三十年間、名称の変更が全くなかったのは、「憲法」「政治学史」「政治哲学」「財政学」だけだった。昭和初期に新設されたものを含めても、「国際政治論」が数えられる程度である。ほかの科目については、少しずつではあったが、何らかの手直しが施された。
科目の新設や変更は、昭和の初めと戦争末期と敗戦直後の三つの時期に目立った。だが、それぞれに特徴を異にしていた。
昭和初めの時期は、新進気鋭の若手研究者が次つぎと学部教師陣に加わったことが切っ掛けになっていた。既に述べた「国際政治論」の新設(昭和二年)は別として、昭和四年の「日本政治思想史」(内田繁隆)と「比較憲法」(天川信雄)の新設、昭和七年の「日本政治史」(内田繁隆)の新設、昭和八年の「欧米政治組織」と「行政学」(いずれも吉村正)の新設は、それに当たる。
こうした科目の新設に併わせて、科目の名称変更や衣替えも、いろいろと試みられた。「政治学」が「政治学原理」に(昭和四年)、「国法学」が「公法学原理」に、できて間もない「比較憲法」が「公法学史」に、「最近政治史」が「英国憲政史」に、「自治政策」が「政治政策学」に、「近時外交史」が「外交史」に(昭和七年)、という具合に。
昭和七年に衣替えになったこれらの科目は、「外交史」(昭和十四年に廃止の)と「政治政策学」を除いて昭和十九年に廃止された。同じ年、「政治哲学」と「欧米政治組織」が廃止され、翌二十年には「行政学」が廃止された。
昭和十九、二十年のこうした措置は、戦争の遂行と関連があったのだろう。廃止のあとに置かれた科目が、それを暗示する。「東亜政策」「戦時政治論」「戦時財政論」「地政学」「戦時行政法」といった科目が新設された(昭和十九年)。それと相補う(?)ようにして科目の名称変更があった。すなわち、「国際公法」が「国際法」に、「行政法総論」が「行政法」に、「政治学原理」が「政治学原論」に、「経済学原理」が「経済学原論」に、「日本政治思想史」が「日本政治経済思想史」に。なお、二年前の昭和十七年には、「政治史」が「西洋政治史」に名称変更されていた。
敗戦は、昭和十九年に新設された〝戦時〟科目を廃止させた。代って昭和二十年十月には「外国研究」という一連の科目が出現した。外国といっても戦争中の四連合国で、「米国研究」「支那研究」「英国研究」「ソ連研究」という四科目である。このほか、新設科目として、「地方行政研究」と「政治制度論」が、翌昭和二十一年からは「社会思想研究」が現われた。因に、「政治制度論」は昭和十八年に設けられ、その年だけで休講になった「政治制度史」の改装新版であった。また、昭和二十二年には、「政党及官僚論」という科目が置かれた。敗戦直後の特徴は、このような形でカリキュラム編成に現われた。
政治学科の科目は、このような移り変りを見せた。特に変化の激しかった三つの時期に焦点を合わせたわけであるが、それぞれの時期は学部の事情だけでなく、大正末期以来の歴史の激変の時期と対応していた。
これらの科目の移り変りとともに、特記すべきは、「政治学特殊研究」の充実である。昭和に入って、英語「原書講読」が複数になったほか、ドイツ語「原書講読」とフランス語「原書講読」とが置かれた。これらは戦後、「政治学外国書研究」に変り、英・独・仏の外国書研究に加えて、露語と華語の「外国書研究」が増えた。既に触れた敗戦直後の「外国研究」では取り上げられていないドイツとフランスが、「外国書研究」に姿を残している。国際社会の勝敗も、学問の世界には及ばない一つの例だと言ったら、言い過ぎだろうか。
カリキュラムは、単に選ばれた科目の特徴によって意味づけられるだけでない。それぞれの科目の担当者が誰であるかによってカリキュラムの特徴が決まってくる。政治経済学部が政治学科と経済学科に共通の必修科目を多く持つと言うだけでなく、科目の担当者の早稲田的特徴が早稲田の政治学科の伝統の形成に大きな役割を演じてきた。ここは担当者の学問的特徴について書く場ではない。せめて担当者の流れを追って、それぞれの科目の内容的特殊の理解に役立てたい。
大正九年から敗戦直後まで引き続いて同一人が担当した科目は、唯一つ「政治史」(「西洋政治史」)である。煙山専太郎が担当者で、大正十一年度だけ代講された以外、二十七年の間、「政治史」を講義し続けた。昭和二十二年度で退任した後、市村今朝蔵に引き継がれた。
煙山は、「政治史」のほか、「最近政治史」(のち、「英国憲政史」)の講義を受け持った。この場合も、大正十一年度には代講者(浮田和民)を頼った。だが、担当し続けたのは昭和十二年度までで、昭和十三年度から大西邦敏が引き継いだ。科目名が「英国憲政史」と改まってから七年目のことである。煙山は「英国憲政史」の科目担当を辞めたが、同じ年度(昭和十三年度)から「外交史」を担当し、敗戦後の退任の時まで受け持った。
「外交史」は、初め「近時外交史」と称し、信夫淳平が昭和十二年まで担当した。この間、昭和二年新設の「国際政治論」も受け持ち、昭和十二年までその任にあった。
「国際政治論」は、昭和十三年からは川原篤の担当となり、昭和十八年度に及んだ。ところが、病を得て担当できなくなったため、昭和十九年度には一時、煙山が代講したあと、昭和二十一年度には神川彦松を迎えた。神川が公職追放令の適用を受けたので、翌年度は休講になり、昭和二十三年度、石田栄雄が新任した。
信夫は、昭和十二年度で「国際政治論」「外交史」の担当を辞めたが、二年経って昭和十五年度に、今度は「国際公法」の担当者として復帰した。「国際公法」は大正十一年以来、この年の前年度まで中村進午がずっと担当してきた科目だった。信夫はそのあとを三年間だけ受け継いで、昭和十八年、川原篤に担当を委ねた。川原の担当はこの年だけで、翌十九年度からは水垣進の担当となり、科目名も「国際法」に改まった。水垣は昭和二十一年に急逝したので、昭和二十二年からは細野軍治がその跡を襲った。
今まで述べた科目のほかに、同じ担当者が長かった科目を挙げてみよう。
十五年以上同じ担当者で担当された科目はと言えば、「政治学史」「自治政策」(のち「政治政策学」)、「日本政治思想史」(戦争末期に一年だけ、「日本政治経済思想史」、敗戦後直ちに旧名称に復した)、「日本政治史」「行政法総論」(戦争末期以降、「行政法」)、「民法」「政治学原理」がある。
「政治学史」と「自治政策」とは高橋清吾が担当して、前者は大正九年以来十九年間、後者は大正十一年以来十七年間勤続した。最後の年度は昭和十三年だった。「政治政策学」は、この年に廃止されたが、「政治学史」は五来欣造が引き継いだ。五来はその後三年間、また一年置いて昭和十八年度の担当者だった。そのあと、昭和十七年度の担当者だった原田鋼が担当し、終戦を迎えた。敗戦直後の昭和二十年十月からは蠟山政道が担当者に迎えられ、公職追放になってからは、昭和二十二年以降、市村今朝蔵によって受け継がれた。
「日本政治思想史」と「日本政治史」は、内田繁隆の担当である。前者は昭和四年から昭和二十一年まで十八年間、後者は昭和七年から十五年間、続けられた。いずれも昭和二十二年度は休講になり、昭和二十三年度、「日本政治思想史」は服部弁之助、「日本政治史」は深谷博治が担当者になった。
「行政法総論」は、天川信雄が十五年間担当した。しかし天川が担当したのは昭和六年からで、それまでは副島義一が大正九年から十年間(大正十三年度は休講)担当していた。天川は昭和二十年に急逝したので、昭和二十一年度は中野登美雄が、その翌年は田上穣治が、そして昭和二十三年度は佐藤立夫が、目まぐるしく代った。
「民法」は、磯谷幸次郎が昭和三年から昭和十七年まで十五年間担当した。この科目は、大正九年に「民法総則」として発足し、遊佐が担当したが、二年後に「民法」と改称されて担当者は牧野菊之助になり、昭和二年まで六年間続いた。磯谷のあと、昭和十八年には林徹が、昭和十九年には外岡茂十郎が、昭和二十年秋からは野村平爾が、そして昭和二十二年度からは薬師寺が担当した。
「政治学原理」も、五来欣造が十五年間担当した。昭和三年から昭和十八年まで、昭和六年度だけ杉森孝次郎が代講して続いた。この講座は初め浮田和民の担当だった。大正の末に大山郁夫が担当したが、一年限りで再び浮田の担当になった。だが浮田も一年だけの担当で、昭和三年から五来の担当に移った。五来のあとを引き継いだのは、吉村正である。
次に同じ担当者が十年前後続いた科目を示せば、「行政学」「欧米政治組織」「公法学原理」」公法学史」政治哲学」それに「憲法」がある。これらは、「憲法」以外は、いずれも敗戦までに姿を消してしまった科目である。
「行政学」と「欧米政治組織」は、昭和八年以来、吉村正が担当して、前者は昭和十八年まで十一年間、後者は昭和十九年まで十二年間受け持った。
「公法学原理」の担当者は中野登美雄で、昭和七年から昭和十八年まで十二年間、「公法学史」の担当者は天川信雄で、同じ期間、同一の担当者だった。「公法学原理」はもともとは「国法学」として講じられていたもので、中野が大正十三年から昭和六年まで担当していたのだ。「国法学」の中野の前任者は大山郁夫だった。また、「公法学史」は「比較憲法」の改称で、これもそれまで三年間、天川信雄が担当していた。
これらの四科目は、それぞれ担当者(吉村、中野、天川)と深く結びついていたようで、担当者が担当を辞めると同時に、科目もなくなった。
「政治哲学」は、大正九年以来長い間(十一年間)、五来欣造が担当していた。五来は「政治学原理」の担当者になってからも三年間は、「政治哲学」をも担当して、昭和六年度からは杉森孝次郎に担当を委ねた。杉森は、以後昭和十八年まで十三年の間、「政治哲学」を講じた。
終りに、「憲法」。この科目は、同じ担当者が比較的に長く、しかも平均して受け持った科目で、初め副島義一が昭和五年まで十一年間、次いで野村淳治が昭和十四年まで九年間、更に中野登美雄が昭和二十一年まで七年間、その後は大西邦敏、という具合に担当は安定していた。
なお、「経済学原理」と「財政学」については、両学科に共通の必修科目であったが、経済学科のカリキュラム編成の項を参照されたい。
昭和二十四年における新制大学の発足は、当然のことながら、カリキュラムの大幅な改編を伴っていた。そしてその特色は、広い教養を持った優れた社会人を育成するという目的に従って教養科目が重視されたこと、学年制にかわり単位制を採用することによって学生の自由意志を尊重し、選択の幅を広げたことにあったと言える。しかしそれらの詳論は他の部分に譲り、ここでは第一政治経済学部の政治学科における専門教育科目の編成とその変遷を辿っておきたい。(新制大学の発足とともに、勤労学生に門戸を開くという目的を持って第二政治経済学部が開設された。しかし昭和四十一年以降の学生の募集停止に至るまで、その学科目編成は大網において第一政治経済学部と同一であったがゆえ、ここでは割愛することにしたい。)
さて、政治学科の専門教育科目は、他の学科と同じく、その学科の学問上の重要度に応じて、必修科目と選択科目に分けられ、先ず第二年度と第三年度に配当された(昭和二十四年度の開設は第三年度生までであった)。第二年度の必修科目は、「政治学原論」(吉村正)、「経済学原論」(酒枝義旗)、「憲法」(大西邦敏)、「西洋政治史」(市村今朝蔵)の四科目、選択科目は、「西洋経済史」(小松芳喬)、「社会学原理」(武田良三)、「民法」(千種達夫)の三科目であった。また、第三年度の必修科目は、「政治学史」(市村今朝蔵)、「行政学」(吉村正)、「日本政治史」(深谷博治)、「外国書研究」(英書―後藤一郎、独書―佐藤立夫、仏書―井伊玄太郎)の四科目、選択科目は、「比較政治制度」(大西邦敏)、「日本政治思想史」(服部弁之助)、「外交史」(石田栄雄)、「貨幣及銀行論」(中村佐一)、「国際経済論」(中島正信)、「国際法」(細野軍治)、「行政法」(佐藤立夫)、「刑法」(江家義男)の八科目であった。
次いで、昭和二十五年度に設置された第四年度の科目においては、必修科目は、「国際政治論」(大山郁夫)、「財政学」(時子山常三郎)、「外国書研究」(英書―吉村健蔵、独書―佐藤立夫、仏書―井伊玄太郎)の三科目、選択科目は、「地方行政」(弓家七郎)、「社会政策」(平田冨太郎)、「経済政策」(出井盛之)、「金融経済論」(中村佐一)、「経済機構論」(杉山清)、「近代社会思想」(井伊玄太郎)、「労働法」(吾妻光俊)、「経済地理」(佐藤弘)、「租税論」(時子山常三郎)、「演習」(吉村健蔵、後藤一郎、石田栄雄、石川準十郎、服部弁之助)の十科目であった。
以上が新制大学発足当初の政治学科の専門教育科目と担当者の構成であり、必修科目十一科目、選択科目二十一科目よりなっていた。卒業に必要な専門教育科目の単位数は、必修科目十一科目四十四単位、選択科目十科目四十単位、計八十四単位であった。因に、単位の計算は、一科目四単位であり、週二時間の通年制であった。
昭和二十四、二十五年度に亘って編成され実施されたカリキュラムは、専門教育科目に関しても、その基本的な骨組みにおいては変更されることなく、昭和四十年度まで継承されたが、その間における変化を、(ⅰ)科目の増設および配当年度の変更、(ⅱ)卒業必要単位数の変更、(ⅲ)担当者の変更、に分けてまとめると次のようになる。
(ⅰ)科目の増設および配当年度の変更
先ず、必修科目は、昭和二十七年度に「外国書研究」が新たに第二年度にも配当され、計十二科目となった。次いで、昭和二十九年度に、「行政法」が選択科目から必修科目に変更されたが、同時に第四年度配当の「外国書研究」が選択とされたため、必修科目数には増減はなかった。しかし、昭和三十四年度には「外国書研究」が必修科目として第一年度にも増設配当されたため、必修科目数は計十三科目となった。
一方、選択科目は、昭和二十七年度に「労働問題」(藤林敬三)が第四年度配当科目として、昭和三十七年度に「都市政策」(磯村英一)が第三年度配当科目として増設された。
次に配当年度の変更については、先ず昭和二十七年度に「経済地理」が第四年度から第二年度に、「労働法」が第四年度から第三年度に移され、次いで昭和二十八年度に「日本政治思想史」、昭和二十九年度に「政治制度論」(昭和二十六年度より「比較政治制度」が「政治制度論」となった)が、それぞれ第三年度から第四年度に移された。更に昭和三十四年度に、「社会政策」が第四年度から第三年度に移され、「経済機構論」が廃止されている。「演習」は、当初は第四年度配当科目であったが、昭和二十七年度より、第三年度後期と第四年度前期に亘って履修されることになった。
(ⅱ)卒業必要単位数の変更
以上の結果、専門教育科目の卒業に必要な単位数にも多少の変化が見られた。すなわち、昭和二十四年発足当時は、八十四単位であったが、昭和二十七年度に必修科目が一科目四単位増え八十八単位となり、更に昭和三十四年に同じく必修科目が一科目四単位増え、計九十二単位となった。
(ⅲ)担当者の変更
この間、担当者にもさまざまの変更が見られた。海外研究などによる一時的な代講を除き、主なものを挙げるならば次のようになる。先ず必修科目のうち、「政治学原論」は昭和三十八年度は堀豊彦、三十九、四十年度は松平斉光、四十一年度は服部弁之助が担当している。また、「経済学原論」は昭和四十一年度より伊達邦春が担当している。「西洋政治史」は昭和二十六年度より松本馨が、「政治学史」は同じく昭和二十六年度より堀豊彦が担当している。更に、「行政学」は昭和三十八年度より後藤一郎が担当し、「日本政治史」は、昭和二十八年―三十六年度内田繁隆、三十七、三十八年度中村尚美、そして三十九年度以降は兼近輝雄がそれぞれ担当している。また、「国際政治論」は、昭和二十七年度より吉村健蔵が担当している。「外国書研究」に関しては、英書担当者として、昭和二十七年度に石川準十郎、内田繁隆、二十八年度に清水望、三十三年度に兼近輝雄、堤口康博、福田三郎、三十四年度に小林昭三、三十七年度に内田満、四十年度に大谷恵教、北岡勲、日下喜一、霜田乾夫(美樹雄)、浜地馨が加わっている。また独書担当者として、昭和二十七年度に水垣進、二十八年度に清水望、三十三年度に堤口康博、小林昭三が加わり、仏書担当者として、昭和三十三年度に兼近輝雄が加わっている(「外国書研究」は担当科目、担当学年の変更が多い。)
次に、選択科目について見るならば、「民法」は昭和三十―三十二年大江保直を除き千種達夫が担当し、「経済地理」は昭和三十八年より田中薫が担当している。そして「貨幣及銀行論」は昭和三十六年度より堀家文吉郎が、「国際経済論」は昭和三十六、三十七年度出井盛之、三十八―四十一年度渡部福太郎、四十二年度以降は岡山隆が担当している。更に、「国際法」は昭和四十一年度より入江啓四郎が、「刑法」は昭和三十三年小泉英一を除き三十四年まで江家義男、三十五年度より斉藤金作が担当している。また、「日本政治思想史」は昭和二十八―三十六年度は内田繁隆、三十九年度より松本三之介が、「政治制度論」は昭和三十七年より清水望が、「地方行政」は昭和三十二年度より後藤一郎が担当している。そして「経済政策」は昭和二十七年度より小松雅雄、三十六年度長守善、三十七年度加藤寛、三十八、三十九年度西宮輝明、四十年度より気賀健三が担当し、「金融経済論」は昭和二十七年度より堀家文吉郎、三十二年度および三十六年度以降は鶴岡義一が、「労働問題」は昭和三十年度より平田冨太郎が、「租税論」は昭和二十七―三十五年度阿部賢一、昭和三十六年度時子山常三郎、昭和三十七年度より平田寛一郎がそれぞれ担当している。
最後に「演習」の担当者としては、昭和二十六年に井伊玄太郎、佐藤立夫、二十七年度に内田繁隆、二十八年度に松本馨、三十年度に清水望、三十四年度に兼近輝雄、小林昭三、堤口康博、福田三郎、三十五年度に堀豊彦、三十六年度に大西邦敏、三十七年度に吉村正、三十九年度に内田満、四十一年度に植田捷雄、大谷恵教、霜田乾夫(美樹雄)、矢部貞治、四十二年度に藤原保信が加わっている。
専門教育科目のカリキュラムが大幅に変更され実施されたのは、昭和四十一年度の入学生からである(それゆえ昭和二十四年度の場合と同じく、それ以前の入学者は旧カリキュラムで履修している)。そしてそれは政経学部における新聞学科および自治行政学科の学生募集の停止の時期に一致する。
ところで、新しいカリキュラムの特色は、これまでの必修制を廃止して、すべての科目を選択制にしたことにあるが、この場合科目の性質に応じて、全体をA・B・C・D群の四群に分け、それぞれの中から所定の単位数に相当する学科目を履修することにしている。
先ず、A群の学科目は、政治学科に最も関連の深い学科目であり、それには、第二年度配当の「政治学原論」「憲法」「行政学」「政治学史」「西洋政治史」、第三年度配当の「国際政治学」「比較政治制度論」「日本政治史」「行政法総論」「地方行政」、第四年度配当の「現代政治学説」が含まれている。
次に、B群の学科目は、A群に次いで政治学科に関連の深い学科目であり、これには、第三年度配当の「政治過程論」「外交史」「国際法」、第四年度配当の「政党論」「日本政治思想史」「国際機構論」「行政法各論」、および第三年度の後期から第四年度の前期にかけて履修する「演習」が含まれている。
更に、C群の学科目は、経済学科のA、B両群の学科目、かつての新聞学科、自治行政学科の配当科目のうち、存続が適当と認められた学科目などであり、これには、第二年度配当の「理論経済学Ⅰ」「経済学史」「統計理論」「日本経済史」「西洋経済史」「社会学原理」「近代社会思想」「社会心理学」「マス・コミュニケーション発達史」「民法」、第三年度配当の「理論経済学Ⅱ」「貨幣理論」「現代経済学説」「社会主義経済学」「財政学」「社会政策」「経済地理学」「経営学」「マス・コミュニケーション理論」「社会調査」「商法」、第四年度配当の「国際経済学」「経済政策」「労働経済学」「金融経済論」(ただし昭和四十四年度より第三年度配当)、「日本経済論」「財政学各論」「地方財政論」「都市問題」「農村問題」「マス・メディア論」「刑法」「労働法」が含まれている。
そして、D群の学科目は、政治学関係の「外国書研究」であり、これは第一―三年度にそれぞれ配当されている。
卒業に必要な専門教育科目の単位数は、A群十科目四十単位、B群六科目二十四単位、C群七科目二十八単位、D群八単位、合計百単位であった。(その他、「その他科目」の十二単位に専門科目からの単位を含めることができることになっていた。)しかしこれには学生の負担が重すぎるという批判があり、その後減ぜられていった。すなわち、先ず昭和四十五年度入学生からA・B両群からそれぞれ一科目四単位ずつ減ぜられて、計九十二単位となり、更に昭和五十三年度入学生からA群から一科目四単位減ぜられて、計八十八単位となり、現在に至っている。(なおB群科目の「演習」は当初四単位の計算であったが、昭和五十二年度より八単位とされた。)
新しいカリキュラムにおける科目担当者は、次のようになっている。
先ず、A群科目のうち、第二年度配当の「政治学原論」は昭和四十二―四十八年度後藤一郎、四十九年度より内田満(五十二・五十三年度は内山秀夫)が担当している。次に、「憲法」は昭和四十二―四十四年度大西邦敏、四十五年度小林昭三、四十六―四十九年度清水望が担当したのち、五十年度以降は小林昭三と清水望が二年ずつ交互に担当している。更に、「行政学」は昭和四十二―五十年度三宅太郎、五十一年度より片岡寛光(五十六・五十七年度は浜地馨)が、「政治学史」は昭和四十二―四十四年度堀豊彦、四十五―四十八年度服部弁之助、四十九年度より藤原保信(五十三年度大谷恵教、五十六年度渋谷浩)が、「西洋政治史」は昭和四十二年度より福田三郎(四十四年度は松本馨)が担当している。
次いで、第三年度配当の「国際政治学」は昭和四十三年度より吉村健蔵が、「比較政治制度論」は昭和四十三―四十六年度清水望、四十七、四十八年度小林昭三、四十九―五十一年度清水望ののち、五十二年度より小林昭三と清水望が二年ずつ交互に担当している。また、「日本政治史」は昭和四十三年度より兼近輝雄(四十五年度は深谷博治)が、「行政法総論」は四十三―五十六年度佐藤立夫、五十七年度堤口康博が、「地方行政」は昭和四十三―四十八年後藤一郎、四十九―五十二年度高木鉦作、五十三年度より寄本勝美が担当している。
更に、第四年度配当の「現代政治学説」は昭和四十四年より今日まで日下喜一が担当している。
次に、B群科目について見るならば、第三年度配当の「政治過程論」は昭和四十四年度より内田満が、「外交史」は昭和四十三―五十三年度石田栄雄(五十年度と五十二年度は内山正熊)、五十四年度以降は内山正熊が、「国際法」は昭和四十三年―四十八年度入江啓四郎、四十九―五十一年度中村洸、五十二年度以降は皆川洸が担当している。また、第四年度配当の「政党論」は昭和四十五―四十九年度内田満、五十一年度以降は岡野加穂留が、「日本政治思想史」は昭和四十四―四十九年度松本三之介、五十一年度以降は河原宏が、「政治機構論」は昭和四十四―五十五年度吉村健蔵、五十六年度より鴨武彦が、「行政法各論」は昭和四十四年度より堤口康博(四十九年度は佐藤英善)がそれぞれ担当している。更に、第三年度および第四年度配当の「政治学研究」は、昭和四十三年度より内田満、小林昭三、岡部史郎、松本馨、藤原保信、佐久間彊、片岡寛光、寄本勝美、渋谷浩、岡野加穂留、佐藤立夫、鴨武彦、穴戸寛、阪中友久が随時担当している。また第三年度後期と第四年度前期にかけての配当の「演習」の担当に関しては、昭和四十三年度に伊藤道機、勝村茂、安井俊雄、四十四年度に佐久間彊、四十五年度に岡部史郎、片岡寛光、浜地馨、四十六年度に寄本勝美、四十七年度に渋谷浩、四十八年度に河原宏、四十九年度に鴨武彦、五十三年度に関嘉彦、五十四年度に大畠英樹、五十六年度に大井孝が新たに加わっている。
更に、C群科目については、第二年度配当の「社会学原理」は昭和四十二、四十三年度武田良三、四十四―四十六年度井伊玄太郎、四十九―五十一年度秋元律郎、五十二年度より寿里茂(五十五年度は柳井道夫)が、「近代社会思想」は昭和四十二―四十六年度井伊玄太郎、四十七年度より関嘉彦が、「社会心理学」は昭和四十二―四十九年度島田一男、五十年度より岩下豊彦が、「マス・コミュニケーション発達史」は昭和四十二―四十四年度内川芳美、四十五年度より香内三郎が、「民法」は昭和四十二、四十三年度千種達夫、四十四年度以降は黒木三郎(五十二年度は高島平蔵、五十六年度は田山輝明)が担当している。また、第三年度配当の「マス・コミュニケーション理論」は昭和四十三年度より岩倉誠一(五十年度は岡部慶三)が、「社会調査」は昭和四十三年度より西平重喜(四十五年度および四十九年度は鈴木達三)が、「商法」は昭和四十三年度以降中村真澄、酒巻俊雄、長浜洋一、金沢理が交代で担当している。そして、第四年度配当の「刑法」は昭和四十四年度斉藤金作、四十五年度より内田一郎(四十八年度は岡野光雄)が、「都市問題」は昭和四十四―四十七年度磯村英一、四十九―五十一年度近江哲男、五十二、五十三年度黒沼稔、五十四年度より星野光男が、「農村問題」は昭和四十四年度より小林茂(四十五年度は鈴木直二)が、「マス・メディア論」は昭和四十四年度酒井寅吉、四十五年度より岩倉誠一が、「労働法」は昭和四十四―四十八年度吾妻光俊、四十九、五十年度および五十七年度は竹下英男、五十二―五十六年度は中山和久が担当している。(経済学科のA群およびB群に相当する科目の担当者については、重複を避けるため省略した。)
最後に、D群科目の「外国書研究」については、英書担当として昭和四十一年度に渋谷浩、藤原保信、四十二年度に河原宏、四十六年度に寄本勝美、四十九年度に鴨武彦、五十年度に大畠英樹、五十三年度に石田光義、渡辺重範、五十五年度に大井孝、五十六年度に砂田一郎が、独書担当として昭和四十九年度に片岡寛光、藤原保信が、仏書担当として昭和四十五年度に松本馨、四十八年に寄本勝美、五十五年度に大井孝がそれぞれ加わっている。
昭和二十六年に「新制」の大学院は発足するが、それ以前のいわゆる「旧制」時代における大学院像はかなり漠然としたもので、明確に把握しがたい。まして、創立当時の東京専門学校に、現在の大学院に相当する制度を見出すことは困難である。しかし、強いて現在の大学院の源流を求めるとすれば、当時から設置されていた研究科にそれを見出すことができるであろうか。
明治二十六年八月発行の『中央学術雑誌』(第弐巻、第八号)に早稲田専門学校の研究科についての規則が載せられている。すなわち、「夙に公にせられたる専門学校の研究科は漸く其規則を定め九月より実施することとせり」と記されており、その中の主要な条項をそのまま収録すれば次の通りである。
第一条、研究科ハ本校得業生ニシテ既修ノ学科ニ付キ尚深ク研究ヲ為サントスル為メニ之ヲ設ク
第二条、研究科ハ本校得業生ニシテ平生品行方正学業優等他日大成ノ見込アル者ヲ本人ノ志願ニ依リ其部委員ノ協議ヲ経テ許スモノトス
第三条、本校ハ研究科学生ノ研究セント欲スル学科ニ関シ其学部ノ講師中ヨリ其指導ヲ担当スベキ者ヲ指定ス可シ研究科学生ハ其指導ニ従ヒ研究ノ業ニ従事スルモノトス
第四条、研究科ノ期限ヲ二ケ年トス
第五条、研究科学生ハ研究満期ニ際シ在学中専攻セシ科目ニ付キ論文ヲ作リ指導講師ノ検閲ニ供ス可シ指導講師ハ之ニ意見ヲ付シテ本校ニ差出ス可シ
第六条、本校ハ研究科学生ノ論文ヲ其指導講師ノ意見ト共ニ其学部委員ノ審査ニ付シ其報告ニ依テ本人ニ対シ研究科卒業ノ事ヲ証明ス
以上長々と引用したのは、これによって当時の研究科なるものの姿を彷彿させることができるであろうと思ったからである。なお、この規則は十二条からなっている。残りの部分をつけ加えるならば、第七条と第八条は入学手続きに関する規定、第九条は「学費ノコト」であるが、当時どの程度の金額であったかは解らない。第十条は、研究生の出席義務をうたったものである。「研究科学生ハ常ニ研究室ニ出席シテ其学業ニ従事スルモノトス」と記されているが、この規定もどれ程の強制力をもったものであろうか。第十二条は「校則遵守ノ義務」が記されている。
明治三十五年九月に、東京専門学校は創立満二十年を機として早稲田大学と改称され、卒業生三千余名、在学生三千名余りという規模をもっていた。同三十六年には「専門学校令」の適用を受けることとなるが、当時の大学における研究科の位置づけは次のようなものである。
本校部門ハ大学部、専門部、高等予科ノ三種ニ分チ大学部ニ政治経済学科……ノ四科ヲ設ケ、専門部ニ政治経済学科……ノ六科ヲ設ケ外ニ研究科ヲ置ク。
(『早稲田大学規則一覧』明治三十五年七月)
修業程度からみると、大学部は高等予科を卒業した者、高等予科、専門部は中学を卒業した者を入学させ、研究科は大学部、専門部の卒業生で更に研究を続けようとする者が入学を許されている。更に同年、研究科規則を第六章に設けている。これを逐条的に、そして特に前述の明治二十五年の規約との相違点を取り出しながら見ていくことにする。先ず第一条の目的であるが、この前半は二十五年の規則と同じく「各学部卒業生ニシテ既習ノ学科ニ就キ尚ホ深邃ナル研究ヲ」なさんとする者のために設けられたものであるが、更に今回の規定には、「傍ラ広ク外国語ノ智識ヲ養ハントスル者ノ為メニ設ク」と追記されているのが目立つところである。第二条は「本科ヲ左ノ部門ニ分ツ」として、国法、行政法、国際法、経済財政、民法、商法、哲学、史学、英文学、社会学の十科目が設けられており、当時における学科目のあり方を偲ぶことができる。第三条は本校得業生以外の者の入学に関する規定である。第四条以下は原文のまま引用する。
第四条 本科ハ別ニ学年ノ区別ヲ設ケズ一年以上三年以内ノ範囲ニ於テ何時ニテモ卒業論文ヲ提出シ指導講師ヲ以テ組織セル試験委員ニ於テ学力相当ト認ムル時ハ得業証書ヲ授ク。
第五条 本科授業課目左ノ如シ。
一講義 毎週 二時間
一名著研究 二時間
一問題研究 二時間
一外国語 六時間
一論文
一卒業論文
第六条 (省略)
第七条 本科ニ於テ研究スベキ名著ハ指導講師ノ指定ニヨルベシ
第八条 研究ノ題目ハ入科ノ始ニ於テ之ヲ定メ指導講師ノ認諾ヲ経ルモノトス。
第九条 (省略)
第十条 卒業論文ハ問題研究ノ為メニ定メタル題目ニ限ル
第十一条 本科ノ学費ハ一ケ年金参拾参円トシ分納金一ケ月金参円トス
第十二条 本校得業生以外ニシテ本科ニ入ラントスル者ハ受験料金五円ヲ納付スベシ。
第十三条には明治二十五年規定の第十条に記されたものと同じく出席義務について、第十五条は学則遵守の義務を規定している。
以上記したような研究科の規則は、恐らく大正九年の「大学令による大学」の頃まで続いていたものと思われる。大正九年になると早稲田大学の学則も全体的に大分明確化されてき、この時「大学院」なる名称もあらわれてくる。学則第一章総則の第四条に「本大学各学部ニ研究科ヲ置キ之ヲ綜合シテ大学院トス」と記され、第八条全部が大学院の規定で充たされている。それは十一条からなっているのであるが、内容の点では明治年代の研究科のものに比べて必ずしも具体化されているとも思われない。すなわち、第一条においては入学時期を「学年初」と規定しているだけで、明治の研究科規定のように設置の目的等については言及していない。第二条は出願および入学許可の規定である。学部を卒業して大学院に入学しようとする者は「研究事項ヲ具シ」大学に願い出ることになっており、これを許可するのは学部教授会であった。大学院の学生を監督するのは当該学部長であり(第四条)、学生の指導は「教授会ノ議ヲ経テ選定シタル一名又ハ数名ノ教員」が担任した(第五条)。大学院学生の在学年限は「一ヶ年以上」であり(第六条)、大学の許可を経て各学部の講義等に出席することができ(第七条)、時々その研究状況を指導教員を経て当該学部長に報告しなければならなかった(第八条)。なお、大学院学生は他の業務に従事することや、東京市またはその近辺以外に居住することができない(第九条)。第十条の規定をそのまま記述すれば次の通りである。
大学院学生ニシテ学位ヲ得ント欲スル者ハ其研究事項ニ付論文ヲ学長ニ提出スヘシ。前項論文の審査ハ当該学部教授会ニ於テ之ヲ行ハシム
大正九年に作られたこの規則は殆ど変ることなく昭和十八年まで続いた。同十八年における最も大きな変化は大学院に特別研究生の制度が新設されたことである。太平洋戦争の激化に伴い、大学教育の年限も短縮され、大学院の制度にも改革が加えられた。当初政府は「全国の官私大学の卒業生の中から五百名を限って文部省において選抜試験を行ひ、これを七帝国大学に配布して研究に従事せしめ、此種の学生に対しては年額一千円の奨学金を数年に亙って支給し、同時に徴兵猶予の特典を与える」(田中穂積「学制改革と大学院問題」『早稲田学報』昭和十八年一月発行第五七五号八頁)計画であった。しかしながら、当時の早稲田大学総長田中穂積、慶応義塾大学塾長小泉信三両先生の御尽力によって、この制度は私学の早慶両大学にも適用されることになった。そこで昭和二十年、大学院の規約は、第十二条から第十八条の六ヶ条が特別研究生のためにつけ加えられた。その主要な点は、「特別研究生たらんとするものは各学部卒業生にして、当該学部教授会の許可を得、さらに総長審査の上文部大臣の認可を経ることが必要」(第十三条)というものであった。このようにして銓衡された特別研究生に対しては「学資トシテ第一期月額金九拾円」(第十五条)が支給されることになった。
以上いわゆる「旧制」の大学院の制度のあらましについて述べてきたのであるが、最初に記したように「新制」のそれに比較して、その内容はきわめて漠然としたものであった。名誉教授の小松芳喬先生が御自分の経験された大学院生活について書いておられるが、その文章の中から自由に拝借し、あるいはそのまま転記させていただいて、旧制大学院史のまとめにしたいと思う。旧制大学院は指導教授の個人的指導が殆ど全部なので、入学に当っても指導の先生の御許しが出さえすればよかった。しかも「カリキュラムなどというものは全然なく、自由放任の極」であった。
修業年限は全く無制限で何年という定めはありませんし、特別な講義があるわけでもなく、特別な施設があるわけでもありません。博士論文作製が目的である筈ですが、法文系では、大学院で学位論文を書いた学生は例外中の例外でしょう。早稲田の場合、図書館の書庫が開放されているのが唯一の魅力で、学生もそれ以上のことを大学に求めるでもなく、また大学当局にもごく少数の大学院学生のためにさらに何かを考えようとする気運は見られませんでした。
(小松芳喬「大学院昔譚――自伝的随想――」『早稲田フォーラム』昭和四十九年七月発行第六号 八頁)
昭和二十六年四月、「学部の教育の基礎の上に、高度にして専門的な学術の理論及び応用を研究教授し、その深奥を究めて、文化の創造、発展と人類の福祉に寄与することを目的とする」(『昭和二十六年四月 大学院学則 早稲田大学』一頁)新制早稲田大学大学院が開設された。この新制大学院は各学部の基礎の上に設けられるというものであり、六研究科が設置されたが、政治経済学部の基礎の上に設けられたのは、政治学研究科と経済学研究科である。本章では、前者の政治学研究科について述べる。
新制大学院が新制学部創設に遅れること二年、すなわち二十六年に開設されたのは、同年が新制学部が第一回の卒業生を送り出す年であったからである。つまり最初の新制学部卒業生を迎えるためであったのである。創設されたのは修士課程のみであり、これは他研究科も同じであった。「独創的研究によつて、従来の学術水準に新しい知見を加え、文化の進展に寄与するとともに、専攻分野に関し研究を指導する能力を養う」(『昭和二十八年四月 大学院学則 早稲田大学』一―二頁)ことを目的とする博士課程の開設は、この修士課程の最初の修了者が出る二十八年四月であった。
新制大学院と旧制大学院との間の際立つ差異は、他ならぬこの修士課程の設置にあった。すなわち旧制では博士の学位を与えることを目的とするだけであったのが、新制では博士の学位を与える課程の他、修士の学位を与える課程も置くことができるようになったのである。
ところで、他大学の大学院の場合は、修士課程を修了した上で博士課程に進む、いわば「二段式」が大部分であったのに対し、早稲田大学の場合には、修士課程を経ないで初めから博士課程に進む制度も設けられた。つまり二年制の修士課程と、五年制の博士課程の「二本立て」制度であったのである。このような制度を採用したのは、修士と博士とではもともとその目指すところが異なり、博士たるために修士の学位は必ずしも必要としないとの判断があったからである。ただし、この五年制博士課程は三十九年に「実情に合しない」として学生募集が停止され、四十五年には現在の「二段式」に改正された。つまり博士課程の入学資格者は、主として「修士の学位を得た者」とされたのである。なお、五十一年度には大学院学則が改正され、それまでの修士課程、博士課程は、それぞれ博士前期課程、博士後期課程と改称された。
新制大学院の特徴としては、更に次のものがある。すなわち、旧制では課程について厳格な規定を有せず、ただ二ヵ年以上在学して研究し、論文を提出できるということを規定しただけで、カリキュラムは存在せず、大学院生の納付する授業料の金額が指導教授に与えられていたのに対し、新制では各課程に関し必要な条件を規定して、旧制に比べると厳格に制度化されたのである。先ず修士課程について見ると、発足した昭和二十六年度の場合には、二年以上在学して三十二単位を履修し、且つ修士論文を提出することとされた。政治学研究科の履修方法は、政治学専攻の学科目中の専修科目から十二単位(講義四単位、演習――現在の研究指導――八単位)を選択必修し、残余の二十単位は政治学研究科の講義または他の研究科の中から選択履修する、ただし、他の研究科の講義は四単位までとするというものであった(『昭和二十六年四月大学院学則早稲田大学』)。なお、ここで言う「専修科目」とは、「指導教授が二年間を通じて指導する科目」のことであり、また「特修科目」とは、「専修科目以外の科目」のことである。各学年の履修方法は左の通りである。
専修科目 特修科目
第一学年 ……講義四単位 演習四単位 講義十二単位
第二学年 …… 演習四単位 講義八単位
博士課程の場合、「博士の学位を取得しようとする者は、五年以上在学し、所定の科目について五十二単位を取得」(「修士の学位を得た者、本大学院の修士の課程を経た者または外国において修士の学位若しくはこれに相当する学位を得た者は、三年以上在学し、二十単位を取得」)し、学位論文を提出することが要件とされた(『昭和二十八年六月 大学院学則 早稲田大学七頁)。二十八年度における各学年の履修方法は、
専修科目 特修科目
第一年度 ……講義四単位 演習四単位 講義十二単位
第二年度 …… 演習四単位 講義八単位
第三年度 …… 演習四単位 講義八単位
第四年度 …… 演習四単位
第五年度 …… 演習四単位
となっていた。なお、修士、博士いずれの学位にも所属研究科名が冠せられるとともに大学名が明記され、「政治学修士(早稲田大学)」「政治学博士(早稲田大学)」と呼称されることとなった。
履修方法は、その後、部分的修正をみたが、現在(五十七年度)でも、修士課程(二年以上四年以内在学)は研究指導および授業科目三十二単位、博士課程(三年以上六年以内在学)は研究指導のみとされ、既述の「二段式」への変更を除けば、創設時とさほど大きく異なるわけではない。
発足時(二十六年度)における大学院政治学研究科担当の専任教員には、憲法学の大西邦敏、行政学の佐藤立夫、外交史の信夫淳平、政治学の吉村正、政治史については渡辺幾治郎がいる。
二十七年度以降、新たに政治学研究科のスタッフに加わった専任教員には、内田繁隆(二十七年度)、矢部貞治(二十七年度)、松本馨(二十九年年度)、後藤一郎(三十三年度)、吉村健三(三十三年度)、堀豊彦(三十五年度)、内野茂樹(三十七年度)、清水望(三十八年度)、岩倉誠一(四十二年度)、兼近輝雄(四十二年度)、小林昭三(四十二年度)、堤口康博(四十二年度)、福田三郎(四十二年度)、内田満(四十六年度)、藤原保信(五十一年度)、片岡寛光(五十三年度)、寄本勝美(五十五年度)がいる。
政治学研究科発足時の学科目は、左の通りである。
演習・講義……政治学特論、憲法特論、政治史特論、政治思想、国際政治特論
講義……行政学特論、比較政治制度論、自治行政特論、行政法特論、日本政治史特論、外交史特論
二十八年度には、博士課程の設置とともに演習・講義の編成も改められ、次のようになった。
演習・講義……政治学研究、憲法研究、政治史研究、政治思想研究、国際政治研究、行政法研究
講義……現代行政学、比較憲法研究、外交史研究、最近日本政治史、自治行政研究、政治学特殊研究、公法特殊研究、国際政治特殊研究
その後も学科目編成は度々修正され、現在でははるかに充実した編成となっている。左に学苑創立百周年に当たる五十七年の学科目編成を掲げ、この間における政治学研究科の発展の一端、ならびに、創立以来の政経学部の豊かな学問的伝統が現代にも確かに継承されていることを窺い知るためのよすがとしたい。
研究指導……政治学研究、国際政治研究、行政学研究、自治行政研究、日本政治史研究、西洋政治史研究、政治思想研究、憲法研究、行政法研究、マスコミュニケーション研究
授業科目……政治学研究、国際政治研究、行政学研究、自治行政研究、日本政治史研究、西洋政治史研究、政治思想研究、憲法研究、行政法研究、マスコミュニケーション研究、現代行政学研究、外交史研究、近世日本政治思想史研究、国際法研究、比較憲法研究、英米政治学特殊研究、英米公法学特殊研究、ドイツ公法学特殊研究、フランス公法学特殊研究
明治十五年、開校当時の東京専門学校における経済関係の設置科目は、「経済学原論」「経済沿革史」「租税論」「貨幣論」「貿易論」「日本財政論」「統計学」の七科目。担任者は天野為之、高田早苗の二名。ほかに当否は不明ながら、砂川雄峻、岩橋三郎の二名が担任者であったろうとされている。もし進級制度を予定していたとすれば、これが第一年度の配当科目と言って良いのだが、当初にどういう計画があったものか。とにかく開校、ついては科目をという程度だったとすれば、これが経済について開講できる目一杯のものだったと推測される。
これと対照するには、本当は大正八年、専門学校令による大学であった時期の最後の年度の設置科目と担任者を示すのが良いのだろうが、この年度を採るには難点が二つある。第一は、大正六年の「早稲田騒動」である。このためこの年度は、創立以来経済学関係で中心的存在であった天野為之とその一統が学苑を去った直後に当っており、余波と余燼が設置科目、担任者についても残っていて、比較の対照とするには適当ではない。第二に、同じく大正六年に高等予科の年限延長があり、これに伴い、大正七年には大学部に一年生が、大正八年には二年生がいなかった。それゆえ、大正八年の科目・担任者は二年生抜きのものとなっていて、全容を知るには不適当である。尤も、大正七年と八年の科目担任者を比較すれば、科目の配当学年がおぼろげに分るという利点はある。けれども「騒動」の影響を考えれば避けたほうが賢明であろう。それで、大正六年度の大学部政治経済学科のカリキュラムのうち、経済関係のものを見る。序でながら、資料の関係で、配当年度は不明である。それは、
Ⅰ◎経済学原理(塩沢昌貞) ○経済学説(塩沢昌貞) ○経済史(平沼淑郎) ◎統計学(宮島綱男) ◎貨幣及銀行論(服部文四郎) ◎財政学(田中穂積)
Ⅱ◎応用経済論(天野為之) ◎農業政策(松崎蔵之助) ◎商業政策(浅川栄次郎) ◎工業政策(塩沢昌貞) ◎社会政策(永井柳太郎) ◎交通政策(伊藤重治郎) ◎金融政策(服部文四郎) ◎保険政策(宮島綱男) ◎植民政策(永井柳太郎) ◎都市問題(安部磯雄)
Ⅲ◎経済財政(田尻稲次郎) ◎経済叢書(和田垣謙三)
であった。表中類別は筆者が任意に行っている。 ◎を付したのは、専門部でも開講されていた科目。従って○は大学部においてのみ開講の科目である。◎が合併によったものか、各々独自の講座であったのかは詳らかではない。しかし、◎がすべて独自の講座で各々一クラス宛設けられていたとすると、例えば塩沢は週七回講義したことになる。なお、専門部には独自の科目として簿記(神尾錠吉)があった。
右の表から明らかなように、大学部独自のものは、Ⅰのグループで経済学説、経済史の二科目、それとⅣ、Ⅴにある四科目の計六科目であった。このうち、Ⅰの中のものは実用から離れたヨリ学問らしい基礎的なもの、Ⅳは少人数の、今日で言えば外国書研究に類するもの、Ⅴは今日の演習に類するものかと思われる。そうして、全般的には、Ⅱに属する応用経済あるいは政策論の充実に力点がおかれていたことが分る。なお、Ⅲはいわゆる大家の大演説(あるいは冗舌中心のもの)に当っていたろう。ともかく、右の表に出てくる科目名は(簿記を入れて)二十二。担任者名は十四を数える。
以下では、明治十五年と大正六年との間を、上に掲げた類別に従って辿ってみたい。と言っても、主として講座名だけからカリキュラムの内容を推測するのは、カタログだけで外国書を注文するのと似ていて、危険ではあるがやむを得ない点であることを断っておかねばなるまい。
少々横道に逸れるが、「騒動」の影響を見ておく。大正六年の右の表に出ていて、大正七、八年の表に出てこない担任者は、浅川、天野、伊藤、大山、田尻、永井、宮島の七名であり、去ったのにはそれぞれに理由があったのだろうが、ここでは触れない。逆に新たに担任者となった者は、粟津清亮(保険政策) 上田貞次郎(商業政策) 宇都宮鼎(貨幣及銀行論) 梅若誠太郎(Economic Classics) 北沢新次郎(Economic Classics) 小林丑三郎(財政学) 佐竹三吾(鉄道政策)の七名であった。このうち、梅若は明治三十三年に「小経済学」(恐らくは英書研究のテキスト名が科目名となったものであろう)を一年だけ担任したことがあり、宇都宮は明治三十三―四十年の間に「財政学」「公債論」等を担任したことがあった。この二名は緊急復活だが、粟津、上田、北沢、小林、佐竹は初めての登場である。これだけの入替えがあって、大正七、八年の科目数は重複分を調整して十七に減っている。だがとにかく、大筋では専門学校令による大学であった時代の最後のカリキュラムが、科目名担任者を含めて、その後の旧制のそれに承け継がれていった。
Ⅰのうちの「経済学原理」と類同すると思われる科目は明治十五年以来、「経済学原論」「経済原論」「経済学」等と名称は変っても一貫して開講されている。担任者は明治三十四年までずっと天野為之、三十五年に塩沢昌貞が加わり大正四年まで天野・塩沢の併立となり、翌五年から塩沢の単独になる。「経済学原理」と改まったのは、塩沢単独になってから以後のことである。この時、天野は上の類別Ⅱに移る。
「経済学史」は明治二十三年に設けられ、当初井上辰九郎が担任している。井上は明治三十年に退き、浮田和民、内田銀蔵を経て、明治三十五年以後和田垣謙三、大正三年からは塩沢が「経済学説」として引継ぐ。ただし、明治四十三―四十五年の間は和田垣・塩沢の併立であった。和田垣はその後「経済叢論(年により叢書とも)」の担任者となった。
「経済史」は明治四十年以後平沼淑郎が担任する。それ以前は、三十年代は断続的に内田銀蔵担任であった。なお、この科目の最初の担任者は天野為之。明治二十二年のことだったが、ただの一年でやめ、彼は以後この名の科目は持たなかった。二十年代には、この科目は「考証経済(考証経済学)」と呼ばれたのかも知れない。担任者で明らかな者は木内重四郎、有賀長文。天野も担任したかも知れないが未詳。いずれにせよ断続していて、二十一―三十年の間に七年しか開講された模様がない。明治十五年の「経済沿革史」はあとが続いていない。
「統計学」は時に「統計原論」とも称された。記録には明治十八―二十年、同二十九―三十二年に開講の記載がない。担任者は、初期は不明。二十一―二十八年は呉文聡、三十三年以後柳沢保恵、四十一年から高野岩三郎、大正二年以後宮島綱男。しかし、大正七、八年の科目表から統計学は消えている。主に外来講師に頼った形跡がある。なお、明治二十一年に限り、呉担当で「統計実習」があった。
「貨幣及銀行論」と名称が落ち着いたのは大正四年以後。大正二、三年に「貨幣及信用論」の名で服部文四郎が初めて担任し、以後担任者は変らない。この系列は、もと「貨幣論」と「銀行論」の二つから成っていたらしい。うち「貨幣論」は高田早苗(明治二十年まで)、松崎蔵之助(明治二十一年)、天野為之(明治二十二年)、井上辰九郎(明治二十三―九年)、加藤晴比古(明治三十一年)、河津暹(明治三十二年、同三十七年)、志田勝民(明治三十三年)、浜岡五雄(明治三十四年)、松山忠次郎(明治三十五―六年)、と担任者が定まらない。漸く、明治四十一年服部が引継いで以後安定する。因に、河津は明治四十年にもこの科目を講じているが、三十八―九年については開講の記録がない。この系列はどちらかと言えば、財政学と関連があった模様である。
「銀行論」は明治十六年からほぼ引続き四十一年まで置かれ、翌四十二年名称が「銀行及為替論」となり明治四十五年まで続き、大正二年の(上述)「貨幣及信用論」に連なる。担任者は当初から明治三十七年まで天野為之(例外として三十五年浜岡五雄)、三十八―四十一年が山崎覚次郎、四十五年までは服部文四郎であった。なお銀行論は貿易、為替、銀行実務とも関連が深かった。「為替論」(「外国為替論」のこともあった)は明治十六―三十三年には天野為之、途中切れて四十―四十一年は山崎覚次郎が担任した。為替論の三十年代の空白は、かなり「外国貿易論」(「貿易論」のこともあった)で埋められている。この科目の担任者は、ほぼ一貫していて、開講されている時は天野であった。ただし、山崎覚次郎が銀行論とともに講じた年(明治三十七、八年)もあった。別に、明治二十五―二十八年には、「銀行事情」「貨幣問題」「銀行実務」が開講されていた。担任者は不明だが、天野か井上辰九郎であったらしい。別に「金融論」が明治三十年には設けられていた。担任者は不明である。
「財政学」の系列も賑やかである。財政に関する科目名は、明治十五年と大正八年の間に十五ほど現われる。これらがどういう意図で結び合わされていたか、今となっては明らかでない。以下、内容を考えずに科目名と担任者を列挙するに止める。
「財政学」は天野為之(明治二十二年)、松崎蔵之助(明治二十三年)、井上辰九郎(明治二十五年)、下村宏(海南、明治三十二年)、宇都宮鼎(明治三十三年)、塩沢昌貞(明治三十五―三十七年)、田中穂積(明治三十八―大正七年)が担任している。このうち田中担任の大正五年と七年には、「二年向き、三年向き」と添え書きがあり、二講座連続で、総論と各論が置かれていたことを示す。「財政論」と上述「財政学」との関係は明らかでない。二つが併置されている年も、一方が欠けている年もあるからである。「財政論」は、天野為之(明治二十一、三十五、三十六、三十七年)、床次竹次郎(明治二十四年)、井上辰九郎(明治二十九年、三十年(?))、松崎蔵之助、宇都宮鼎、神戸正雄(共に明治三十四年)、浜岡五雄(明治三十五年)が担任しているが、明治三十四年の三名併立、三十五年の二名併立をどう解したら良いのだろうか。なお、明治二十六年にも「財政学」は置かれているが、担任者は解らない。この他に明治三十一、三十二、三十四年の三年度には、「財政」が開講された。松崎蔵之助(三十一、二年)と神戸正雄(三十四年)が担任である。しかし、これと、「財政学」「財政論」との関係も分らない。
以上は総論と思われるものだが、別に「財政論(租税・公債・予算)」が明治二十七、八年(井上辰九郎か)に、「財政学(租税・公債・予算)」が大正三、四年(田中穂積)にある。「租税論」は、明治十五―二十一年に開講(二十年まで高田早苗が、二十一年松崎蔵之助)され、二十六―二十九年(二十九年松崎蔵之助か、他は担任者不明)と、三十五・三十六年(松崎)および四十三、四年(田中穂積)にも置かれている。租税関係ではこの他に「米国租税論」(明治十九、二十年、天野為之)、「地租問題」(明治二十六―二十八年、担任者不明)と「租税法」(明治三十四年、松崎蔵之助)が講ぜられた。「国債論」は明治十六―八年と同二十年(天野為之か)に、「公債論」は明治二十五―三十六年(ただし、三十四年は「公債法」)が、天野為之(三十三年まで)と宇都宮鼎によって担任された。他に「公債及予算論」(四十三―五年、田中穂積)があったが、これは予算だけを取り上げる方式が廃った後におかれたものである。
予算は重視されていた。天野為之は、明治二十五、二十九―三十一年、三十三年には「歳計予算論」を、三十二、三十四年には「予算論」を講じている。宇都宮鼎は、「歳出歳入論」を明治三十五、六年に、「予算論」を明治三十七、八年と四十年に担任している(三十九年については資料がない)。別に、明治十五―七年には「日本財政論」(十七年については臨時課外として小野梓が担任し、他の年は不明)が講義されていた。
Ⅱのグループに移る。これは各種の政策論や産業論を含み、ごく包括的には応用経済applied economicsと呼ばれた分野である。「応用経済学」「応用経済」「応用経済論」の三種の科目名は頻繁に交替して出没する。三種の科目名については区別せず、担任者と開講年度のみを記せば、添田壽一(明治二十一―三年、同三十一年)、井上辰九郎(明治二十五―三十年)、天野為之(明治三十二―三十八年、同四十二年、大正三―六年)、塩沢昌貞(明治四十―四十二年)であった。従って明治四十二年は天野と塩沢が併講している。別に「応用経済(社会政策)」(明治三十三年、安部磯雄)があった。しかし、起源が古いのは「商政学」「商政論」などと呼ばれた「商業政策」の分野である。これは明治十九年に始まっている。名称としてはこの他に「商業制度」「商業経済」「商業学」があった。この分野についても、科目名を区別せず、担任者名を記せば、天野為之(明治十九、二十年、同二十二、二十四年、大正二年)、別に、明治二十七年には「商工実務」がある。しかしこの年の担任者は不明である。以後は石川文吾(明治三十六―八年)、河津暹(明治三十八年、同四十―四十五年)、浅川栄次郎(大正三―六年)、上田貞次郎(大正七、八年)が担任した。なお、明治二十六―八年にも開講されているが担任者は天野のようであるが不明。
次いで古く始まったのは「農業経済論」「農業経済」「農政経済」「農業制度」「農業政策」「農制経済」の系列である。これも科目名を区別せず、開講年度と担任者名のみを記す。すなわち、高橋昌(明治二十一年)、山本悌二郎(明治三十一、二年)、石阪橘樹(明治三十三年)、柳田国男(明治三十四―六年)、松崎蔵之助(明治三十七年―大正七年)。なお、明治二十六―八年にもこの種の科目があったことは分るが、担任者は不明である。
明治二十六年には、「保護会社論」「社会問題」「移民論」「鉄道及通信事業」が置かれ、これらはいずれも、明治二十八年で一応尻切れになる。これらについては資料不備で担任者は分らないが、「保護会社論」は後の「工業政策」の、「社会問題」は後の「社会政策」の、「移民論」は後の「植民政策」の、また「鉄道及通信事業」は後の「交通経済」のそれぞれ源流を成すものと推測される。このうち、「工業政策」は大正七、八年には「騒動」の影響で「工業政策及社会政策」と改まるのだが、それまでは一貫して「工業政策」で、明治四十三年から大正八年まで断絶なく塩沢昌貞が担任した。「社会政策」は(右の大正七、八年を除けば)明治三十二年、同三十四年―四十四年は安部磯雄、明治四十五年塩沢昌貞、大正二―六年は永井柳太郎がそれぞれ講じていた。「植民政策」は明治四十二―大正六年の間、間断なく永井柳太郎が担当している。「交通経済」「交通政策」「鉄道政策」の分野は、下村宏(明治三十二年)、関一(明治三十七―四十五年)、伊藤重治郎(大正二―六年)、佐竹三吾(大正八年)という人々によって受け持たれた。
グループⅡには、他に「都市問題」がある。これは明治四十四―大正七年の間設置されて安部磯雄が担任した。また、「保険政策」は、大正二―四年と六―八年に設けられ、それぞれの時期を宮島綱男と粟津清亮が担当した。「金融政策」は最も開設が遅れて、大正五年から八年まですべて服部文四郎が講義している。これらを綜括すると、大正六年にはこのグループに属する科目は既述のように十に達していたことが分る。これが最大であって、これに次ぐのは明治二十六―八年の間であり、当時、講義があったのは「応用経済学(又は論)」 「保護会社論」 「商工業制度」 「商工実務」 「農業制度」 「社会問題」 「移民論」 「鉄道及通信事業」の八科目であった。彼此比較すると、実質三科目つまり、「都市問題」 「保険政策」 「金融政策」が大正六年の科目表には加えられていることが分る。
第Ⅲのグループには右のⅠⅡからはみ出した大家の演説が入る。具体的には、「経済財政」は明治三十五―大正六年の間途切れることなく、すべて田尻稲次郎が担任し、「経済叢書」(「経済叢論」と呼んだ時もあり)は、明治四十三―四十五年は天野為之、一年空白ののち大正三―七年は和田垣謙三がそれぞれ講義している。天野は大正四年に学長に就任するが、大正三―六年の間も(既述のように)「応用経済論」は講じている。だからこの時期天野の「応用経済論」はこの第Ⅲグループに入れるべきかも知れない。
第Ⅳのグループは「経済原書」「名著研究」「原書研究」「Economical Classics」「Economics Classics」の呼び名を持った科目群である。今日でいう外国書研究に当るものであろう。科目名で区別せず、担任者のみを示せば次の通りである。すなわち、天野為之(明治三十三年)、塩沢昌貞(明治三七―大正七年、ただし明治三十九年は恐らく担任したと思われるが不明)、服部文四郎(明治四十一―三年、明治四十五―大正三年)、永井柳太郎(明治四十二―大正六年)、田中穂積(明治四十四年)、伊藤重治郎(大正二、三年)、大山郁夫(大正四―六年)、梅若誠太郎(大正七年)、北沢新次郎(大正八年)である。外国書研究は概ね専任の若手がやるという不文律が当時もあったとすれば、若手陣にどんな人物が育ってきていたか分るだろう。なお明治三十四年―六年にはこの種の科目名が科目表に全く見当らない。東京専門学校から早稲田大学への改称が明治三十五年だから、肩肘張るためにも置く必要があったと思うのだがそれがない。ところが、当時は科目名に教科書名を用いることがあったようで、例えば明治三十三年には梅若誠太郎が「小経済学」を、千葉広蔵が「最近経済学」を、三十四年には天野が「(ウォーカー)経済原論」を、浜岡五雄が「(アダムス)財政学」を担任したという事実があるし、明治三十六年には天野為之が「経済大意」を講じたとも記録されている。これらは教科書名と関係ある科目名だと推察できるが、そのようだとこの空白期間は説明がつく。
第Ⅴのグループは今日で言う演習に類するものから成る。「経済財政実習」「経済及財政研究」「経済実習」「財政実習」「経済研究」「財政研究」として示された諸科目がそれに当る。上に付くのは「経済」か「財政」かその二つを重ねた語で、下に付くのは「実習」か「研究」かの語である。担任者は複数であることが建前で、かなり後にならないと科目表には現れない。明治三十八年以降断絶なく設けられているが、その初年度は、天野為之、塩沢昌貞が受け持った。しかし、(一年だけ全く記録を欠く三十九年を過ぎると)明治四十年以後はずっと、一年の例外もなく塩沢と田中穂積とが担任している。経済は塩沢、財政は田中と分担も不変であった。
明治十六年―大正八年の科目表を適宜類別して経過を辿ってきたが、次の諸科目はどこに篏めて良いのか皆目分らなかった。設置年次と担当者を列挙するに止める。「経済論理(明治十六年、天野か)」「経済研究法(明治二十一、二年、天野為之)」「経済学攻究法(明治二十六―八年、担任者不明)」「法制経済(明治四十一年、安村良公)」。これらのうち、終りの二つは専門部のみの科目。あるいは通論に属すべきものかも知れぬ。だとすれば言うまでもなく安村の担当分は「法学通論」に当るだろう。
最後に、此ところまで触れてこなかった簿記会計の科目についても書いておく。先ず明治二十年に一年限りだが「会計法」(天野為之)がある。担任者の名からして、会計の方法なのか、法規なのかと疑うが、多分前者だと思う。この頃天野は八面六臂であった。次いで、これも一年限りだが明治二十七年に「簿記原理」が置かれている。担任者は桑田熊蔵かと推定されるが、資料不備である。「簿記」と改まったのは明治三十五年以降で、専門部のみの設置科目だったが今度は断続がない。科目名は不変だが、担任者は代った。年次によって示せば、吉田良三(明治三十五年、大正二年)、土屋長吉(明治三十六年)、小林行昌(明治三十八―四五年、三十九年については資料不備だが小林が略〻確実か)、河野安通志(大正三―五年)、神尾錠吉(大正六―八年)であった。
以上、経済関係のカリキュラム(科目名、担任者名)を通観してきたが、専門学校令による大学部政治経済学科の経済科目は、明治四十年頃に目立って充実してきたと概括できるであろう。第一に、この頃、主要科目の担任者が動かなくなり、それも本校卒業生が占めるようになったことで知られる。以下に、東京専門学校卒業生が、初めて主要科目を担任した年度と科目を弧括内に示すと、塩沢(明治三十五年、「経済学」、明治四十三年、「経済学史」)、田中(明治三十八年、財政学)、平沼(経済史、明治四十年)、服部(貨幣論銀行論、明治四十一年)となるからである。第二に、外国書研究の担任者が初めて二人となったのは明治四十一年、三人となったのは明治四十二年であった。第三に、演習担当者二名が定着したのは明治三十八年であった。創設後二十五年、一世代を経て漸く自校の卒業生で中心が固められるようになったのである。それまでは天野が一人で取り仕切る趣があった。過去の貢献と成果が「騒動」の一方の主役に彼を仕立てたのかも知れない。しかし、基礎を据えたのは天野であった。
次に、カリキュラムそのものから見ると、優れて財政が重きをなしていたが、それでも全般的には実学を尊ぶ高等商業学校の風貌であった。東京高商(当時は神田に校舎があった)や東京帝大からの講師も多かったが、実業界にある卒業生等が多く出講している。これらの中には、経済政策学会の創立に貢献した者が多かった。彼らは学問のファンである。政経の学風が、アカデミズムを中心にしながら、実学を疎かにしない風を保っているのは、このせいかも知れない。とにかく、このような三十数年を経て、政経は旧制大学令による大学学部としての歩みを始めた。
付記
一、典拠は、早稲田大学大学史編集所編『東京専門学校校則・学科配当資料』、川口浩編「政治経済学部教員学課担任調』(いずれも同編集所所蔵)である。
一、但し、右資料は、⑴科目・担任者共に不明の年度(明治三十九年)⑵担任者名が不明の年度(明治十六年、同二十六年)⑶科目名と担任者名が対応していない年度(明治十五年、同二十七年、同二十八年、同三十年)⑷科目担任者表が二枚載せられている年度(明治十八年)を含み、更に右資料には⑸学科目の配当年次、担任者の資格(専任・非常勤の別)を載せていない。
一、右の不十分がある上に、科目名のみでは講義内容は推測できないという基本事情、および現実に科目名が屢次に変更されているという付加事情により、カリキュラムの全貌とそれを貫く精神を完全に明らかにはし得なかった。遣憾ではあるが、右二資料は今日得られる最良のものであることは疑いなく、これに拠らざるを得なかった。後日の補充に期待したい。
一、本稿の記述では、東京専門学校における明治二十一年以降の邦語政治科、英語政治科のカリキュラムの別、および専門学校令による早稲田大学における大学部、専門部のそれは特記する場合を除き、殆ど配意していない。
一、担任者の一人一人について、せめて当時の現職だけでも記したかったが、紙幅がない。後日に譲る他ないのは残念である。
大正九年の「新大学令」による、いわゆる旧制早稲田大学の発足とともに、我が政治経済学部は政治学科と経済学科の二学科に分かれた。本項では、この大正九年度から新制政経学部が開設された昭和二十三年度までの経済学科のカリキュラムについて述べる。
大正九年の経済学科は第一学年のみの開設であったため、三学年がすべてが揃ったのは、大正十一年である。先ず、同年の経済学科の学科配当表を見ると、第一学年には七科目の必修科目(「政治学」「憲法」「経済学原理」「政治史」「民法」「刑法」「経済学」)と一科目の随意科目(各学部共通の第二外国語――「独語」「仏語」「露語」「支那語」から一科目選択)、第二学年には六科目の必修科目(「財政学」「貨幣及銀行論」「工業政策及社会政策」「経済史」「農業政策」「特殊研究」)、九科目の選択科目(「行政法総論」「国法学」「社会学」「政治学史」「最近政治史」「文明史」「統計学」「民法総論」「民法債権総論」)、および一科目の随意科目(第二外国語――第一学年に同じ)、第三学年には五科目の必修科目(「経済学史」「商業政策」「交通政策」「植民政策」「特殊研究」)、十三科目の選択科目(「金融政策」「保険政策」「政治哲学」「行政法各論」「自治政策」「国法学」「労働政策」「日本財政論」「商法」「近時外交史」「国際公法」「国際私法」「最近東洋史」)および一科目の随意科目(第二外国語――第一学年に同じ)が、それぞれ配当された。ただし、第一学年の必修科目の大部分は政治学科と共通しており、経済学科独自に設置したのは、「経済学原理」の一科目だけであった。経済学の専門的学習の前に、政治学の基礎教育を行おうというのである。政治と経済の密接不可分な関係を重視した、政治経済学部たる所以であろう。なお、第一学年配当の経済学および第二、第三両学年の「特殊研究」は、いずれも英語原書講読で、前者も大正十三年に「特殊研究」と改称された。
これらの科目のうち、経済学関係科目を担当した政経学部専任教員には、安部磯雄(経済史)、粟津清亮(保険政策)、猪俣津南雄(農業政策、特殊研究、経済学史)、宇都宮鼎(財政学)、太田正孝(日本財政論)、河津暹(商業政策)、塩沢昌貞(経済学原理)、信夫淳平(植民政策)、二階堂保則(統計学)、二木保幾(特殊研究)、林癸未夫(工業政策及社会政策、労働政策)がいる。なお、社会学は文学部の遠藤隆吉が担当した。
さて、その後いくつかの科目が追加あるいは廃止されたものの、カリキュラムの基本的な枠組み自体には特に大きな手直しが加えられることなく推移したが、昭和七年に至って、大がかりな改革がなされた。この改革は、その前年に第四代総長に就任した田中穂積のもとで断行された全学的学制改革の一環を成すもので、その趣旨は「自修的研究といふことが教授上のモットーとしてあるが、この点が未だ充分に実現出来ないでもない」(塩沢昌貞「大学教育行詰りに対する所感」『早稲田学報』昭和五年六月発行 第四二四号 四頁)という状態を改善するために、いま一度「自修的研究」という建学の精神に立ち返り、大正九年以来の学制を見直すことにあった。そして、我が学部経済学科のカリキュラムも、こうした学制改革の趣旨に基づいて大幅に改められたのである。
カリキュラムに関する改革の要点として、先ず第一に指摘すべきは、旧制政経学部発足当初は他学年と異なり、必修科目と随意科目のみからなる第一学年にも、多くの選択科目が置かれたことである。第一学年には、既に昭和二年に「社会学」「極東外交史」「文明史」の三科目、昭和三年に一科目(特殊研究、担当浅見登郎)がそれぞれ選択科目として新たに配当されていた。しかし昭和七年には、それまで必修科目であった「政治学原理」(昭和三年に設置)、「政治史」「刑法」の三科目と、「統計学」「日本政治史」の計五科目が一度に追加され、「極東外交史」「特殊研究」の二科目はなくなったものの、選択科目は都合七科目と大幅に増加したのである。この結果、必修科目は「経済学原理」(塩沢)、「憲法」「民法」「特殊研究」(阿部賢一、久保田明光、大西邦敏)の四科目と、昭和二年に追加された「経済史」(平沼淑郎)の五科目となったから、第一学年も、他学年同様、学科配当のウエイトが必修科目から選択科目に移行したと言える。
こうした傾向は、他学年についても言える。先ず第二学年の場合、前年の昭和六年には、必修科目七科目、選択科目八科目であったのが、必修科目は「財政学」(宇都宮)、「貨幣及銀行論」(服部文四郎)、「工業経済」(林)、「農業経済」(久保田)、「特殊研究」(酒枝義旗)の五科目、選択科目は「現代経済学説演習」(後述)、「商業経済」(村瀬忠夫)、「統計学」(小林)、「政治学史」、「公法学原理」「行政法総論」「民法」「国際政治論」「英国憲政史」の九科目となった。また第三学年でも、昭和六年の必修科目五科目、選択科目十科目から、必修科目は「経済学史」(二木)、「社会政策」(林)、「商法」(時子山常三郎)、経済学演習(後述)の四科目、選択科目は「交通経済」「金融経済」(服部)、「保険経済」(村瀬)、「特殊研究」「政治政策学」「国際公法」「行政法各論」「政治哲学」「日本政治思想史」「支那問題研究」「外交史」「公法学史」の十二科目に改められた。
第三に、各学年とも他学部の学科目を選択の対象としたことが挙げられる。
第四に、第三学年に「演習」という科目を新設し、これを重点科目としたことである。昭和五年から、第三学年に「セミナール」が選択科目として設置されていたが、これは担当教員が阿部賢一一人で、しかも週一時間しかなかった。しかるに七年は担当教員に、阿部の他に服部、林、二木、村瀬、宇都宮、久保田、塩沢、杉森孝次郎の八人を加え、既述のように必修科目(「経済学演習」)として第三学年に配したのである。なお、これに伴い第二学年においても「現代経済学説演習」が設置された。ただし、これらは選択科目で、担当教員も二木、服部、久保田の三人しかいなかった。
こうして建学の精神に基づく全学的学制改革を契機として政経学部経済学科のカリキュラムも大幅に手直しされたのであるが、その後、我が国が政治的、経済的、そして社会的にも戦時体制へ徐々に移行していく中で、こうした学科編成方針は後退を余儀なくされ、戦時色の強いものにとって代られていくことになる。
先ず昭和八年に、「軍事教練」が各学年に随意科目として設置された。そして昭和十四年に、これは必修科目になった。昭和十一年には、アジア諸国、とりわけ満州国からの留学生受け入れを主たる目的とするが、日本人が聴講することもできる「外国学生特殊研究」が、先ず第一学年に置かれ、翌年は第一、第二両学年に、そして昭和十三年に三学年のすべてに設置された。この昭和十三年においては、第一、二両学年を青柳篤恒、第三学年を吉村正が担当した。なお、この「外国学生特殊研究」は昭和十七年に「国語特殊研究」と改称されるが、十九年からは「特別研究」と称した。また十八年には、第二学年の選択科目に「東亜政策」が加わった。
なお、この間、その他の科目にもかなりの変更があったが、それらのすべてを述べる余裕はない。ここでは、第二学年の「現代経済学説演習」がその後担当教員数を徐々に増やし、昭和十六年には七人(久保田、小松、酒枝、杉山清、時子山、中村佐一、平田富太郎)となり、十九年には一応必修科目となったものの、担当教員は敗戦まで未定であったこと、そして昭和十年に従来の随意科目としての「第二外国語」はなくなり、代って、選択科目に「独語特殊研究」(各学年)、「仏語特殊研究」(各学年)、「支那語特殊研究」(第一学年)が置かれ、いずれの学年においても一科目選択とされたことにだけ触れておこう。担当教員は、同年は第一学年は時子山(独)、久保田(仏)、青柳(支那)、第二学年は内田繁隆(独)、村瀬(仏)、第三学年は久保田(独)、天川信雄(仏)であった。
戦時色は、昭和十九、二十年に至って、一挙に強まった。昭和十九年十月および二十年四月の学科配当表を見ると、先ず第一学年では、選択科目がなくなった。そして、必修科目には、第二学年から移行した「東亜政策」(大西、杉山)が新たに加わった。なお、第一学年の他の必修科目には、先の「外国学生特殊研究」が改称した「特別研究」「憲法」「経済原論」(酒枝)、「政治学原論」「経済政策」(林)、「民法総論」「国際法」「日本経済史」(小松芳喬)、「日本政治史」の九科目、更に、既述のように昭和十年から選択科目の「外国語特殊研究」が改称した「外国書研究」(英語、独語、仏語――いずれも経済学、政治学の二つに分かれた。学生は一ヵ国語の政治学・経済学を選択。経済学の担当は、それぞれ杉山、大西、久保田)も必修科目に加わった。なお、「外国書研究」は、第二、第三学年にも設置されたが、この両学年では選択科目であった。
また、第二学年では、必修科目には、「戦時経済論一部」(林)と「戦時経済論二部」(久保田)とが新たに加わり、「経済学史」(久保田)、「経済政策」(林)、「財政学」(時子山)、「金融論」(中村)、「西洋経済史」(小松)、「演習」(担当未定)、「特別研究」と合わせて合計九科目となった。選択科目にも、新たに「戦時政治論」が加わった。なお、選択科目にあった「東亜政策」はなくなり、代わって「東亜史」が置かれた。
更に第三学年でも、必修科目に「戦時経済論」(服部)、「戦時財政論」(時子山)、「東亜経済研究」(杉山)が新設され、また、選択科目にも「東亜政治研究」の他、「戦時行政法」「戦時配給論」(山川義雄)が追加された。なお、以上の他に第三学年に配された科目は、必修科目では「厚生論」(平田)、「欧米政治経済研究」(煙山専太郎)、「演習」「特別研究」(小松)、選択科目では「日本政治経済思想史」(内田)、「地政学」(吉村)、「商法」「外国書研究」(独、仏、英、支、担当はそれぞれ久保田、小松、平田、青柳)があったが、これらのうち「演習」は、先に述べた第二学年同様、担当教員が敗戦を迎えるまで未定であった。
さて、敗戦後、早くも昭和二十年九月に授業が再開されたが、同年十月の経済学科の学科配当表を見ると、先に触れた「軍事教練」「戦時経済論」等の戦時期特有の科目がなくなり、戦時色が払拭されていることが分る。しかし、カリキュラムの基本的枠組みが、戦争直前、つまり建学の精神に基づいて断行された昭和七年のカリキュラム改正の段階にまで戻ったわけでもなかった。先ず、第一学年の場合、昭和初頭の改革の際に設けられたものの、戦時下において廃止されてしまった選択科目は復活されず、必修科目のみ九科目が置かれた。なお、その内訳は、「経済学原論」(酒枝)、「政治学原論」「憲法」「日本政治史」「日本経済史」「統計学」(時子山)、「民法」「社会思想研究」(酒枝)、および「外国書研究」(英、独、仏、支、露が置かれ、いずれも経済学、政治学の二つに分かれた。経済学の担当は、それぞれ小松、山川、久保田、青柳、露は未定)である。
また、第二学年の場合には、一応選択科目も置かれたが、その科目数は、必修科目に比べると僅かであった。すなわち第二学年においては、必修科目には「経済学史」(久保田)、「経済政策」(林)、「貨幣及銀行論」(中村)、「西洋経済史」(小松)、「産業経済学」(久保田)、「商業経済学」(山川)、「経済機構論」(杉山)、「政治制度論」(大西)、「外国研究」(「米国研究」「支那研究」担任未定)の九科目が置かれたのに対し、選択科目は「民法」「行政法総論」「地方行政研究」の三科目にすぎなかったのである。
第三学年においては、選択科目は比較的多かった。すなわち必修科目は「財政学」(時子山)、「国際経済論」「社会政策」(平田)、「金融経済論」(中村)、「商法」「外国研究」(「英国研究」、「蘇聯研究」、担当は前者が小松、後者は未定)の六科目、他方、選択科目は「日本政治思想史」「行政法各論」「刑法」「国際政治論」「外交史」「戦後経済研究」「演習」(久保田、小松、酒枝、杉山、時子山、中村、平田)の七科目であった。しかしながら、戦前には必修科目の重点科目とされた「演習」が選択科目とされ、ここでも戦争直前のカリキュラムの基本的枠組みが復活していないのである。
敗戦後の混乱にも拘らず、早くも二十年九月に授業を再開したという学苑教職員の学問、教育への情熱が称賛されるべきであって、カリキュラムに不備があったとしても、決して非難には当たらないのかもしれないが、それはともかく、敗戦直後のカリキュラムの改正が既述のように、必ずしも建学の精神に基づかない不十分なものであったためであろうか、翌二十一年に、再びカリキュラムが手直しされた。
この改正は全学的規模で行われたものであるが、我が学部の改正の趣旨は、昭和二十一年四月に文部省に提出された改正申請書によれば、「戦後ノ日本再建及世界経済ヘノ積極的参加ニ応ズベキ教育ノ確立ヲ期」すために、「戦時ノ要請ニ依リ学問ノ簡素化ヲ理由トシテ実施シ来レル学年制」を廃し、「学年制ト科目制トノ長所ヲ綜合シテ学生ノ自主的勉学奨励」を促すことにあったという(大学史編集所保管『昭和十九年七月起 文部省関係 教務課』)。
しかし実際のカリキュラムを見ると、二十年のそれと、さほど異らない。
先ず、第一学年は二十年とほぼ同様で、選択科目がなく、必修科目も「社会学」が追加されただけで、その他は同じであった。第二、第三両学年の場合には、第二学年では選択科目が前年よりも充実し、三科目から七科目に増えたことが特徴的である。第三学年は、前年とあまり異なるところがないが、強いて言えば、選択科目の中に、「戦後経済研究」という、いかにも戦後期にふさわしい科目が置かれたことであろう。いずれにしても、敗戦直後の時期におけるカリキュラムの改革は、建学の精神である自学自修という観点からすればなお不徹底であり、そうした課題は、二十四年四月に発足した新制政治経済学部にまで持ち越されるのである。
昭和二十四年度に、新制大学として、第一政治経済学部(昼間学部)と第二政治経済学部(夜間学部)が発足した。これら二つの学部の経済学科のカリキュラムは大綱に関して同一であり、また第二政治経済学部は昭和四十一年度以降学生の募集を停止したから、以下においては、第一政治経済学部と、それに続く政治経済学部の経済学科における専門教育科目の編成を取り扱うことにする。
第一政治経済学部には、昭和二十四年度に、第一年度生・第二年度生・第三年度生が同時に受け入れられたが、経済学科の専門教育科目は、必修科目と選択科目に区分されて、第二年度と第三年度の科目として配当された。
第二年度の必修科目は、「経済学原論」(酒枝義旗)、「政治学原論」(吉村正)、「西洋経済史」(小松芳喬)、「憲法」(大西邦敏)の四科目であり、選択科目は、「西洋政治史」(市村今朝蔵)、「社会学原理」(武田良三)、「民法」(千種達夫)の三科目である。また、第三年度の必修科目は、「経済学史」(久保田明光)、「貨幣及銀行論」(中村佐一)、「統計学原理」(保田順三郎)、「外国書研究」(英書―小松雅雄・山川義雄、独書―山川義雄、仏書―増田冨壽のうち一つ)の四科目であり、選択科目は、「現代経済学説」(久保田明光)、「工業経済学」(平田冨太郎)、「商業経済学」(山川義雄)、「経済機構論」(杉山清)、「日本経済思想史」(野村兼太郎)、「日本経済史」(野村兼太郎)、「行政学」(吉村正)、「比較政治制度論」(大西邦敏)の八科目である。
次いで、昭和二十五年度に、第四年度の科目が設置され、当初の科目編成が完成された。必修科目は、「財政学」(時子山常三郎)、「経済政策」(出井盛之)、「外国書研究」(英書―杉山清・堀家文吉郎・伊達邦春、独書―酒枝義旗、仏書―久保田明光のうち一つ)の三科目であり、選択科目は、「国際経済論」(中島正信)、「金融経済論」(中村佐一)、「農業経済学」(久保田明光)、「社会政策」(平田冨太郎)、「近代社会思想」(井伊玄太郎)、「国際政治論」(大山郁夫)、「労働法」(吾妻光俊)、「商法」(大浜信泉)、「経済地理」(佐藤弘)、「祖税論」(時子山常三郎)、「演習」(中村佐一、増田冨壽、保田順三郎、出井盛之、小松雅雄、堀家文吉郎、堀江忠男、伊達邦春)の十一科目である。
全体としては、必修科目が十一科目、選択科目が二十二科目であり、卒業に必要な専門教育科目の単位数は、必修科目が十一科目で四十四単位、選択科目が十科目で四十単位、合計八十四単位である。
昭和二十四・二十五年度に編成された専門教育科目の学科目表は、その基本的骨組みについて何らの変更もうけずに昭和四十年度の入学者まで適用されたが、その間、(ⅰ)科目の増設、(ⅱ)科目の配当年度の変更、(ⅲ)卒業に必要な単位数の変更、および(ⅳ)担当者の変更が行われた。
(ⅰ)科目の増設
必修科目は、先ず、昭和二十七年度に「外国書研究」が第二年度にも配当されたことにより、十二科目になった。次いで、昭和二十九年度に、「日本経済史」が選択科目から必修科目に変更されたが、同時に第四年度配当の「外国書研究」が必修科目から選択科目に変更されたので、必修科目数は変らなかった。更に、昭和三十四年度に「外国書研究」が第一年度配当の必修科目として増設されたので、必修科目数が十三科目になった。
一方、選択科目は、先ず、昭和二十六年度に、「交通経済学」(河辺㫖)、「会計学」(黒沢清)、「経営学」(古川栄一)が、第三年度配当科目として増設された。次いで、昭和二十七年度に、「簿記」(黒沢清)が第二年度配当科目として、「行政法」(佐藤立夫)が第三年度配当科目として、そして「計量経済学」(山田勇)、「現代経済史」(増田冨壽)、「労働問題」(藤林敬三)が第四年度配当科目として増設された。次いで、昭和二十八年度に、「中国経済研究」(安藤彦太郎)が第四年度配当科目として増設された。更に、昭和三十四年度に、「地方行政」(弓家七郎)が第四年度配当科目として増設された。
(ⅱ)科目の配当年度の変更
先ず、昭和二十七年度に、「経済地理」が第四年度から第二年度に、「経営学」が第三年度から第二年度に、「農業経済学」「商法」「労働法」が第四年度から第三年度に変更された。次に、昭和三十四年度に、「社会政策」が第四年度から第三年度に変更され、また、昭和三十五年度に、「現代経済学説」が第三年度から第二年度に変更された。更に、「演習」は、当初、第四年度に配当されたが、昭和二十七年度から、第三年度の後期と第四年度の前期を通じて履修させることに改められた。
(ⅲ)卒業必要単位数の変更
卒業に必要な専門教育科目の単位数は、昭和二十七年度から必修科目が一科目四単位増えて、八十八単位となり、また昭和三十四年度から、必修科目が一科目四単位増えて、九十二単位になった。
(ⅳ)担当者の変更
必修科目のうち、「経済学原論」は、昭和四十一年度から伊達邦春が担当し、「政治学原論」は、昭和三十八年度について堀豊彦、三十九・四十年度について松平斉光、四十一年度について服部弁之助が担当した。また、「貨幣及銀行論」は、昭和三十六年度から堀家文吉郎が担当し、「日本経済史」は、昭和二十六年度から滝川政次郎、昭和三十七年度から正田健一郎が担当した。また、「経済政策」は、昭和二十七年度から小松雅雄が担当し、昭和三十六年度については長守善、昭和三十七年度については加藤寛、昭和三十八・三十九年度については西宮輝明、昭和四十―四十三年度については気賀健三が担当した。更に、「外国書研究」のうち、英書の担当者として、鶴岡義一、阿部賢一、堀江忠男が昭和二十六年度に、河辺㫖、出井盛之、山岡喜久男が昭和二十七年度に、正田健一郎、平田寛一郎が昭和二十八年度に、田中駒男が昭和三十二年度に、安藤哲吉、大和瀬達二、深沢実が昭和三十三年度に、柏崎利之輔が昭和三十五年度に、岡山隆が昭和三十八年度に、渋谷行雄、小林謙三、古賀比呂志、佐竹元一郎、上原一男が昭和四十年度に加わった。また、独書の担当者として、杉山清が昭和二十八年度に、伊達邦春が昭和二十九年度に、小松雅雄が昭和三十三年度に、大和瀬達二が昭和三十六年度に、平田寛一郎が昭和三十七年度に加わった。そして仏書の担当者として、山内義雄と鶴岡義一が昭和二十六年度に、保田順三郎が昭和二十七年度に、岡山隆が昭和三十年度に加わった。
一方、選択科目のうち、「西洋政治史」は昭和二十五年度から松本馨、「現代経済学説」は昭和二十七年度から伊達邦春、「経済地理」は昭和三十八年度から田中薫が担当した。また「農業経済学」は昭和四十一年度から田中駒男、「工業経済学」は、昭和二十六年度について、および昭和三十五年度から山岡喜久男、「交通経済学」は昭和四十一年度について高橋秀雄、「日本経済思想史」は昭和三十五年度から島崎隆夫、「行政学」は昭和三十八年度から後藤一郎、「比較政治制度論」は昭和三十七年度から清水望、「商法」は、昭和三十一年度について林義雄、昭和三十二年度について高鳥正夫、昭和三十三―三十九年度について大野実雄、昭和四十一年から星川長七が担当した。更に、「国際経済論」は、昭和三十六・三十七年度については出井盛之、昭和三十八―四十一年度について渡部福太郎、昭和四十二・四十三年度について岡山隆、「金融経済論」は、昭和二十七年度から堀家文吉郎、昭和三十二年度についてと昭和三十六年度から鶴岡義一、「労働問題」は昭和三十年度から平田冨太郎、「祖税論」は昭和二十七―三十五年度について阿部賢一、昭和三十七年度から平田寛一郎、「国際政治論」は昭和二十七年度から吉村健蔵、「地方行政」は昭和三十六年度から後藤一郎が担当した。
また「演習」の担当者として、杉山清、山川義雄、鶴岡義一、伊部政一、佐倉重夫、山岡喜久男が昭和二十六年度に加わり、次いで阿部賢一が昭和二十八年度に、酒枝義旗、正田健一郎、平田寛一郎が昭和三十年度に、安藤彦太郎、岡山隆、藤田武夫、山辺孝が昭和三十一年度に、早川三代治が昭和三十二年度に、久保田明光、小松芳喬、平田冨太郎、田中駒男、松村勝治郎、古川栄一が昭和三十三年度に、安藤哲吉、大和瀬達二が昭和三十四年度に、時子山常三郎、河辺㫖、菅谷重平が昭和三十六年度に、柏崎利之輔が昭和三十七年度に、渋谷行雄、小林謙三、古賀比呂志、佐竹元一郎、上原一男、安藤良雄、深沢実が昭和四十一年度に、そして島崎隆夫が昭和四十二年度に加わった。
経済学科の専門教育科目の学科目表が大幅に改訂され、それが適用されたのは、昭和四十一年度入学者からである。同年度は、新聞学科と自治行政学科の学生の募集が停止された年である。新しいカリキュラムでは、専門教育科目における必修制が廃止され、すべての専門教育科目が選択科目にされた。その際、それぞれの学科目は、その性質に従って、A・B・C・Dの四群に分類された。
A群の学科目は、経済学科に最も関連の深いものである。そこには、第二年度配当の「理論経済学Ⅰ」「経済学史」「統計理論」「日本経済史」および「西洋経済史」、第三年度配当の「理論経済学Ⅱ」「貨幣理論」「現代経済学説」「社会主義経済学」「財政学」「社会政策」および「経済地理学」、そして第四年度配当の「国際経済学」および「経済政策」の合計十四科目が含まれている。これらのうち、「理論経済学Ⅰ」と「理論経済学Ⅱ」についてはそれぞれ三組、その他の科目についてはそれぞれ二組が設置された。
B群の学科目は、A群の学科目に次いで経済学科に関連の深いものである。そこには、第三年度配当の「経済統計」「現代日本経済史」「現代西洋経済史」「交通経済学」「日本経済思想史」「経営学」「会計学」「金融経済学」「経済学研究」および「演習」と、第四年度配当の「計量経済学」「労働経済学」「農業経済学」「工業経済学」「商業経済学」「日本経済論」「中国経済論」「国際金融論」「財政学各論」「地方財政論」「社会保障論」「経済学研究」および「演習」(第三年度の「演習」の継続)の二十二科目が含まれている。
C群の学科目は、政治学科のA群・B群科目や、昭和四十一年度以降学生募集を停止した新聞学科・自治行政学科の配当科目のうち引続き設置することが必要と認められた科目である。その中には、第二年度配当の「政治学原論」「憲法」「行政学」「政治学史」「西洋政治史」「社会学原理」「近代社会思想」「社会心理学」「マス・コミュニケーション発達史」「民法」および「簿記」と、第三年度配当の「国際政治学」「比較政治制度論」「日本政治史」「行政法総論」「地方行政」「経済数学」「マス・コミュニケーション理論」「社会調査」および「商法」と、第四年度配当の「現代政治学説」「都市問題」「農村問題」「マス・メディア論」「労働法」および「手形・小切手法」がある。
D群科目は、経済学関係の「外国書研究」であり、英語・独語・仏語によるものが、それぞれ、第一年度、第二年度、および第三年度に配当されている。
昭和四十一年度入学者については、卒業に必要な専門教育科目の単位数は、A群科目から四十四単位、B群科目から二十八単位、C群科目から二十単位、D群科目から八単位、合計百単位に定められた。また、「その他」部門から十二単位履修することが卒業に必要な要件とされたが、この部門の履修は、専門教育科目、一般教育科目、および「その他外国語」の中から自由に選択できるものとされた。しかし、昭和四十二年度入学者からは、B群科目とC群科目からの取得単位数がそれぞれ四単位削減され、また昭和五十三年度入学者からは、A群科目と「その他」部門からの取得単位数がそれぞれ四単位削減された。この結果、現在、卒業に必要なA・B・C・D群科目からの取得単位数は八十八単位、「その他」部門からの取得単位数は八単位である。
昭和四十一年度入学者から適用された新カリキュラムにおける科目担当者は、次の通りである。
(ⅰ)A群科目の担当者
第二年度配当の「理論経済学Ⅰ」は、昭和四十二年度から一組を大和瀬達二が、そして二組を伊達邦春が担当し、後者のうち一組を昭和五十五年度から薬師寺明久が担当している。「経済学史」は、昭和四十二年度について久保田明光と山川義雄が一組ずつ担当したが、昭和四十三年度から山川義雄が二組を担当し、そのうちの一組を昭和四十八年度から上原一男が担当し、更に昭和五十三年度から西川潤が担当者に加わり、昭和五十六年度まで二組を三人が交替で担当してきた。「統計理論」は、保田順三郎が当初から二組担当し、そのうちの一組を昭和四十八年度から佐竹元一郎が担当している。「日本経済史」は、昭和四十二・四十三年度については速水融が担当し、その後は、二組とも正田健一郎が担当している。「西洋経済史」は、当初、小松芳喬と増田冨壽が一組ずつ担当し、前者の定年退職後、一組を昭和五十四年度について尾上一雄が担当し、昭和五十五年度から鈴木健夫が担当している。
第三年度配当の「理論経済学Ⅱ」は、昭和四十三年度から一組を大和瀬達二が、そして二組を伊達邦春が担当し、後者の一組を昭和五十七年度から薬師寺明久が担当している。「貨幣理論」は、昭和四十三年度から二組を堀家文吉郎が担当し、そのうちの一組を昭和五十五年度から柴沼武が担当している。「現代経済学説」は、昭和四十四年度から二組を柏崎利之輔が担当しているが、昭和五十四年度については小野俊夫が担当した。「社会主義経済学」は、昭和四十三年度から二組を堀江忠男が担当し、そのうち一組を昭和五十六年度から鈴木勇が担当している。「財政学」は、昭和四十三年度から時子山常三郎と平田寛一郎が一組ずつ担当し、昭和四十六年度以降、二組とも平田寛一郎が担当している。「社会政策」は、昭和四十三年度から平田冨太郎と安藤哲吉が一組ずつ担当し、前者の定年退職後、その分を昭和五十四年度については安藤哲吉が、昭和五十五年度から古賀比呂志が担当している。そして「経済地理学」は、昭和四十三年度については田中薫、昭和四十四年度から奥田義雄が二組とも担当している。
第四年度配当の「国際経済学」は、昭和四十四年度について田中喜助、昭和四十五年度について大畑弥七が二組とも担当し、昭和四十六年度から岡山隆が二組とも担当している。「経済政策」は、昭和四十四年度から小松雅雄が二組とも担当し、そのうちの一組を昭和五十一年度から諏訪貞夫が担当している。
(ⅱ)B群科目の担当者
第三年度配当の「経済統計」は、昭和四十三・四十四年度について梅村又次、昭和四十五―四十七年度について保田順三郎が担当し、昭和四十八年度以降、小林謙三が担当しているが、昭和五十二年度について保田順三郎、五十三年度について林文彦が交替して担当した。「現代日本経済史」は、昭和四十三年度以降、安藤良雄が担当している。「現代西洋経済史」は、昭和四十三年度から増田冨壽が担当し、昭和四十九年度から尾上一雄が担当している。「交通経済学」は、昭和四十三年度について河辺吉、昭和四十四・四十七年度について中西睦、昭和四十五・四十六年度について細田繁雄が担当し、昭和四十八年度から岡田清が担当している。「日本経済思想史」は、昭和四十三年度以降、島崎隆夫が担当し、昭和五十七年度から長幸男が担当している。「経営学」は、昭和四十三年度以降、古川栄一が担当し、昭和五十年度から別府祐弘が担当している。「会計学」は、昭和四十三年度から黒沢清が担当し、昭和四十八年度から新井清光が担当しているが、昭和五十二年度については染谷恭次郎が担当した。「経済学研究」は、昭和四十三年度以降、小松雅雄、安藤哲吉、上原一男、古賀比呂志、小林謙三、遊部久蔵、佐竹元一郎、諏訪貞夫、西川潤、田中駒男、山辺孝、小松憲治、鶴田俊正、鈴木健夫、金子敬生、和田禎一、南部宣行が、順次に担当してきている。
第四年度配当の「計量経済学」は、昭和四十四年度について倉林義正が担当し、昭和四十六年度から金子敬生が担当している。昭和四十四年度以降、「農業経済学」は田中駒男、「工業経済学」は山岡喜久男、「商業経済学」は山川義雄(昭和五十六年度まで)、「中国経済論」は安藤彦太郎、「国際金融論」は鶴岡義一が担当している。「財政学各論」は、昭和四十五年度から平田寛一郎が担当している。「労働経済学」は、昭和四十八年度から古賀比呂志が担当しているが、昭和五十二年度について永山武夫、昭和五十四年度について水野朝夫が担当した。「日本経済論」は、昭和四十四年度について金森久雄が担当し、昭和四十五年度から高橋毅夫が担当している。「地方財政論」は、昭和四十四年度以降、藤田武夫が担当し、昭和五十年度から佐藤進が担当しているが、昭和五十三・五十四年度について高橋誠が担当した。「社会保障論」は、昭和四十四年度以降、安藤哲吉が担当しているが、昭和四十九―五十一年度について平田冨太郎が担当した。
第三年度から第四年度にかけて配当されている「演習」は、昭和四十二年度までに担当者となった、安藤哲吉、安藤彦太郎、安藤良雄、上原一男、大和瀬達二、岡山隆、柏崎利之輔、河辺㫖、古賀比呂志、小林謙三、小松雅雄、小松芳喬、佐竹元一郎、渋谷行雄、島崎隆夫、正田健一郎、伊達邦春、田中駒男、鶴岡義一、平田寛一郎、平田冨太郎、深沢実、古川栄一、堀江忠男、堀家文吉郎、増田冨壽、保田順三郎、山岡喜久男、山川義雄の他に、岩倉誠一(政治学科の演習と共通)、安井俊雄(同上)、諏訪貞夫が昭和四十三年度に担当者となり、次いで奥田義雄、柴沼武、田村貞雄、西川潤、別府祐弘、孫田良平、松田寛が昭和四十五年度に、金子敬生が昭和四十六年度に、蔵田久作が昭和四十八年度に、鈴木健夫、薬師寺明久が昭和四十九年度に、小野俊夫が昭和五十年度に、南部宣行が昭和五十二年度に、そして和田禎一が昭和五十五年度に担当者に加わった。
(ⅲ)C群科目の担当者
ここでは、重複を避けるために、政治学科のA群・B群・C群に含まれていない科目について、担当者を挙げることにする。第二年度配当の「簿記」は、昭和四十二年度以降、黒沢清が担当し、昭和四十八年度から小川冽が担当しているが、昭和五十三年度については染谷恭次郎が担当した。第三年度配当の「経済数学」は、昭和四十三年度以降、蔵田久作が担当している。第四年度配当の「手形・小切手法」は、昭和四十四年度以降、長浜洋一、金沢理、酒巻俊雄、中村真澄、奥島孝康、星川長七が交替で担当してきている。
(ⅳ)D群科目の担当者
「経済英書」は、昭和四十年度までに担当者となった、安藤哲吉、上原一男、大和瀬達二、柏崎利之輔、古賀比呂志、小林謙三、佐竹元一郎、渋谷行雄、田中駒男、深沢実、山岡喜久男の他に、松田寛、山之内光躬が昭和四十一年度に担当者となり、次いで諏訪貞夫が昭和四十二年度に、柴沼武が昭和四十三年度に、小林茂が昭和四十四年度に、西川潤、田村貞雄が昭和四十五年度に、鈴木健夫、薬師寺明久が昭和四十七年度に、小野俊夫、小松憲治が昭和四十八年度に、和田禎一が昭和五十年度に、内島敏之、南部宣行が昭和五十二年度に、小林逸太が昭和五十三年度に、金子敬生が昭和五十四年度に、浅野克己、古賀勝次郎、田村正勝が昭和五十六年度に、そして川勝平太、永田良が昭和五十七年度に担当者に加わった。また「経済独書」は、昭和四十年度までに担当者となった大和瀬達二の他に、難波田春夫が昭和四十一年度に担当者となり、次いで古賀比呂志と小林謙三が昭和四十四年度に、鈴木健夫と南部宣行が昭和五十二年度に、大西健夫が昭和五十四年度に担当者に加わった。そして「経済仏書」は、昭和四十年度までに担当者となった岡山隆と鶴岡義一の他に、諏訪貞夫が昭和四十二年度に、西川潤が昭和四十五年度に担当者となったが、昭和五十七年度については堀川士良が担当している。
大学院というものを、一応、学部ないし本科の卒業生が、更に研究を深める課程と考えてみると、明治二十六年八月十五日付『中央学術雑志』第二巻第八号に「夙に公にせられたる専門学校の研究科は漸く其規則を定め九月より実施することとせり」という記事が初めて現われる。これは創立以来十一年目のことである。従って、研究科の実体はこれ以前に発生していた。つまり「本校得業生」で、「既修ノ学科」を「尚深ク研究」せんとする者のためで、「品行方正学業優等」で「大成ノ見込アル者」を「其部委員ノ協議ヲ経テ入学」が許される。「指導ヲ擔当」する講師を指定し、「期限ヲ二年」とする。「論文ヲ作リ」指導講師が「意見ヲ付シテ本校ニ差出ス」。論文と講師の意見が学部委員の「審査」をつけて、本人に研究科卒業を証明する。このように、「研究室ニ出席シ」、「本校ノ許可ヲ得テ本校ノ授業ヲ傍聴」でき、論文の作成を主として、研究することが示されている。
明治三十二年八月「私立学校令」が公布されたので、明治三十三年三月に、東京専門学校はこの法令による学校となった。
東京専門学校は、学問の独立が国の独立の前提であり、そのため、日本語で教える大学を目指し、学問の活用つまり、知識・理論の応用を重視した。明治三十五年、創立二十周年を期し、早稲田大学と改称した。地名をもつ大学としては本邦で最初のものであり、三月二十八日付けで三代校長 鳩山和夫が東京府知事に改称願書を提出し、同年九月二日に、文部大臣より「校名改称認可書」を受けている。そして、大学部(政治経済学科、法学科、文学科)、専門部、高等予科、研究科が設置されている。
『早稲田学報』臨時増刊第七〇号(明治三十五年七月十五日発行)に「早稲田大学規則一覧」が掲載されている。「早稲田大学規則」第六章が研究科規則になっている。それによると、「各学部得業生」で、「既習ノ学科ニ就キ尚ホ深遼ナル研究ヲ為シ傍ラ広ク外国語ノ知識ヲ養ハントスル者」のために設けている。
国法、行政法、国際法、経済財政、民法、商法、哲学、史学、英文学、社会学の部門に分ける。しかも、他大学の卒業生の入学を拒まず、「本校試験委員ノ検定ヲ経ル」を条件として認可している。年限に関しては、「別に学年ノ区別ヲ設ケズ一年以上三年以内ノ範囲ニ於テ何時ニテモ卒業論文ヲ提出シ、指導講師ヲ以テ組織セル試験委員ニ於テ学力相当ト認ムルトキハ得業証書ヲ授ク」とある。
「授業課目」は、「講義、毎週二時間」。これは指導講師が担当するが、科外講師も嘱任されることがある。ただし、講題は学年初めに予め定められる。「名著研究、毎週二時間」これは指導講師が指定するが、講師の同意の上で書名を定めたり、それに関する質問を学生ができることになっている。「問題研究、毎週二時間」これは特修ないし専攻科目のようである。入学時に定めて、指導講師の「認諾ヲ経ル」となっている。「外国語、毎週六時間」「論文」は指導講師の指示で起草することになっている。「卒業論文」は「問題研究ノ為メニ定メタル題目ニ限ル」と規定している。従って、「講義」「名著研究」「問題研究」「外国語」「論文」「卒業論文」の六つの種類となる。そして、年三十三円が学費で、分納は月に三円である。また他大学卒業生の受験料は五円である。図書、他の講義の傍聴、学則遵重の規定は一般学則による。
このような学則によって、研究科が設置され、運営されて、大学を自称して十七年が経過した。その間、明治三十七年に、「専門学校令」による大学として、大学部商科を設け、明治三十八年には、大学部卒業生に学士号の授与を決定した。明治四十二年には大学部理工科を設置した。
大正九年二月「大学令」による大学として認可され、大学自称の時代が終った。そこで、同年四月、政治経済学部、法学部、文学部、商学部、理工学部の五学部と大学院と付属早稲田高等学院が設置された。こうして、研究科に代り、大学院が登場する。これが、いわゆる旧制大学院なのである。
昭和九年四月、「早稲田大学学則」の改正が行われている。この学則の第九章が大学院に関するものである。この章は十一条で構成されている。その要旨は次のとおりである。
入学は学年初めとする(一条)。「各学部卒業生ニシテ大学院ニ入学セント欲スル者ハ研究事項ヲ具シ本大学ニ願出ツヘシ……当該学部教授会ノ議ヲ経テ……許可ス」(第二条)となっており、他大学卒業の大学院入学志望者は「当該学部教授会ノ検定ヲ経テ」許可され、「検定料金拾円ヲ」納入することになっている(第三条)。「大学院学生ハ当該学部長」の「監督」のもとにあり(第四条)、「当該学部教授会ノ議ヲ経テ選定シタル一名又ハ数名ノ教員」の指導を受ける(第五条)。「在学年期ハ一ヶ年以上」(第六条)。「大学ノ許可ヲ経テ各学部ノ講義又ハ実験等ニ出席スル」(第七条)。「時々其研究状況ヲ指導教員ヲ経テ当該学部長ニ」大学院学生は報告しなければならない(第八条)。また、他の業務を持ち、「東京市又ハ其附近以外ニ居住」してはならず、「本大学附属学校ノ教職」に就くことだけが例外とされている(第九条)。大学院学生が「学位ヲ得ント欲」すれば、「其研究事項ニ付論文ヲ総長ニ提出」する。その論文の審査を当該学部教授会に総長が行わせる(第十条)。学費は、百四十円で、一学期、二学期に各五十円ずつ、三学期は四十円の分納も認め、入学登録料は五円である(第十一条)。
更に昭和二十年四月改正の学則によると、前掲の十一条に七条を加へて、十八条になる。
「大学院ニ昭和十八年文部省令第七十四号ニ依リ特別研究生ヲ置ク」(第十二条)。特別研究生志望者は先づ大学院学生として入学した者のうちから「更ニ総長審査ノ上文部大臣ニ推薦シ其認可ヲ経テ第一期ノ特別研究生」となる(第十三条)。「第二期ノ特別研究生ハ本人ノ研究事項、研究業績及指導教授ノ意見ヲ徴シ第一期ノ特別研究生ニ準シ」て選定する(第十四条)。特別研究生に学資として第一期月額九拾円を給与し、引続き三ヵ月以上に渉り休学するとき四ヵ月目より半額とする(第十五条)。休学、復学は指導教授および学部長を経て総長に届けでること(第十六条)。「昭和十八年文部省令第七十四号第十六条ノ規定ニ依リ返還スベキ学資及研究費ノ額」については第十七条が規定する。また、第三条に、「外国留学生ハ別ニ国語考査ヲ経テ其合格者ニ限リ当該学部教授会ノ検定ニ附スル」という項を追加し、大学院への留学生受け入れを認めている。
「学則」附録、早稲田大学学位規程、第二条には、「学位ハ本大学大学院学生ニシテ二年以上研究ニ従事シ論文ヲ提出シテ学部教授会ノ審査ニ合格シタル者」に授与するとの定めになっている。
昭和二十年改正「早稲田大学学則」の第十二条以下に見られる「特別研究生」に関して若干補足しておこう。
昭和十二年から中国との戦争は拡大を続け十六年に太平洋戦争に突入した。そこで学制改革、大学教育年限の短縮が軍事上の必要から断行された。その結果、学力低下を防止するのみでなく、優秀な学者の養成を目的とし帝国大学の大学院を拡張整備し、年々全国官私大学卒業者中より五百名を限り、文部省が選抜試験をして七帝大に配付し、研究させて年千円の奨学金を数年に亘って支給し、徴兵猶予の特典を与える。これが特別研究生に関する原案である。『早稲田学報』第五七五号(昭和十八年一月一日発行)で、「学制改革と大学院問題」と題して田中穂積総長が文部省案を批判している。「官私大学を平等視せる三十年来の伝統を破壊し、官学万能の旧態」に戻り、「我邦文化の発展を根底より阻碇する」として理由をあげている。政府案によると、早大の教授たるべき人材の養成を帝大に托することになり、我が国の官私の大学の教授・助教授すべて帝大大学院出身者になり、各大学の特長がなくなる。そうすれば我が国文化の発展を促すものがなくなる。七帝大大学院のみに優秀な学生養成を限るのは、優秀な学者を多く必要とすることと矛盾する。また五百名では僅少すぎる。選択試験が文部省で行われ、試験委員が主として官立大学教授であれば、受験者にとって不公平である。選択試験が一回のみではなく寧ろ官私大学の教授会に最善の方法を考えさせ、政府は大学院拡充整備のための金額を官私大学に公平に分配して、簡易・適切な方法を求めるのがよいと力説している。
また、『早稲田フォーラム――大学問題論叢――』第6号〈特集 大学院の現状と改革〉で、小松芳喬名誉教授が「大学院昔譚――自伝的随想――」を書かれている。それによると、昭和三年頃から、昭和四十九年頃までの様子が分る。先生が旧制大学院に昭和三年に入学され九年に退学されるまでが大学院学生として、その後は教授として体験された記録である。「旧制大学院はカリキュラム等というものは全然なく、自由放任の極でした」と書かれ、指導教授によっては研究計画も指導計画も学生にまかせる方針の方もおられ、毎週、一週間おき、二週間おき月に一度とか二ヵ月に一度、指導教授の「お宅にお伺いして報告する。」このような「指導教授の個人的指導が殆ど全部なので学生間の交渉もまずなく、教員も大学院学生をあまり知らないのが普通のようです。」それでも、図書館長林癸未夫先生、出井盛之先生の門下生はそれぞれ教授を中心に毎月一回ぐらいの割合で研究発表をし、時に田中穂積総長が顔を出されたり、機関紙を発行したりもされている。「また在学年限の定めもなく、納入した学費はそっくり指導教授に大学から交付されていた。大学院学生数の制限がなく、特別入学試験もなく個人指導が原則で最善とされていた。」ただ例外として外国人留学生等を引き受けられた教授は集団指導もされていた。
「昭和十八年秋の大学院特別研究生は、全国十二の大学、私立では、早・慶の両校のみのごく少数の者でした。なかには選ばれても辞退された方もおられた」が、戦後、就職先発見の困難、繰上げ卒業者の学力不足の自覚、外地からの復員、引揚げ後の内地への順応のためなどの理由で大学院に籍を置くこともあってかなり急速に大学院学生数が増加した。
旧制大学院には、「修業年限が全く無制限、特別な講義も特別な施設もなかった。博士論文作製が目的でも、法文系では大学院で学位論文を書いた学生は例外でしょう。」早大の場合、「図書館の書庫が開放されているのが唯一の魅力で、学生もそれ以上を求めなかったので、大学当局もごく少数の大学院学生のために何かを考える」姿勢はなかった。旧制大学院は「野放しとも言うべき制度で、ヨオロッパ大陸の大学のやり方の日本的特殊性濃厚な亜種とも見られましょう」と描かれている。
第二次大戦後、六・三・三・四のアメリカ的学制の導入が行われ、これが新制大学院として結実したのは、「いわば革命的な変革」(小松芳喬、前掲)だった。昭和二十三年一月二十九日、翌二月一日の二回大学院基準について理事会で報告があり、八月五日に理事会で大学院について協議した。昭和二十四年九月「大学院制度研究会」委員嘱任が理事会で協議され、十二月二十四日、大学院基準の報告が理事会で行われ、翌二十五年一月、「大学院に関する小委員会」の中間報告を受け、委員追加を協議した。二月の理事会で「大学院設置準備委員会」の設置を決め、吉村正、久保田明光、河辺㫖、山本研一、佐々木八郎、中谷博、中村宗雄、松田治一郎、堤秀夫、南和夫の十教授を学部長会議を経て、委員に嘱任している。
「「基準協会」成立の二年前に文部省に「大学協議会」があり、当時の国・公・私大をメンバーとして、商大学長上原専禄、日大総長呉文炳など二十名が集まって、間接的にGHQの要望を聞き、戦後の大学はどういう型にすべきかを話し合っていた。アメリカで、各大学がグループを作り、自主的に大学の品位を高めているので、日本でも自主的に「基準協会」を設置してはどうかということで、昭和二十二年七月に発足した。」(伊原貞敏「鼎談大学院創設のころ」『早稲田学報』昭和四十六年六月発行第八一二号)新制大学、大学院の問題はここから正式にはスタートした。
ところで、本学の「大学院設置準備委員会」は総長に対し、昭和二十五年五月二日に「報告書」を提出している。また同月十八日に、同委員会の答申書を理事で会議している。この頃より大学院を巡る論議が活発に行われた。
理事会記録によると、前記十名に末高信、中島正信を加えた十二名の「大学院設置準備委員会」は島田孝一総長に「報告書」を提出した。この内容は、大学院には修士と博士の課程があるが、まだ「大学設置審議会」の審議要項が確定していないので、修士課程のみを取扱い、「一、大学院の組織と学部学科の組織との関係」「二、研究専門課程別学科目概要」「三、履修方法及び学位授与概要」「四、研究科別学生定員」「五、職員組織」「六、建物」となっている。
本大学院は六研究科からなり、政治学研究科(政治経済学部政治学科・自治行政学科)、経済学研究科(政治経済学部経済学科)、法学研究科四専攻(法学部)、文学研究科(文学部哲学・文学・史学科・教育学部教育学・国語国文学・英語英文学・社会科)、商学研究科(商学部)、工学研究科(理工学部機械工学・電気工学・鉱山学・応用化学・金属工学・電気通信学・工業経営学・土木工学・応用物理学・数学科)の系統となる。学部の延長とはしないことが多数意見で、少数意見に各学科を学部内に置くべきであるとした。学科目の配列は形式的配列主義を採らず、十分な能力のある教員に則して編成することを建前とした。そして単位制を導入する。その計算は、大学基準に則り、講義は毎週一時間十五週を一単位、ただし、演習は毎週一時間十五週を二単位としている。経済学研究科はこの時点で未定となっている。経済学修士の学位を得るには、全日制で二ヵ年以上在学し、専攻科目について三十単位以上履修し、研究論文を提出しなければならない。修士の合格は一科目六〇点以上、平均七〇点とする。各研究科学生定員は各研究科ごとに専任教員一名につき学生十名以下としている。大学院教員は、設置時において、大学院教員銓衡委員会を設け、「大学院に関する基準要項」を尊重して、高度の基準で旧制学部または部・科・学校の教員の中から選び、大学院設置後は、大学院担当教員で組織する委員会が銓衡する。また教員の所属は学部本属ではなく、専攻に適する研究科にしたいし、授業担当時間は週六時間以内で、待遇も特別に考えられたいと希望を述べている。建物として、文科系研究科専用校舎は恩賜館跡(現七号館)、工学研究科は理工学研究所の復興を第一期工事とするよう希望している。
この「報告書」を叩き台に十六回の理事会での協議を経て、昭和二十五年十一月九日の理事会で新制大学院設置を決議した。
昭和二十六年四月に新制大学院を設置し、大学院の目的を明確にした。「学部の教育の基礎の上に、高度にして専門的な学術の理論及び応用を研究教授し、その深奥を究めて、文化の創造、発展と人類の福祉に寄与すること」である。大学院には修士と博士の課程があり、博士課程は昭和二十八年四月設置とす。修士課程は学部卒業者で二年以上大学院に在学し、三十二単位を履修し、論文の判定に合格すれば修士の学位を与える。経済学研究科は教授七、講師六名、毎年入学定員七十、総学生収容定員百四十名である。大学院に大学院委員会と各研究科委員会を置く。法文系大学院校舎は昭和二十六年六月三十日完成予定で恩賜館跡、予算は、収入千三百七十五万二千円、支出は人件費千百万三千八百円、物件費百八十五万七千九百円で、差引八十九万三百円の黒字を昭和二十六年度に計上し、他に基本勘定として、収入百九十九万五千円、支出五百五十万、差引不足三百五十万五千円を提案した。
十一月二十五日、定時維持会員記録を見ると、総長は、「専攻については将来多少の変更があるかもわからぬ。……教員数及び学生数についても同様」と述べている。そして、「今後の努力を条件に維持員会の討議を終りたい。文部省から無条件で認可されるよう努力する。」と述べている。この無条件認可とは、新たに教員を採用する場合などに、いちいち「設置審議会」の教員資格審査を受けなくてもよいということで、この特権を人事・施設面で獲得することを意味している。また、「全国で……新制大学が逐年増加しつつある。充実した大学院を設置して……全国から俊才を集めて教育することが緊急と存ずる」とも力説する。早大の「意見は或いは文部省の大学設置審議会に、或いは大学基準協会にも反映させると共に学内で各学部教授会を挙げて御尽力を願って参りました。……新制大学院を設置いたしますことは一方大学の財政からみますならば、なかなか容易なことではない」としながらも、設置認可申請の手続を直に進めると言う。十一月三十日に申請が出され、大学院設置審議会の実地審査(翌二十六年三月十一日)を経て、四月五日付で大学院設置認可となった。
早稲田大学大学院は、総長を長とする大学院委員会と六つの大学院研究科委員で運営され、そこに二十三専攻が含まれ、その一つが、経済学研究科経済学専攻である。学部担当教員中、大学院担当教員は専任教授七名、兼任講師五名である。そして入学試験が四月十九日より第一次専攻科目、外国語(一ヵ国)第二次と行われた。定員五十名に対し、志願者は六十二名(内学内五十八)で合格者は四十三名の学内卒業生であった。志願者が少かった理由は、認可が遅れ、大部分の卒業生は就職が既に決定していたし、官公私立新制大学中、数校しかこの時点で卒業生を出していないためである。しかし近い将来全国新制大学からの卒業生が増加するので、特色のある大学院にしたいとした。
新制大学院学則(昭和二十五年十二月十五日)は、「第一章 総則」「第二章 学科目・単位数・履修方法」「第三章 試験・課程修了・学位」「第四章 教員・委員会・事務職員」「第五章 学年・学期・休業日」「第六章 入学・休学・退学・転学・懲戒」「第七章 入学検定料・入学金・授業料・実験実習費」「第八章 委託生」「第九章 図書館・博物館・研究所」「第十章 厚生・保健施設・附則」という構成で、六十三条という比較的細則に亘っている。
政経学部を基礎として、政治学研究科と経済学研究科の二つがあり、経済学研究科は定員百名の学生を持ち、次の科目(単位)で構成されている。一専攻(経済学)、六専修科目(「一般経済理論」「経済政策特論」「金融論」「西洋経済史特論」「日本経済史特論」「財政学特論」)他に、「社会主義経済論」「社会政策特論」「経済地理特論」「財政制度論」を持ち、一般経済理論専修は四部に、他の専修はそれぞれ二部に分かれ、それぞれの部が講義と演習からなり、各四単位である。専修以外の特論は講義のみである。合計百二十八単位の科目を、第一年度に六十八単位、残りを第二年度に分配している。また専門課程の学科目を二種に区別し、指導教授が二年に亘って指導する専修科目とそれ以外の特修科目とである。
履修方法は、経済学専攻の専修科目の第一、二部または第三、四部から一六単位(講義八、演習八単位)を選択必修する。残り十六単位は本研究科の講義または他研究科の講義の中から選択履修するが、他研究科の講義は四単位以内としている。講義十六単位と演習四単位を第一年度に、講義八単位と演習四単位を第二年度で修得するのだが、財政学特論専修科目は第一年度講義二十単位、第二年度講義四単位と演習八単位としている。学生は指導教授の指導で、学年初めにその年度の履修科目を選定する。
学年末に履修科目について試験を行う。平常成績を以て試験に代えることを研究科委員会が認めれば、その科目は試験を行わない。試験の方法は研究科委員会が決定し、成績は優・良・可・不可の四級とし、優・良・可を合格として単位を与える。論文は専攻の専門分野の精深な学識と研究能力を証示するに足るものを合格とし、審査と試問の二段階の綜合判定による。論文審査は、その指導教授を主査とし、二名以上の関連科目の担任教授を加え、ただし、必要がある時は講師を加えて行われ、試問は、研究科委員会が定めた審査員が共同して行う。所定の単位を取得し、論文に合格すれば、経済学修士の修士号を与える。
大学院の各研究科の運営は、所属教授で組織する研究科委員会が行い、研究科委員会は、⑴研究・教授に関する事項、⑵学位授与に関する事項、⑶学科課程に関する事項、⑷学生の入学・休学・退学・転学及び懲戒に関する事項、⑸その他研究科に関する重要事項を議決する。
また、各研究科に関する共通事項を審議するために、各研究科委員会から選出された者で組織する大学院委員会を置き、⑴研究及び教授に関する事項、⑵学生の懲戒に関する事項、⑶教務及び教則に関する事項、⑷その他大学院に関する重要事項を議決する。
大学院への入学資格者は⑴大学卒業者、⑵外国で十六年の学校教育課程を修了した者、⑶文部大臣の指定した者、⑷本大学院において、大学卒業者と同等以上の学力があると認めた者が所定の検定に合格し、手続き書類を提出した者である。入学検定料一千五百円、入学金五千円、授業料は法文系研究科年額一万四千円、工学研究科年額一万五千円である。更に、官公庁、外国政府等の委託に基づいて委託生を本大学で学習を許すこともある。
以上が、昭和二十六年四月一日より施行された早稲田大学大学院学則の概要である。
昭和二十六年五月上旬から大学院経済学研究科経済学専攻の授業が開始され、大学院校舎は建設中であった。大学院委員会は各研究科から二名ずつで構成されたが、経済学研究科は久保田明光、中村佐一両教授を送っており、経済学研究科委員長に久保田明光教授が選出された(昭和二十六年四月十三日学部長会記録)。
創立六十九周年記念日(昭和二十六年十月二十一日)、法文系・理工系両大学院校舎の落成式を兼ねた新制大学院開設式が秋雨のなか十時から大隈講堂で、教職員八百名、学生三百六十名、来賓に慶応義塾大学の潮田塾長など名士多数が集い、総長式辞、来賓祝辞、校歌の順で行われた。図書館ホールでの祝賀会では明治大学鵜沢総長の発声で早稲田大学万歳を三唱している。島田総長は、現在のところ六研究科、教員百四十二名、学生三百五十六名を数え、「特に本大学大学院は少数精鋭主義を採り、学生指導の面では情操の陶冶という点にも充分に考慮を払い、学問技術は勿論真の意味の人間完成への創造に努力しております」「大学院校舎は大いに誇り得るものと信じますが、教育の内容はむしろ実質的には人物創造の面にあると思います」「内容充実は実にかかって今後にあることを痛感いたします」と述べている。
大学院修士課程が開始されて間もない昭和二十七年一月十六日に、経済学研究科は学科目配当を変更した(定時評議員会議決事項)。
経済学研究科は、一専攻、八専修科目(二科目追加)となる。それは、専修科目に「社会政策特論」「社会主義経済理論」が特修科目から専修科目に移動したに過ぎない。また専修科目の名称変更(「経済理論特論」←「一般経済理論」「金融論特論」←「金融論」)があり、また専修科目一般経済理論のうち「第一部」は「英・米・仏――近世」に、「第二部」は「英・米・仏――現代」に、「第三部」は「独・墺――近世」に、「第四部」は、「独・墺――現代」になり、「経済政策特論」のうち「第一部」を「基礎論」に、「第二部」を「特殊研究」に、「金融論特論」も「貨幣」「銀行・金融」に、「西洋経済史特論」も「中世」「近世」に、「日本経済史特論」も「中世」「近世」に、「財政学特論」でも「基礎論・国家財政」「地方財政」に変えて明確にした。
履修方法については、選択必修の十六単位は社会主義経済理論を除く専修科目の中から選択できるようになった。更に、第一年度で「経済理論特論」「経済政策特論」のいずれかを専修科目とした者は第二年度に「社会主義経済理論」を専修科目とすることが許されるようにもなった。
大学院に博士課程を置くことが予定されていたが、昭和二十七年五月二十三日、学部・大学院合同会で、「大学院博士課程設置研究委員会」を設けることに決定した。各系統学部教授会から互選で一名ずつ、大学院各研究科委員会から互選で一名ずつ委員を出して構成する。この委員会は、十月十七日の臨時学部長会で「大学院博士課程設置委員会」について審議した。この委員の選出法も「設置研究会」と同じであるが、政治経済学部にあってはその必要があれば、政治学系統、経済学系統から各一名計二名を選出できる。この委員会は翌十八日から開催される。十一月七日の学部長会で「大学院博士課程設置委員会」が設置され、特別委員制を採ると報告している。特別委員は常時委員会に出席し、発言でき、学科目配当と教員人事を提議する時は出席が義務づけられているが、票決権はないという制度である。委員は十三名で、政治経済学部から吉村正(政治学系統)、中村佐一(経済学系統)の両教授、政治学研究科の大西邦敏、経済学研究科の久保田明光両教授の四名が含まれ、特別委員は九名で、総長島田孝一教授、時子山常三郎第二政治経済学部長が入っている。
中島正信教授の「新制大学院の新構想」なども発表された。昭和二十七年十一月二十一日の定時評議員会で「大学院博士課程設置」を各研究科で昭和二十八年四月より行い、そのための設置認可申請をすることが決定した。それに伴う大学院学則の改正を十二月一日の臨時評議員会で行った。
「早稲田大学大学院博士課程設置要項(一)」によって、発足時の様子を見ることにする。この要項は、(一)目的及び使命、(二)名称、(三)位置、(四)校地、(五)校舎研究所等建物、(六)図書標本機械器具等施設概要、(七)大学院の組織と学部学科の組織との関係、(八)研究科専門課程別学科目概要、(九)学位、(十)職員組織概要、(十一)研究科専門課程別学生定員、(十二)大学院、(博士課程)設置者、(十三)大学院維持経営の方法概要、(十四)博士課程開設の時期、(十五)開設学年、という構成である。
昭和二十六年四月新制大学院六研究科の修士課程が開設され、昭和二十八年三月はじめ修士の学位を授与されて社会に修了者が出ていく。これに続く四月から博士課程が開設される。修士課程または博士課程は全く別個の課程という感を与えるが、修士あるいは博士の学位を得ようとする学生の研究に対し学習の課程を示したものである。本大学院以外の殆どの大学院は、修士課程を終了した上で、博士課程に進む構造になっているようである。本大学院の場合は修士の学位を得なくとも博士課程で研究できる。これが本大学院の特徴である。従って、修士課程のものと博士課程とを統合しているので、博士課程に関するものだけを拾うことにする。
「博士課程においては、独創的研究によって従来の学術水準に新しい知見を加え、文化の進展に寄与するとともに、専攻分野に関し、研究を指導する能力を養うものとする」と目的と使命を示している。
経済学研究科経済学専攻は「講義」が三十七科目、百四十八単位、「演習」十科目、四十単位、合計四十七科目、百八十八単位で構成されている。この研究科で博士の学位を取得するには、五年以上(修士の学位を得た者又は外国でこれに相当する学位を得た者、若しくは本大学院の修士課程で二年以上在学し所定の単位を得た者は三年以上)在学し、五十二単位を取得し、履修科目の成績と学位論文および試問の方法での最終試験の成績の総合判定に合格する必要がある。また、本大学院の博士課程を経ないで論文を提出して博士の学位を請求できる道が残されている。
教員は専任教授百二十七、助教授二、講師五計百三十四名に兼任講師六十七の総計二百一名であり、職員は技術員七十三、事務員三十二計百五名で、総員で三百六名となっている。
経済学研究科経済学専攻の学生定員は博士毎年入学者十名、総学生定員四十八名とされているが、同時に修士の毎年入学者が五十名から六十四名に、総学生定員が百から百二十八名に発足時点で増加している。
博士課程で、博士の学位を取得しようとする者は、専修科目二十四単位、その他の科目二十八単位が必要であるが、専修科目は、第一に講義四単位、演習四単位、第二年度から第五年度まで各演習四単位を修得し、その他科目は第一年度に講義十二単位、第二・第三年度に講義各八単位を修得する。修士の学位を持つ者、本大学院の修士課程を経た者、外国で修士の学位若しくはこれに相当する学位を得た者は、第一年度に講義八単位、演習は各年度四単位ずつ、計講義八、演習十二単位総計二十単位を履修する。昭和二十八年度には博士課題の第三年度までを開設し、翌年度より逐次第五年度まで及びそして完成する。
大学院が単位制と条件制に基礎を置くので、修士の学位を持つ者が博士課程に進むのが大半であるが、修士の学位がなくとも博士課程で研究し、二年以上在学して検定を受けて博士候補者になってから、所定の単位を整えて、博士論文を提出することもできる。
昭和四十九年に、文部省が「大学院設置基準」(文部省令第二十八号)を制定、施行し、これに関連して従来の「学位規則」が一部改正(文部省令第二十九号)された。大学院設置基準を制度化し、新制大学院制度の建前を再認識して課程制大学院を制度として確立し、大学院の学部に対する独自性を強化するのがこの省令であった。こうして、大学院が柔軟、多様な形態を採り得ることになった。
これに対応して、新たに制定された大学院設置基準に則し、学位に関する事項を学則から分離し、現行制度の運用を改善するために昭和五十一年四月一日に、早稲田大学大学院学則の全面改定が行われた。
「総則」「教育方法等」「課程の修了および学位の授与」「教員、委員会および職員」「学年、学期および休業日」「入学、休学、退学、転学、専攻の変更および懲戒」「入学検定料・入学金・授業料・演習料・実験演習料および施設費等」「外国学生」「委託学生・特殊学生」「特別聴講学生・特別研修学生」の十章、五十九条に付則がついている。
変更のうち重要なものは、「本大学院に博士課程をおく」「標準修業年限は五年とする」で、それを「前期二年、後期三年の課程に区分し、前期二年の課程を、修士課程として取り扱う」として、博士課程大学院であることを明確にしている。博士課程は、自立して研究活動を行う能力を与え、研究者を養成し、前期課程も研究者養成の博士の条件であるが、高度の専門性を要する職業教育を行うことができるとしている。六研究科はそのままで、経済学研究科の専攻が「理論経済学・経済史専攻」と「応用経済学専攻」になっており、学生定員も、前期課程はそれぞれ四十四、三十六、後期課程もそれぞれ二十二、十八名が入学定員で、総定員は前期八十八、二十七、後期六十六、五十四名で、総定員は「理論経済学・経済史専攻」が百五十四名、「応用経済学専攻」が百二十六名、計二百八十名になっている。教育方法は授業科目と学位論文作成等の指導である研究指導の二つで行う。委託関係つまり、当該研究科委員会が教育研究上有益と認めるとき、十単位を超えない範囲で、他の大学(外国の大学を含む)の大学院とあらかじめ協議の上で、その大学院の授業科目を、また、後期課程学生には、研究指導の一部を履修、受けさせることができるようになった。前期修了要件は各研究科で所定単位数を決めるが、教授科目について三十単位以上と基準が設けられた。博士課程修了要件は後期課程三年以上の在学を要するが、優れた研究業績を挙げた場合には、一年以上在学すれば足りる。博士論文を提出しないで退学しても、後期に三年以上在学し、所定の研究指導を受けていれば、三年以内に限り、研究科委員会の許可により、博士論文の提出、最終試験の受験ができる。学位の中に、学術博士が追加された。大学院授業科目の担当は、本大学の教授のみならず、助教授、講師、客員教授に拡げ、研究指導も、本大学の教授、助教授、客員教授、特別の事情ある時は専任講師が行うと拡大された。各研究科委員会についても構成員は、研究指導を担当する教授、助教授、また研究指導担当の専任講師のうち、授業科目を担当する教授、助教授のうち、研究科委員会を選任する者である。研究科委員会の決議事項も、教員の嘱託および解任、研究科委員長候補者の選挙が追加され、当研究科の予算審議権が付加された。「大学院委員会」を「研究科委員長会」に改め、「研究および教授に関する」が「研究および教育」に、「教務および教則」が「大学院学則または大学院に関する規約の制定、改廃および運用」と具体化され、「大学の諮問」が決議事項となった。外国人学生、委託学生(官公庁、外国政府、学校、研究機関、民間団体の委託)、特殊学生(一科目または数科目の授業科目、特定課題の研究指導を履修する)、特別聴講学生(他大学の大学院の学生で本大学院の教授科目を履修する)、特別研修生(他大学大学院の学生で大学院の後期課程の研究指導を受ける)の受け入れを定めている。
新聞学科の創始から停止に至るまでを記述するまえに、それ以前の学部における新聞教育の経緯を振り返っておくことが、この際かなり重要なことのように思われる。そこで生起した問題には、後の新聞学科の存立事情に照して、相似した事象があることを看取できるからである。
明治四十二年、大学は新聞研究科を開設したが、その設立意図を次の天野為之の文章が語っている。
早稲田に新聞科を開設して、新聞記者としての才能知識を正式に研修せしめ、以て適当にして優秀なる新聞記者を養成せんとするは、余が多年の持論なり、人或は新聞記者は生るべくして作るべからずと説くものあれども、余は俄かに賛同する能はず、如何となれば新聞記者は一個の専門の業務にして、専門的知識を必要とする者なり……
……早稲田の校室より多数の新聞記者を輩出せしめつゝあるは、在来の事実なり、勿論校内には有志相団結して、新聞研究会を組織し、田中穂積氏之が指導の任に当りつゝあれども、特に組織的設備なく、随つて一定の科程を課するものにあらざれば、余は未だ之を以て満足する能はず、余の信ずる所に依れば、更に一歩を進めて、正式の教育を施し、記者として適切なる知識と才能とを発揮せしむるに於て遣憾なからしめんとするは、刻下の急要事に属す、故に余は政学部の一科として新聞学科の設備を希望するや、切なるものある也。
(天野為之「早稲田に対する希望」『早稲田学報』明治四十年十一月発行第一五三号 六―七頁)
大学創立二十五周年を迎えて表明された天野のこの考えは、文中に紹介された僚友田中穂積の協賛のもとに、新聞研究科の創設に具現されていったと考えられるが、明治三十年代の新聞界は、政論新聞と言われたものから、報道重視の新聞へと、新聞が性格を変えていった時期であり、従って、言論記者の旧套を捨てた新しい種類の記者を求める気運をつくり出していた。報道機関としての職責を担い得る新しい知識と抱負とを持つ青年が必要とされたのである。そして、これに応えることへの意味が天野により説かれたのであった。
しかしながら、設立された新聞研究科の内容が、天野たちが期待したような、記者としての資質を育成するに足る教育であり得たかと言うと、疑問に思わざるを得ない。
先ず、研究科の教科内容を概観すると、毎日新聞を退社した小山東助(一八六〇―一九一〇)を講師に迎えて、「論文記事練習」と「西洋新聞雑誌研究」を担当させ、大学からは、政治経済学科の田中穂積、文学科の抱月島村滝太郎と小波厳谷季雄、また青柳篤恒に依頼して科目を兼担させている。更に科外講話として、六科目六人の講師名が挙げられており、その中には、東京朝日新聞の楚人冠杉村広太郎(一八七二―一九四五)や報知新聞の頼母木桂吉(一八六七―一九四〇)などの名が見られる。
ここで問題となる点は、研究科の定員が、政治経済学科と文学科の学生のうちから選考された者二十名で、第三学年の一ヵ年に限っての教育であったうえに、講義科目のすべてが隔週授業で、田中の「新聞史」に至っては月一回であり、科外講話は年間一回から数回という僅少な教育時間でしかなかったことである。そのうえ、研究科の中心的人物であった小山は、大正元年十一月に他大学へ転出してしまい、その結果、研究科がいつまで続き、いか程の課程修了者を出しているのか不明で、多分、小山の退任とともに研究科は廃止されたのではなかったか。
新聞教育に対し大学がかように消極的であった理由の一端は、研究科創設の主唱者であった天野の前掲文章の中に現われている。すなわち、「人或は新聞記者は生るべくして作るべからずと説くものあれども」の一節である。この意見は、後に新聞の企業化が一段と進む中、記者は新聞社が作るという主張に変って行き、研究科からほぼ三十五年を経た昭和二十一年の新聞学科の設置決定から以降、この問題は再び学内に蘇るのである。
ともかく、明治の後年、日本の大学教育の進展状況から見ても、かなり早期に、新聞教育を拓こうとした先人達の高邁な意図は頓座してしまった。学内では将来展望に立つ教育理念よりも、現状追認の牢固とした思念の方が優ってしまったのである。
一方で、新聞界そのものは、社会の発達に応じて、いよいよ自己拡張を目指すようになり、大正期に入ると、大量化し多面化した読者の関心を、価値の多元的共存と普遍性という枠組の中に繫ぎ止めようとして、商品的性格を顕在化させた。
そうした状況は、新聞に対する社会一般の関心を高めると同時に、あらためて新聞研究の学問的価値を引き出し、また、新聞教育についても再考する気運をもたらした。だが、そうは言っても、新聞研究の基本に関する論議は、欧米においても未整序の状態にあり、研究と言っても、日本で重だったものは、英米の新聞事業の経営学的把握の方法かニュース価値論、また、ドイツ新聞学による新聞の本質に関する概念的提示などに過ぎなかった。新聞と社会の関係が緊密化したにも拘らず、未だその関係を、総合的、体系的に洞察する原理は生まれていなかったのである。ただ、それだけにまた、日本での学問的関心は振興され、外国の研究成果を意欲的に摂取する一方、新聞研究の原理的なものを問い質す努力が重ねられるようになった。
こうした経緯の中で、昭和四年、小野秀雄(一八八五―一九七七)の努力で東京帝国大学文学部に新聞研究室が開設され、次いで上智大学は、小野の協力を得て、昭和七年、専門部三ヵ年制の新聞学科を設立した。そして、この上智大学新聞学科に設置された比較新聞学の講義を、小野とともに担当したのが喜多壮一郎であった。
喜多壮一郎(一八九四―一九六八)が本学政治経済学部で「新聞研究」を担当したのは、昭和二年から十五年の間であった。彼は、大正六年、法学科英法を卒業すると、直ちにアメリカに留学して新聞学を学び、同十年、専門部法律科、十一年、第一高等学院の教壇に立つようになったが、十四年には大学派遣留学生として再度アメリカの大学で新聞研究に当り、昭和二年に帰朝して、学院教授・大学部講師になった。
喜多の新聞に関する主な著作は、『新聞展望台』(昭和四年)と『ジャーナリズムの理論と現象』(同七年)で、その研究の基本的姿勢は、新聞を社会的現象として見る一方、そこにアメリカ文明=機械的文明の図式を投影することにより、一種のアメリカ文明論を通じて、工業化が造り出した社会状況と、その所産である新聞の社会的機能、この相関性を解明しようとするものであった。
彼の研究は、究極のところ、もし、新聞のような精神的交通手段が、社会の進化からする特殊な環境心理に対応する必要から生じたとすれば、その社会が制度的、経済的に変化した場合、それに順応した精神的交通手段は、社会的関係と経済的関係の維持と調和のために作用するという、彼のメディア史観に裏付けられた社会との相互作用を重視する新聞論であった。しかしながら、その相互作用は、例えば新聞の営利性がもたらす反作用の面は捨象してしまう、いわば社会発展の要因間の均衡性の上で論じられたものであった。それにしても、喜多には新聞読者に対する希望が大きくあったと思われる。新聞の本質を社会意識の交通手段として認識することにより、新聞読者に社会的意識の向上を期待し、これによって、新聞と読者間の相互作用を十全なものとする、そうした見取図を読み取ることができるからである。
喜多は昭和十一年、衆議院議員に当選、以後政治活動に入ったため、「新聞研究」の講義は十六年に中外商業新報の小汀利得(一八八九―一九七二)により引き継がれた。しかし、十八年十月一日付を以て非常勤講師に対し一斉に辞職を促す措置が採られたことにより、この講義は終焉した。
第二次世界大戦の結果、日本を占領した連合国の総司令部は、初期対日方針に則り、旧体制の解体と民主的な諸制度の創設に力を尽した。取り分け、言論および出版の自由が、日本人の再教育のためにも、占領目的達成上の重要な手段と考えられ、その一環として、新聞の民主化と記者教育の必要性が強調された。こうして、戦後の新聞研究は、先ず記者教育という占領政策の一つにより位置づけられたのである。
大学は昭和二十一年八月、学部に新聞学科を新設して三学科とする学則の変更を文部省に申請した。その理由として掲げた内容は、次のようである。
社会文化の向上・輿論の健全妥当なる発達は、正に民主国家再建の必須条件である。玆に於て今や新聞の社会文化、輿論の健全妥当なる発達に対して持つ役割は往昔の比にあらず。かくて新聞文化の発達、この為めの優秀なる新聞人の養成は緊急なる国家的事業となり来つてゐる。本大学政治経済学部は既に有力なる新聞人多数を輩出せる歴史と伝統を更に生かし新たに新聞学科を創設して、この国家的要請に沿はんとするものである。
また、暫定的に、学科のための学生数を増員せず、学部一学年と在学生から五十人を採用して学科を編成し、二十二年四月からの開講を目指した。予定された第一学年の学科目は十七、うち新聞学科独自のものは九科目あったが、「新聞学原理」などの講義担任者は未定のまま申請が行われた。
これを承けて、文部省は翌九月に認可の旨を大学に伝えている。新聞学科創設の大学による意図は、アメリカの学制にならった新聞学部の設置を勧奨していた総司令部の意向に合致し、また、日本新聞協会が新聞教育促進のため早稲田、慶応、東京の三大学に対し、助成金を提供し始めたその目的にも適うものであった。しかし、大学における記者教育の是非を巡る議論は、総司令部の意思が絶対的であった当時の環境にも拘らず、大学の内外で起きていた。そして、この雰囲気は、設立後の新聞学科の内部にも持ち込まれ、総司令部から示唆された配当学科目にも問題が多く、この学科の性格は、設立趣旨からすれば職業教育機関であるのに、次第に異質なものに変っていった。
新聞学科を併設した学部は、二十二年四月、新聞学関係科目の担当者として、内野茂樹(一九一一―一九六三)を新設の新聞研究資料室に迎え入れた。内野は十二年に経済学科を卒業していたが、経済学史に関心を示していたものの、新聞学研究に携わろうとは思わなかったと後に述べている。そして、当面、アメリカ新聞史の研究に刻苦して取り組み、学科では先ず「新聞雑誌発達史」を担当し、やがて、その研究成果を学内外に意欲的に発表し始めた。その成果の集成であるアメリカ植民地時代から革命期へかけての新聞研究に対し、三十五年には法学博士の学位が授与され、これを加筆補正して『アメリカ新聞の成生過程』を上梓した。
学科の配当科目については、新制大学への切り替えを機に検討が加えられ、これは、後出の第四表新聞学科学科目配当表に見るように、以後、数次の手直しにより、学科独自の科目が消失してゆく傾向を示した。そして、この学科目の変動には、内野が東京大学の小野とともに設立に努力した日本新聞学会が二十六年に発足し、この学会を通じて、新聞学教育のあり方についての議論が盛んになり、またこれが、二十八年から九年に開かれた大学基準協会の新聞学教育基準分科会における決定にも影響したこと、更に、アメリカからマスコミュニケーション理論が導入され、折からの日本における放送事業の飛躍的発展の時期と併せ、新たにこの理論を中核とした教育課程を設ける大学が増えはじめ、特にこれは文学部の課程に設置されるのが普通であったことから、ここにあらためて、政治経済学部における新聞学科の性格が問い直されるという事情があった。
このような状況の推移の中で、内野は「新聞学原理」の講義をも担当するようになった。いま、彼が遺した二冊の「新聞学原理」講義案ノートを通覧して、この講義の中心的課題となったものを考えてみると、戦時体験から出発して言論自由の確保の方策を模索する一方で、新聞をはじめとするマスメディアの倫理性を強調していたことが窺われる。しかも、こうした課題が、折から流入してきたアメリカのマスコミュニケーション理論批判の立場で構想されたことは、注目に価する事柄であろう。この批判内容を、彼のノートから再録してみよう。
日本新聞学会成立以来、米国社会心理学者のマスコミ研究の成果は、日本のマスコミ研究者に由々しい影響を与えてきた。ラズウェル、カッツ、ベレルソン、ラザースフェルド等の影響により、コミュニケーション過程の図式的理解は急速に進んだが、同時に、与件の設定による抽象化されたる図式的理解は、飽くまで現実からの抽象で、いわば数学的な抽象であって、その図式と大衆との関係、その図式と歴史との関係に対する分析は、未だ研究の余地を残すものといわねばならない。以上も結局、一部研究者の間における出来事にすぎないのである。
つまり、歴史研究から出発した内野にとって、人間や風土と交錯しないコミュニケーション論は考えられず、民族と歴史を基軸とした理論的展開のうえに、言論の自由と倫理の問題は見出され得るものであった。そして、彼のこの基本的思考は、「表現の自由量に対する社会的配分」について講述している箇所に、顕著に現われているように思われる。
もともと、この問題は、第二次大戦後の英米で、議会の内と外にそれぞれ組織されたプレスの自由委員会の報告書に端を発している。戦争によるさまざまな事情により後退してしまった言論表現の自由を、いかに復興させるか、その方法を提言させることが、この両国の委員会に課せられたもので、現状は、プレスの発達に反比例して、自己の意見をプレスを通じて表明できる国民の比率は低下しているというのが、両委員会に共通した認識であった。従って、「配分」の問題を扱うことは、いわば内野が課題としていた言論自由の確保、およびマスメディア倫理の二つの問題を考究することに繫がるものであった。
内野によると、表現の自由量は、内容的には、いか程表現の機会があるかということと、いか程多くの人々にいか程の効果を及ぼし得るかに区分され、この機会と効果との相乗積と考えられた。そして、この自由量の配分の問題が現われるのは、「万人に表現の自由を等しく与えようとする民主主義と、表現の自由を一身に集中しようとする資本主義との間に存在する矛盾」からなのである。ところで、民衆にとっての表現の自由とは、その生活上の利害に結びついた意見や感情であり、従って、一定の行動への意欲をはらむとともに、権力批判の道を辿る必然的な運命を行くものである。しかるに、新聞がいかにこの民衆の表現の自由を採り上げようとしても、永遠に新聞は送り手、読者は受け手であるからして、機会と効果との相乗積である表現の自由量は新聞だけに大量に蓄積され、読者には殆ど分配されない。更に、より多くの自由量はより多くの読者を持つ新聞により獲得されるという結果をもつ。
右の講述から知られるように、内野は現代新聞批判の視点を表現の自由量の配分問題に据えて、そこから新聞の倫理問題と言論自由確保の方途を論じようとしたのである。彼の講義案ノートは、配分の問題に続く「新聞製作者の立場」の項で、資本の問題とならび従業員、特に記者について言及し、記者倫理のあり方を大部にわたり論じているし、次の「新聞とは何か」の項では、現代新聞により普遍的読者像として想定された「平均人」を採り上げ、新聞読者の問題を省察している。
この中で、内野にとりいくら説いても説きやまぬのは倫理の問題であった。それは次の記述からも推察できる。「ジャーナリズムとは、国定の資格者でなく、教育学部の出身者でなく、偶然の機会を捉えて登場した人生教師である。ジャーナリズムは、今や公共事業であることに変りはないが、その担当者は一介の賭博師でもありうるという事実を正視する必要があろう」と。これは講義案のはじめの部分、「マスコミュニケーションの社会問題」に現われてくる文章であるが、内野がここで論じている社会問題としてのマスメディアの弊害は、現在ではこの時以上に広がっている。これよりすれば、自由量配分の不均衡の一層の拡大に対し、今日ではコミュニケーション政策という、時には行政施策をも含む広範囲な検討の場が用意されている。ただ、内野がこうした制度論の立場を採っただろうかという仮定の問題には、疑問を呈したい。それというのも、彼の新聞論では、常にメディアの行為とその受け手の意識とが先行する問題としてあった。例えば、ニュースは事件とそれに対する人間の関心度、そしてマスメディアという三要素から構成されると彼は考えていたからである。また、それだけ彼の新聞論は、人間的要素に対して直截的であったし、新聞学教育の一つの目標を示したものであったと言えよう。
内野が亡くなって二年目、折から大学は全学的に第二学部をなくす方向に動きはじめ、学部ではこれを機会に、学部組織を再検討するための委員会を設置した。そして、この委員会は四十年六月に、学部学生の定員増が望まれている現状で、このままの新聞学科の存続を不可とする多数意見を学部長に答申した。これを承けて、七月十四日の教授会は、この多数意見を支持する票決を行い、四十一年度以降の学科学生募集の一時停止を決定した。また、この決定に至った主たる理由の専任教員数については、大学院課程を通じて増員を計るとの学部長見解が示された。そこで、夏期休業あけの十月の教授会では、大学院課程でマスコミ研究科を設置するための素案の作成、学科設置科目のうち学部に残置する学科目の決定、更に、希望する学科学生に対して政治ないし経済学科への転籍を認める手続方法等のため、移行措置に関する委員会が組織された。
この結果、四十年に学科に入学した七十名の学生のうち、四十四年三月の学科最後の卒業生として記録されている者は二十六名に過ぎないし、また、学科の消滅により、それとの関連を失った新聞学関係科目は、講述内容の変更を余儀なくされた。「新聞雑誌発達史」は「マスコミュニケーション発達史」に、「新聞学原理」は「マスコミュニケーション理論」に、そして、「編集論」と「放送論」を併合した「マスメディア論」が、学科から学部の設置学科目に移行して現在に続いている。すなわち、新聞学からジャーナリズムの部分が後退し、折からのコミュニケーション革命と言われたニューメディアの発達状況を反映して、マスコミュニケーションの扱いが大きくならざるを得なかったのである。しかし、その次の段階のことを考えると、内野が示唆していたマスメディア倫理の問題が、従ってまた、マスコミュニケーション状況における人間的要素の問題が、社会的にも学問的にも、強く要請される事態の到来が予想されているのである。
第三表 新聞学科学科配当表(昭和二十三・二十五・三十・三十五・四十一年度)
昭和二十三年度(旧制)専門科目のみを掲出した。○は必修科目、✕は選択科目である。
昭和二十五年(新制)
昭和三十年
昭和三十五年
昭和四十一年度
政治経済学部に自治行政学科が設置されたのは、早稲田大学が新制大学として新発足した昭和二十四年四月である。すなわち、政治経済学部が、新制大学発足とともに、組織上昼間に授業を行う第一政治経済学部と、夜間に授業を行う第二政治経済学部に分かれた際、自治行政学科は、旧来の政治学科、経済学科と並んで、同時開設の新聞学科とともに、第一政治経済学部を構成する四学科の一つになったのである。
第四表 専門部政治経済科自治行政専攻授業科目一覧(昭和23年度)
尤も、早稲田大学における「自治行政」分野の教育課程の設置は、この学科新設をもって嚆矢とするのではない。新制大学の発足に伴って政治経済学部に統合された専門部政治経済科に、既に前年の昭和二十三年四月に自治行政専攻が付設されていたからである。自治行政学科は、実質上これを受け継ぐ形で開設されたのである。因に、専門部政治経済科自治行政専攻の各学年ごとの授業科目は第五表の通りであるが、これらの学科目中、基本科目は必修、選択科目については、第二、三学年においてそれぞれ二科目選択、と定められていた。
第二次大戦直後の時期における、このような「自治行政」分野の教育課程の設置を促した直接的な要因が、昭和二十二年五月三日に施行された日本国憲法および同日に施行された地方自治法において、「地方自治」が、我が国の民主政治の運営における基本的原則の一つとして高く掲げられたことにあったことは、否むべくもない。昭和二十二年十二月二十四日付で早稲田大学が文部大臣森戸辰男あてに提出した、専門部政治経済科への自治行政専攻の付設に関する「認可申請書」は、この専攻新設の理由を次のように説明している。
新憲法の実施に伴い地方公共団体の組織及び運営が地方自治の本旨に基き根本的改訂を加へられ政治、経済、社会の各般に亘つて地方民主化の実現が企画されてゐる。由来民主主義は人民自治を理想とし、人民自治は地方自治体の健全なる発達を基盤とする。然るにわが国にあつては多数人民が未だ民主主義の精神と原則に習熟せず、日常の生活体験においてさうした思想的訓練を多く経て来てゐない。従つて地方自治の有効なる実施は、何よりも多数人民の良識による民主精神と、その原則の把握を前提とせざるを得ないのであつて、そのために地方の政治、経済、社会各般に亘る民主主義的指導育成が正に国家再建途上の急務と言はざるを得ない。
本大学は専門部政治経済科多年の歴史と伝統に顧み、かうした新事態に照応して新たに同科に自治行政の専攻科を新設し、地方自治体の指導者を養成して地方自治の健全なる発達に寄与せしめ、以て叙上の国家的要請に資せんとするものである。
また、自治行政学科設置と第二次大戦後の地方自治重視の政治動向との関連については、『第一政治経済学部要覧』(昭和三十二年)が、「政治経済学部の沿革と特色」について説明している一節で、自治行政学科の新設を
在来、本学部出身者が地方自治体に大なる勢力を占めてきた歴史に鑑み、且つ新憲法の下、地方自治の充実の緊要に目覚め、この分野での卒業者の大きな活動を熱望した結果……
としているところにも、容易に窺えるであろう。
しかし、政治経済学部における地方行政ないし自治行政の分野への研究上・教育上の関心は、単に戦後の政治動向によって触発されたものではない。寧ろ、学部内におけるこの分野への関心は、それまでに既に数十年の歴史を持っていたのである。例えば、高橋清吾は、大正三年から七年までのアメリカ留学において、政治学とともに自治政策の研究に当たり、特に大正六年七月から翌七年七月までの間には、当時まだ創設後まもなかったニューヨーク市政調査会(New York Bureau of Municipal Research一九〇六年設立)で市政調査に従事し、帰国後は、「政治学」「政治学史」と併せて「自治政策」の講義を担当したのである。
このようにして、専門部政治経済科における自治行政専攻や第一政治経済学部における自治行政学科の設置は、政治経済学部における多年の研究上・教育上の関心が、地方自治重視の戦後政治動向を契機として制度的に具現されたものと見ることができよう。
ところで、自治行政学科は、入学定員を八十人とし、第一政治経済学部の他の三学科が、第一年度から第三年度までを昭和二十四年四月に同時に開設したのに対して、第一年度のみを以て開設し、昭和二十七年度になって漸く第四年度までの学生を擁する学科として完成した。因に、昭和二十七年度の専門教育科目配当は、第六表の通りであるが、自治行政学科で取得する学士号が政治学士と定められたこと、政治経
第五表 第一政治経済学部自治行政学科専門教育科目配当表(昭和二十七年度)
済学部における学科間の共通の基盤が重視されたことなどの結果として、専門必修科目十三科目中の八科目(「政治学原論」「経済学原論」「憲法」「行政学」「行政法」「財政学」「一年外国書研究」「二年外国書研究」)は、他の三学科、あるいは政治学科と共通である。
この中で、自治行政学科独自の学科目として設置された科目としては、専門必修科目に「比較地方制度」(第三年度配当)、「地方行政」「行政法各論」(第四年度配当)の各科目、専門選択科目に「都市政策」「農村政策」「社会教育」「社会事業」(第三年度配当、昭和三十五年度から「社会福祉論」に名称変更)、「協同組合論」(第四年度配当)等があるが、昭和四十一年度に第三年度配当の専門選択科目として「国土開発論」が新設されたのを除けば、自治行政学科独自の学科目配当については、その後全く変化はなかった。
このようにして、いわば時代の脚光を浴びて登場した自治行政学科であったが、その後の学科の現実のあり方は、必ずしも設置の趣旨に十分に沿うものではなかった。なによりも、同学科の卒業生が、地方自治の方面へ進出することよりも、寧ろ政治学科、経済学科の卒業生と同方面での職業を選ぶ傾向が強かったのである。他方で、政治学や経済学と比べて、自治行政という学問分野は一つの独立学科の基礎とするには不十分ではないかという意見が、次第に学部内外で強く打ち出されるようになってきた。このような成行きの中で、遂に昭和四十年七月十日の第一政治経済学部教授会は、同じような問題を持つ新聞学科と併せて、昭和四十一年度以降の自治行政学科の学生募集停止を決議し、同年十月十五日の大学評議員会は、この方針を承認した。
因に、学部が公にした自治行政学科廃止の主要理由は、①学科の専任教員数の不足、②他学科との学科目の共通性、③自治行政の学問分野を独立の一学科の基盤とすることの困難性等であるが、①と②については、第一政治経済学部が、「第一政治経済学部新聞学科および自治行政学科学生募集停止に関する件」について教授会決議の直後に作成した文書において、次のように説明されている。
新聞学科、自治行政学科の専任教員数は、現在著しく不足しているが、これらの分野の研究者の絶対数は現在わが国で僅少であるため、その早急な補充はきわめて困難である。
現在自治行政学科に配当されている学科目は、政治学科に配当されている学科目と共通するところが多く、また自治行政学科独自の学科目はこれを政治学科に配当しても支障がない。教育的にはむしろ自治行政学科を政治学科に統合することが望ましい。
また、③については、第一政治経済学部教授会名で、昭和四十年十月十九日に、新聞、自治両学科の学生募集停止決定に関する事情説明のために学部学生を対象として発表された「学生諸君へ」と題する掲示文が、「民主政治において地方自治が重要であることは言うまでもなく、また、自治行政が学問研究の対象として一分野を構成することは疑いないが、これを直ちに学部教育の次元における学科の基盤とすることには難点がある」と指摘している。
なお、教授会は、両学科の廃止後も「新聞学科および自治行政学科に配当されている主要な専門教育科目は、検討の上、これを政治学科または経済学科、もしくは両学科に配当し、両学科の学生が履修できるようにする」ことを決定するとともに、経過措置として、昭和三十八年以降の入学者に限り、学生の希望により、自治行政学科在籍者の政治学科への転科を認めることとした。
こうして、自治行政学科は、学生募集停止から七年を経過した昭和四十八年三月末に在籍学生数が零となり、二十四年の歴史の幕を閉じたのである。
戦後における高等教育機関の改革の一環というよりも、その眼目であったいわゆる新制大学は旧制高等学校・大学予科の果していた役割の大部分を包摂するというものであった。新制高等学校は建前としては旧制高等学校、大学予科の一部を担うものであったが、実質的には旧制中学の延長という面が強かった。建前と実質の罹る乖離は大学入試難からくる高等学校の予備校化によって、更に更に進んだ。従って、新制大学は旧制高等学校・大学予科と旧制大学とを合体するという無理難題を抱え込まされるものとなった。「広い教養の上に高度な専門教育」をとの新制大学の趣旨は実行不可能な課題を可能であるかの如くによそおうスローガンだと言ったら、酷にすぎるであろうか。いずれにしても新制大学においても一般教育科目・語学が導入されたのである。
尤も、昭和初期の学制改革の断行の際にも、既に専門教育偏重の是正の必要性が叫ばれたことを我々は看過すべきではない。政治経済学部では昭和七年度のカリキュラム改正の際に、選択科目として新たに「他学部学科目」が設置され、学生は政治学、経済学関連以外の学問領域の学科目をも選択することができるようになったのである。従って戦後の一般教育科目・語学の導入は、戦前における教育方針・学制改革の精神のすべてではないが、その一部を継承し、より徹底させるという内的契機による変化という面があったことは指摘されて然るべきであろう。
ただ、そうした科目を専門に担当し教授する教員が各学部にいわば「縦割り」に配されたことは、国立大学を中心とする多くの大学とは異なる著しい特徴を成す。それらの大学においては「横割り」、すなわち教養部という制度を採ったが、新制早稲田大学では一般教育・語学担当の教員のすべてがいずれかの学部に所属するという形を採ったのである。
かくて、昭和二十四年度に発足した新制政治経済学部も他学部と同様「教養諸学をその中に包蔵」し、「優秀な諸教授・助教授その他を迎えて、教養高き人材の育成に当」たる(中村佐一「教養諸学研究の発刊に際して」『教養諸学研究』第一号一九五四年 二頁)ことになったわけであるが、当時の状況について、政治経済学部教授時子山常三郎は言う。
新学制の施行によつてわが学部にも教養学科(一般教育学科)が設けられ、敗戦の苦難の中にも新生の息吹き漲り、われわれ教職にある者も、また、覚悟を新たにした。多数の教養学科の新スタフを迎え、学生も年齢層のより若い潑剌気鋭の諸君をうけ入れた。かくて学部が幅広い地盤の上に、政治経済の専門分野についてあらたな体制で研究を進めることとなつた。(時子山常三郎「創刊に際して」同誌同号 三頁)
新制政経学部が発足した昭和二十四年度における一般教育科目は、先ず第一政治経済学部の場合、人文科学・社会科学・自然科学の三系列十七科目であった。それらの内訳は、次の通りである。
人文科学系……哲学、心理学、歴史学、国語及漢文、文学、論理学、人文地理
社会科学系……政治学、経済学、法学、社会学、統計学
自然科学系……数学、物理学、化学、生物学、自然科学論
また第二政治経済学部においては、左の如き人文科学・社会科学・自然科学の三系列十九科目が設置された。
人文科学系……哲学、心理学、歴史学、国語、漢文、文化史、文芸、論理学、人文地理学
社会科学系……政治学、経済学、法学、社会学、統計学
自然科学系……数学、物理学、化学、生物学、自然科学論
必須科目としての語学(第一外国語、第二外国語)には、両学部ともに英語、独語、仏語、露語、中国語の四ヵ国語が配当された。
発足時の二十四年度において一般教育・外国語を担当した専任教員には、数学の蔵田久作、高見清、化学の田上信、英語の大内義一、鈴木悌二、西野入徳、山田良治、独語の小柳篤二、島村教次、仏語の恒川義夫、山内義雄、そして中国語の安藤彦太郎がいた。
なお、新制大学における学科目の履修方法は、すべて単位制となったが、新制政治経済学部発足時の一般教育科目・語学のそれは、第一学年、第二学年において八科目三十二単位を取得することとされていた。その内訳は、既述の社会科学、人文科学、自然科学の各系列から、それぞれ二科目八単位ずつ取り、その他二科目八単位は、いずれかの系列からも自由に取得できる、というものであった。また語学については、二十四年度までは十二単位(第一学年、第二学年ともに第一外国語四単位、第二外国語二単位)とされていた。
ところで新制早稲田大学発足とともに、全学共通の夏季学期が設けられた。二十四年度においては一般教育科目、専門科目を通じて一科目を選択、聴講することができ、また外国語(英・仏・独)の補習授業も行われた。この夏季学期は本来第二学部学生を修業四ヵ年で所定の単位を取らせるためのものであったが、第一学部生も受講できた。とにかく「勤労しなきゃならぬ時代」(「席談会 新制早稲田大学の発足」『早稲田大学史記要』第十五巻 昭和五十七年 二二一頁)であったから、第二政経学部生のみならず第一政経学部生も大いにこの夏季学期を利用したものと見られる。なお、昭和四十年前後に第二文学部を除く第二学部が相次いで学生募集を停止したが、そうした動きの中で夏季学期の存在意義が希薄化し、四十五年度に、遂にこの夏季学期は廃止された。
こうして新制政治経済学部の一般教育・語学教育は出発したが、その後、専任教員の顔触れは変わり、また制度面でも手直しが加えられている。その変遷の軌跡を以下に記そう。
先ず二十五年度以降新たに嘱任された一般教育・語学関係の専任教員には、北田勤(二十五年度)、篠崎高之助(二十五年度)、南英耕(二十六年度)、大山聡(二十六年度)、長谷川晃一(二十八年度)、平野孝一(二十八年度)、増田俊雄(二十八年度)、秋山澄夫(三十一年度)、林文三郎(三十二年度)、笠井鎮夫(三十三年度)、牧野力(三十三年度)、飯島衛(三十四年度)、石井美久(三十四年度)、鈴木弘(三十四年度)、新島淳良(三十五年度)、清水徹(三十七年度)、林勉(三十七年度)、金田真澄(三十八年度)、鵜月洋(三十八年度)、坂崎乙郎(三十九年度)、高儀進(三十九年度)、光延明洋(三十九年度)、志賀謙(四十年度)、武田勝彦(四十一年度)、中村三郎(四十二年度)、福原嘉一郎(四十二年度)、山本忠尚(四十二年度)、鈴木三喜男(四十三年度)、佐藤総夫(四十五年度)、中村利治(四十五年度)、西尾巖(四十五年度)、藤井章雄(四十五年度)、市川慎一(四十七年度)、根岸喜久雄(四十七年度)、原子朗(四十九年度)、米村貞蔵(四十九年度)、ギュンター・ツォーベル(五十一年度)、山下元(五十二年度)、岩田駿一(五十三年度)、原章二(五十三年度)、楊為夫(五十三年度)、大竹正次(五十四年度)、岩井方男(五十六年度)、奥村忠男(五十六年度)がいる。
学科目については、「教育学」「日本文学」「東洋文学」の新設(二十六年度、一政・二政)、「国語及漢文」の廃止(二十六年度、一政)、「数学」の原論、応用への分化(二十六年度、一政・二政)、「国語・漢文」の廃止(二十六年度、二政)、「地学」の新設(二十八年度、一政)、「文化史」の廃止(二十八年度、二政)、「人類学」の新設(二十九年度、一政・二政)、「教育学」の廃止(三十五年度、一政)、「国語学」の新設(三十七年度、一政・二政)、「地学」の新設(三十九年度、二政)、「社会教育」「自然科学概論」の新設(四十一年度、一政)、「社会思想史」「社会科学概論」「人口論」「西洋文学」「芸術」「倫理学」「科学史」新設、「自然科学論」の廃止(四十二年度、一政)、「東洋文学論」「文芸」の廃止(四十二年度、二政)、「コンピュータ」(全学共通)の新設の他、四十一年度には専門科目とは別に、一般教育科目にも「演習」が第二年度選択科目として設置された。これは第一政経学部では各系列に、第二政経学部では人文科学系列にのみ設置されたもので、教員から示されたテーマに基づき、少人数で研究するものである。
なお二十九年度には、こうした「多数の教養学科の新スタフ」の研究成果を発表する機関誌として、『教養諸学研究』が早稲田大学政治経済学部教養諸学研究会から発刊され、今日に及んでいる。
新制政治経済学部の一般教育・語学教育はおおよそ以上のような変遷を辿ったが、この間その履修方法にも変化があった。
新制発足時の履修方法については既述したが、それは、その後二度変更され今日に至っている。最初の変更は二十六年度におけるものである。すなわち同年度入学者から一般教育科目の履修方法は、社会科学、人文科学、自然科学の各系列から、それぞれ三科目十二単位の合計九科目三十六単位とされたのである。こうした各系列から均等に単位を取得する履修方法は、四十七年度に再び変更された。すなわち、六科目二十四単位については以前と同様に各系列からそれぞれ二科目八単位ずつを履修し、残り三科目十二単位は各系列から任意に取ることができる、とされたのである。
また、語学の履修方法も発足時と今日とでは異なっている。すなわち二十四年度では、既述のように十二単位(第一学年、第二学年ともに第一外国語四単位、第二外国語二単位)とされていたが、四十一年度に改正され、第一外国語十単位、第二外国語八単位の計十八単位という現在の履修方法になったのである。
小野梓は早稲田大学にとって、創立者大隈重信とともに忘れることのできない大恩人であるが、学者としても実証主義的政治学の先駆者となり、東京専門学校では「日本財政論」を講じ、その政治学は高田、山田、市島らによって継承発展された。その意味では政治経済学部との関係は特に深いと言えるであろう。
小野は嘉永五年二月、土佐国幡多郡宿毛村に生れた。彼は幼少時代に儒学を学び、やがて藩校の日新館に進み、次第に頭角を現わして、同館随一の秀才と称せられるに至った。彼は自から士格を脱して平民となった後、明治三年中国に旅行しているが、その時『救民論』を執筆し、気宇雄大な世界政府論を展開していることは注目に価する。翌明治四年から明治七年にかけて米英に留学し、財政学・法律学等の研究に従事している。
帰国後「共存同衆」を組織し、活発に啓蒙活動を展開した。明治九年彼は迎えられて司法省の官吏となったが、明治十四年の政変により会計検査官を最後に大隈に従って下野した。在官中より大隈に私淑していた小野は、大隈の立憲改進党結成に当り、高田、山田、岡山ら東京大学卒業直後の新進気鋭の人々から成る鷗渡会を率いて結党に参加し、大隈を助けてその指導的役割を演じた。
また、大隈の意を承け遠大な理想を持って東京専門学校の創立に尽力し、講義と経営に心魂を傾け、早稲田大学の基礎を築いた。
彼はそのような多彩な実際活動を精力的に展開する中で、多数の著書・論文を執筆している。その主なるものを挙げると、『羅瑪律要』(明治九年)、『国憲汎論』全三巻(明治十五―十八年)、『民法之骨』上篇(明治十七年)、「利学入門」(明治十一―十二年)、『日本財政論』(明治十六―十七年)、『条約改正論』(明治十七年)等である。以上のうち『国憲汎論』は彼の憲法論であるとともに彼の政治学ないし政治思想が集大成された大著であり、今日に至るまで不滅の光を放っている。
彼の諸著作に展開されている政治思想的特質として三つのものを挙げ得るであろう。その第一は彼の思想全体の基底を貫流する功利主義の原理である。彼はベンタムの強い影響下に、彼独自の功利主義原理を構築しようとしている。第二はイギリス流立憲主義思想の導入ならびにその政治体制の早期実現である。自由と民権が強調されたのもそのためである。第三はナショナリズムへの志向であり、彼は国民的統一と国家的独立を強く希求している。
彼はこれらの思想的展開過程において、きわめて実証的態度を示すとともに、多数の欧米学者の理論や思想に学びながら、一貫して主体性を堅持し、独創的見解を展開しているところに彼の学問の特徴が見出される。彼が日本の歴史に深い関心を抱いていたのもそのためであった。
東京専門学校の創立に当って、その事業を双肩に担っていた小野梓から学科編成の相談を受けた高田早苗は、政治学の独立を進言した。彼の主張は従来東京大学では文学部の中の一学科に過ぎなかった政治学と経済学を合して独立した学科を設置することであった。この提案が容れられ、今日の政治経済学部の前身である政治経済学科が東京専門学校の開校と同時に発足した。彼は当初より専務講師として政治学関係諸講座を担当し、政治学の学問的独立に情熱を注ぐとともに、科長として学科の充実に努力した。この意味で高田は早稲田大学全体にとってのみならず、政治経済学部の発展にとっても最大の功労者であると言えるであろう。
高田は万延元年三月十四日江戸深川に生れた。彼は東京英語学校を経て東京開成学校に入学したが、同校は間もなく東京大学と改称された。大学在学中彼は市島・山田ら六人の同僚を誘い、小野梓の傘下に集り鷗渡会を結成した。大学卒業後大隈・小野を助けて東京専門学校の創立に参画し、爾来、科長・学監・学長・総長などを歴任して東京専門学校ならびに早稲田大学の経営発展に絶大な貢献をした。
彼はまたこの間に第一回総選挙において、埼玉二区から当選して以来五回衆議院議員に選出された。更に、外務省通商局長・文部省参事官・文部大臣などを歴任し、政治家としても活躍した。
高田は実際活動ばかりでなく、学者としても優れた業績を残している。彼には『英国政典』(明治十八年)、『通信教授政治学』(明治十九―二十二年)、『英国憲法史』(明治十九年)、『代議政体論』(明治二十年)、『英国憲法』(明治二十二年)、『政治汎論』(ウイルソン著高田早苗訳明治二十八年)、『国家学原理』(明治三十四―五年)等の他多数の著訳書がある。彼がこれらの著訳書や講義において志向していたところは英国流の政治学の導入であり、政治学の法学からの独立であった。そのために彼は英国の憲政史や外交史を研究し、代議制、殊に二院制の導入、普通選挙制の実施、婦人参政権の実現等を説き、また投票法を詳説するなど、進歩的且つ実証的な研究を展開していった。
しかし、彼は単なる実証主義に安住したのではなく、政治学を実証的研究と哲学的研究との総合によって体系化し、独立科学たらしめようとしていた。すなわち、彼は『国家学原理』において、国家の研究に関する方法的反省を行い、国家を歴史的に解明する方法と、国家の理想を発見するための哲学的推論の二つの方法を提起している。そして彼は前者における事実崇拝と後者における空理空論の弊を指摘し、両者の正しい併用を強調している。このような思考方法は『教通授信政治学』においても既に見られるところであった。
天野為之は万延元年(一八六〇)、唐津藩藩医の息子として江戸深川に生れた。幼少の時に父と死別、母とともに唐津に帰った。明治六年に再び上京し、開成学校を経て十一年、東京大学に進み、文学部の政治学および理財学科で経済学を修めた。彼は大学入学後間もなく高田早苗と知り合い、高田を通じて小野梓に接し、鷗渡会のメンバーとなり、卒業後、改進党員として活躍する一方、東京専門学校の創設に加わり、政治経済学科の育成に努力した。
政治と学問・教育との両刀使いは東京専門学校創設者たちの共通のあり方であったが、天野は性格的にかかる二元性にはなじめない人物であったようだ。明治二十三年、天野は衆議院議員となるべく、郷里福岡で立候補し選挙運動を行ったが、一度で懲り懲りしたらしく、以後、政界から離れ、経済学の研究・教育に専念する。
天野が最初に触れた経済学は東京大学でのフェノロサの講義であったが、この講義を通じて知ったJ・S・ミルの思想、理論に深く感銘し、その新自由主義経済学を以て自己の学問体系の基礎とした。明治十九年に刊行した最初の著作『経済原論』は、ミルの思想・理論に彼の考えを加味したものである。二十四年にはラフリンの要約したミルのThe Principles of Politicat Economyを『高等経済原論』の名で訳出している。
ところで、天野の学問研究には江戸時代以来の「経世済民」の志が太く貫いている。彼は自己の研究成果を学苑のうちにのみ止めて置くことに飽きたらず、世に出して経済(実業)界の啓蒙、訓練の具たらしめたいと願った。『経済原論』と同じく、明治十九年に刊行した『商政標準』の序言において、彼は「本書述作ノ目的タルヤ政府ハ商業ニ向フテ如何ナル所為ヲナス可キヤトノ問題ヲ講明シ一ハ政治経済ノ学者ノ為メニ教科書ヲ供シ一ハ実際ノ政務家並ヒニ事業家ノ為メニ参考書トナサンコトヲ期スルナリ」と述べている。
天野は明治二十二年『日本理財雑誌』を創刊し、三十年には『東洋経済新報』の主幹となり、経済評論家として活躍する。また、明治三十五年には早稲田実業学校の校長を兼務し、更に商科開設の必要を大学当局に熱心に説き遂に実現させ、三十七年九月、開設とともにその科長になっている。それらはすべて学理(ミルの新自由主義経済学)の考究とその実際への応用という志に連なる。すなわち、政治経済学科の教授、商科科長、実業校長、経済評論家、これらは天野の学問研究の根幹から伸びる必然的分肢であったのである。
天野は大正四年八月、学苑の第二代学長となるが、そのことが却って仇となっていわゆる「早稲田騒動」の渦に巻き込まれ、六年九月、学苑と絶縁する。それは学苑にとってまことに残念な出来事であった。しかし、天野は、日本の経済界を啓蒙、訓練するという志は終生失わず、学苑を去った後には昭和十三年三月の死に至るまで早稲田実業学校校長として努力したのである。
山田一郎は東京専門学校の開校と同時に講師となり、明治十八年まで約三年間に亘って、「政治原論」をはじめ、「政体論」「政理学」「論理学」「心理学」等を講じた。すなわち、彼は、短期間ではあったが、東京専門学校の政治経済学科における最初の「政治学原論」担当者として、早稲田系政治学建設の先駆者の一人となった。
山田は万延元年五月二十八日安芸国安芸郡府中村に生れ、藩校修道館に学んだ後、広島英語学校から東京開成学校に進学した。彼もまた鷗渡会の一員として大学在学中から小野の下に出入りしていたが、明治十五年大学を卒業すると、東京専門学校の講師陣の一翼を担うとともに、小野によってその文才と政治的能力が買われ、市島とともに『内外政党事情』の創刊に当った。しかし、同紙は間もなく廃刊され、更に東京専門学校の移転問題によって親友の岡山兼吉が講師を辞任したため、彼もまた同校を辞した。その後『静岡大務新聞』『越中富山新聞』によって論陣を張るとともに、全国二十余紙に寄稿してその健筆は全国の読者を魅了した。そのため彼は「天下の記者」と称せられるに至った。
山田は大学在学中から優れた才能が認められていたが、東京専門学校における講義はきわめて意欲的であり独創的であった。市島も彼の講義を評して「多くは外国の説を其儘受売する間に立って独り山田君の政治学講義は全く独創の物であった」(薄田貞敬『天下之記者』明治三十九年 四一頁)と述べている。彼の講義をまとめて出版したと思われるものが、『政治原論』(明治十七年)である。本書は総論六〇頁、政党論一七一頁から成る小著であるが、政治学を国家論や国法学等の法学とは別個の独立科学として自立せしめようとしているところにその特徴と先見性が看取される。
彼は先ず学とは「事実ノ道理ヲ究ムルコト」(前掲書 二頁)であるとし、物理工芸の学科と政法経済の学科との間に本質的差異はないと考えている。そこで、政治学が学問として不完全であることを認めながらも、その使命を事実の因果関係の発見に置いている。彼は政治学の対象を動的事実、ことに集団の心理の動態に置き、その中に一定の法則を定立すること、すなわち政治学を集団心理の法則的解明に見出そうとしている。ここには法学的政治学とは異なる新しい実証的政治学の構想が提示されている。
彼はまた政治を上下関係すなわち制御と服従の関係として把えているが、そのような関係の必要性すなわち政治の目的を保護に求めている。彼は更にスペンサーに準拠して、政治を教法・礼儀・産業・文辞・教育・道徳・美術とともに社会業務の一つとして分類しており、政治を社会機能として理解しようとする立場が窺える。このように政治を機能概念として把握する山田は、政治現象を国家以外の集団にも認め、ただ今日においては、国家が最大の政治社会であると述べている。これは彼が国家から政治概念を導き出すのではなく、寧ろ政治現象から国家を説明しようとしているものであると言えよう。このような政治概念は現代政治学への方向を示唆するものとして、高く評価されよう。
有賀は万延元年摂津生れ、明治十五年東大文学部哲学科を高田早苗、天野為之両博士と同時に卒業した文学士で博覧強記、東西の歴史・外交史および美術史系に精通するのみならず国法学・憲法および国際法等に対する造詣も深かったことは文学博士と法学博士の両学位を有していたことからも窺われる。
有賀の法学者として、政治家として、教育者として、また文学者として貢献したところは枚挙に暇がない。彼の学問の範囲は非常に広汎なもので、社会学・哲学・法学・文学・心理学・教育学・国家学・国法学・行政法・財政学・国際法・日本史・法制史・外交史・欧洲政治史の各般に亘り、「八人芸を一人で引受けた様であった」(『外交時報』昭和八年六月号)と東京大学の立作太郎博士が激賞したように博学多才で八面六臂の活躍をなした。
有賀は早くから元老院および枢密院書記官として伊藤、山県等の元老諸公に重用され、あるいは農商務省特許局長、帝室制度調査局御用掛として、あるいは陸軍大学兼海軍大学教授として政府の枢機に参加する機会が多かったので、その等身大の著述も概ねかかる時勢に貢献する必要上研究せられた成果の発表であったように思われる。
有賀は明治憲法制定の前後から明治十六年の『社会学』をはじめ、国法学および国家に関する研究――『国家哲論』(明治二十一年)、『国家学および帝国憲法篇』(明治二十二年)、『大臣責任論』(明治二十三年)――において独自の研究方法を以て政治公法学界に寄与するに至った。その後研究対象を内政から外政に転ずる機縁となったのは日清戦役の際、戦時内閣事務調査を委嘱されて大本営詰となってからである。そして彼は『近時外交史』(明治三十一年)、『最近三十年外交史上・下』(明治四十三年)をはじめ『国際公法』(明治三十六年)、『戦時国際公法総論陸戦』(明治三十七年)、『満洲委任統治論』(明治三十八年)、『日露陸戦国際法論』(明治四十四年)を公刊し、外交史家等国際法学者として活躍した。
特に有賀の畢生の大作は仏文の「日露陸戦戦時国際法論」(La guerre Russo-Japonaise au point de vue Continental et le droit international, 1909)である。本書は彼が陸軍および海軍大学において国際法教授として勤務し、日露戦役中陸海軍の参謀部の将校とは熟知の間柄であり、平和回復後は海軍省において海上捕獲規程の改正委員に指名され、また陸軍参謀本部においては、その戦史部に収める豊富な資料により日露戦役中に生じた国際法関係の事件の集録を目撃する機会を与えられ、およそ野戦に係る公文書類は極秘に属するものまでも閲覧することができ、之等の資料を基礎にして書かれたものである。本書に対して仏国陸軍大臣は訓令を発して仏国陸軍の各兵営文庫に備えつけさせ、仏国国際法大家であり『国際公法雑誌』の主幹パウル・フォーシェル教授は有賀を目して、彼は最も純潔なる文明戦争の原則に依拠し十分軍事上の必要性を顧慮する理想家たると同時に実際家たる二面をもつ卓抜した学者と評価したのは当然であった。彼の外交史および国際法研究は実践に裏打ちされた理論的研究であり、概ね事実の来歴に基づいての戦争や外交の因果関係を科学的に究明する点にあった。この点我が国における外交史および国際法の科学的研究のパイオニアの一人として高く評価されるであろう。
有賀は東京専門学校講師となったのは開校間もない明治十七年九月からである。高田、天野、市島らと東大同窓の故を以て出講して、同三十二年には教授となり国際法・外交史を講じた。我が国で外交史の講座を設置したのは早稲田大学を以て嚆矢とする。その門下生には外交官として明治外交史に輝く早稲田外交官の草分けである埴原正直外務次官・駐米大使がおり、学者としては信夫淳平博士がいる。彼は大正二年には袁世凱の政治顧問として清国に渡り、袁世凱歿後も引続き在職し清国憲法制定に尽力した。大正十年に歿。
市島謙吉が山田一郎の後を承けて東京専門学校の政治経済学科で政治学を講じたのは、明治十八年から十九年にかけての一年間に過ぎなかった。従って、政治経済学部との直接の関係は短期間であったが、その講義は高田、山田らのそれとともに早稲田政治学の基礎を形成するものであった。
市島は安政七年二月新潟県北浦原郡の豪農市島家の分家に生れた。彼は幼少年期に漢字を学び、やがて上京して東京英語学校を経て開成学校(東京大学)文学科に入学し、明治維新後の新しい息吹の中で、漢学の基礎の上に西欧の近代的学問を身につけていった。彼は明治十四年の政変後大学を中退し、大隈の傘下で政界に挺身する決意を固め、立憲改進党の結成と同時に入党した。
その後彼は文筆の才によって、『内外政党事情』『高田新聞』『新潟新聞』『読売新聞』等の創立に当り、あるいはその主筆となり、言論を通じて改進主義の普及滲透に力めている。その間に、明治十八年から一年間東京専門学校講師として、「政治学」「経済学」「論理学」等を講じた。
また、政治活動としては新潟で「亀田協会」「同好会」等を設立し、改進党系勢力の組織化に尽力するとともに、第三回総選挙から三回連続して衆議院議員に当選し、議会においても活躍した。しかし、明治三十四年不幸にして病に倒れ、以来政界を引退した。翌年再度早稲田大学に招かれて初代図書館長に就任し、十五年間に亘って図書館の整備拡充に献身的努力を重ね、更に大学理事をも兼任して早稲田大学の発展に多大の貢献をした。
市島の学問的思想的著作は、明治十年代の後半から二十年代の前半にかけて書かれている。その主著を挙げると『政治原理』(明治十九年、東京専門学校政治科講義)、『改進論』(明治二十一年)、『平民論』(明治二十二年)、『非大同団結論』(明治二十二年)、『政治原論』(明治二十二年)等である。
彼が政治学を講じたのはきわめて短期間であったが、彼もまた高田、山田らとともに政治学を国家学、国法学から独立させ、一個の独立科学として体系化することに意を注いでいる。彼も山田と同様に政治を上下関係ないし「治御」と「服従」の関係として把握している。しかし、彼の政治学の特徴は政治の目的を幸福に求め、人間相互の幸福の追求が矛盾衝突を生ぜしめた場合、全体の幸福のために矛盾を調整することが政治の任務であると説いていることにある。その際、彼は「多数の為に一人一己の幸福を多少制限する場合ある可しと雖も是れ現時制度のまだ完全に至らざるに坐するのみ、決して政治の本旨にあらす、否な政治の本旨は寧ろ多数の為めに少数の幸福を制限するが如きこと無らんを期するなり」(『政治原論』四八頁)と説き、全体というものを実体視せず、全体の幸福を個々の幸福の総和に求めようとしていた。ここに市島の政治学の近代的、市民的性格を読み取ることができる。また山田が実証的各論の一つとして「政党論」を挙げるに止まっていたのに対し、彼は、代議制、選挙、議会、政党、政府、地方自治、植民等の諸問題を一通り論じて、なお不十分であることは免れないが、ともかく実証的政治学の体系を作り上げたところにその功績が認められよう。
志賀重昂は文久三年、愛知県岡崎に生れた。長じてはじめ東京大学に入ったが、程なく退学し、明治十四年、札幌農学校に入学し、地理学を修めた。その代表的成果は思想と地理を独特の手法で交錯させた明治二十七年刊行の『日本風景論』である。しかし、先ず志賀の名を高からしめたのは『南洋時事』であった。
明治十九年、地理学研究の一環としてオーストラリア、ニュージランド、南洋諸島を巡遊した志賀は、そこで西欧列強の現実の姿を見た。すなわち、未開人種の国土を収め、自国の利益のために行動するいわゆる帝国主義国としての西欧諸国である。巡遊から帰るや、志賀は一気呵成に前記『南洋時事』を書き上げ、西欧諸国を自由民権の鑑として美化することをやめ、今こそ日本人は国の独立のために国力の充実を計らねばならぬことを説いた。これを機に志賀は自他共に認めるナショナリズムのリーダーとなったのである。
明治二十一年には、三宅雪嶺らと「政教社」を興し、雑誌『日本人』の主筆となり、一連の国権論を展開した。勢の赴くところ、政治の実際にも足を踏入れ、明治二十九年の進歩党の結成に際しては、その名誉幹事となり、松隈内閣、隈板内閣のもとでは農商務省山林局長、外務省勅任参事官等を歴任し、小笠原島の南方マーカス島の所属問題については日米間を奔走した。明治三十五年からは数回、衆議院議員に立候補し、当選している。
『日本風景論』の著述等にも見られる如く、志賀は地理学の研究を決してやめたわけではないが、精力のより多くが政治に注がれていたのは事実である。しかし、日露戦後になると、志賀は次第に政界から離れ、東京地学協会の主幹になるなど、地理学の研究に専念するようになる。
志賀と我が政治経済学科との関係は明治三十年に始まり、講師として、後には教授として「地理学」を講じた。尤も、志賀は大学部、学部では講義を持たず、専門部・専門学校の講義担当者として終始したようである。明治三十五年の課程表でも、「地理学 農学 志賀重昂」とあるのは専門部政治経済科のところであり、後には、それも随意科とされている。政治経済学科以外のところで講義を担当した形跡もない。
志賀は昭和二年の死に至るまで、我が学苑の教授であったが、その講筵に列なった学生の数はそう多いとは言えないようである。
副島は慶応三年(一八六七)佐賀県に生れ、昭和二十二年八十二歳で歿。明治二十七年東京帝国大学法科大学卒業、同二十八年九月より東京専門学校講師となり、憲法、行政法を講じ、同三十五年第一回早稲田大学留学生としてドイツに赴き、ベルリン大学で憲法、行政法を専攻、同四十年早大教授、評議員となり、四十一年法学博士となる。従来天皇機関説問題で、東京大学の一木喜徳郎、美濃部達吉両博士の線があまりに顕著であるが、寧ろその源流には小野梓の『国憲汎論』(明治十六年―十八年)が挙げられるべきで、彼はその中で国家を統治権の客体とみる天皇主体説に対峙して、天皇と国民との関係も、これを権利主体と客体との関係とみず、両者とも国家という一種の有機的団体を形成するという国家法人説の天皇機関説の立場を主張した。
小野の学説を継ぐ副島は、「凡ソ法律上人ト称スルハ権利ノ主体トナルヘキ能力ヲ有スル者ハ一個人ナルモ又ハ多数人ノ団体ナルモ均シク之ヲ人、即チ人格ト言ハサルヘカラス国家ナルモノモ亦多数人カ共同一致ノ目的ヲ永遠ニ保持センカ為ニ結合シタル団体ニシテ権利ノ主体ナル可キ能力ヲ見備スルカ故ニ国家ノ法律上ノ位置ハ之ヲ人格ト云ハサル可カラス」という。
ここで彼は「機関」の概念を援用する。「国家ノ目的ヲ達スル為ニ国家ナル人格ノ意思ヲ為スル人ヲ国家ノ機関ト云フ」。「機関ノ行フ権利ハ即チ国家ノ権利」にして、「機関トシテハ権利ヲ有セス只権限ヲ有スルニ過キサル」もので、つまり機関とは権利の主体ではなく権限の主体ということになる。ここで初めて天皇の憲法上の地位が問題となる。彼はこの問題を明快にして、「玆ニ注意スヘキハ統治権ノ総攬者ト統治権ノ主体トノ別是ナリ天皇ハ統治権ノ総攬者ナレトモ統治権ノ主体ニ非ス統治権ノ主体ハ即チ国家ナリ天皇ハ国家機関ニシテ統治権ヲ執行スルモノナリ故ニ総攬者ナレトモ主体ニ非ス統治ノ権限ヲ有スレトモ権利ヲ有セス天皇力統治スルハ自己固有ノ権利ヲ行フニ非スシテ国家ノ機関トシテ国家ノ権利ヲ行フ」(『帝国憲法講義』)。ここで初めて我が国における天皇機関説を科学的に基礎づけたのである。天皇機関説問題については、当時東大の美濃部学説のみが喧伝されていたが、寧ろこの系譜の筆頭に挙げられるべきは小野の『国憲汎論』と副島の『帝国憲法講義』を中心とする早稲田学派であったと言っても過言ではない。
この他、『政治学』『行政法各論』『日本帝国憲法要論』『日本帝国憲法論』がある。後二者は近代憲法理論の先駆的役割をなしたもので、「副島の憲法」として当時洛陽の紙価を高からしめた。また学界のみならず大正九年衆議院議員として政界に進出し、有賀が袁世凱に招かれた大正初期の頃、副島は孫文の同志黄興に招かれて中国に渡り、政治顧問となり、昭和六年には南京政府顧問に就任のため早稲田を辞任した。
浮田和民は、安政六年(一八五九)肥後国(熊本県)に生れた。明治四年熊本洋学校に入学、長老教会宣教師ジェーンズの感化を受け入信する。明治九年卒業とともに新島襄創設の同志社に学び、のち同校教員となり「西洋史」「文明史」「政治学」等を講ずる。この間明治二十五年より二年間イェール大学に学び、歴史学、政治学を研鑽する。明治三十年東京専門学校に招かれ、明治三十一年教授に就任、昭和十六年八十三歳で退職するまで「西洋史」「政治学」「国家学原理」等を講じた。図書館長、理事を歴任し昭和十一年に早稲田大学名誉教授、昭和二十一年八十八歳で歿した。
このように浮田博士は、大西祝、安部磯雄らとともに同志社より早稲田に迎えられ、その政治学的伝統を培った一人であった。『帝国主義と教育』『倫理的帝国主義』『政治原論』等、著訳書も多いが、また『太陽』(明治末から大正にかけて約十年間主幹)、『中央公論』等を舞台に活発な文明批評を展開し、健筆を奮った。早稲田出身者が多く浮田の影響を受けたことは言うまでもないが、大正デモクラシーの思想的先導者吉野作造もまたその根底に『太陽』を通じて得た浮田の自由主義的思想の影響があったことを述懐している。浮田によれば、人間は各人おのれの幸福を追求する自由と権利を持っている。それゆえ社会・経済的にも思想的にも、原則的には可能なかぎりの自由が認められなければならない。そして罹る自由の衝突を調整し、最大多数者の福祉を図るために社会が存在すると言うのである。かくて浮田によれば、「社会とは協同生活の状態」そのものである。国家もまたこのような社会制度の一部であり、それは強制力を持つとしても最終的には常に社会全体の意志、すなわち「社会意志」によって支えられている。かくして浮田によれば、政治現象は社会現象の一部であり、「政治学は社会学の一部」と言うことになる。けだし浮田が我が国における社会学的政治学の伝統を築いた一人に挙げられる所以である。思想的には浮田は、頑迷な保守と性急な革命とを排し、秩序ある進歩を信奉した穏健な進歩主義者であったが、人間的にも鳩のような柔和さと正義に徹する頑固一徹さとをともに備えていたと言われる。
安部磯雄は、慶応元年(一八六五)黒田藩士の子として福岡市に生れた。明治十二年同志社に入学、新島襄より洗礼を受けキリスト者としての生活を始めるとともに、ラーネットの経済学に深い刺戟を受ける。明治十九年同志社の教壇に立ち、また一時岡山で牧師をしたのち、明治二十四年から二十七年まで、アメリカのハートフォード神学校、およびベルリン大学に留学する。帰国後一時期同志社で教鞭を執ったが、やがて早稲田に迎えられ、明治三十六年早稲田大学教授、以後昭和二年退任まで「社会政策」「社会問題」等を講ずる。この間政経学部長、図書館長、理事を歴任、更に体育部長、野球部長として体育の発展に寄与する。一方、既にハートフォード留学中に社会問題に深い関心をよせキリスト教社会主義者として、この分野で先駆的役割を演ずる。因に安部は、日本最初の社会主義政党であった社会民主党(明治三十四年)の創立者の一人として宣言を起草し、また大正十三年には日本フェビアン協会を創設、大正十五年には社会民衆党委員長に就任した。昭和三年第一回普選に東京二区より当選以来、昭和五年の選挙を除き、昭和十五年辞任するまで衆議院議員に連続当選。著書は『社会問題解釈法』『社会主義小史』『産児制限論』『社会主義の時代』『社会主義者となるまで』等多い。
既に明らかなように安部は終始一貫、キリスト教的社会主義者であった。安部自身ハートフォード時代を回顧して、「私は基督教の人道主義によりて将来社会主義者となるべき素地を与えられて居た」と言う。そしてマルクス主義との関係については、次のように言っている。
言うまでもなく私の社会主義思想が多くマルクスに負う所あるは事実であるが、私は其当時から現在に至るまで常に社会主義を精神方面から見て居た。私共は生きんがために食ふのであつて、食はんがために生きて居るのではない。結局私共には精神生活が目的であつて、物質生活は其手段に過ぎないといふのが私の考へ方である。……此人類愛を中心として宗教と社会主義が渾然として私の心に融和して居るのである。
かくして安部にあっては、精神の救済と制度の変革とが一体を成していたとも言える。政治的には安部は、高い理想を掲げながらも過激に走らず、現実を直視して一歩一歩進む穏健な社会主義者であった。それゆえ社会政策と社会主義との関係についても、安部は社会政策を社会主義への一順路と考え、この点からさまざまの社会問題に関心を寄せた。最初の著書『社会問題解釈法』(明治三十四年)は、明治後半期に経済学を学んだ人々にとって必読の書であり、日本における経済学の発展に大いなる貢献をしたと言われる。
元治元年(一八六五)九月二十一日父長左衛門の二男として新潟県南蒲原郡中の島村に生る。父は大地主にしてまた剣客、維新の役に長岡、会津に籠城してより世を憚って大久保の姓を宇都宮に改めた。十二歳で小学の課程を了ると、当時聖堂の儒生として北越にその名を馳せていた遠藤軍平の西軽塾に入り、神童と呼ばれた。
まもなく東京に出て神田の共立学校で英語を学び、次いで一橋大学予備門に入り、高橋是清、金子堅太郎等の指導を受く。在学すること二年余にして退学、海軍の主計官に応募して海軍に入る。海軍経理学校第一回卒業生にして、主計部講習生として最優等の成績を収め、特に明治天皇の拝謁の光栄に浴す。
明治二十六年選ばれて海軍派遣留学生としてドイツに遊学、ゲッチンゲン大学において財政、銀行、貨幣の諸学を研究、更にベルリン大学に転じて有名なアドルフ・ワグナーやシュモラー教授指導の下研鑽を続け、明治三十一年八月“Die Warenpreisbewegung in Japan seit dem Jahre 1875, ihre Ursachen u. ihre Einwirkung auf dem Volkswirtschaft.”によってベルリン大学より邦人初のドクトル・デル・フィロソフィーの学位を受く。
滞独六年明治三十二年帰朝するや海軍教授に任ぜられ、海軍大学校、同経理学校、東京高等商業学校(商科大学)、学習院、慶応義塾大学および本大学において教授もしくは講師として教壇に立つ。特に経理学校においては校長の職を歴補。大正二年海軍主計総監に累進、呉鎮守府経理部長となり同三年予備役編入。同六年には内閣嘱託として戦時中の欧米視察のため、同八年には再びドイツその他交戦国の戦後経済および社会状勢調査のため出張した。
我が学苑との関係は帰朝の翌年すなわち明治三十三年山本権兵衛伯の大隈老侯への推挙によって「財政学」の担当を要請したことに始まったが、大正三年予備役編入後は専ら我が学苑に協力され、教授となり財政学の他に「貨幣及銀行論」「経済学」「経済学演習」を担任され、殊に大正十五年からは大学各部の授業の他に第二高等学院長として尽瘁されるとともに、体育会ラグビー部部長として、当時としては新興のスポーツの理解者後援者としても活躍された。昭和九年四月十九日歿、従四位勲三等功四級享年七十歳。
経歴の示すように、先生は当時我が国経済学界の先覚の一人であり、海軍の要職を歴任されたため実際の事情に精通され、学理と実際の渾然融合したその所論は、つとに高く評価されていた。
なかでも、財政学に関しては、先生は、当時世界の財政学会を風靡していたワグナーの財政学を日本に紹介された先達であり、その学説は正統派に属し、租税義務説を展開する。主著に『財政学』二巻(大正二年三月 有斐閣書房)、『最新財政学綱要』(大正十一年七月 厳松堂書店)がある。なお「我が予算の編製を論ず」を初めとする財政・租税関係の七編の論文が『早稲田政治経済学雑誌』に、「金本位復興問題について」を初めとする貨幣・金融・景気変動に関する十編の論文が『早稲田商学』に見られる。
因に、先生が我が学苑に残された人は、昭和三年政経学部を卒業し、第二学院と専門部政治経済科で、経済学を教え、昭和十七年代議士となった本領信治郎教授(昭和四十六年歿)であった。
和田垣譲の次男として、万延元年六月十四日、兵庫県豊岡町(現在豊岡市)に生れた。幼にして英才の誉高く、東京開成学校を経て明治十三年東京大学文科大学を卒業し、翌十四年から十七年に至る間英独(キングスカレッジ〔ケンブリッジ大学〕、ベルリン大学)に留学して理財学を修めた。十七年帰朝して文部省御用掛(東京大学勤務)を命ぜられ、同十九年東京帝国大学法科大学教授に任ぜられた。その後同大学書記官、文官試験局書記官を兼ねて歴任し、同二十四年法学博士の学位を受け、同三十一年東京帝国大学農科大学教授に転じ、大正八年七月十八日腎臓病のため歿するまでこの職にあった。これより先、明治二十三年より東京商業学校に教鞭を執り、同三十年その校長となり、同三十六年日本女子商業学校長を兼ね、また早稲田大学、明治大学等においても学生の教育に当った。
早稲田大学では、明治三十年より歿するまで、政治経済学部(および同専門部)で講師として「経済学史」「経済叢談」「商業政策」を講じた。草創期の我が国学界において、英国古典学派経済学の祖述ではなく、独逸歴史学派経済学に拠って立ち、併せて社会問題研究の先駆をなした。別に趣味広く、殊に英文学に擢で、行政的才幹をも持っていた。風流酒落の好謔家として広く知られたが、真面目は寧ろ謹厳熱誠の士たるにあったとする者は少くない。
早稲田大学関係者との交友は緊密なものがあったようで、昭和八年雑司ヶ谷墓地に墓碑建設が行われた時、賛助した者の中に左の氏名があることでも知られる。すなわち、天野為之、井上辰九郎、市島謙吉、小林行昌、塩沢昌貞、田中穂積、高田早苗、坪内雄蔵、平沼淑郎。市島、天野、高田と同年輩であったためか。
経済学に関して著書あるを知らず。趣味の書として『兎糞録』『吐雲録』等があるのみ。講義は諧謔が多く、経済学の授業としては如何かとの説も当時農科大学内にはあった模様である。
墓碑の傍に句碑あり。晩年の作を自筆したものを刻む。曰く、はしたなく雨の辛夷のこぼるゝよ 吐雲。行年六十歳。歿後、勲一等瑞宝章を贈られた。
○『人事興信録』(第五版、第六版)○渋木直一編『吐雲余影』(昭和九年)○『紀念金蘭簿』(政経第一回卒業記念、明治三八年四月)○大学史編集所『早稲田大学講師科目要覧』(草稿)○河津暹「和田垣法学博士薨去」(『国家学会雑誌』大正八年八月)
明治三年十月二十日水戸市に生る。同二十一年三月東京英語学校卒業。同年九月東京専門学校英語政治学科入学、同二十四年三月卒業。同二十九年九月―同三十四年北アメリカに留学、ウィスコンシン大学においてPh・Dの学位を受く。同三十四年早稲田大学留学生となり、同年十月より同三十五年九月まで、ドイツ・ハルレ大学、ベルリン大学において研究、イギリス、フランスを経て帰国。早稲田大学講師嘱任(経済学担当)。同四十年四月早稲田大学教授(教授会設置による)。同四十二年法学博士。同四十四年五月政治経済学科長。大正十年十月早稲田大学学長。同十二年五月―六月早稲田大学総長(校規改正による)。大正十二年十二月―昭和十七年八月、政治経済学部長。昭和九年帝国学士院会員(勅旨)。同十八年三月定年退職。同年四月名誉教授。同二十年七月七日静岡県伊東町において死去(行年七五歳)。
明治期の若き俊英は衆望を担って欧米に留学し、新知識を収め帰国し、それぞれ、興隆期日本の各界において大きな貢献を果したことは弘知の通りである。塩沢昌貞博士の場合は六年有余の欧米留学後、我が学苑に招かれ、以来一意大学人として活躍することになった。勿論博士は当時の代表的な新進学識者として、各種の政府団体の役員、国際会議の日本代表として参加し、それが早稲田大学の地位を高めたが、最大の功績は、学苑教授を本務として四十二ヵ年、学苑の理事として、総長として、政経学部長として、その充実発展に力を尽したことであった。
博士は若い研究者に対してよく、経済学の研究は狭く偏することなく、理論・政策・歴史に亘るものでなければならないと力説された。博士の経済学の基礎は、六ヵ年余の欧米留学のうち、五ヵ年余をウィスコンシン大学(アメリカ)のR. T. Ely教授の下で、更にドイツに移りハルレ大学のJ. Conradベルリン大学のG. SchmollerおよびA. Wagner教授の下での研鑽によるところ大であった。従って博士は経済学派の系譜としては新歴史学派の影響の下で研鑽を積んだのであって、博士の経済学上、特に労働政策・経済政策への関心と造詣の深さ、学外の評価と活動も、これと無縁ではあり得ない。政経学部について言えば、大正―昭和初期、博士の壮年期に身近に接して薫陶を受けた諸先学こそ、学問上ではそれぞれ博士の蘊蓄を吸収して後進にそれを伝承し、教務上では学部長としての博士を補佐して、学部の基礎固めに貢献したと言わなければならない。
学苑内外における高い評価にも拘らず、博士には一冊の著書もなかったと謂われる。尤も『塩沢昌貞先生略歴・著作年譜』(早稲田大学史編集所編、昭和四十六年六月)には、二十篇の業績と多数の学外団体の役職が示されている。そして塩沢経済学の理解のためには、博士の上述の諸業績の詳細な吟味に基づく、久保田明光「塩沢昌貞―新歴史学派から綜合的・現実主義へ」(早稲田大学七十五周年記念出版社会科学部門編纂委員会『近代日本の社会科と早稲田大学』昭三十二年十月)が絶好の資料となるだろう。昭和六・七年頃の塩沢博士の「経済原論」には、博士自らはそれについて一言も言及されなかったことからすれば、聴講学生の私版であるらしい講義プリントが流布していたが、その講義は吶々とした語り口で、豊富な諸説や事例をあげて続けられた。その博識にも拘らず寡作に終ったのは、その学問的な慎重さと、学内外において余儀なくされた多忙だったと言わなければならない。
晩年の塩沢昌貞博士を偲ばせる胸像は、メインキャムパスの三号館の中庭にある。
内ヶ崎は明治十四年宮城県に生る。同三十四年東京帝国大学文科大学英文科卒業後、同四十一年英国に留学、オックスフオード大学、マンチェスターカレッヂ卒業、内務省の嘱託となり、英国および独逸への社会事業を視察、また同四十三年ベルリンに、大正九年ボストンに開催の第六回および第八回進歩的宗教世界大会において日本代表となる。
内ヶ崎は政治家的素質あり、大正十三年郷里宮城県より推されて衆議院議員に連続七回当選、最初憲政会に属し、昭和二年六月同党政友本党と合併して立憲民政党の結成を見るや同党の政務調査会副会長、遊説部長を経て昭和四年浜口内閣の内務参与官、その後累進して民政党総務、第一次近衛内閣の文部政務次官となり、昭和十六年には衆議院副議長に選任され昭和二十二年、七十歳で歿。その間、社会事業調査会、神社制度調査会、宗教制度調査会、国語審議会、教育審議会、科学振興調査会等各種政府審議会の委員および国際聯盟協会理事を勤む。戦時には翼賛議員同盟、翼賛政治会、大日本政治会、大政翼賛会総務を委嘱される。
内ヶ崎の政界での活躍は右のように華々しいものではあるが、他方東京帝大卒業後、早大講師となり、その後明治四十四年教授となり、累進してその間理事、評議員となり、教育者としては終生を早稲田に捧げた異色ある政治家である。政治経済学部では「文明史および文化史」を講じ、その博覧強記の諧謔を織りまぜた漫談風の講義は一種独特の雰囲気を感じさせるものであった。著書としては、文明批評を中心に、『近代人の信仰』『ロイドヂョージ』『リンカーン伝』等がある。
岩手県大川目村の生れ(明治十年)。旧制二高から東大の史学科に入ったが、坪井九馬三教授が宿題として地図を写させたことを、バカなことをさせたと思う経緯もあって、哲学科に転じた。言うまでもなく坪井は地理を覚えさせるためだったのだが、煙山は、地名が出てくるといつも地図や地名辞典で頭に入れる人だったから、坪井の宿題に腹を立てたのだ。哲学科ではケーベルに学んだことを徳としていたが、十何ヵ国語に通じているとの評判の井上哲次郎教授が、バクーニンの正しい発音はベクーニンだと言うのを聞いて以来、井上の講義には出席しなかった。そんな煙山だったが、哲学科は卒業した。そして早稲田に招かれ、のち、政治経済学部および文学部教授となった。定年後も、特に求められて、五年間、大学院政治学研究科教授をつとめ、昭和二十九年、広島で歿した。岩手県煙山村に埋葬。
担当科目は、「英国憲政史」「西洋政治史」「演習」等だが、初期には「日本政治史」も講じた。時間一杯、休講なしの授業が印象的。
政治史と言うと、狭く、政治権力の発展過程あるいは政治制度史としてとらえ、政策や政治思想等との関連を見ていく風が強いようだが、煙山のは、政治を歴史把握の中心に据えるが、それに条件を与え、それに影響される、自然・民族・社会・経済・思想・文化等の諸現象をも考慮に入れる態度に貫かれている。しかも歴史を根本において作り出すのは人間だとの考えから、政治を動かした重要人物、例えばビスマルク、ウィッテ、ニコライ二世、李鴻章、スホムリーノフ将軍等の日記・書簡・回想録の類を幅広く丹念に、しかも原本で渉猟し、事件・制度・革命・戦争等を解明しようと努めた。
彼は、こうして具体的に、個別的に事実を明らかにする作業を積み重ねて行って、最後に一般的把握に到達しようとした。事実がどうであったかを確定する仕事をなおざりにして、いきなり理論や哲学によって事実を――しばしば事実らしく見えることをも――整理按配し、歴史の普遍性や「合法則性」を認識し得たとするやり方は、彼の採らないことだった。その無数と言ってよい論文や、『近世無政府主義』(明治三十五年)、『征韓論実相』(明治四十年)、『独逸皇帝』(大正三年)等の著書は、個別的な事実解明の労作であり、『独逸膨脹史論』(大正七年)、『西洋最近世史』(大正十一年)、『英国現代史』(二巻昭和五、十一年)、『世界史上の支那』(昭和十三年)、『南方発展史』(昭和十七年)などは一般的把握の著述であり、『世界大勢史』(昭和十九年、昭和二十五年増補)は最も普遍的な把握の成果である。
煙山の書物はどれも立派な学位論文だと言ったのは、浮田和民博士である。そのような煙山の業績の主要なものは前記したので、ここにはその他の中から、トルコ滞在中に刊行された異色の仏文の著述『歴史上より見た東洋と西洋』(表題は増田冨壽仮訳、大正十二年)および、五冊に及ぶ仏独英書の訳本の中の二冊、ドビドゥール『欧洲最近外交史』(大正八年)、デッケルト『英国と其領土』(大正十年)の名を挙げるに止めよう。
多数の論文の中で特に注意を喚起したいのは、「樺太懐古」(明治三十一年)、「露国黒竜江地方侵略史」(明治三十三年)に始まり、「日清日露の役」(昭和十一年)を含む日露関係を扱ったもの、「〝血腥(なまぐさ)き日曜日〟から矛盾せる三月三日の詔勅へ」(昭和三年)、「十月大詔前後のロシア」(昭和三年)その他ロシヤ大革命を主題とした諸論文である。日本・ロシヤ双方の根本史料に拠った研究で、しかもいずれも優に一巻になる分量を持っている。別に、煙山にはロシヤ史概説の原稿ができていたのだが、紙不足の戦時中だったこともあり、大部になりすぎたとして依頼した出版社が刊行を渋ったために、戦災で灰燼に帰してしまった。それを思うと、これらの論文の価値は、一層大きいかと思う。
煙山は西洋政治史の専門家と見られている。しかし彼は、西洋諸国の政治――広く言って文明――が現代世界の歴史に最も大きな役割を演じているということで、それに興味を持ち、それを主題として多く扱ったというだけなのである。彼の眼は、若い時から、世界に向けられ、西洋のみならず東洋も視界に入れていたのだ。煙山の言葉を借りれば、「歴史家の頭には事実を年代別に整頓する棚があるだけで、それらを縦割りにして西洋や東洋に区切る壁はない」のだった。彼には、初めから世界史家たる眼が開かれていたと言えよう。例えば『西洋最近世史』における支那・日本に関する二章を見よ。
煙山のような意図でなくても、重要問題につき、多角的・徹底的に追究したり、比較史的見地を採ろうとするならば、西洋とか東洋とかに分け、更に国や地域を限ってその内部だけを考察するのでは不十分なことは、誰にも分ることである。また、外国に史料があったり、外国人学者に優れた研究があったりすれば、それらも参照しなければならないのも、当然なことである。だが、そうすることは、言語という障壁があるから、煙山ほどの学者でないと言うべくしてなかなか行い難いことなのである。
若いころ一緒に『外交時報』の仕事をしていた煙山を「語学の天才」と評し、その力量に舌を巻いたのは、自らも天才的な語学力を秘めていた法学者牧野英一博士だが、事実、煙山は、ずば抜けた漢学の素養は別として、少くとも英独仏露の読解力は完全に身につけていた。その上、文字通りの博覧強記で、『両世界評論』(仏)のような一般誌、『政治家年鑑』(英)その他の年鑑類からベデカーの旅行案内書(独、地理・歴史に詳しかった旧版)に至るまで広く眼を通していたし、二十年も前に読んだ筈の外国文献の一節を、読み終って間もない筆者よりも鮮明に想起したりした。
しかし執筆の時には、読んだことをそのまま引用することは、あまりしていない。十分に咀嚼し、消化して書くからである。また、典拠を悉く示すのは、ひけらかしになるだけで、その典拠に当たり得ない日本の読者の多くには無用のことと思われもしたからであろう。参考文献を掲げる場合でも、主題に直接係わるものを若干記すに止め、それ以上は、これらを見れば分るという態度を持している。
煙山の時代にも、まともに読んだのは五―六冊なのに、それを通して知り得た研究や史料等を五十冊も六十冊も参考文献欄に掲げたり、更に、それらを拾い読みして博引旁証したりして、まんまと虚名を博す人もいなくはなかった。だが、取れる学位を取らず、伝達された名誉教授の称号をすら辞退した、名誉心の全くない彼には、衒学ぶりを発揮しての虚名など何の魅力もなかったのである。
明治十年八月九日、山形県米沢に生れる。幼少に父と死別し、苦学の目的で上京、叔父の宮島大八の門に入ったのが契機となり、中国研究の道に進んだ。宮島は、ロシヤ語における二葉亭四迷と並称される日本の中国語教育の創始者で、しかも古典学に通暁し、私塾善隣書院を主宰して、中国語教育界および中国研究の分野に人材を輩出した人物である。青柳教授はその善隣書院の一回生で、中国語学および中国古典学の俊秀として嘱望された。
善隣書院を終えると、そこで教鞭を執りながら、東京専門学校に入学、在学中既に陸軍大学校教授、東京外国語学校講師に任じ、のちには早稲田大学講師を兼ねて中国語を教えた。学生にして教員を兼ねたことで有名になり、大隈重信や高田早苗の知遇を得た。
明治三十六年、早稲田大学政治経済科を卒業、明治四十一年、教授に昇任。大正三年、有賀長雄博士に従って二年間、中華民国大総統袁世凱の顧問として北京に滞在、早大に帰任してのち十二年間、校外教育部長を兼ね、また多年、科外講演部長に任じた。昭和二十三年定年退職まで、政治経済学部教授として中国問題・中国経済論・極東外交史・中国語等の課目を担当、その学殖と爽やかな弁舌で、名講義を謳われた。また、柳士廉と号し、書・詩文を能くした。退職後、名誉教授となり、昭和二十六年一月八日死去した。
同僚の大山郁夫教授が青柳を「真正な意味に於ける支那通」(大正五年の発言)と評したように、中国研究の先駆者であると同時に、綿密な文献資料を踏まえた手法は、その後の研究の基礎を築いた。いわゆる「事情調査」的な弱点を今日なお内包する日本の社会科学分野の中国研究の中で、卓抜な文献読解力に支えられた青柳の研究は、正に「真正」の名に価いすると言えよう。また、中国問題のオピニオン・リーダーとしても活躍し、特に辛亥革命に際しては、当時の俗論を排し、正確な予測を提供して、その科学性が注目を引いた。
自己の体験を織りまぜた『極東外交史概観』をはじめ、多数の著書があるが、なかでも清朝公文書の最初の解説書である『支那時文軌範』は、今なおこれを超えるもののない名著である。中国近代の経済史・政治史研究に清末の文献の解読は必須な基礎作業でありながら、日本でその面での蓄積は少い。青柳の有した学識と方法とは、この分野で今後ぜひとも受け継がれなくてはならない学術上の稀少な遺産、と言ってよいであろう。
大山郁夫は明治十三年、福本剛策、すみゑの二男として兵庫県に生れた(のち明治三十年大山晨一郎の養子となり、大山姓を名のる)。明治三十四年神戸商業学校、明治三十八年早稲田大学大学部政治経済学科を首席で卒業する。早大時代に特に感化を受けたのは小野梓、高田早苗、浮田和民らであった。明治三十九年早稲田大学講師となり、先ず高等予科において「英語」を担当した(のちに政治経済学科において「国家学原理」「政治学史」「政治哲学」「原書研究」等を担当する)。明治四十三―大正三年シカゴ大学、ミュンヘン大学に留学、帰国とともに教授、大正四年以降『新小説』『中央公論』を舞台に進歩的な政治評論を発表し、吉野作造とともに大正デモクラシーの思想的チャンピオンと称せられる。「早稲田騒動」ののち一時早稲田を離れ、大阪朝日の論説記者となるも、やがて退社。大正八年長谷川如是閑とともに雑誌『我等』を刊行し、活発な言論活動を展開する。大正十年早稲田大学教授に復帰。大正十二年我が国における近代政治学発達史上画期的な意味をもつ『政治の社会的基礎――国家権力を中心とする社会闘争の政治学的考察――』、大正十四年に同じく『現代日本の政治過程』を公刊する。大正十五年労働農民党中央執行委員長に就任、早大教授を辞し、昭和七年アメリカに亡命するまで無産階級運動に挺身する。昭和二十二年帰国とともに早大教授に復帰、以降日本の平和運動を指導する。この間昭和五年東京五区より衆議院議員に、昭和二十五年京都地方区より参議院議員に当選、昭和二十六年国際スターリン平和賞を授賞される。昭和三十年十一月歿。
このようにして政治学者、評論家、実践家として輝かしい足跡を残した大山郁夫は、文字通り早稲田の生んだ逸材(大山は生粋の早稲田出身の最初の政治学者)であった。思想的には最初はアメリカン・デモクラシーを信奉するリベラル・デモクラットとして出発したが、やがてL・グムプロヴィッツらを中心とするオーストリア社会学派、H・J・ラスキ、G・D・H・コールらのイギリス多元主義の影響を受け、実証的、科学的政治学の樹立を志向していった。その結晶が前掲『政治の社会的基礎』および『現代日本の政治過程』である。前者は、伝統的な法治国家観、福祉国家観、文化国家観を概念崇拝の遺物として退け、政治の本質を「集団的生存表現の法則に従って、各自の集団意志を追う」社会集団間の闘争として捉えながら、罹る視点から政治の体系的把握を心掛けたものであり、後者は罹る立場から日本政治の実証的分析を試みたものであった。このようにしてこの期の大山は既にかなりマルクス主義にも接近していたが、昭和初年の頃には自からマルクス主義者をもって自認していたように思われる。しかし罹る思想的遍歴のうちに一貫して流れるものを求めるならば、それは限りなき大衆への愛であり、自由への渇望であり、これを支える道徳的理想の追求であった。この点においても大山は早稲田の伝統を継承し、発展させた典型的な早稲田人の一人であったと言える。
杉森は明治十四年静岡県に生る。明治三十九年早稲田大学文学部哲学科卒業、在学中彼が私淑した学者としては文学部には大西祝、田中王堂、金子馬治、島村抱月など錚々たる人物が揃っていた。翌四十年文学部予科講師となりドイツ語と哲学を教えた。大正二年倫理学研究のため三ヵ年の予定で独・英・米三ヵ国に文部省留学生として渡り、その間英国留学中The Principles of Morat Empire London University Press, 1917を公刊した。ロンドン大学ではLL・Dの学位を与えようとしたが、これを断ったという逸話がある。
帰国後大正八年早稲田大学教授として政治経済学部では社会学を講じた。昭和九年附属第二早稲田高等学院長、昭和十一年維持員、同十五年理事に就任、また対外的には同十七年十二月外務省交換教授としてフイリッピン国立大学に出講、翌十二年には同じく外務省嘱託として講演のためタイに出張、同十三年八月には東亜文化協議会準備委員として渡支するなど国際的文化人として海外との交流に貢献した。同十九年早稲田大学を辞職後は駒沢大学教授として学生のため教育指導に当たった。杉森には独特の世界観がある。各人が自己の経験と実感を素材として、そのもつ意味を十分に洞察することを以て哲学であると考え、哲学は認識・構想・思索における正しき根本的態度を意味する。哲学はそれ故に人間が事実と理性から出発せずいわゆる権威から出発することを痛感し、このような外的権威を排し、自己を権威とする理性主義的宗教・彼のいわゆる「科学的新世界宗教」と言わるべきものを樹立することを壮年時代から念願していた。彼にとって宗教は哲学であり、集団的信仰であり、その信仰の対象は哲学である。新世界宗教とは、人間的生存の現実の諸様相を無限の完全なる価値、可能的完成に向って創造的に実現するための信仰と実践を意味する。
彼の処女作とも言わるべき「道徳王国」の最終章は、「新宗教の必要」であり、戦後、彼は全権力を尽して公刊されたThe Religion Universally Needed, 1963は遺著となった。いわば第一著の続篇とも言わるべきものであった。杉森はこの著の原稿完成後間もなく病に倒れ昭和四十三年八十七歳で歿。杉森の生涯の大部分は論壇および教壇において多彩な活動を続け、学生の教育のみならず政治家、社会運動家、そして戦時には軍人を啓蒙することにあった。彼の思想はきわめて独創的で洞察力に富み、個性の強い文章、独創的思考力、多彩な多面的総合的学問視野において他の追随を許さないものがある。当時杉森はジャーナリズム世界の第一人者であり、『中央公論』『改造』等の毎号は常に巻頭論文によって独占される有様であった。著書としては、『国家の明日と新政治原則』『倫理学』『社会学』『綜合倫理学』『行動政治哲学』『社会倫理学序説』等あり、彼の学問は最初哲学から出発し、その後社会学、政治学に及ぶ多彩なものとなったが、その底流を成すのはアメリカの機能主義的社会学者マッキーヴァーの多元的国家論にあったと思う。
服部又七の三男として、明治十一年一月八日、滋賀県神崎郡旭村(現在五箇荘町)に生れた。小学校卒業後上京して家業(商業)手伝いをしたが、向学心強く、東京専門学校に入り、明治三十五年七月、同校英語政治科を首席で卒業し、同年渡米してプリンストン大学に学び、同三十九年hP・Dとなった。次いで早稲田大学留学生として英独仏(主にベルリン大学、ベルリン商科大学)に駐まること二年、同四十一年十月帰国して早稲田大学講師、同四十四年には教授に挙げられ、政治経済学部、専門部政治経済科において、「貨幣論」「銀行論」「経済原論」等を担任し、別に後進育成に力を用い、昭和二十年退職するまで変らなかった。中村佐一(別掲)は弟子である。この間昭和二年より退職まで、専門部政治経済科長の職にあり、昭和三年に論文『我国の金融と景気』を以て経済学博士の学位を授けられた。
右は、全一巻十七章を以て成り、菊版五百頁を超える大著で、服部の多数の著述中代表的なものと言うべく、主意は国民経済の変動は、国際経済、国際金融により、著しく影響を受けるとし、これを大正三年の第一次大戦勃発より、昭和二年の金融恐慌に至る我が国経済の推移によって論証しようというにあった。一貫して学問と実際の連携を重視する立場から書かれており、我が国が食料、工業原材料とも自給率低く、外国経済の変転は、国内の物価、株価、金利の変動となって端的には表われることを力説している。所論の詳細は多岐に亘り、直接該書に就いて知る他はないが、例えば、円の下落が正貨輸出禁止によるのは言うまでもないものの、より基本的には経常収支の不均衡によると言い、あるいは我が輸出商品に粗製濫造の悪評あるを避けようとすれば、中小工業者に共同設備を利用させるのが捷径であると唱え、別に当時の国内の高金利を避けるには、保証準備発行額を拡張するに如かずという論に対しては、比例準備制確立の妥当を説くなど、きわめて実際論的色彩が強く、且つ穏当中立のものである。
別に社会的国際的活動の範囲広く、いずれも早稲田大学教授のまま、大正七年東京府市場協会理事、次いで理事長となり、大正八年より一時ジャパンタイムス社長、大正十四年より昭和十六年までグワテマラ国名誉領事になるなどした。
早稲田大学は昭和十九年、その推持員に推薦したが、同年郷里に疎開し、翌年五月早稲田南町の居宅が戦災に遭ったのを機に自然退職した形になった。戦後は三浦三崎に居を移して、再び早稲田大学の教壇に立つことなく、専修大学教授、立正大学講師、千葉商科大学学長、横浜市立大学講師等を歴任したが、昭和二十四年明治学院が大学として発足するに際して教授となり、同二十七年からは初代経済学部長に就任して、昭和三十年二月十六日、心不全のため歿するまでこの職にあった。早稲田が生んだ最初の金融論専攻者の行年は七十七歳。葬儀はキリスト教式を以て行われ、墓は青山墓地にある。
○「経済学部長服部文四郎先生小伝」(『明治学院論叢』、三八―二)○早稲田大学維持員会決議○『早稲田大学新聞』(昭和十三年二月十六日)○『早稲田学報』(明治三十五年七月)○早稲田大学学科配当表(昭十八年度、十九年度)○服部文四郎『我国の金融と景気』(昭三年、早大出版部)○『人事興信録』
永井は明治十四年石川県に生る。同三十八年早稲田大学政治経済学科卒業、翌年早稲田大学留学生として英独に渡り、オックスフォード大学、マンチェスターカレッヂ卒業、帰国後早稲田大学教授となり、「植民政策および社会政策」講座を担当、傍ら雑誌『新日本』の主筆を兼ね、北陸毎日新聞社長としても論陣を張った。学苑では阿部磯雄の薫陶を受けたと言われる。
大正六年早稲田騒動で教授を辞任、大隈老公の知遇のもとに政界進出を決意、大正九年郷里石川県から衆議院議員に初当選、連続八回を重ね、同十三年に加藤高明内閣の外務参与官をはじめ、昭和四年には浜口内閣の外務政務次官となり、浜口内閣総辞職後第二次若槻内閣では五十一歳の若さで民政党幹事長に選任され党務に専念した。外務参与官としては、「進んで国際聯盟の活動に協戮し、以て世界の平和と人類の福祉とに貢献するのは我国崇高な使命である」とする幣原外交に協力した。その後準戦時体制に入るに従って、斉藤、近衛、阿部内閣において拓務、逓信、鉄道各大臣とを歴任して政界に確固たる地歩を確立した。また人口食糧問題調査会、教学刷新評議会、電力審議会等各種政府審議会委員となり、昭和十七年には対支外交調整のため平沼騏一郎らとともに中華民国国民政府に対する答訪特派大使として中華民国に派遣され汪兆銘と会談した。その間九月二十五日南京国民大会堂で、「中華民国国民議長に想う」と題する講演の中で日・満・華三国の提携協力を強調して東亜新秩序の結成を訴えた。閣外では大政翼賛会総務、同東亜局長として東亜新秩序の国民再編成論を唱えた。
永井の政界進出に当たって特筆せられるべきは、大正九年八月の議会における思想、労働問題に関する原敬内閣に対する糾断演説であろう。曰く「今日の世界において階級専政を主張する者は西に露国過激派政府のニコライ・レニンあり、東にわが原総理大臣あり、レニンは労働者階級であり、原総理大臣は資本家階級であるが、ともに民主主義の大精神を失うことは同じである」と喝破せる大雄弁は俄然、院の内外に多大の感銘を与えた。当時東京日日新聞(大正九年七月九日)は、「奥議長を虜にした議政壇上の若武者」と言う三段見出しのタイトルに、「永井柳太郎君初陣の質問振、聞き惚れて議長が与党を叱咤す」と言うサブタイトルをつけた。また高橋内閣の第四十五議会における普選案の四日間に亘る論戦の中で永井の演説は、その論旨の明快さは群を抜き、尚早論を痛烈に批判し、政友会をして顔色なからしめ、加藤高明内閣の第五十議会において憲政史上画期的意義をもつ普選法を成立せしむる契機となった。筆者も永井の雄弁に魅せられたのは凡そ六十年以前に旧制盛岡中学時代、外務参与官として東北遊説を機に同校弁論部主催の講演会においてであった。その時の印象は今にして忘れることはできない。
永井が世に出る頃の我が国はデモクラシーの黎明期から敗戦に至る未曾有の激動の時代であった。彼はこの間にあって内はデモクラシー確立のため、外はアジア民族解放擁立のために全生涯を捧げた。永井は本来学者としてよりも国務大臣としてあるいは党幹事長として国政の枢機に参加し、天賦の雄弁を以て政界で活躍したが、昭和十九年六十四歳でその華麗なる生涯を終えた。また電力国家管理法案、大日本育英会法の成立に尽力し、初代の大日本育英会長に就任したことも逸することはできない。教授としては、『植民原論』『社会政策十講』、文筆の人としては、『戯曲大隈重信』『グラットストン伝』『戯曲銭屋五兵衛』等の著書がある。
大正中期から第二次大戦末期までのおよそ四半世紀に亘って、早稲田の政治経済学部で政治学の中心的存在の一人であったのが、五来欣造である。五来は、明治八年に茨城県に生れ、第一高等学校を経て、明治三十三年に東京帝国大学法科大学仏法科を卒業、同三十七年から九年間フランス、ドイツに留学し、パリ大学、ベルリン大学などで政治学の研究に当った。大正三年帰国後直ちに読売新聞主筆となり、同六年には雑誌『大観』を創刊するなど、素川と号してジャーナリズム界で活躍したが、大正七年に早稲田大学講師、翌八年教授となり、昭和十九年八月に六十九歳で死去するまで早稲田の教壇に立った。なおこの間、昭和五年に国民新聞に入り、同八年に主筆に就任している。
五来が政治経済学部で主として担当したのは「政治学史」であったが、その他に一時「政治学原理」をも併担し、また法学部、文学部等で「国家学」を講じたこともある。政治学上の五来の業績は、主著『儒教の独逸政治思想に及ぼせる影響』(昭和四年)に集約的に見られる、儒教のドイツやフランスの政治思想に対する影響をゴットフリード・ヴィルヘルム・ライプニッツ、クリスチャン・ウォルフ、バロン・ドルバック、フレデリック大王等の思想の検討を軸として考究した比較政治思想研究の領域で最も顕著であり、この領域での業績としては、ほかに啓蒙専制主義との比較において儒教の精神の再確認を試みた『東洋政治哲学』(『現代政治学全集』第二巻、昭和九年所収)がある。他方で、五来は、政治学の理論面での研究にも関心を示したが、この領域での著作としては、政治の概念、国家、代議制、政党、政治思想などについて概説した『現代の政治』(昭和六年)や政治学理論をより専門的・体系的に叙述した『政治学要領』(初版昭和十年、全訂五版昭和十六年)等がある。
これらの業績に一貫しているのは、議会政治の行き詰りという事態をマルクス主義との対決において打開するための、義務の観念を基礎とした「新東洋主義」あるいは東洋の義務主義の復活への主張であり、この主張の延長線上で、五来は、社会連帯主義から、次第にファシズムへの傾斜を強めていった。その中での所産の一つとして挙げられるのが、ファシズムの国家理論を紹介し、「天皇全体主義」を唱道した『ファシズムと其国家理論』(昭和十年)である。
大山郁夫に次いで早稲田が生んだ二人目の政治学者が、高橋清吾である。高橋は、明治二十四年三月に宮城県宮城郡利府村(現利府町)で生れ、同村高等小学校卒業後、早稲田中学講義録および政治経済講義録によって独学し、明治四十四年に早稲田大学専門部政治経済科第二学年に入学、大正二年に同科を卒業し、更に翌三年八月に早稲田大学留学生としてアメリカへ留学した。留学中、高橋は主として、コロンビア大学でチャールズ・A・ビーアド(Charles A. Beard)に師事し、政治学および自治政策の研究に当り、同大学から大正五年にMA、翌六年にはStudy of the Origin of the Japanese Stateと題する論文によりPh・Dの学位を受けた。その後大正六年七月から翌七年七月までニューヨーク市政調査会New York Bureau of Municipal Researchで市政調査研究に従事した。
大正七年八月に満四年の留学を終えて帰国、同年九月に早稲田大学講師、翌八年九月に教授に任ぜられ、政治経済学部において政治学、政治学史、自治政策等の講義を担当、大正十三年四月から昭和二年一月まで政治経済学部政治学科教務主任を務めた。また、この間に、大正十一年には財団法人東京市政調査会の創立に参画し、昭和十三年六月には、議会制度審議会臨時委員を委嘱された。昭和十四年一月病歿(享年四十七歳)。
高橋の政治学者としての活動期間は、比較的短く、二十年余りに過ぎないが、この間に、高橋は、政治思想史、都市問題、政治理論の領域で精力的に研究活動を続け、二十を超える著作を著わした。これらの著作の中には、『デモクラシー』(大正八年)、『欧洲政治思想史』(大正十年)、『現代政治の科学的観測』(大正十五年)、『現代の政党』(昭和五年)、『政治科学原論』(昭和七年)、『政治思想史』(昭和十一年)、『現代政治の諸問題』(昭和十二年)等が含まれる。
高橋は政治学の研究において、一貫して「政治科学」の立場を標榜した。高橋がここで意味したのは、「事象を在るがままに没価値的に見る方法」の上に立つ政治学であったが、高橋は、ここから従来の法律学的・形式論的政治学研究を脱却した、政治現象の現実的・動態的分析を志向したのである。この見地から、政治現象を主として「一種の力の現象――圧力関係の現象」とみなした高橋は、取り分け政治過程における政党と圧力団体の意義に注目し、我が国における現代政治学の発達に対して先導者的役割を果した。
信夫淳平は、政治経済学部で、主として「近時外交史」(大正十一年―昭和六年)、「外交史」(昭和七年―昭和十二年)、「国際政治論」(昭和二年―昭和十二年)および「国際公法」(昭和十五年―昭和十七年)を担当した。
信夫は、特に国際政治学および国際法学の分野できわめて優れた研究業績を発表し、斯学の発展に大きな貢献をした。
先ず国際政治学の分野では、信夫は、『国際政治の進化及現勢』(大正十四年刊)、『国際政治の綱紀及連鎖』(大正十四年刊)、『国際紛争と国際連盟』(大正十四年刊)、『外政監督と外交機関』(大正十五年刊)という国際政治論叢四巻を公にした。信夫は、大正末期に、国際政治の本質を論じ、国際政治学という学問分野を規定したという点で、我が国における国際政治研究の開拓者であったと言っても過言ではない。
また信夫は、国際法学、取り分け戦時国際法学の発展に偉大な寄与をなした先駆者でもあった。もともと、信夫の学問的研究は、国際法学の分野から出発し、彼の国際政治に関する理論も、彼の国際法理論に裏付けられたものであった。従って、権力的アプローチから国際政治学を構築しようとしてきた現実主義的国際政治学者の場合と異なり、彼の国際政治研究が法学的色彩の強いものであることは否定できない。このことは、信夫が、国際政治を維持し向上せしめる一つの綱紀として、国際法の存在と価値を強調していることによっても理解されるであろう。
国際法学に関する信夫の主著は、『戦時国際法講義』(昭和十六年刊)である。それは、彼の戦時国際法に関する研究を集大成した全四巻五千頁に及ぶ大著であり、国際法学の発展に大きな貢献をした名著であり、恩賜賞の栄誉に輝いた労作である。我が国の国際法学界における信夫の学的地位と名声を高からしめたのも、この著作によってであった。
信夫の国際法観によれば、国際法がたとえ理論的な欠陥を持ち、諸国家によって侵害されることがあるとしても、その真の価値は厳然として存在し、国際政治の一つの綱紀であることには何ら変りはないと言うのである。信夫は、このような国際法観から、諸学者の国際法学説や歴史的事実を分析検討し、戦時国際法の諸法規慣例のいかなるものであるかを綿密に論究したのである。
出井盛之は、明治二十五年七日二十八日、栃木県安蘇郡葛生町の素封家に生れた。長じて、大正五年、早稲田大学政治経済科を卒業し、爾来、その生涯を通じてエコノミストとして多方面に亘って汎く活躍し、昭和五十年十一月一日に心不全で歿した。
出井の経済問題への関心はその時代の重要課題に向けられて多岐に亘っており、そして、その活動の場は広く世界的規模に及んでいたと言えよう。
出井は、早大卒業後、翌年の大正六年に渡米し、オタワ大学およびシカゴ大学で経済学を研究して九年に帰朝し、同年九月に母校商学部の講師に就任し、経済学を講じた。
大正五―六年と言えば早稲田騒動の時であり、六年には大山郁夫が早稲田を去った。九年はその大山が早稲田大学教授に復帰した年であった。若い出井盛之の心に、この激動の歴史は何を刻みこんだのであろうか。
大正十一年十月に商学部教授に任ぜられたが、昭和元年から一年半の間、米国経由で渡英し、英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミックスおよびオックスフォード大学ラスキン・カレッジにおいて経済学説および経済諸問題について研究し、四年四月に帰朝して、専門学校講師を兼任しつつ、再び、母校の教壇に立った。
けれども同年八月には依願解任となり、ジュネーブの国際労働事務局調査部職員として赴任し、世界大不況と失業対策について調査研究を行う。駐在六年余の後、十年帰国し、十一年四月から、三たび、母校に帰り、法・理工学部講師として「経済問題」「経済政策」を講じた。
しかし、昭和十七年六月には、また、依願退職し、直ちに大連商工会議所理事として赴任し、戦後二十一年三月に帰国した。そして、六月から連合軍総司令部経済科学局調査統計部に経済専門家として勤務していたが、二十二年、四たび、母校に帰り、政経学部講師に就任し、二十七年には専任講師となり、二十九年には大学院経済学研究科を兼担した。この期間の担当科目は、「経済政策」「国際経済学」「演習」「経済英書」に及んでいる。
この間にも、三十二年米国出張、三十四年ジュネーブ出張、三十七年アフリカ・リベリヤ国際連合協会世界大会に出席するなど、国際人として活躍していた。
そして、昭和四十年三月、定年にて退職した。
林癸未夫は明治十六年生れで岡山県高梁の出身であった。明治三十八年早稲田大学を大学部法学科の第一回生として卒業し、古河鉱業に就職、同社より派遣されてヨーロッパに留学、帰国後労務課長を勤めた。大正十年母校に招聘されて政治経済学部講師に嘱任され、同十二年教授に就任し、昭和二十二年在職中逝去するまで、教育研究と大学行政に多大の貢献をなした。講義としては主として「工業政策」「社会政策」「経済政策」を担任し、平田冨太郎はじめ多数の後進教員を育成し、かたわらラグビー部の名部長として学生スポーツの振興にも力を尽くした。また教授就任と同時に図書館長に就任、二十年間その職にあって図書館の近代化と整備充実に精力を尽くし、更に第二次大戦終戦前後の学内外の困難な時期に常務理事兼政治経済学部長、次いで中野登美雄総長の公職追放後総長代行を務めた。
学者および思想家としての林の研究と思索は非常に広範囲に亘っており、専門領域のほか東洋哲学、暦学、人類学、考古学、文学等々に及び、また自ら洋画を描いた。その博学多識ぶりは林の論文・随筆集『強者にも弱者にも』『社会と宗教と芸術』『西洋思想の日本化』等の著書に見られる通りである。
専門領域に関する林の著書・論文はきわめて多数に上るが、なかんづく昭和二年に授与された経済学博士の学位論文となった『社会政策新原理』(大正十五年刊)および『社会問題各論』(昭和四年刊)と、『国家社会主義原理』(昭和七年刊)とを代表的著作と見ることができよう。林の主たる二つの学問的業績の一つは前者による新社会政策理論の学問的形成であり、他は後者による国家社会主義原理の理論的建設であって、いづれも先駆的業績と見ることができるものであった。
林は前者において、社会政策をそれに判然たる目的意識を与える社会哲学と、その目的達成の方法を規定する社会科学との交叉する特殊学と考えた。そして、林は講壇社会主義以来の伝統的社会政策理論である階級協調論に対抗して、階級廃止論としての社会政策理論を形成したが、これを類似のハイマンや河合栄治郎の著作と比較しても先駆的業績であった。
しかし、林の社会政策論の真髄は彼の考える国家社会主義原理に基づいており、社会政策は労資階級対立から生ずる社会的弊害を排除するため、階級対立そのものの廃止を目的として国家が国家のために行う諸方法であるが、「この社会政策目的は更に上位にある協同的本然社会の建設という社会理想によって指導されていなければならない。そして、国家は政党、労働組合など特殊利益を追求する構成社会は勿論、本然社会の体系をも制律する超階級的普遍意思を持つ存在である」と考えていた。なお、その詳細な内容については、平田冨太郎稿「林癸未夫」(早稲田大学七十五周年記念出版『近代日本の社会科学と早稲田大学』所収)に紹介されている。
猪俣津南雄は明治二十二年、新潟に生れ、長岡中学を経て、早稲田大学専門部政治経済科に入り、大正三年に首席で卒業、研究科に残った。こう書くと、勉強一点ばりの学生だったように見えるが、そうではなかった。帝国学士院書記その他のアルバイトで学資を稼ぎながら、俳句に親しみ、根岸の碧梧桐の所へ出入りして、『日本俳句』に毎号入選という幅の広さも持っていた。
研究科在籍中、知人の山口健蔵(後に長岡銀行の専務となる)が、学資を出すから洋行しないか、と言ってくれた。これが彼の人生の転機となった。大正四年に渡米、ウィスコンシン大学に入った。そこで、H・C・テイラーの下で農業経済学を研究したと言うことになっているが、多才な彼は、それだけでは満足しなかった。先ず、ジョン・デューイのプラグマティズムの哲学とソースタイン・ヴェブレンの制度派経済学に大きな影響を受けたようである。この米国で学んだ実証主義的精神が、後年のマルクス主義理論家としての彼の活動の一つの特徴となる。
在米中の猪俣をボルシェヴィズムに決定的に接近させたのは、ポーランドから移住してきた女子学生バーサで、彼女はアメリカのコミュニストの間に友人を持っていた。二人は暫く結婚生活を送った。猪俣は、ウイスコンシンから、コロンビア大学、シカゴ大学へと転ずる中で、片山潜らの在米日本人社会主義者グループをも知った。
大正十年帰朝、早稲田大学講師となったが、学者に甘んずる気はなく、翌大正十一年七月に成立した第一次共産党の幹部となり、翌大正十二年の共産党検挙で七月に逮捕、投獄された。
その後は再建共産党には加わらず、党の理論的主流となった福本イズムと対決して、昭和二年以降、日本における革命戦略について独自の主張を展開した。猪俣イズムと名付けてもよかろう。
同年、雑誌『労農』同人、翌昭和三年、無産大衆党中央執行委員、翌昭和四年、山川均らと意見対立して、労農派を脱退した。その後は『改造』『中央公論』等に拠って、帝国主義論、農村問題その他について広く論陣を張った。
昭和十二年、「人民戦線事件」で検挙され、健康を害して、昭和十四年、出所。昭和十七年、五十二歳で死去。著書は『日本の独占資本主義』『農村問題入門』等十九冊。
猪俣は、言うまでもなく、資本主義崩壊の必然性を信ずる立場の人物であった。それは、彼の死ぬまで変らぬものであったろう。だが、革命の方法論において、日共および労農派と対立した。ここでは、彼が日本資本主義分析、戦略問題等について続々発表した論争的な諸論文の理論的基礎を成した「資本主義崩壊の理論的根拠」(『改造』大正十五年新年号)という論稿を紹介、評価しよう。これは、福田徳三の資本主義永続論を反駁すると同時に、河上肇の福田批判の的外れを批判し、自己の資本主義崩壊必然論を展開したものだ。
先ず福田批判について。彼は「福田博士ないしはツガンによれば」という皮肉な書きだしで議論を始めている。福田が例の有名なツガン・バラノフスキーの均衡表式を使って資本主義永続論を展開しているからだ。この表式は、機械化が極度に進行して、労働者は一人だけになっても、部門間の均衡が保たれていれば、再生産は円滑に進行する、と言うものだ。
このバラノフスキーに依拠した福田派を、川上肇はローザ・ルクセンブルグの表式を論拠として批判した。ローザ表式は、マルクス『資本論』の表式を批判して、それは、需給の均衡でなく、消費資料の生産過剰の証明である筈だと論じ、そこから「資本主義は、非資本主義的環境を侵略し尽したら、価値実現の不可能から、不可避的に崩壊する」と主張したものである。
猪俣は、この二人の論争を紹介した上で、福田(ツガン)と川上(ローザ)の誤りを指摘し、自らはマルクス自身の正統派的な解釈者として、次のように論ずる。マルクス表式における均衡条件そのものが、利潤率低下法則を中心とする恐慌論と結びついて、資本主義の予盾に満ちた発展と死滅の弁証法的な説明を成している。
以上の論戦に対する堀江忠男の評価は次の通りである。ツガンについては、彼の「一人の労働者しかいない資本主義社会」は、全く抽象的な理論としてはそれも可能だと言う意味のものだ。これを資本主義永続論に採用した福田も誤っているが、ツガン表式をそう言う現実的な永続論として受けとって批判した川上も同じ誤りを犯している。その誤りに猪俣も気づいていない。
川上の依拠したローザの議論には正しいマルクス批判が含まれているが、彼女が表式を使って行った消費資料過剰の証明自体は明らかな誤りである。猪俣の川上(ローザ)批判はそのことに気づかず、マルクスを擁護するに止まっている。
現時点から振り返って見れば、猪俣の仕事も要するにマルクスを超えることはできていない、の一語に尽きる。しかし、大正十五年、日本でマルクス経済学が漸く本格的に研究され始めた時期に、福田(ツガン)、川上(ローザ)に挑戦して、マルクス理論の解釈を深めようとした業績は「マルクス主義者としてあくまで真実を求めようとした僅かに数指を屈する人々の内に数えてよい論客」(大内兵衛)という評価に値しよう。
〈参照文献〉
久保田明光「早稲田大学と経済学」『近代日本の社会科学と早稲田大学』一九五七年、早稲田大学刊。
平田冨太郎「猪俣津南雄――マルクス主義の解釈における貢献」同右所載。
佐藤能丸「早稲田大学研究室蹂躙事件」『早稲田大学史記要』第八巻。
王城素「猪俣津南雄の再評価」『信濃毎日新聞』一九七三年六月一九日付。
津村喬「若き日の猪俣津南雄」『社会新報』一九七一年一二月一九、二二、二九日付。
堀江忠男「猪俣津南雄の資本主義崩壊論」『早稲田政治経済学雑誌』一七七号。
堀江忠男『マルクス経済学と現実』(学文社、一九七九年改訂版)、特に三二八―三三二頁のローザ表式批判。
(付記) なお参考文献として雑誌『猪俣津南雄研究』一―一六号(一九七〇年三月―七四年二月)をあげておく。
明治二十三年八月二十八日徳島県板野郡大山村大字神宅村四二番屋敷で父猪馬三郎、母ツネの長男として農家に生れる。明治四十一年京都同志社普通部(中学)を卒業、同年九月早稲田第一高等予科に入学、同四十五年七月早稲田大学大学部政治経済学科卒業、大正元年九月同志社大学法学部講師に就任、大正五年海外留学を命ぜられ、はじめの一年を米国ジョンズ・ホプキンズ大学院、次の一年をコロンビア大学院において、経済学、財政学の研究を重ね、英国に渡り第一次大戦終戦後のロンドン生活を体験して帰国、大正八年四月より同志社大学法学部教授として「財政学」「経済学史」「金融」の講義を担当す。
約十年の京都生活の後大正十一年四月母校早稲田に戻り、昭和十一年三月まで、政治経済学部教授として、他学部を含め「経済学」「経済学原理」「財政学」「英書講読」「経済学演習」を担当した(当時の学科配当表を見ると、本学部の「財政学」は宇都宮鼎が担当しており、阿部賢一は「英書講読」を担任、「財政学」は法学部で担当している)。
大正十五年経済学博士、この頃岳父徳富蘇峰経営の国民新聞を助けるため同社に入社、昭和四年三月蘇峰とともに東京日々新聞社(毎日新聞社)に論説委員として入社、その後同社取締役主幹となる。昭和十二年四月本社の大阪毎日新聞社へ経済部長として転任のため教授の職を辞するまで、大学教授と新聞人の二足の草鞋をはく。昭和二十五年十月戦後三年間の追放が解除されるや昭和二十六年五月から再び早稲田大学第一政治経済学部に臨時講師として復帰、昭和三十六年三月定年退職まで、「租税論」の講義を担当、その間二十九年には商議員、常任理事、三十七年評議員会長、四十一年五月総長代行、四十一年九月より四十三年六月まで第八代総長として、大学紛争の収拾に尽力、また学外においては昭和三十年十月以降東京都公安委員、のち四十四年八月から五十四年十月まで同委員長、四十四年以降サンケイ新聞社常任顧問、四十五年以降中央教育審議会委員を務め、四十六年勲一等瑞宝章受章、昭和五十八年七月二十六日歿、享年九十二歳、従三位に叙せられる。
主著に学位論文「租税の理念と其分配原理」(大正十五年)、『財政学』(大正十三年初版、昭和四年改訂版、昭和七年三版)――この書は大内兵衛が留学より帰朝後東大で教科書として使っていた――の他、『財政学講義』(大正十一年初版、二年増補再版)、『財政学史』『財政政策論』(改造社経済学全集第二十巻)、『財政学原理』(同第十九巻)がある。
その学説は、「われ等は経済的利害を異にする群の間、階級の間に不断に行われる財政闘争を如実に認識しなければならぬ」「租税の決定は社会的経済的に優勢な階級もしくは団体の力によるものである。すなわち租税闘争の結果である」とする階級国家観より財政現象を説明し、各人の富および所得の大小は、勿論個人的能力や勤惰がその重要な決定条件に相違ないも更にこれらの条件を決定する有力なものとして、時の法律、習慣等を総称した意味における社会経済制度をいかに利用しうる地位に居るか、またいかに之を自己に有利にするかにあり、各人の享有する富および財産は全く時の社会経済制度が各人に授与する利益なりと見、この「制度的利益」に応じた租税負担の配分こそ公平であるとする独自の創見を打ち立て、租税利益説の立場に立って「所謂能力説は、既に其時代的任務を尽したらしく考へる」とし、正統派学説に対する批判として大内兵衛学説出現以前の代表的学説であった。
こうした学説の形成は『早稲田政治経済学雑誌』に寄稿したそれまでの数多くの研究の積み重ねの上に成るものであることは言うまでもない。
明治二十五年六月二十九日長野県に生る。同四十三年四月早稲田大学高等予科入学。大正三年七月同大学部政治経済学科卒業。同四年十月―同七年一月東京朝日新聞社。同八年十一月―同十一年二月早稲田大学留学生として経済学および財政学研究のため米・独・仏に留学。同十一年四月早稲田大学講師。同十二年十月教授。大正十三年三月―昭和九年九月政治経済学部経済学科教務主任。昭和九年九月二十一日死去。(行年四十三年三ヵ月)
二木保幾の学問的活動は、前記年譜の通り、大正十二年十月早稲田大学教授に嘱任され昭和九年九月急逝に至る、約十二年余の短い年月に過ぎない。その業績の学問的評価については、後輩であり同僚である久保田明光によって、特に詳細には二木門下であり政治経済学部教授として貢献した酒枝義旗(他の一人は西洋経済史の小松芳喬)によって書き残されている(酒枝義旗「二木保幾―経済哲学の批判的研究」早稲田大学創立七十五周年記念出版『近代日本の社会科学と早稲田大学』二一七―二三四頁)。学内外の高い期待と切なる要望にも拘らず、二木が寡作の学者として終ったのは、行年四十三歳、教授生活約十二年半という短い生涯と、しかも同時並行してその殆どを経済学部経済学科教務主任として、きわめて多事多端な時期の教務の補佐の役目を果さなければならなかったことによるのである。
学究者として、しかも教務主任としての二木が当面した時期は、当時の旧制学部の学生数は少かったにせよ(一学年、政治一クラス、経済二クラス)、学内的には大山事件―大山教授解任(昭和二年)、学生諸団体(雄弁会等)の解散(昭和三・四年)、早慶野球戦切符事件(昭和四年)、社会的には昭和金融恐慌(昭和二年)、世界恐慌(昭和四年)、満州事変(昭和六年)等々、失業と学生就職難、社会的騒情と戦時色の重層の時期であって、講義に、しかも学生対策に全力を傾注しなければならなかったのである。
寡作に終った業績から見た二木経済学の構想と評価については、日常直接指導を受け、やがて学部の「経済原論」の講座担当者となった故酒枝教授の前記論文にまつのが至当だが、それは「故二木教授の年譜及び主要著作目録」(早稲田政治経済学雑誌第三七号、昭九・一〇)にある、著書二、講義録・講座類掲載論文五、雑誌論文十五、計二十三の労作によったものである。ここで著書二というのは、『経済学講義』(大十三・十二、明善社)『経済哲学』(昭八・一、改造社)であるが、更に昭和八年度の新学期には『経済学史』の講義プリント版が出版されており、これが二木の『経済学史』の著書に発展する筈のものであったことを付け加えておこう。酒枝論文は上述の二木の諸労作から、それらは経済学、経済哲学の分野ばかりでなく、社会科学の認識論、社会哲学、宗教哲学に及ぶと捉えつつ、しかし二木の学問的業績には、「深遠な思索と探求の成果が萠芽の形において生々と息づいている」けれども、「未完成に終った」としている。
広い視野に立って多くを探求しようとした精進の跡は、政経学部の図書室に収蔵されている二木蔵書の中で外国留学時に、そして教務主任としての繁忙の中で読み込んだ多くの文献(パレート、マーシャル、マルクス等々)への、赤・青の鉛筆で印された書き入れによって知ることができる。その成果とし遺された業績に上述の十五の雑誌論文が含まれるが、そのうち半ば以上がマルキシズムに係わる批判的論究である。こうした二木論文に対して批判がなされた。「マルクスの価値論に於ける平均観察と限界原理の矛盾」(昭四『中央公論』十二月号)に対する、三木清「資本論の冒瀆……」(昭五、同誌二月号)がその一例である。しかしこれは経済諸学説の理論史的考察を通じて自己の立場を深めようとする二木の真意を正しく理解したものではない。二木の精神を貫く基本線は、二木自身の言葉で言えば、「絶対観」を戒め、「相対観」に立とうとするにある。すなわち諸説の理論的考察に当って、何らかの言説を絶対的なものと決めて固執し、他の諸説を批判し無視する「超越的批判」――ドグマティックな批判――を排し、取り上げる学説を理論史の中の同等の一コマとして容認し、その上でそれを「内在批判的」に考察しようとするのである。従ってマルクス学説への二木批判は、批判のための批判等ではなくて、内在的理解に基づく批判と摂取を意味するのである。そこからは「資本論に対する冒瀆」等ではなく、内在批判的研究を通じてのマルクスに対する高い評価をもたらすのである。こうした自省と批判精神に基づくマルクス学説の、更に同じくして得られたマーシャル学説の理解から、両者は「理想としては総合せらるべきものだ」(前掲、『経済哲学』)とする二木の認識が生れるのだが、この洞察は敗戦後の我が国における、いわゆる「近経」と「マル経」の総合の試みに遥かに先立つものであった。
中野は明治二十四年北海道札幌に生る。大正五年に政治経済学科を卒業、直ちに大学院研究科で国法学および国際法学を専攻した中野は同七年アメリカ留学の途に上り、ジョンズ・ホプキンズ大学院でウイロビーの政治学ならびに公法学の講筵に列する機会を得た。当時ウイロビーは国家および政治に関する実証主義研究によりアメリカ政治・公法学界の第一人者であり、その著書の多くは中野の最も深く耽読し、また最も多く影響を受けたものであった。中野の同大学にPh・Dの学位論文として提出した「天皇の命令権」(“Ordinance Power of the Japanese Emperor,” 1923)は当時程度高き米国東部大学の卒業生によって名誉とされていたユニバシティ・プレスから公刊され、同年六月三十日にはボルチモア・サン紙上に写真入りの記事が掲載されて絶讃を博した。ジョンズ・ホプキンズ大学で業を終えるやヨーロッパに渡り、ハイデルベルク大学では自由主義的実証主義学者として著名なアンシュッツ、ソルボンヌ大学ではガストン・ジェーズに学んだ。
大正十二年五ヵ年に亘る欧米留学から帰国した中野は多数の学術論文のほか、著書としては、ハンス・ケルゼン『国家原理概要』(一九二八年、訳)、『国法および国法史の研究』(昭和四年)、『法律綱要』(昭和七年)、『戦時の政治と公法』(昭和十五年)、『憲法講義』(昭和十七年)、『国防体制法の研究』(昭和二十年)を公刊し、政治経済学部では、最初、「公法学」、後に「憲法」の講座を担当するようになった。これらの著書の基礎を成すのは近代憲法制度の歴史的実証的研究にあった。彼が欧米留学中親しく指導を受けた近代実証主義公法学者が彼の公法理論の展開の上に与えた最大の意義は、常に抽象的空疎な概念操作に満足することなく進んで歴史的実証的概念構成を試みたことにある。
中野が実証主義公法学者として、その精緻な方法論的真価を問うたのは学位請求論文として提出した「統帥権の独立」(昭和九年)において遣憾なく発揮された。東大の美濃部達吉博士は、本研究を以て「斯界における世界的な唯一最高の権威」と激賞した。ここに「統帥権の独立」とは明治憲法第十一条に規定する軍統帥の国務に関して国務大臣の干与を許さず、従って国務大臣の責任の外におかれ、これを問責し得ない原則を言う。彼が本書を編むに当り広く内外の資料を蒐集し、遍く我が国および欧米の諸学者の所説を参考にしつつ我が国の現行制度に論及し、「統帥権の独立」に関するあらゆる問題に対して明快な結論を下した功績は学界で高く評価された。
中野は戦時の言動の責任を問われ、終戦後パージという悲運の中に昭和二十三年五十八歳で波瀾の生涯を閉じた。しかし彼の真価は知る人ぞ知る。当時の軍の独走に対して激しい警告を発している。曰く、「兵権の独立が最高国策に対する輿論の自然的且つ合理的な統一を妨げ、国策に対する国民の不安と疑惑を招き、国民をして軍部が恰も政府における政府であり、国家内における国家たる如き感を抱かしめ、一方においては政府および議会、武官と文官、軍人と一般国民との対立観を助長するものとして議会によって憂慮されるのも畢竟するに制度がその運用において往々妙を得ざりしに由るものにほかならない。従って統帥権の独立の実際を以て、適当なる限界を守らしむることは制度の将来のために欠くべからざる条件と言わざるを得ない。最近十二年間における一部軍人の矯激なる言動が国民に著しく不安の念を与えていることは否定し得ない事実である。著者は独り我が軍政の基本組織のためのみならず国防そのもののためにも切に軍部当局の自重を重ねて望まざるを得ない。蓋し挙国一致なきところに真の国防なく国民が国家機関、特に軍部の行動に不安を有せざる能わざる所に挙国一致は望み得ないからである」(「統帥権の独立」七二九頁)。彼が既に終戦に先立つ十数年前に、軍部の横暴と終焉を極めてヴィヴィットに描写し軍に警告を発していたことは、本書の価値を弥が上にも高からしめるものであった。
中野は戦争が苛烈になるにつれ、外部からの懇請も出し難く己の学問と国家の当面せる現実問題を調和せしめようとして、『中央公論』その他の総合雑誌に論筆を張ってジャーナリズムの花形となった。昭和十七年には政経学部長となり、敗戦の色濃き同十九年九月から二十一年一月まで第五代早大総長として連日空襲下の本部の総長室に寝泊りして宿痾に悩まされながら多難な戦時下の大学行政の運営に当たった。空襲警報のたびごとに本部の防衛室に馳せ参じて早大防護団長として鉄兜、ゲートル姿が瞼に浮ぶ。これが彼の死期を早めたものと思う。総長として経倫を行う期間は少かったが、昭和十九年の人文科学研究所の創設、理工学部研究所の充実に尽力したことは特筆せらるべきであろう。
天川は明治二十八年福島県に生る。大正六年早稲田大学高等予科入学、同十二年同大学政治経済学部政治科を卒業、直ちに大学院に入学、公法学・政治学を専攻、同年九月専門部講師となる。同十四年五月早稲田大学より公法学および政治学研究のため欧米留学の途につく。同年十月フランスのボルドー法科大学に入学、レオン・デュギーおよびボナール両教授につき二年間に亘り公法および行政法を専攻、昭和二年ウイーン大学でハンス・ケルゼンおよびアドルフ・メルクル教授につき国家学・国法学および行政法を学び、翌三年独墺その他ヨーロッパ諸国および米国を視察の上帰国、同年十二月に早稲田大学助教授、翌四年四月政治経済学部において比較憲法を講ずる。同六年七月同学部教授に嘱任され「行政法理論」を担当、その間専門部政治経済科教務主任となり、終戦直後同二十一年二月講演先の宿舎にて五十一歳で歿。
天川は、その経歴にも見られるように主としてフランス学説の影響の下に「行政法」を講義し、しばしばオーリユーの「公共役務」概念を披露した。論文としては、「ルッソー社会契約論の一先駆者ジュリウの政治思想」「パルテルミー・デュエズ著憲法要論」「アドルフ・メルクル一般行政学における法段階説」「仏蘭西組合国家思想の再検討」「地方自治概念としての構成要素」「現代地方自治の趨勢」「連邦主義と行政上の統合地方主義」「現代法学における団体行政の本質」「ジョセフ・パルテルミイの自由の価値」がある。準戦時体制に入るに従って、「ナチス理論における法概念」をはじめ、特に中華民国の新体制運動に関心を向けたようである。その間の論文として「中華民国初期中央行政機構の再検討」「国民政府地方政治機構の再検討」「民国初期自治制の一考察」「国民政府市制の一考察」「葡萄牙組合国家の特質」「仏蘭西組合国家思想の再検討」がある。
明治三十年九月八日東京に生る。大正四年四月一日早稲田大学政治経済学科予科入学。同八年七月二十五日同学科卒業。古河合名会社、財団法人協調会に勤務を経て、同十三年四月一日早稲田大学講師嘱任。昭和二年―同四年仏、独に留学。同四年四月早稲田大学助教授(「農業経済学」担当)。同六年七月早稲田大学教授。同九年十月より「経済学史」担当。同十九年十月経済学博士。同十月―同十六年三月政治経済学部経済学科教務主任。同二十年四月―同二十四年六月政治経済学部長。同二十三年三月―同二十九年九月早稲田大学理事。同二十三年十二月―同二十九年三月日本学術会議会員(二期)。同二十六年四月―同三十八年三月大学院経済学研究科委員長。その他経済学史学会代表幹事、日仏経済学会会長等を歴任。同四十三年会長三月三十一日定年退職。名誉教授。同四十六年六月十一日神奈川県鵠沼において死去。(行年七十四歳)
久保田明光教授の我が学園における四十二年に亘る講義は種々の部門に亘るが、政治経済学部におけるはじめの主要講義は「農業経済学」であった。その著書『農業経済学概論』(初版昭六)、『農業経済学の基礎理論』(初版昭二十三)、『農業経済学入門』(初版昭二十四)等々において見られるように、それは農業政策論的なものではなく、「農業の経済理論」の確立を目指したものであった。ところが昭和九年九月二木保幾教授が急逝され、十月から「経済学史」の講義をも担当することになった。従って「農業経済学」と同時に、「経済学史」の講義のために系統的な再考が必要となったわけである。尤も久保田は早くから社会、経済思想に深い関心を持ち、その労作を発表している。博士は「経済学史」の講義担当以降、『ケネー研究』(昭三十時潮社)およびケネーを中心とする『重農学派経済学―フィジオクラシイ』(初版昭二十五、第五版昭四十)等々によって、我が国「ケネー研究」のスペシャリストとして高く評価されているわけだが、こうした関心を示したのは、はるかに早い。ケネーが『百科全書』に寄稿した初期の経済論文『借地農』(一七五六年)、『穀物』(一七五七年)の精細な研究成果が、『フィジオクラートの大農論』(『早稲田政治経済学雑誌』昭五、第一九、二〇号)として発表されているのである。
当然のこととして「経済学史」の講義であるから少くとも近世の学説から始めるが、博士の場合も時間の制約から現代理論に至るすべてを取り上げるということはできない。しかし昭和十年代前後の学部演習では、古い学説を演習指導のテーマにすることなく、オーストリア学派とかシュムペーターとかを読ませた。新制学部になって博士の発議によって一八七〇年代以降の「現代経済学説」の講座がそれ以前の「経済学史」と分けて設けられたのであり、新制大学院での博士の担当は「理論経済学」部門であって、ここでは学生の選好に応じて現代理論の各分野を指導していた。従って久保田経済学史の講義は、ますます現代経済理論との関連に言及しつつ行われた筈である。こうした現代経済理論への絶えざる深い関心の一端を示したものがフランスのF・ペルウを中心とする「フランス社会学学派」の研究労作『現代フランス経済学』(昭三十二、東洋経済新報社)である。
我が学内における教学行政について、学外における学会その他の運営について、その細心さは学内外ともに等しく驚嘆の的であった。博士は元来それほど健康に恵れたとは言い難い。後年次第に雑務を敬遠して、研究と新制大学院学生の指導に専念したといってよい。学問上の細密細心の心構えを伝えて、多くの研究者を送り出したのが、久保田明光博士の最大の功績である。
博士歿後その蔵書はすべて大学に収められてある。和文図書は大学院経済学研究科に「久保田文庫」として。欧文図書類は同じく「久保田文庫」として大学中央図書館に。特に欧文図書中のフィジオクラシーおよびドイツ・カメラリスムスの原典は稀覯書である。
第二次大戦後の早稲田政治学で支柱的役割を演じたのは、吉村正であった。吉村は、明治三十三年三月に福井市に生れ、大正十三年に早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業、引き続き大学院で政治学を専攻し、昭和四年七月から七年七月まで早稲田大学留学生として欧米に留学、主としてコロンビア大学およびベルリン大学において政治学・行政学の研究に従事したが、とりわけコロンビア大学では、昭和四年九月から六年十二月まで二年余りに亘って、ロバート・M・マッキーバーに師事した。
帰国後、昭和七年九月に早稲田大学講師に嘱任され、助教授を経て、昭和十三年に教授となり、昭和四十一年に自ら創設に当った東海大学政治経済学部の初代学部長に就任するため退任するまで、三十余年に亘って早稲田の政治経済学部で「欧米政治組織」「行政学」「政治学原論」等の科目を担当した。この間、大学行政の面でも指導的な役割を果たし、戦後の混乱期から新制大学発足前後期に島田孝一総長の下で常任理事、昭和三十年から三十一年にかけては社会科学研究所の初代所長、昭和三十一年から三十七年までは第一政治経済学部長を務めた。また、大学外の活動においても大きな足跡を残しているが、その中には憲法調査会委員、選挙制度審議会委員としての活動が含まれている。
政治学者としての活動は、政治学博士取得(昭和二十四年)論文を基にした『現代政治に於ける官僚の地位』(昭和二十五年)をはじめとして、『現代政治の機能と構造(新版)』(昭和五十七年)、『デモクラシーの現代化』(昭和四十七年)、『日本政治の診断(新版)』(昭和四十八年)、『現行憲法の矛盾』(昭和五十年)、『シティ・マネージャー』(昭和五十二年)、『政治科学の先駆者たち』(昭和五十七年)等の著作に集約的に示されているが、研究上の中心的関心は、官僚・政党を軸とする現代民主政治の分析、日本政治の問題状況の解明、地方自治の改革などにあった。
吉村の政治学上の立場は、実証主義的政治科学であるが、同時に一貫して民主政治の改革への志向性を強く持っていたところに、その研究の際立った特徴がある。吉村の立論が、政治学界に対してのみでなく、実際政治家や官僚に対しても強い影響力を持ったのは、このような吉村政治学の特徴の故にほかならない。なお、『政治科学の先駆者たち』は、「早稲田政治学派の源流」を形成する山田一郎、高田早苗、浮田和民、大山郁夫、高橋清吾の政治学的世界の解明を試みたもので、早稲田史と我が国の政治学発展史に対するきわめて貴重な貢献である。
中村貫平の長男として、明治二十四年二月六日、長野県上水内郡柏原村(現在信濃町)に生れた。生地の高等小学校卒業に前後して、父の事業失敗倒産、一家の東京移住に伴い、海城中学校に編入学、大正二年同校卒業後直ちに単身台湾に渡り、総督府税関に就職したが、同七年志を立てて、早稲田大学高等科第一部に入学、同十二年同大学政治経済学部経済学科を、苦学の後、三十三歳をもって卒業した。続いて同大学大学院に進み、服部文四郎に師事し、五来欣造、林癸未夫らの知遇をも得、同十五年助手、昭和七年には早稲田大学留学生として独英に遊び、翌八年帰国して同学部専任講師、同十三年同教授に任ぜられ、「貨幣および銀行論」「金融論」「経済原論」等を、政治経済学部を中心に、法学部、理工学部、教育学部等において担任、他に日本女子大学、明治薬科大学等の講師を兼ね、同三十六年定年の規定により早稲田大学を退職するまで、学生の指導、後進の育成に力を尽した。鶴岡義一、堀家文吉郎、柴沼武は早稲田大学内において衣鉢を継ぐ者である。この間昭和二十四年より同三十一年まで、第一政治経済学部長の職にあり、他に体育局競走部長となるなど、研究教育のほかでも、学内に重きをなした。別に昭和十七年、論文「貨幣の原理」により、経済学博士の学位を授けられた。
この書は、貨幣が何故に貨幣であるかの貨幣本質論に関し、多種の財貨が交換される経済にあっては、生ずることあるべき多種、複雑、無秩序、雑多の交換比率を統一総合する単一の価格を、一つの実在に結び付ける必要が生ずるとし、博引旁証の後に、この単位化価格の具象化実体が貨幣であると論定した。クナップ以後の貨幣本質論が名目主義から抽象学説に傾き、信用貨幣が支払手段の中で重きを加えつつあった当時の状況の中で、なお貨幣の本質を実体としたのは、貨幣価値に国内国際の二元性を認めざるを得なかったことに拠るものと考えられ、公正の論と言うべきものであった。当然学界においても重んぜられ、金融学会創立当初に会員に挙げられ、昭和二十年同学会再建に際しては理事となり、同四十六年までこの地位にあった。
早稲田大学退職後同大学名誉教授となったが、この年大東文化大学経済学部長となり、次いで同四十年から四十九年まで富士短期大学学長、五十一年より歿するまで同大学理事であった。
終生質素堅実の生活を保ち、資性謙譲であったが、自恃するところも強く、教室では学生に常に端正謹聴の態度を求めて已まなかった。趣味に旅行を好み短歌を嗜み、専門に関する著書論文多数の他に、歌文集『人間として想う』の小冊子がある。なお後年、生地信濃町は中村を、名誉町民第一号に挙げた。
老年に至り脳軟化症を患い、病床にあること二年余の後、服部文四郎を襲いで早稲田大学の貨幣論の第二世代を担った中村は、昭和五十三年六月十八日、老衰のため埼玉県蕨の自宅において永眠した。行年八十七歳。戒名は智海院釈正受広在居士。墓は郷里信濃町明専寺にある。
○「中村佐一教授略歴および著作目録」(早稲田政治経済学雑誌』、昭和三十六年四月)。他に、未亡人中村きみ刀自書簡(私信)
内田繁隆は学究生活の主要な時期を早稲田大学政治経済学部の教員として過し、その優れた研究業績と旺盛な探究心ならびに真摯な研究態度は後身に多大の影響を与えた。
内田は明治二十四年福井県に生れた。彼は少年時代に全国遊説中の大隈の演説に深く感銘して上京し、大正四年早稲田大学高等予科を経て大学部政治経済科に入学した。同科卒業後研究者としての道を選んで研究科(後に大学院)に進学し、政治学、欧米政治学史を研究し、更に日本政治思想史および日本政治史を専攻するに至った。
大正十五年政治経済学部の助手に採用され、昭和四年同学部の講師となり、助教授を経て昭和八年には教授に進んだ。終戦後一時大学を離れたが、昭和二十七年再び迎えられて教授に復帰し、昭和三十六年国士館大学政治経済学部の創設に協力するため同学部の教授に就任するまで、早稲田大学政治経済学部において、教育研究に尽力した。その間専門学校・学部・大学院等において、「日本政治思想史」「日本政治史」「政治学原理」等の科目を担当している。
彼はまた専門学校政治学科教務主任、政治経済学部教務主任、大学院政治学研究科委員長、早稲田大学商議員、同評議員等を歴任し、学部ならびに大学の充実発展に貢献した。更に社会経済史学会評議員、独伊文化研究会理事、日本国際政治学会監事、アジア政経学会理事等を務め、学外の研究活動にも積極的に参加して、学問の進歩発達に寄与するところが大きい。
内田の研究は広範囲であり多岐に亘るが、主要な研究としては先ず日本政治思想史および日本政治史の研究が挙げられる。彼の歴史研究の特徴は比較史的視点、ことに西洋との対比においてその研究を進めていることである。そのような観点から日本の近世政治思想を究明した『日本政治社会思想史研究』(厳松堂、昭和五年)は我が国の政治思想史における体系的著述としては先駆的業績である。またその歴史観としては、一元論的唯物史観を批判し、多元論的史観の立場から歴史的発展を社会経済的要素、思想文化的要素および政治的要素の相互作用によるものと解し、更に三要素の相互作用における序次を明確にすることに努力している。
次に政治学の研究である。内田は政治学の基礎的研究として共同体原理に早くから取り組んでいたが、戦後は同原理を基礎に体系的政治学の構築を企図し、共同体原理と民主主義および福祉共同体の理論的総合に努力してきた。その研究の集大成が『政治学新原理』(前野書店、昭和五十年改訂版)であり、この研究により博士号が授与された。
以上の両分野を含む彼の研究成果は前掲二著の他、『現代日本の総合観』(社会書房、昭和七年)、『日本社会経済史』(章華社、昭和九年)、『世界大戦時代』(太陽閣、昭和十二年)、『日本政治史』(大観堂、昭和十五年)、『日本政治学大綱』(実業之日本社、昭和十九年)、『社会主義政治学』(勁草書房、昭和二十五年)、『日本政治社会思想史』(前野書店、昭和三十五年新版)、『福祉国家論』(編著、成文堂、昭和三十七年)等の多数の著書論文として発表されている。
明治三十二年十一月一日出生(本籍、香川県三豊郡柞田村)、大正九年成城中学校四年修了後、早稲田大学附属第一高等学院文科を経て、大正十五年早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、卒業後直ちに同大学院に進学、中野登美雄教授のもとで憲法・比較憲法を専攻、昭和四年政治経済学部助手に嘱任された。助手在任中、『早稲田政治経済学雑誌』に論文「欧米諸国戦後の新憲法に於ける国民投票制」(一六号および一七号)を発表した。その後、昭和六年四月に講師に嘱任されたが、昭和十年に助教授に嘱任されるまで、『早稲田政治経済学雑誌』に論文「憲法改正権の実証組織」(二三号および二四号)をはじめ、「二院制度」(二八号)、「議会解散制の比較国法的研究」(三一号および三四号)等、主として議会制度に関する論稿を発表した。
助教授在任中、昭和十一年四月欧米、主としてドイツに留学し、昭和十三年一月に帰国した。既に講師時代にドイツの著名な公法学者G・イェリネックの名著『一般国家学』の一部を水垣進と共訳したところからも窺うことができるように、ドイツの公法学者の影響は、その後の研究にも少なからず反映しているようにおもわれる。帰国後も、議会制度に関する研究を続け、その成果は、「議会制度改革の理論と実際」(『早稲田政治経済学雑誌』六一号および六二号)、「議会補助制度の研究」(同六五号)という形で公けにされた。その後、昭和十五年二月、教授に嘱任されるが、それまでの比較憲法的研究の方法論を確立するため、同年論文「比較憲法学の任務、方法及意義」(『早稲田政治経済学雑誌』六九号、七〇号)を発表した。この論文では諸学者の比較憲法学の定義が詳細に紹介されているが、学界の注目を浴び、第二次大戦後においても諸学者によってしばしば引用された。旧憲法体制下での比較憲法的研究は多くの困難を伴ったが、その数多くの論稿は丹念、精緻にして、戦後においても稗益するところ少くない。
戦後も比較憲法的視点から数多くの論稿を発表した。これまでタブー視された国体については、「国体概念の再構成」(『早稲田政治経済学雑誌』九六号)を、統治機構関係では、「内閣関係の憲法上の疑義について」(同九八号)、「参議院の性格」(同一〇三号)、「法令審査制と憲法改正」(『法律タイムス』二一号)を発表した。また民主政治を成功せしめる諸条件のうち最も基本的なものとして、「民主政治成功の精神的前提条件」(『早稲田政治経済学雑誌』一〇〇号)を世に問うたことも注目されてよい。そのほか「世界各国憲法年表」(『公法研究』二号)を発表したが、基礎的資料として研究者に不可欠なものを呈示したものと言えよう。
大学では、第一政治経済学部自治行政学科主任、第二政治経済学部学部長、大学院政治学研究科委員長等の役職に就いたが、学部、大学院を通じて、「憲法」「比較政治制度」「比較憲法」等の講義を担当した。著書としては、『現代政党論』『日本憲法要論』『比較憲法論』、更に戦前・戦後の論文を収録した『比較憲法の基本問題』等がある。
その長年に亘る研究は、ひとり学界のみならず、実際においても認められ、昭和三十二年七月より四十年六月まで内閣憲法調査会委員として活躍、そこで発表、報告したものも多数に及ぶ(『憲法調査会議事録報告書』に収録)。
酒枝義旗は、明治三十一年(一八九八年)、愛媛県南宇和郡に生れた。若くして向学心に燃えていた酒枝は、大正二年四月、意を決して上京した。そして、苦学の末、中学校を経て、大正九年、第一早稲田高等学院開校とともに同校に入学した。
高等学院卒業の後、政治経済学部経済学科に進学したが、学部在学中、一年志願兵として兵役義務に従事した。復学の後、昭和二年、同学部を卒業し、直ちに大学院に進み、二木保幾教授のもとで経済哲学を研究することになった。
そして、昭和六年、早稲田大学講師に就任した。昭和九年からドイツに留学し、フォン・ゴットル教授との交渉が始まり、それによって、酒枝は経済学上の思惟について決定的な影響を受けた。
酒枝が政治経済学部において担当した科目は、長い間、「経済英書」「経済独書」の講読だけであった。後に、塩沢昌貞の後を襲って「経済原論」を担当したのは昭和十七年のことである。
昭和四十三年四月、大学の制度により定年退職し、名誉教授に推薦された。
教授在職中、昭和三十一年九月―三十三年九月の間は第二政治経済学部長、昭和四十一年五月―四十一年九月の間は第一政治経済学部長の責任を完うした。第一政治経済学部長就任時は、早稲田大学史上未曾有の長期紛争(百五十五日間)の最只中のことであった。
また、酒枝は、本学の他に、日本聖書神学校、東京女子大学、明治学院大学等の講師、後には富士短期大学の学長を務めた。他方、日本キリスト者学会ならびに日本クリスチャン・アカデミーの理事でもあった。
昭和五十六年三月、昇天した。
酒枝の経済学は、存在論的認識論に基づいて構築されたものであった。その研究成果は、『構成体論的経済学』(昭和十七年)、『構成体論的思惟の問題』(昭和十九年)、『ゴットルの経済学』(昭和十九年)として発表された。
また、酒枝の思索の根源はキリスト教の信仰にあった。彼は、大正十一年入信以来、きわめて真摯なキリスト者として生き、晩年、自宅においてキリスト教待晨集会を主催して、多くの人々に師と仰がれた。
酒枝は、その魂の旅路を、『さまよう魂の告白』(昭和三十七年)、『今に至るこそ』(昭和四十三年)等で語っている。
明治三十三年四月八日、大阪府堺市東山三番地生、財政学者、第九代総長。大正十年「大隈侯に傾倒して」第一高等学院(二回生)に入学、昭和二年政治経済学部経済学科卒業、昭和八年財政学・統計学研究のため英・独に留学、昭和十五年政治経済学部教授、昭和三十五年経済学博士、昭和四十六年定年退職となるまで、本属の政治経済学部で、「財政学」「統計学」「租税論」「演習」「英書経済学」「独書経済学」を担当、専門部政治経済科で「英書講読」「統計学」「財政学」「現代社会思潮」、大学院経済学研究科で「財政学研究」「財政学演習」「財政学特論」「財政制度論」を担当した。
この間、昭和二十一年―二十六年まで専門部政治経済科科長、昭和二十四年―二十九年まで第二政治経済学部長ならびに附属専門学校長、昭和二十九年―三十五年まで第二政治経済学部学科主任、昭和三十七年―三十九年第一政治経済学部新聞学科主任を務めた他、昭和三十七年十月から四十一年五月まで大学常任理事、昭和三十九年評議員、昭和四十三年六月から四十五年十月まで大学総長として、大学機構の改革、大学紛争の収拾に力を尽し、昭和四十六年定年に伴い名誉教授、名誉評議員に推挙された。
また、昭和二十四年以降早稲田大学雄弁会会長、昭和二十五年以降体育局米式蹴球部長として活躍、学界および学外においては、日本統計学会評議員、日本財政学会理事、日本経済学会連合会評議員・理事、大蔵省財政制度審議会委員、大蔵省関税審議会委員、文部省大学設置審議会常任理事、私立大学連盟常務理事、私立大学連盟会長、全私学連合代表、文部省私立大学審議会会長等、幾多の要職を歴任、こうした業績に対し、昭和四十六年、先代総長阿部賢一とともに勲一等瑞宝章を親授されたが、なお退職後も、昭和四十七年日本私学振興財団理事長として、私学の発展に尽瘁した。
学位論文であり、またその主著でもある『財政本質論』(昭和三十五年、東洋経済新報社)は、社会は技術の進歩によって発展し、財政もまた、こうした社会発展に伴って、それに応じた形態を採りつつ発展してきているという認識に基づき、「社会発展に関する技術的解釈」すなわち「技術史観」なる独自の方法論に立ち、財政の根形態を個人の家政に認めながら、国家を家政主とする「国家公家政」から国民を家政主とする「国民公家政」への発展を説明することによって、新たに出現してきたフィスカル・ポリシーやそれ以後の財政の経済学、ケインズ主義財政学の無体系な財政学への吸収を批判し、財政の本質を国民公家政に求めることによって、初めてそれらをよく吸収整序し得ることを説き、日本の財政学者による財政学説の中に、確固たる一説を形成したものである。著者によれば「技術史観」は、高等学院時代佐野学よりドイツ歴史学派の説明を聞いて感動したのが始まりであり、また大学院において恩師塩沢昌貞に出会ったのがその契機であったという。
他にニコラス・カルドア『総合消費税』の監訳(昭和三十八年)、『財政学(新版)』(昭和四十一年)のほか、財政・租税関係その他の多数の論文が、自らその発行に参画した『早稲田政治経済学雑誌』に掲載されている。
昭和五十九年六月二十六日、享年八十四歳を以て歿し、従三位に叙せられた。
川原篤は、大学院で信夫淳平の指導のもとに国際政治を研究し、昭和十三年から、信夫の後継者として「国際政治論」を担当した。
国際政治に関する川原の主要な研究業績は、『早稲田政治経済学雑誌』に発表された。その幾つかを列挙すれば、「安全保障の政治的考察」(第三七号、昭和九年刊)、「同盟に関する若干の政治的考察」(第五九号、昭和十三年刊)、「『勢力均衡』の政治的考察」(第六三号、昭和十四年刊)、「国際政治に於ける『安全』の動態性を論ず」(第六九・七〇号合併、昭和十五年刊)、「国際政治に於ける真正安全の問題」(第八三号、昭和十七年刊)、「『安全』に関する若干の問題」(八八・八九号合併、昭和十八年刊)等である。
これらの論稿のタイトルを見ただけでも推測されるように、川原の国際政治研究における主たる関心は、安全の問題に向けられていた。それと言うのも、川原は、安全が、「国際政治の基本的且つ包括的なる問題である」(「『安全』に関する若干の問題」一三三頁)と認識していたからであった。川原によれば、真正な安全は、国家の内部的安全、国家の対外的安全、国家の構成する一定国際社会の与える安全の三者の調和一致の中に認められ(「国際政治における真正安全の問題」一〇七頁)、しかも、安全は、静態的安全と動態的安全の両面から考えられるべきであると指摘している。(前掲論文、一一〇頁)
なお、川原は、「転換期国際政治と国際政治論」(『早稲田政治経済学雑誌』第八一号、昭和十七年刊)という論稿で、国際政治の本質に関して究明しているが、「国際政治現象を科学的に研究するには、……その国際現象を政治行為と権力の関係を標準として取扱うことに新しき方法を認証することも得る」(前掲論文、九六頁)と指摘していることは、注目すべき点であろう。つまり、川原は、権力的アプローチによる国際政治研究の必要性を認めていたと言うことである。
それにしても、不幸なことに、川原は、第二次大戦中の昭和十九年に応召し、昭和二十年一月に中国で戦病死したために、彼の目指した国際政治の科学的研究を完成することができなかった。もしも川原が、戦後も健在であったならば、必ずや国際政治学の研究に大きな貢献をしたであろう。
小松芳喬は明治三十九年、東京・神田で生れた。第一早稲田高等学院を経て昭和三年、政治経済学部経済学科を卒業、直ちに大学院に進み、二木保幾教授のもとで経済学史の研究に従事した。昭和八年『早稲田政治経済学雑誌』に載った論文「エドマンド・バァクとアダム・スミス」および昭和十九年に刊行された翻訳『マルサス・経済学に於ける諸定義』はこの時代の研究成果である。
しかし、小松の関心は次第に経済史へと移っていった。その理由について、小松は自分の興味の方向と学部の必要が合致したからだと言う。とにかく、昭和十年に発表された二番目の論文は経済史の論文――「Elizabeth朝に於ける若干の貨幣問題」――であった。また、昭和十二年、小松は大学から派遣されてイギリス留学の途に就くが、その時、大学から与えられた課題は経済史研究である。
留学から帰った小松はイギリスの封建農村、特にマナー制度に関する論文を次々に発表した。それらは昭和十九年一本にまとめられ、『封建英国とその崩壊過程』と題して出版された。本書は当時の研究水準を遥かに抜くものであった。また、それは研究者としての小松の態度、持ち味をもくっきりと示すものであった。いわゆる理論で歴史を割り切るのではなく、事実をできるだけ事実として研究し、以て人間の営みには理論では割り切れない、不合理な部分が含まれることを暗示する態度がそれであると言ってよいであろう。こうした研究態度は過去の内外の研究業績を最大限に尊重するというもう一つの態度を生む。戦後の外国文献の入手困難な時期にも、小松はあらゆる手段で入手に努力した。どんな条件にあっても、小松は見るべきものを見ないで論文を書くことはしなかった。参照すべしと考えた文献は大小洩れなく参照し、自分の立場に反するものであっても、少しでも取るべき点があれば、それを尊重したのである。かかるる態度は小松の研究に高度の精緻さ、実証性を附与することとなった。戦後、今日までに発表された研究の大半は『英国産業革命史』(昭和二十七年)、『英国資本主義の歩み』(昭和二十八年)、『イギリス農業革命の研究』(昭和三十六年)、『イギリス封建制の成立と崩壊』(昭和四十六年)、『産業革命期の企業者像』(昭和五十四年)などに収められている。
なお、小松は『イギリス農業革命の研究』によって昭和三十五年、経済学博士の学位を得、また『産業革命期の企業者像』によって昭和五十五年度日経出版文化賞を得た。小松の諸業績は御自身の研究者としての能力と精進を示す証しであると同時に、早稲田大学政治経済学部における西洋経済史学の確立を告げる金字塔でもあるのである。
小松は昭和五十一年年三月、定年制度の故にその能力を惜しまれながら学苑を退職、現在名誉教授の地位にある。
平田冨太郎は明治四十一年秋田県横手市で生れた。早稲田大学付属第二高等学院を経て昭和六年、政治経済学部経済学科を卒業、直ちに大学院に進み、林癸未夫教授の指導を受け社会政策を専攻した。昭和十二年同学部講師に嘱任され、助教授を経て昭和二十年に教授に就任、昭和五十四年定年退職まで在任し、この間社会政策を主とし、「労働問題」「工業政策」「社会保障論」「労働経済学」等の講義を担当した。また教育行政の面では、第一・二政治経済学部長、評議員、図書館長、大学院経済学研究科委員長などを歴任し、かたわら定年まで約三十年スケート部長として学生スポーツの振興にも力を尽くしてきた。退職後は早稲田大学名誉教授に嘱任されるとともに日本社会事業大学学長に就任、現在(昭和五十七年)三期目を迎えている。
同教授の業績と活動は学内外ともに広汎多岐に亘っており、この紙幅では極く一端しか紹介できない。詳細は同教授の古希記念自筆論文集『労働と福祉をめぐって』(昭和五十四年早大出版部刊)を参照されたい。
同教授の研究業績について見れば、⑴『社会政策論研究』(昭和二十八年刊)に代表される社会政策理論の学説史的研究、⑵『社会保障研究』(昭和三十二年刊)および『社会保障――その理論と実際――』(昭和四十八年刊)に代表される社会保障の理論的および実証的研究、⑶『労働問題』(昭和三十七年刊)および『社会政策問題』(昭和四十八年刊)に代表される労使関係ならびに労使協議制、および労働運動史に関する研究、⑷編著『退職金と年金』(昭和三十一年刊)および共著『企業年金の理論と実務』(昭和三十八年刊)に代表される高齢化社会の到来に伴う公的ならびに企業年金問題の研究を主なものとして挙げることができる。
なかんづく⑴の『社会政策研究』は学位主論文となった主著である。同書において平田は、内外の社会政策諸理論の特質を、独自の二重的視点――社会政策の本質を経済外的に理解しているか資本制経済構造の内的必然性との関連で把握しているかという視点と、資本制社会経済構造に対して肯定的であるか否定的であるかという視点――から解明・類型化し、学説史的位置付けを行った。同書は社会政策諸学説の集大成的宝庫であるとともに、従来の混沌錯綜していた本質論論争に論点の整理と明確化を与え論争に一応の終止符をもたらし、以後の我が国の社会政策研究を寧ろ一層実り多い実証的研究へ誘導するという重要な貢献を成したものとして学界で高く評価された。同書と副論文『社会保障研究』によって平田は昭和三十年、慶応義塾大学より経済学博士の学位を授与された。こうした理論的研究を基礎としてその後執筆された多数の著作・論文は、同教授の各論的研究と見ることができるが、いずれも優れた先駆的・実証的研究として社会政策研究者の間で高く評価されている。
平田の学界ならびに学外活動は広汎に亘っているが、なかんずく中央労働委員会の公益委員および会長としての仕事は、社会政策の実践的研究の豊肥ともなったため、これに熱心に尽粋した。主としてこの功績によって昭和五十三年十一月勲一等瑞宝章を受賞した。
明治三十八年十月九日静岡県榛原郡川崎町静波の地に杉山惣藏の長男として生る。静岡県立榛原中学校に学び、次いで、小樽高等商業学校に入学。同校を卒業後、昭和四年四月早稲田大学政治経済学部経済学科に入学。戦前の早稲田大学の各学部の学生の殆どが付属の第一および第二高等学院の出身者であった点からすれば、数少い傍系の学校からの出身者の一人であった。昭和七年の三月に同学部を卒業、引続き同大学の大学院に入学、四年間に亘る大学院での研究生活を終えた後、昭和十一年五月早稲田大学政治経済学部助手、翌十二年四月講師、十六年三月助教授、終戦時の昭和二十年四月、早稲田大学教授となる。助教授時代の昭和十六年八月十四日より三ヵ月間、国際文化振興会、海軍省ならびに外務省より派遣せられて、仏印および泰国の経済事情を視察、その成果を、一書、『泰国経済の分析』(昭和二十年、日本評論社)として発刊す。また、昭和十八年十二月より二年間に亘って日本産業経済新聞社論説委員の一人として紙上に健筆を奮い教授の経済学者としての幅広い活動の一面を印象づけた。
学部での主たる講座は、昭和二十四年四月から、昭和三十三年十一月十一日急逝されるまで担当された、『経済機構論』であった。教授は勿論マルキストではなく、寧ろ、マルクス経済学の長短を徹底的に究明し、その短所をば近代経済学あるいは教授自身が追究しようと努めていたより包括的な経済学でもって補完し、両者の接合点を求めようとしたのがこの講座の中心的テーマであったものと思われる。この傾向は、昭和三十年八月から一年間、教授が早稲田大学留学生として、経済理論および経済政策研究のため、英国ケンブリッジ大学においてJ・ロビンソン教授の指導を受けたことにより、一層鮮明なものになった。帰朝後の昭和三十二年度および昭和三十三年度の学部要覧に記載されている、「経済機構論」の教授による講義内容の記述はこのことの真なることを端的に物語っている。すなわち、「ミセス・ロビンソンはI have Marx in my bones and you have him in your mouthと書いています。この意味をよく嚙みしめて、いわゆる近代経済学とマルクス経済学との接触点を、ミセス・ロビンソンに求めてみたいと思います」と。近代経済学者の中でもマルクスの最も良き理解者の一人であったJ・ロビンソンとの出会い、ロビンソンの名著、『資本蓄積論』の教授の手になる翻訳の出版、教授の経済学研究への情熱が一段と燃えさかった矢先、過労による突然の死が教授を見舞い、五十三歳というまさにこれからという教授の一命を、しかも自らの研究室において奪い去ったということは劇的というにはあまりにも不幸な出来事であった。
明治四十四年十月山形に生れる。昭和十年三月早稲田大学政治経済学部経済学科卒業の後、久保田明光教授門下生として経済学の研鑽に努め、昭和十八年十月早稲田大学専任講師、昭和二十三年助教授、昭和二十四年四月教授にそれぞれ嘱任され、昭和五十七年三月末日をもって定年退職した。
教授の担当科目は「商業経済学」と恩師の定年退職によりその跡を継いだ「経済学史」である。従って教授の主たる研究分野もおのずと二つに分たれる。すなわち、その一つは「独占的競争理論の主論点とその歴史的推移」であり、他の一つは「一六世紀―一八世紀フランス経済学の展開」である。前者は商業経済学の講義に関連して深められたミクロ経済学研究から発展したもので、その一端がE・シュナイダー『経済理論入門』(全三巻、英訳、昭和三十六―三十九年、ダイヤモンド社)と、A・E・オット『市場形態と行動様式』(監訳・昭和五十五年、早大出版部)の二点の訳業に窺われる。しかし教授が専ら意を注いだのは後者の経済学史に関する研究である。フランス重農学派研究の権威であった恩師の指導の下に着手されたその研究は「フランス重商主義の展開」と「フランス主観価値論の形成」とを二本の柱とするもので、それらの成果は『近世フランス経済学の形成』と題する学位請求論文となって結実し、それによって教授は昭和三十五年一月経済学博士号を取得した。なお同論文は同一題名の単行本として、昭和四十三年に世界書院から公刊された。その後も続けられた一連の当該研究の業績と、昭和四十五年十月の日・仏経済学会会長就任後の活動による日・仏経済学の交流の成果とが、仏政府の高く評価するところとなり、昭和五十一年二月、Ordre des Parmes Académiques(Ofhcier)受賞の栄誉に輝いた。また経済学史に関する訳業にはE・ジャム『経済思想史』(上・下二巻、昭和四十―四十二年、岩波書店)がある。昭和六十三年八月二十三日死去。行年七十六歳。
教授は経済学研究に際して邦語と英語の文献のみで事足れりとする風潮と、既成の現代的観点ないしは概念をもって過去の学説を解釈し割り切ろうとする傾向を慨嘆し、原典に忠実に、且つ地味に地道にをモットーに、自己の研究と後進の養成に当った。そしてその直接・間接の指導により英語以外の外国語文献もよくこなしうる研究者が育成され、学内・外に送り出されたことは特筆さるべきであろう。また在職中に第一・第二の各政経学部教務主任、第二政経学部長、大学院経済学研究科委員長を歴任し、学内行政にも尽力した。教授の学部ゼミナール出身者は三百余名に上り、広く各界で活躍している。
佐藤貞次郎・てるの三男として、明治四十五年三月二十三日、岩手県九戸郡野田村に生れた。盛岡藩学校「作人館」館長で、明治憲法の制定に当たり、進歩的議会主義に立って元老院「国憲」草案への所見を述べた小田為綱は母方の曾祖父に当たる。明治政府の有司専制を弾劾してしばしば建白書を提出した叛骨の代議士(大隈系)でもあった。
旧制盛岡中学、第一早稲田高等学院を経て、昭和十一年早稲田大学政治経済学部経済学科を卒業。学部在学中、「法と道徳―その政治史的及び組織的研究」によって、早稲田大学恩賜記念賞を受賞した。二百字三千枚を超す大作で、ギリシャ以来現代に及ぶ主題の展開を代表的学説によって系列的に扱ったものである。卒業と同時に同学部大学院に進み、国法学の大家、中野登美雄教授に師事し公法学を専攻する。その後、昭和十八年、政治経済学部助手に嘱任されたのを皮切りに昇進を重ね、二十四年に教授となり第一、第二学部で主に「行政法総論」ならびに「各論」を担当した。更に二十六年、新制大学院創設以来、五十七年に定年退職するまでの政治学研究科ならびに法学研究科兼担教授として行政法学の研究指導に当たった。この間、三十六年には「弾劾制度の研究」を以て東京大学法学部より法学博士の学位を授与されている。英・米・独・仏ならびに我が国弾劾制度の比較研究で、理論的問題とともに歴史的発展をたずね問題点を明らかにしたものである。
三十三年から約一ヵ年、在外研究員として欧米留学を命ぜられ、主としてハイデルベルク大学において公法学を中心に、憲法および行政法を研究した。なお四十八年にも、約六ヵ月間、同じく在外研究員として再度西ドイツ、ヨーロッパを訪ね、憲法・行政法を研究の傍ら各国憲政の実情を調査している。
この間、学内では、教務主任(第二政経・二十八―三十三年)、学部長(第二政経・三十八―四十三年)、大学院委員(政研・四十一―四十二年)、大学院委員長(政研・三十八―三十九)、大学商議員(二十七―四十九年)、同評議員(三十八―四十二年)の要職を歴任した。また対外的にも議会・政府関係の調査員や各種審議会委員を歴任したほか、今なお、日本公法学会理事、東京都収用委員会委員として活躍を続けている。
著書、論文等多数に上るが、教授の四十年に渉る研究業績は、大きく二つの系統に分けられよう。第一は、ドイツにおける法哲学ならびに公法理論の研究である。翻訳書『ヴァッス・先験的法哲学』(昭和十六年・雄風館)を出発に、『公法における理念と機能』(昭四十三・早大出版部)――特にその「理念篇」――、『現代の国家と憲法論考』(昭四十八・早大出版部)とその『増補版』(昭五十一)、そして『現代ドイツ公法学を築いた碩学たち』(昭五十七・早大比較法研究所)と続く膨大な一連の研究である。
第二の系統は、公法制度の実証的比較研究である。この系統に属する代表的著作としては、『貴族院体制整備の研究』(昭十八・人文閣)、『職能代表制度論』(昭二十一・実業之日本社)、そして学位論文となった『弾劾制度の研究』(昭三十三・前野書店)とその新版(昭五十四)、『公法における理念と機能』(前記)――特にその「機能篇」――、『イギリス行政訴訟制度の研究』(昭四十三・早大比較法研究所)等が挙げられる。
第一の系統に属する諸研究では、新カント派から今日までほぼ一世紀間の、ドイツ法哲学ないし公法理論の壮大にして絢爛たる発展が辿られている。そこでは、規範と現実、ないしは憲法と国家の認識を巡る代表的学説の特質と意義が精緻な手法で解析されている。ことに『碩学たち』は、教授が定年退職を間際に筆を擱かれたもので、その第一部には、ケルゼン、シュミット、スメントらドイツ公法学を創り推し進めてきた碩学達の燦然たる学殖の真髄が展べられている。それはそのまま教授の研鑽の深さを物語るものとなっており、教授が若かりし頃よりこれらの人々に畏敬の念を抱きつつ、倦むことを知らなかったドイツ公法学研究の集大成をも成すべきものと思われる。
第二の系統に収められた諸研究は、ひろく世界各国に渉る公法制度の本質と機能とを、それぞれの歴史的・社会的背景との関わりの中で分析し、問題点を明らかにしようとしたものである。いずれも、その探求を通じて、我が国戦後憲法下における公法制度の健全な組織、運営のあり方に稗益しようとする問題意識の展開であった。
教授四十年の研鑽の跡は両者融然として独自の学風を成し、我が国公法学の発展に多くの貴重な価値と功績とを残したと評されよう。
昭和二十五年六月、市村は政経学部四〇四教室(現在の学生読書室)で「西洋政治史」の講義を終え、講壇を下り廊下に出た途端に倒れそのまま不帰の客となった。亡くなった翌二十六年遺著として発刊された『政治概論』の「跋」に、松本重治先生は次のように書いている。
市村の終生愛した浅間山は、……人類に対する激しき迄の愛情と秋霜のごとき操持とを内に秘めつつ、他に対しては寛容そのものであつた市村の風格を彷彿せしめる。
親友が故人を偲んだ文章であるだけに胸を打つものがある。
市村は早稲田に在学中から大山郁夫教授に私淑し、政治学科を出てからシカゴ大学でメリアム、スモール両碩学の指導を受けた。市村の政治思想史に対する学問的関心、社会の現実に迫り、現実を把握せんとする態度と情熱、そして、徹底した民主主義者としての根本的立場など、すべてこの三教授の薫陶に負うところであろう。
主な著作として、帰朝後間もなく『近代政治思想史』(昭和二年)を著わし、その後、東京政治経済研究所の同人として、第一次大戦における日本と世界との政治経済一般についての実証的な共同労作に従い、これを啓蒙的な形に盛って、数次の政治経済年鑑として刊行した。次に翻訳としてラスキの『政治学範典』(昭和八年)、著書として『再組織された英国の経済』(昭和十四年)、『西ヨーロッパ連邦論』(昭和十七年)、『英国の企図する世界新秩序』(昭和十八年)、第二次大戦終了後は、『英国の憲法』(昭和二十一年)、『英国政党論』(昭和二十四年)を出版した。その傍ら、昭和二十三年から蠟山政道先生達と政治学研究会を組織し、その機関誌『政治学研究』に毎号論文を執筆している。更に、英国憲政の諸研究を集大成して『英国における憲政の理論と実践』全六巻の大作を計画し、その第一巻『国王篇』(昭和二十三年)を刊行、次の内閣、行政に関する原稿を完成したところで急逝したのであるが、その原稿は蠟山、我妻両先生の御尽力により、文部省の補助を得て『内閣篇』(昭和二十七年)、『行政篇』(昭和二十九年)として刊行された。なお、遺著となった『政治概論』は、日本女子大学の通信講義録のために昭和二十四年に執筆されたものである。その著の序文に蠟山先生は次のように述べておられる。
政治学は、その学史、理論および制度の三方面にわたって、これを統一的に叙述することは頗る困難な学問である。それにも拘らず、著者は本書においてこの仕事に挑戦し、美事に開拓の鍬を入れるのに成功した。
井伊玄太郎は、明治三十四年鳥取県に生れた。京都府立宮津中学校、早稲田大学第二高等学院、同政治経済学部経済学科を卒業の後、大正十五年大学院に進学し浅見登郎教授のもとで植民政策を研究する。浅見教授死去の後は特に五来欣造、杉森孝次郎教授の指導を受ける。同志社大学専門学校講師、神戸女子神学校講師等を歴任の後、昭和二十三年早稲田大学政治経済学部専任講師、昭和二十四年同教授に就任、昭和四十七年定年まで、主として「社会学」および「近代社会思想」を担当した。早稲田大学商議員、評議員を歴任、昭和四十七年六月早稲田大学名誉教授。著書に『社会学』(昭和二十四年)、『フランス社会思想史』(昭和二十四年)、『社会思想史入門』(昭和二十八年)、『文明社会学』(昭和三十四年)、『社会文化人類学』(昭和三十七年)、『社会学要論』(昭和四十二年)、『社会思想要論』(昭和四十二年)、『近代フランス社会思想史』(昭和四十四年)、『文明論』(昭和四十五年)、『社会学新論』(昭和四十六年)、訳書にデュルケム『社会分業論』(昭和七年)、ルソー『社会契約論』(昭和二十二年)、トクヴィル『米国の民主政治』(昭和二十三年)等多い。
このように井伊は植民政策の研究より出発し、特にフランス思想の影響を受けつつ、社会学、社会思想を専攻するに至ったように思われるがその学問の方法的特徴は、綜合性にある。それは自らの社会学を「一部門的専門科学と異なって、社会や文化の一部的分野のみを対象とする」ものではなく、全体としての社会と文化とを対象とする社会総合学的方法によって構成しているところにも、社会思想史を「思想の歴史的社会的=文化的背景とともに、綜合的に統一的に有機的一体性においてとらえなければならない」としているところにも表れているが、このような目的にかなう素材をおよそあらゆる思想・学問的分野に渉猟し、自家薬籠中のものとしつつ総合化を企てていったところに表れていると言える。思想を「社会を改善する原動力である」としながら、しかも教条主義、権威主義を排し、あらゆる思想構造物を相対化しつつ、批判的理性を創造的に堅持していったところに、早稲田人井伊の面目が表れていると言える。
明治四十四年一月埼玉県比企郡小見野村(現川島町)に出生、大正十四年同村尋常高等小学校を卒業、昭和四年早稲田大学出版部『早稲田政治経済講義録』による検定試験に合格、昭和九年早稲田大学専門部政治経済学科卒業、昭和十二年政治経済学部の卒業に際して教職員賞を授与され、倉敷絹織株式会社に入社した。昭和十三年から十七年まで兵役にあり、十九年応召してフィリピン・レイテ島方面に従軍し、二十一年に復員した。
昭和二十二年政治経済学部に新聞学科が創設されたのに伴い、専任者として招かれて同学部附置の新聞研究資料室勤務となる。昭和二十三年早稲田大学専任講師に嘱任され、資料室長を兼務する。昭和二十五年助教授嘱任。この頃、日本新聞学会の設立に参画。昭和二十六年創立総会で理事に選出され死去するまで在任。昭和二十九年教授嘱任。昭和三十五年学位請求論文「アメリカ新聞の生成過程」に対し日本大学より法学博士の学位を受け、同論文を弘文堂から上梓した。昭和三十八年二月、前年八月より入院加療中の東大病院で死去、逝年五十二歳であった。
右の閲歴から窺われるように、内野は昭和二十二年四月から死去するまでの間、新聞学科において「新聞学原理」および「新聞雑誌発達史」を担当した。そして昭和二十五年以降、主に『早稲田政治経済学雑誌』ならびに新聞学会機関誌『新聞学評論』を通じて、アメリカの植民地時代および革命期の新聞と新聞人に関する研究論文を発表し続け、これらは彼の博士論文に集成されていった。こうして内野は、アメリカ合衆国の独立までを彼のアメリカ新聞史論の第一部とし、続けて南北戦争後までの期間を第二部に、そして現代までを第三部とする全体構想を持っていたが、死去により中断されてしまった。
「新聞学原理」の講義内容については、前述の新聞学科の項で多少は仔細な検討を行ったつもりであるが、内野が講義を通じて強調した点は、表現の自由量に関する社会的配分の不均衡に対する問題であった。彼のこの問題提起は、言論の自由確保の方策を模索する過程で、一つは、特に第二次大戦下で体験した我が国の言論の問題、更には、折から紹介され始めたアメリカのマスコミュニケーション理論が持っていた図式主義、この双方に対する反省と批判から作られたものであった。それは、歴史研究から出発した内野にとり、見過すことのできぬ課題でもあったのである。
講義内容の次の重点は、現代の新聞記者に広汎な倫理観が要求される理由の説明にと続き、記者の職業が歴史的に規定されていることの重大意味の自覚を述べたが、これは、内野の新聞論が記者育成という新聞学科の当初の目的とともにあったことを示している。と同時にこれは、ジャーナリズム研究が内包している一つの特性を明白にしたものと評価できるであろう。
石川準一郎は明治三十二年六月一日、岩手県盛岡市に生まれ、岩手県立盛岡中学校を卒業した後、大正八年早稲田大学高等予科第一部に入学した。同予科を終了後、政治経済学部政治学科に進学し、大正十三年に卒業している。
石川は学生時代から行動力がありまた熱心な勉強家であった。彼は新聞学会を創設してそのリーダーとして活躍するとともに、一方では読書会を組織して社会主義の研究に熱中した。読書会では高畠素之がマルクスの『資本論』を講じたのをはじめ、大山郁夫、安部磯雄、北沢新次郎、石川三四郎等の著名な学者が協力し、彼等の指導に当っている。
学生時代のこうした体験が彼のその後の人生に深い関わりを持っていたと考えられる。すなわち、新聞会での活動が彼の文筆生活への契機となったであろうし、読書会での勉強と、それを通じて結ばれた高畠との師弟関係が彼を国家社会主義の研究と実践に没頭させることとなったのであろう。
彼はやがて高畠門下の高弟として学界・思想界に知られるようになった。昭和の時代に入り高畠が歿して間もなく我が国にもファシスト団体が次々と結成されるに至った。石川は高畠理論の継承者として、昭和六年九月国家社会主義理論の確立とファシスト団体の連絡・統一を目的とする(木下半治『日本国家主義運動史』下)日本社会主義研究所を設立してその所長となり、更にその組織を拡大して日本国家社会主義学盟に発展させ事務局主事となった。次いで昭和九年三月には大日本国家社会党を創立し、総裁となった。彼はこうして、第二次大戦前の日本における国家社会主義の理論的、実践的指導者として活躍したが、戦争中満州新聞顧問として渡満し、満州で終戦を迎えた。
戦後昭和二十四年四月早稲田大学に迎えられ、第一政治経済学部の専任講師となり同時に第二政治経済学部をも兼担した。次いで昭和二十六年彼は教授に昇格した。彼は政治経済学部において、「演習」「英書研究」等を担当したが、その研究は一貫して社会主義の研究に置かれていた。ことにマルクス主義に対する批判的研究が主要課題であり、マルクス主義に内在する誤謬や矛盾を究明し、それを理論的に克服しようと努力していた。その研究成果は『早稲田政治経済学雑誌』に発表されていたが、それらの論文をまとめて体系化したものに『マルクス主義批判』がある。石川はその研究の一層の発展が期待されたが、惜しくも病気のため昭和三十七年三月退任した。
後藤一郎教授は大正九年三月、大分県に生れた。昭和十四年四月、早稲田大学付属第二高等学院を経て同政治経済学部政治学科に進学した。在学中、五来欣造、吉村正教授等の知遇を受け、学問の世界へ誘われた。真理の探求への憧憬を持ち、母校で教鞭を執るのが夢であったが、生憎卒業したのがパールハーバー事件のあった翌年の昭和十七年であったので、一時日本銀行東京支店に入社した。早稲田大学政治経済学部の助手として迎えられ、学窓で研究者としての道を本格的に歩み出したのは、昭和二十二年のことであった。時既にその天分は多くの人の認めるところであった。
講師、助教授時代には「政治学」「政治英書」等を担当したが、教授になってからの担当科目は、「地方行政」「行政学」および「政治学原論」であった。大学院でも当初は「自治行政研究」を担当していたが、昭和四十二年五月より「政治学研究」に代った。従って、学者としての業績も、自治行政に関するものと政治学に関するものとに分けられる。
「地方行政」は早稲田大学において由緒ある科目であるが、この分野における教授の業績は、『イギリス地方自治制度論』(昭和四十七年、敬文堂)に集大成された。本書は、地方自治の母国であるイギリスにその原点を求め、地方自治制度の根幹を解明すると同時に、コナーベイション、ニュー・タウン建設の問題等、現代的状況への適合について論じ、更に行政の能率化問題と再編成過程に触れて地方自治制度の将来への展望を行っている。本書により、昭和四十八年二月、早稲田大学政治学博士の学位を授与された。
政治学の分野では、ラズウェル、イーストン、ダール、アイリッシュ、プロス等碩学の業績を逸早く日本に紹介する傍ら、内外の投票行動、選挙制度、政党、圧力団体、政治過程等の実証的研究に励み、理論的にも権力の本質の解明に当った。不幸にも業なかばで病魔に襲われ、昭和四十八年に他界された。没後、その遺稿は、『政治学原論』(昭和五十四年、敬文堂)にまとめられた。本書は、政治と行政の関係にも触れたユニークなものである。その他、政治学の分野では、『アメリカの政治』(昭和三十八年、日本国際問題研究所)、『各国の政治機構Ⅰ・Ⅱ』(編著、昭和四十年、敬文堂)がある。また行政学の分野でも『行政学』(昭和四十年、敬文堂)、『各国の地方自治制度論』(編著、昭和四十八年)がある。独立した『政党論』の構想もあったが、果さなかった。
後藤教授は、資料に忠実で、綿密な実証研究を旨とした。常に前進的に理論の彫琢に努め、政治学の諸側面を網羅した体系化を心掛けた。政治学の分野では、行動主義、体系分析に興味を寄せたが、理論を集大成していく足掛りとしてであった。『早稲田政治経済学雑誌』等に寄稿した論文は五十点以上を数えている。昭和四十四年には政治経済学部長、昭和四十五年からは大学院政治学研究科委員長を歴任した。その急逝は人々の惜しむところであった。後進の指導にも積極的であり、多くの弟子を輩出している。
執筆者一覧)